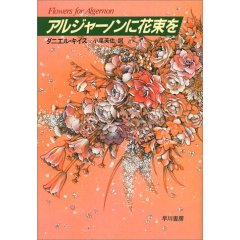097「生理的にキモい生物が出てくる作品」
今回は趣向を変えて、タイトルのような物をやってみようと思います。
いろいろな作品にいろいろな思いもかけないような生き物が出てくることがありますが、その中でもこれはキモいと思った物がいくつかあります。
何もそんな物を取り上げなくてもとも思いますが、でも、反面それはとてもインパクトがあった作品とも言えるので、そんな感じで見てやってください。
 最初は、「DUNE」シリーズに出てくる、砂虫。もう砂の中からぐわっと出てきちゃう結構危険で巨大な虫です。
最初は、「DUNE」シリーズに出てくる、砂虫。もう砂の中からぐわっと出てきちゃう結構危険で巨大な虫です。
左の画像は拾い物ですが、こんなイメージ。
これを乗り回したりしちゃうんですよね〜。
DUNEシリーズは、環境SFの走りだったかもしれませんね。
「風の谷のナウシカ」なんかDUNEの影響もあるんじゃないかなぁとも思ったり。そうそう、ナウシカには「王虫(出ない……虫が三つの漢字)」っていうのも出てきましたよね。
王虫→も決して気持ち良い生物じゃないね〜。
「高野聖」/泉鏡花

この作品にもいや〜んな生き物が出てきますね。ヒルの森を抜けなければならなくなって、巨大なヒルに体中食いつかれて必死で逃げるというシーンがあるんだけれど、これはダメだ〜。
ヒルはいかんですよ、ヒルは。
今でも、治療にヒルを使うことはあるそうですが、うわぁ、ダメだ。
「IT」/スティーヴン・キング
 ヒルからの連想。この作品にも、ある登場人物が体中ヒルに食いつかれて殺されるという場面が出てきます。うわぁもうダメだ。
ヒルからの連想。この作品にも、ある登場人物が体中ヒルに食いつかれて殺されるという場面が出てきます。うわぁもうダメだ。
それは、すべて、「デリー」という町に巣食った「IT」(そいつ)が作り出す幻影なんだけどね。
「IT」は、色んな姿で現れます。
登場人物が恐れを感じる物の姿で現れます。それは、ピエロであったり、狼男であったり、巨大な鳥であったり。
でも、最終的に出てくる姿は、巨大な(卵を抱えた)醜悪な雌蜘蛛の姿でした。
蜘蛛も大の苦手なんだよね。
しかも描写が粘液質でキモい。
どうも、スティーヴン・キングは、この作品を書くにあたって、H.P.ラヴクラフトや、エイリアンのデザインをしたギーガー(ITの蜘蛛の卵を踏み潰すシーンなんてエイリアンでしょう!)を意識していたんじゃないかなぁなどと思います。
これは「連想」シリーズになりそうですね。
ここでまた連想しました。
「H.P.ラヴクラフト」
ラヴクラフトの作品にも生理的にキモい生物が出てきます。
「インスマウスの影」あたりが一番良いのかしら。
生臭い、水棲の、うろこをもった、ぬめぬめとした……あーこれもダメだぁ。
とにかく、湿り気があって、ぬめぬめ系です。
それが人間の姿を借りて、というか、人間がそのような異形の物に変わっていってしまう恐怖を描いていたりもします。
「サンドキングス」/G.R.R.マーティン

これもイヤ〜な生き物が出てきます。そもそも、人間らしい存在の成れの果ては「人蛆」になって宗教的に崇め奉られるという設定。
誰が蛆になんてなりたいものですか! 手足ももがれてただうねうねとしているだけの存在(うねうねとすらできていないかも)。
でも作中人物たちはそれが至高のことであると信じて疑いませんし、享楽的な貴族のような生活を楽しみ、そうして、六本足の「グラウン」と呼ばれる汁気たっぷりの「肉」をうまそうに喰っているのですが、この「グラウン」は地中深くに生息しており、特殊な技能を持った「肉はこび」でしか持ってくることはできないんです。
作中人物たちは、とある事情から、自分たちの世界の地下に広がる「グラウン」達の巣穴に降りていくことになるのですが、この醜悪なこと。
なぜ、「肉はこび」だけがグラウンに喰われることなく、彼らの肉を持ち帰れるのでしょう?
この辺のストーリーテリングは、いつものG.R.R.マーティンです。とてもおもしろい。
でも、「グラウン」はキモいよ〜。
さて、今回は異色の展開で、しかも、「キモい」のばかり集めるという、ある意味非常に悪趣味なことをしてしまいましたが、ですが、それぞれの作品に魅力があるのも本当です。
「恐怖」の要素には様々なものが含まれていると思います。
「未知」であることの恐怖、逆に「知っている」ことの恐怖。ショッキング(急激な驚かしの意味)なことも恐怖を呼びます。
今回取り上げた、生理的に相容れない物の存在も一つの恐怖の形でしょう。
蒸し暑い夏の夜、ぞっとできることは請け合います。
読んでみますか?
096「死都ブリュージュ」/G.ローデンバック
 最愛の人を失った後、その人と瓜二つな人に出会えたとしたら?
最愛の人を失った後、その人と瓜二つな人に出会えたとしたら?
これがこの作品の基本的コンセプトです。
人は、誰でも、色んな意味で最愛の人を失い続けて生きているのかもしれませんね。
死別、破綻……
誰も、初めから別れを望んでなどいるわけではないのに、それでも、唐突に別れは訪れるのですよね。
そんな辛い別れを補ってくれるような、最愛の人と瓜二つの人が現れたとしたなら、みなさんはどうしますか?
それは、あまりにも辛すぎるから遠ざけるでしょうか?
それとも、やはり、失った人を取り戻したい一心から、その人に近づいていくのでしょうか?
この作品には何枚かのブリュージュの街を撮した写真が添えられています。
Amazonのレビューでは、「こんな写真が必要だったのか?」という意見もありますが、私は必須だと思いました。
主人公が、「そうした」街は、こんな街だったのとだと、それはローデンバックが訴えたかったことなのです。
文学作品に写真が添えられているものはいくつかあります。
「えふの本棚」で以前ご紹介した、ゼーバルトの「アウステルリッツ」もそうですし、ジュリアン・グラッグが幼少期過ごした街のことを老成してから描いた「ひとつの町のかたち」という作品にも写真が添えられています。
それらの写真にはとても訴えるものがあるように感じました。
そしてまた、「街」、そう、その場所が意味を持つ作品も沢山あります。
これも、以前ここでご紹介した、ロレンス・ダレルの「アレクサンドリア四重奏」などその最たるものでしょうか?
いずれもはかない、壊れやすい感性を感じます。
「死都ブリュージュ」も、そうした作品の系列に並ぶのではないでしょうか?
095「バーナム博物館」/スティーヴン・ミルハウザー

ミルハウザーの魅力は、おそらく、ファンタジックであり、凝っていて、少年の時の気持ちがあって、ちょっと恐いことかもしれません。
得意な舞台設定に、カーニバル(この辺はブラッドベリも同じですね)、遊園地、百貨店、色々な商品を陳列しているお店、本、などがありますが、本書のタイトルにもなっている作品「バーナム博物館」の博物館もいかにもミルハウザー好みの舞台設定ではないでしょうか。
本書は、ミルハウザーの中、短編集ですが、どの作品にもそんなテイストが詰め込まれているように思えます。
「アリスは、落ちながら」
不思議の国のアリスは、うさぎを追いかけているうちに「うさぎ穴」に落ちてしまうでしょ?
そうして、不思議な世界に行ってしまって、そこで、おかしなお茶会に出くわすんだよね。
ところで、その落ちる過程ってどんなだったか想像してみない?
あっという間に落ちちゃった? 本当に?
もし、もしも。ずっと落ち続けていたら?
いつまで経っても終わり無く落ち続けているとしたら?
「探偵ゲーム」
「探偵ゲーム」として取り上げられているこの作品のテーマともなっているボードゲームは、日本でも手に入ります。
古典的なボードゲームの「クルー」というものなんだよ。
この作品は、断片的に、このゲームに加わっている各人の心理や、このゲーム自体の解説、そうして、ゲームの中の登場人物の心理等々を描いていきます。
ゲームの進展に連れて、ゲーム中の登場人物と、その駒を操っている作中人物が入り交じって来て……
なかなか凝った造りの作品です。
「セピア色の絵はがき」
これも不思議な味わいの作品です。ある海岸沿いの小さな町に失意のまま逗留に来た男性が主人公です。
天候はあいにくの雨続きですが、別にここで何をするという目的も無かった主人公は、うらぶれた町にある土産物屋にぶらりと入ってみます。
店の奥には陰気そうな女主人が一人いるだけで、何とも居心地が悪い。
何も買わずに出て行くことがはばかられた主人公は、古い絵はがきを1枚買って帰るのですが……
「バーナム博物館」
ミルハウザーお得意のテーマです。ミルハウザーは、巨大デパート、遊園地等の施設を舞台にして、その複雑さ、巨大さ、変容の様などを描いた作品が何作もありますが、この作品もそれらの流れを汲むものでしょう。
舞台となるのはいつも改修工事をしている不思議な博物館です。
その博物館には、到底有り得ないような物が多数展示されています(人魚が泳ぐ池とか空飛ぶ絨毯とか)。
訪れる客は、迷宮のような博物館を歩き回り、時に出口を見失いながらその存在を受容してきました。
あぁ、なんてミルハウザーチックなんでしょう。
他3作を収録した短編集ですが、どれも不思議な味わいの作品ばかり。こういうテイストがお好きな方にはお勧めです。
094「ティンブクトゥ」/ポール・オースター

ウィリーは、もう持たない。今にも死にそうなんだ。
ウィリーというのは、僕のご主人様。この後は、「主人」と書くことにする。
主人に名前をつけられた僕のことを、みんなは汚らしい雑種の犬と呼ぶ。
「ミスター・ボーン」というのは、主人が僕につけてくれた僕の名前だ。
僕は、もう、長いこと、主人と一緒に、喰うや喰わずの旅を続けてきた。
主人は、何度も血を吐いた。
それは、主人が、まだ少しはまともだった頃、親の遺産を蕩尽して、酒と麻薬に溺れたどうしようもない日々を過ごしたせいなんだ。
そのことも、僕は知っている。
主人は、自称「詩人」だ。
酒と麻薬に溺れていながらも、時々、狂ったように書き続けていた。
その書きためたノートを持って二人で旅に出たんだ。
主人は多弁だ。
狂ったように話し続ける。
僕が犬だからといって、人間の言葉が分からないなんて思わないで欲しい。
全て理解できているんだ。
ただ、言葉を返そうと思っても、犬の舌では、人間のような発音はできなくて、一生懸命、ウォオ、アゥオとやってみるのだけれど、人間の言葉にならないだけのこと。
しゃべれないからといって、人間の言葉が分からないとは思って欲しくないよ。
全部分かってるんだ。
主人がまだ学生だった頃、主人をただ一人認めてくれた女性の先生がいたんだそうだ。
一時期、文通もしていたそうだ(主人はそう話していた)。
主人も、自分がダメになったことはよくわかっているようだ。
僕のことも気にかけてくれている。
「この詩と、お前を預けられるのは彼女しかいないからな」って、何度も言ってた。
そんなこと言えないだろうにと思う。
だって、もう十何年も彼女との文通は途絶えたままなんだよ。
最後に彼女から来た住所に行ったってそこに彼女がいるとは思えない。
金も無いから、ヒッチハイクや歩きづめの行程だよ。
それも、主人は血を吐きながら。
他人(ひと)は、それを「自業自得」と言うのだろう。
でも、主人は、僕が、人の言葉を理解しているということをわかってくれた一人だけの人間なんだ。
主人は、何度も僕に言ったよ。
「中華料理屋は気を付けろ。あそこは犬を捕まえてその肉を料理に出すぞ。俺がくたばったら、お前はそんなところに行っちゃダメだ。つかまって喰われちまうぞ。」ってね。
それから……
「ティンブクトゥっていう場所があるんだ。そこはとっても遠い所だけれど、良い所だぞ。俺はもうすぐくたばるが、そこに行くぞ。ミスター・ボーン、お前も来いよ。そこに行けば何でも願い事が叶うんだぞ。」って。
「ティンブクトゥかぁ」って、僕は思った。
何でも願い事が叶うのなら、僕の人間の言葉にならない声を、どうか人間にわかってもらえる声にしてもらえたらなぁって思った。
これが、「ティンブクトゥ」の、ほんの出だしの感じです。
主人公のダメ人間ウィリーと、汚らしい雑種犬のミスター・ボーンとのやりとりの一部だけご紹介しました。
書いたとおり、ミスター・ボーンは、人間の言葉を完全に理解できます。
それは、以前書いた別のお話、「ウォッチャーズ」の「アイン」のようではありませんか。
ただ、悲しいことに、犬は、人間の言葉を理解できても、自分の感情を人間に伝えるすべがありません。
もちろん、それを分かることができる人間もいます。
ですが、全ての人間がそうできるわけではないのですよね。
それでも、犬は健気に人間に尽くすのですね(涙)。
タイトルの「ティンブクトゥ」という言葉はご存じでしたか?
私は、全く知りませんでした。
ええ、この小説を読了してさらに相当の時間が経った後でも知りませんでした。
主人公の、ウィリーが勝手に作った言葉とばかり思っていたのですが、そうではありませんでした。
以前からある英語の言葉でした。
「遠い場所」みたいな意味で良いのかな?
ポール・オースターは、どうしても、喉に小骨がひっかかるような感じがして、必ずしも全面的に好きな作家さんではないのですが、でも、わんこが出てくるのなら話は別です。
とても短い小説です。
すぐに読み切れるので、わんこ好きな方は読んでごらん。
093「ホフマン短編集」/E.T.A.ホフマン
E.T.A.ホフマンは、ドイツの小説家にして作曲家。ポーと並ぶ幻想文学の祖と言われます(ポーの方がホフマンの影響を受けたと言われていますが)。
チャイコフスキーの「くるみ割り人形」の原作である「クルミ割り人形とネズミの王様」の作者であり、その他著名な作品を多数残していますが、最近はあまり読まれないのかもしれませんね。
今回ご紹介する「ホフマン短編集」も、有名な「砂男」が収録されているのに絶版です(私は、「砂男」を読みたいがために古書で買いました)。
収録作をご紹介しましょう。
「クレスペル顧問官」
とても風変わりなクレスペル顧問官は、ヴァイオリンの名手であり、また、自らヴァイオリンを製作していました。クレスペル顧問官と知り合いになった主人公は、顧問官の娘であるアントニエに恋をしてしまいます。人々の噂では、アントニエは絶世の美声の持ち主だとか。しかし、どんなに乞い願っても、アントニエは歌ってはくれませんでした。何とかしてアントニエの美声を聞きたいと願った主人公は、機を見計らってピアノを弾き出し、アントニエも今にも歌い出しそうになったのですが、たちまちクレスペル顧問官が間に割って入り、演奏を止めさせ、主人公を家から叩き出してしまいました。
夢やぶれた主人公は、アントニエをを諦め、就職のために町を離れて行ったのです。2年後、町に戻った主人公は、アントニエが亡くなったことを知ります。そして、クレスペル顧問官とアントニエの秘密も知ることになるのですが、その秘密とは……
「G町のジュスイット教会」
旅の途中、G町で足止めを喰った主人公は、その町のジュスイット教団附属の学院で教鞭を執っていた教授と知り合いになり、教会を案内してもらいました。
丁度、教会は修復中で、壁などに着色中のベルトルトという画家とも知り合いになります。
その仕事ぶりに感嘆した主人公は、ベルトルトに対し、これほどの腕を持っているのに何故ペンキ屋のような仕事をしているのかと尋ねますが、ヘルベルトは答えようとしません。
ヘルベルトに興味を持った主人公は、教授にヘルベルトのことをしつこく尋ねると、教授は教会に飾ってあった一枚の絵を見せてくれました。それは素晴らしい出来映えでしたが、未完成のままであり、また、ヘルベルトが教会で仕事をする時には必ず布がかけてあったのです。教授の話によれば、この作品はヘルベルトの最後の作品であり、彼は、この絵を見たとたん、大声で叫び声を上げると気を失ってしまったのだとか。
ますますヘルベルトに興味を持った主人公は、さらに教授に食い下がったところ、ヘルベルトの過去を書いたというノートを手渡してくれました。
そのノートを読んでみると……
「ファールンの鉱山」
航海中に最愛の母親を失った船乗りの物語です。ようやく上陸し、船員達は浮かれ騒いでいましたが、主人公は母を亡くしたことを悲しみ、また、そばにいてやれなかったことを悔やみ悲しみに沈んでいました。もう船になど乗りたくもないと思っていたところ、不思議な老人が話しかけてきて、是非鉱夫になれと勧め、鉱山の魅力を熱く語って聞かせました。
その気になった主人公は、老人から聞いたファールン鉱山に行ってみたのですが、鉱山の様子を見た途端恐ろしくなり、あんな地底の奥底まで降りていくのはまっぴらだと翻意し、もと来た道を戻り始めました。
その時、正装した鉱夫達の一団と出くわしたのです。鉱夫達は仕事に一区切りがついたこの日、鉱区所有者の屋敷を訪れ、祝いの宴に招かれたところでした。
立派な身なりをした鉱区所有者は、鉱夫一人一人と握手をし、屋敷に招き入れ、素晴らしいごちそうを振る舞ったのでした。そして、その美しい一人娘のユッラが鉱夫達にファールン特産の見事なビールを注いで回っていました。
ユッラに一目惚れした主人公は、屋敷の入り口に呆然と佇み、中の様子を見つめていたところ、ユッラから中に入って一緒に楽しんでいって下さいと声をかけられます。
自分は鉱夫となることを諦めた船乗りに過ぎないと思い、ためらっていたところ、鉱区所有者がやってきて、どういう用向きでいらっしゃったのかと尋ねました。
主人公は、母を亡くし、船乗りに嫌気がさし、鉱夫となろうと思ってファールンに来たと話しました。鉱区所有者は、それならば是非ここで働いてみないかと誘ってくれたのです。
主人公は、少し前までは、あれほど嫌だと思っていたのに、何故か自然と鉱夫として働かせて欲しいと申し出てしまったのです。
気をよくした鉱区所有者は、主人公を屋敷に招き入れ、他の鉱夫達に新しい仲間だと紹介し、ごちそうを振る舞ってくれました。
主人公は、非常に真面目に働きました。いつか認めてもらい、ユッラと結ばれることができたらと願いつつ。ユッラもそんな主人公に惹かれていき、また、ユッラの父親である鉱区所有者も好もしく見守っていました。
めきめき腕を上げた主人公は、今日も仕事に精を出していたところ、鉱山の奥で突然あの老人と出くわしたのです。一体どこから現れたのでしょう?
老人は、「ユッラなどに恋してはいかん、お前はあんな女ごときのために鉱山の喜びを捨てるのか、ここには莫大な鉱脈が眠っているというのに誰一人気付いておらん、鉱山の女神こそを崇めよ。」と言います。
主人公は、「自分の雇い主のために懸命に働いて何が悪い、ユッラのどこが悪い。」と怒ったところ、老人は岩の間に消えて行ってしまいました。
その後……
「砂男」
子供の頃、親に聞かされた恐い話がいつまでも心に残っていることってありませんか?
主人公もそんな男の子でした。毎晩9時になると寝るように言われ、寝ようとしないと「砂男」がやって来て目玉を取ってしまうぞと脅かされていたのです。
ある夜もそんな話をされていた時、何者かが階段を上ってくる足音を聞いてしまったのです。「砂男」だ!
それ以来、主人公は、「砂男」のことが心から離れなくなってしまったのでした。
大きくなってもなお、「砂男」のことが気になり続けており、実際に何度もあの階段を上る足音を聞いたことがありましたし、また、その後、隣の父の部屋から嫌な匂いが漂ってくることもありました。
どうしても「砂男」の正体を見極めてやろうと思った主人公は、あの足音が聞こえ始めた夜、隙をみて素早く父の部屋の物陰に忍び込んだのでした。
すると父の部屋にやって来たのは、時々食事にやってくる弁護士のコッペリウスだったのです。コッペリウスは見るからにいやらしい男で、子供達の嫌がることばかりわざとしますし、それを楽しんでいるような男でしたから、母親も子供達も毛嫌いしていたのですが、父親だけはコッペリウスのことを丁寧に扱っていたのでした。
この夜も、父親はやってきたコッペリウスに丁寧におじぎをしていました。コッペリウスは「さっそく始めるぞ」と言うなり、父親と二人で作り戸棚の奥に隠されていた炉に火を入れ、その中から何かを取り出すとしきりにその塊を叩き始めたのでした。
「目玉よ出てこい、目玉よ出てこい」。コッペリウスは低くうなるように言い続けます。
その様子が余りに恐ろしかったため、主人公は思わず声を上げてしまい、コッペリウスに見つかってしまいます。主人公はコッペリウスに捕まってしまいました。
コッペリウスは、「これで目玉が一組揃ったじゃないか」と言ったところ、父親は「お願いします。その子の目だけは勘弁して下さい」と嘆願していました。
主人公は、恐ろしさのあまり気を失ってしまい、気がつくとベッドに寝かされていました。
それから1年ほどしたある日、それまで姿を見せなかったコッペリウスが家にやってきました。あの階段を上る足音が聞こえ始めたのです。
父親は、母親に対して、「早く子供達を子供部屋に行かせるんだ」と言い立てます。子供達を部屋から出しながら、母親も「どうしても会わなければならないのですか?」と父親に問いかけます。
父親は、「今日が最後だ。これで最後なんだよ。」と言います。
この物語は冒頭のこのエピソードでも分かるように「目」が全体を貫くモチーフとなっています。
成人した主人公の前には、コッペリウスそっくりの男が現れ、眼鏡や望遠鏡などを売りつけようとします(いずれも「目」にまつわる物です)。
早くこの男を追い出したい主人公は望遠鏡を買い求めます。そうして、何気なく部屋の窓からその望遠鏡を覗くと何とも美しい女性が見えるではないですか。
主人公はこの女性に恋してしまうのですが……
本書には、その他、町中にある不思議な廃屋を舞台にした幽霊譚?とでも言うような「廃屋」と、窓から見える人々の様を色々に解釈して楽しむ従兄弟達のお話である「隅の窓」が収録されています。
いずれの作品も、幻想的なお話です。
こういったお話も、たまにはいかがですか?
092「紅はこべ」/バロネス・オルツィ

まるで「ベル薔薇」のような、あるいはシャーウッドの森から姿を見せる「ロビン・フッド」の様な、はたまた颯爽と登場する「怪傑ゾロ」のような、そんな印象を持ちました。
時は、フランス革命のまっただ中。ロベスピエールやダントン率いる共和主義者は、長い間自分たちを苦しめてきた貴族達を徹底的に血祭りにあげていきます。
それはある意味狂熱的であり、人々は血を見ずしては収まりがつかなくなっているかのよう。
毎日何百人もの貴族達(女性や子供たちも含めて)が処刑されていました。
貴族達は何とかパリから逃れようとしますが、街道の要所には共和主義者達が陣取っており、そこをすり抜けようとする貴族達を容赦なく処刑場に送り込みます。
この処刑に使われたのが、かの「ギロチン」です。
今の私たちの目からすると、何とも残酷な処刑具としか見えないのですが、実はこれ、内科医だったギヨタン(これがギロチンという名前の由来です)が極めて人道的な理由から設計した処刑具だったんですね。
苦痛もなく、一瞬にして首を切り落とすことができる器具として。
ドーヴァー海峡を挟んだ対岸のイギリスでは、フランスのこの狂熱の様を苦々しく見ていました。
もちろん、王制を敷いているイギリス(現在もエリザベス女王をいだいていますよね)としては、王を廃してギロチンにかけるようなフランスを容認できるはずもなく(それは、当時のヨーロッパ諸国が全てそうで、自国への革命の波及をひどく恐れ、警戒もしていたんですね)。
かと言って、まともな政治が期待できない当時の狂乱のフランスに対して、外交的に何を言えるわけもなく、時の英ピット政権はこの惨状を黙視するしかなかったのです。
そこで、義勇の人たちが現れます。
首領を含めて20人からなるイギリス人達の組織なのですが、死を目前にしているフランス貴族達を、厳重な警戒網を破ってイギリスに渡らせることを繰り返していました。
フランス共和主義者達は怒りに燃えたぎります。
まんまと門をすり抜けられてしまった、その門を担当していた軍曹をもギロチン送りにしてしまうほどに。
彼等は、いつもメモを残して行きました。
「○○公爵をお連れする」という予告メモですね。
そのメモには、署名代わりに、星形の花が書かれていました。
それが「紅はこべ」の花でした。
救出側のイギリスは、紅はこべの活躍に拍手喝采です。
少しでも多くの人たちを助けるんだ! そんな感情がイギリス側にはあったと描かれています。
フランスだって黙っていません。何とか「紅はこべ」を引っ捕らえろということで、全権を委ねた狡猾なショーヴランをイギリスに送り込みます。
ショーヴランが目をつけたのは、表面上は共和主義者を装っているけれどどうやら「紅はこべ」と連動してフランス貴族達の救出にあたっていると思われるアルマン・サン・ジュストの妹であり、ヨーロッパ随一の才媛と言われていたマルグリートでした(フランス人ですよ)。
彼女は既に、イギリスの大富豪、サー・パーシー・ブレイクニーに嫁いでいました。
この旦那のパーシー・ブレイクニーが、またとんでもな男で。
伊達男を絵に描いたような美丈夫ではあるのですが、まぁまるで間抜け。
人々は、彼の財力や地位があるので面と向かって何も言いませんが、陰では揶揄しているんです。
加えて、何故、欧州一の才媛たるマルグリートが、よりにもよって抜け作パーシー・ブレイクニーの妻になったんだ?と口さがない噂話ばかり。
金や地位目当てだったのか? とかね。
でもね、マルグリートにはそれなりの愛情が、過去にはあったんです。
結婚する頃には、それはそれは、パーシー・ブレイクニーは誠実で熱烈な愛情をマルグリートに捧げたのだとか。
並み居る求婚者を退けて、パーシー・ブレイクニーを選んだのは、まさにその情熱的な愛情にほだされてのことだったんです。
二人は結婚したのですが、ある時、マルグリートは、噂に聞いた話を何の気なく人々の前で話してしまったことがありました。
それは、フランスのとある貴族が、フランス革命に反対していて、オーストリアと結託して革命政府を転覆させようとしているという話。
マルグリートとしては、悪意があって話したことではなかったのですが、それがきっかけで当の貴族はギロチンにかけられ、一族全員が処刑されてしまったんです。
フランスの共和主義者の人々は、この「悪事」を告発したマルグリートを口々に誉め称えました。 さすが欧州一の才媛だと。
イギリス人の妻になっても祖国フランスの革命を支持しているのだと。
でも、その時から、パーシー・ブレイクニーは、マルグリートに対する態度が変わってしまい、マルグリートも夫の心変わりと捉え、 夫婦仲は冷え込んで行ったのでした
夫婦仲は冷え込んで行ったのでした
こんな「ロマンス」も織り込みながら、さあ、「紅はこべ」はフランス貴族達を救出し続けられるのか?
あるいは、狡猾なショーヴランの毒牙にかかって捕縛されてしまうのか。
実際、ショーヴランの追求の手は徐々に「紅はこべ」本人に迫ってきます(そこに再度利用されてしまうマルグリート)。
こんなお話が「紅はこべ」なのでした。
ところで、「紅はこべ」って、どんな花なんだろうって思いませんか?
星形の署名に描かれている花ってどんな花なんだろうって。
こんな花だそうですよ。
091「ウサギ料理は殺しの味」/ピエール・シニアック

何と奇妙な味の小説でしょう。本書は、一応ミステリということになるんですけれどね。
主人公のセヴラン・シャンフィエは、元警察官で、現在はしがない私立探偵をやっています。今回もとある調査のために雨の夜、おんぼろ車でフランスの郊外を走っていました。「今夜あるいは明日までに目的の町までたどり着いてボスに報告を上げないと、本気で怒鳴り散らされるなぁ」などと考えながら。
ところが、あ〜あ! ついに車が故障してしまい、仕方なく一番近くの町まで修理を依頼しに歩き出します。
ずぶ濡れになりながら、結構な距離を歩いた後、ようやく見えてきた最初の店に入ると、ラム酒入りカフェを注文するのでした。
店のマダムに町の修理工場を教えてもらい、何とか修理工場のおやじに会って修理を依頼したところ、4〜5日かかると言われてしまう有様。
仕方なく事務所のボスにその旨電話をしたところ、案の定、すぐにでもクビにされそうな勢いで怒鳴りつけられたのでした……ため息。
そうは言っても車を修理してもらわなければどうにもならないわけで、取りあえず町のホテルに宿泊することにしました。
することもなく手持ち無沙汰のシャンフィエは、「我が家の1週間」なる地元新聞を読み始めました。
そうしたところ、こんな田舎町で殺人事件が既に2件も起きていることが分かりました。被害者はいずれも妙齢の女性で、死体のそばには扇が残されていたとのこと。
これはどうにもおかしいと思い始めたシャンフィエは、探偵事務所もほとんどクビになりそうだし、ここは一つこの未解決の殺人事件を捜査して犯人を捜し出し、名前をあげるのも悪くないなどと考えます。
もう、本来の探偵業なんて放り出して町に滞在しつつ、殺人事件の捜査に乗り出すのですが、という出だしのお話です。
シャンフィエは、町に2つだけあるビストロのうち、味がよいと言われている「三本のナイフ」という店の常連となり、シェフである店主とも親しくなります。またこの店の料理が評判通り美味でして、特に木曜のディナーに出る「狩人風ウサギ料理」は絶品なのでした。
ところが、特段の理由は無いのに、実はシェフはこのウサギ料理が大嫌いで、できるものなら作りたくも無いと考えているとか。美味しいのになぁ。
色々調べてみると、この町は、まぁ、田舎町にしては結構な商店があったり、映画センターもあれば、色々な文化活動が行われていること、件の「我が家の1週間」という地方新聞もきちんと発行されていること、娼館までもがあることなどが分かってきます。
そうこうしているうちにまた例の扇の殺人事件が発生してしまいます。 被害者の接点もよく分かりません。
一体誰が何のために?
さらに、連続殺人は続いていきます。
どうやら、この連続殺人は、必ず木曜の夜に行われるらしいことも分かってきます。
そして、「三本のナイフ」亭の主人のもとには、「殺人を止めたかったらウサギ料理を出すな。」という謎の手紙が届けられたのでした。
な〜んで「ウサギ料理」と殺人が関係あるの?
驚愕の設定ですね。
最終的には謎はすべて解決されるのですが、「うっそ〜!」という結末に口があんぐり開いたまま……。
通常の推理小説だと思って読むと、結末で本を床に叩きつける人も出て来そうなほど。
私も、最初は普通の推理小説のつもりで読み出したのですが、段々雰囲気が怪しくなってきて……そして、あぁ。
これ、作者さん一流のユーモアですね。
本書は永らく絶版だったところ、この度復刊されました。
とある書評サイトによれば、「あれはすごかったね。」と語りぐさになっていた作品だとか。
この機会に読んでみますか? 怒っちゃっても責任は持てませんが(笑)。
創元推理文庫 ISBN978-4-488-280402-2
090「[ウィジェット]と[ワジェット]とボフ」/シオドア・スタージョン
 スタージョンには、切なさと、少年の気持ちがある、って以前書きましたが、この中・短編集も思いっ切りそういう要素満載です。
スタージョンには、切なさと、少年の気持ちがある、って以前書きましたが、この中・短編集も思いっ切りそういう要素満載です。
日本で編まれた作品集です。
「帰り道」
家出してやる、家出してやるって、男の子なら一度は考えたことあるんじゃないかな。
家を出て行ったって、何とかなる。やってみせる、って考えちゃうんだよね。
でも、多くはそれができなくて、いや、実行に移すことすらできなくて、年をとってしまうのでしょうね。
「午砲」
「男の子」というものは、一度はヒーローに憧れるのでしょうね。それは、TVや映画に出てくるタフ・ガイで、素敵な女の子がみんなたなびくような。
それでも、現実っていうのは、そんなことは許してくれないわけで、劣等感にさいなまれつつも、自分の隣にいる、決して美人とはいえない、いつもおどおどしている女の子に辛く当たります(だって、ヒーローだったら、こんな娘じゃなくて、もっといかした娘が隣にいるはずじゃない)。
でも、自分でも分かってるんです。駄目な俺にはお似合いだって。
そんな彼でしたが、何がどうなったのやら一発やらかしてしまいました。
……もし、そういうヒーローになれたら、こんなちんくしゃな、しゃくに障る娘なんかもう相手にしない?
「必要」
とても切ない中編です。
人は、良かれと思ってしていることの中に、とても誰かを傷つけていることが紛れていても、容易には気付かないのかも知れません。
そのことを、責めるのは簡単。でも、それじゃ、何も解決しない。
本当は、傷ついた、と言っている人にだって問題があるのでしょう。
それでも、「必要」だと、気付いたなら幸せなのでしょうね。
「解除反応」
スタージョンは、「SF作家」というくくりに入れられて紹介されています。とは言え、上記3作はさほどにはSFなんかじゃありません(「午砲」なんてふつーの小説です)。
「解除反応」は、まぁSFらしいと言えばそういう作品なのですが、そこはスタージョン。
訳も分からず、ブルドーザーに乗っている自分に気がつくところから物語りはは始まります。
何か、工事をしなければならないみたいなのだけれど、さっぱり訳が分からない。
でも、手は覚えていて、すらすらと作業を継続できたりします。一体どうなっているの?
あぁ、結末は、やっぱり切なくさせちゃうのでした。
「火星人と能なし」
ちょっとユーモラスな作品。少年の頃、大好きになった女の子って、素敵だったんです。それは、とっても。
現実は、そうじゃなかったとしても。例えそれが、とんでもない女の子だったとしても、恋は盲目?
でね、この作品には、味のある父親が出てきたりしちゃいます。
何とも、良い味の作品です。
「[ウィジェット]と[ワジェット]とボフ」
不思議なタイトルの作品ですが、本書の表題作。一応、設定はSFですが、中身は切なくなるお話の中編。
人は、みんな弱みを抱えているですよね。でも、それがどういう弱みなのか、自分のどこがいけないのかなんて、さっぱり分からない。
「何で?」、「じゃあどうしてそうしたの?」、「それで?」……っていう具合にどんどん突き詰めていったら、そうしたらどうなっちゃうのかな?
この作品には、少年らしさ(というよりはもっと幼かった頃の純粋さ)も描かれます。
趣味はそれぞれだと思うのですけれど、私としては、スタージョン、大好きなので、未読の方には是非オススメしたいきもちなのでした。
089「タフの方舟」/G.R.R.マーティン
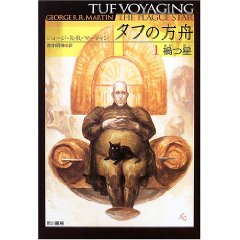
またまた、G・R・R・マーティンのご紹介になっちゃいますが、だって面白いんですもの。
タフは宇宙商人でございます。おんぼろではございますが、「良い品をお安くお分けする豊饒の角」号に、猫2匹と乗り込んで商売をいたしております。
身長は2メートルを超え、横幅もたっぷりな、禿頭、色白、無表情な男であります(左の表紙絵のイメージがぴったり)。
あるとき、「禍つ星(まがつぼし)」と呼ばれていた天体まで、怪し気な人達を乗せていくという御商談にあずかったのでございます。
怪し気などというと失礼でございましょうか。
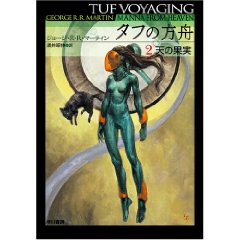
この星がEECの胚種船であることを発見した教授達とそのボディーガードの様な御一行様でございました。
はい。「禍つ星」とは呼ばれていましたが、実はその実体は、過去の失われたテクノロジーが満載された旧地球連邦帝国環境工学兵団(EEC)の胚種船(全長30キロメートルという超巨大船)だったのでございます。
船の中には、幾万もの星々から収集された沢山の生命サンプル(DNA)が満載され、それを甦らせるテクノロジーも積載されていたのでございます。
兵器としての船でございましたから、まさに、敵星に対して生物化学攻撃をしかけるために作られたものでございました。
このような船を入手できますれば、それこそ一攫千金でございます。
教授達が血眼になるのも無理はございません。
というわけで、第1作の「禍つ星」は、この胚種船(方舟と呼ばれています)を奪取するまでのお話です。
あ、上記の語り口が気になりましたか? タフはこんな感じで話すんですね〜。
ネタばれになっちゃいますが、この方舟は、結局の所、タフが手に入れることになってしまい、タフはその後、商人をやめて「環境エンジニアリング」として星々を巡ることになります。
色々な星で、様々な出来事に遭遇しつつ、その星が抱えている難題を、方舟の持つ力を使って解決していくというお話。
SFですから、そういうテイストのお話になりますが、、物語としてもとても面白いです。
作者は、現在は別のシリーズを執筆中とのことですが、このタフシリーズにも愛着があるようで、続編を書きたいとの思いもあるとか。
是非、書いて頂きたいものです。
「タフの方舟1 禍つ星」
「タフの方舟2 天の果実」
ハヤカワSF文庫 ISBN978-4-15-011511-1,ISBN4-15-011516-8
088「WILD CARDS」/G.R.R.マーティン編
 またまた再読シリーズからのご紹介です(今では絶版のようなのでごめんなさいなのですが、とても面白いので)。
またまた再読シリーズからのご紹介です(今では絶版のようなのでごめんなさいなのですが、とても面白いので)。
時は、1946年9月19日。不審な飛行船がブロードウェイ上空に浮かび、米政府に対して巨額の「身代金」を要求してきます(今で言うなら、テロリストですかね)。刃向かうのなら目に物見せてやるみたいな脅し文句と共に。
そこで登場したのが「ジェット・ボーイ」です。彼は、第二次世界大戦で驚異的な活動を見せたヒーローです。当時としては卓越したテクノロジーを誇ったジェット機を操る非正規のヒーロー。軍に所属してはいないのですが、多くの戦果をあげていました。とある戦いで行方不明になっていたんですが、実は生還していたのです。
米正規の空軍も不審な飛行船に攻撃をかけますが、高度が高すぎて届かないのです。この危機にはジェット・ボーイに頼るしかない!
ジェット・ボーイは愛機JB-1を操り、空高く舞い上がります。それでも敵の高度は高い!
かろうじて届く砲撃を加えつつ、最後には飛行船に体当たり攻撃を仕掛けます。自らの命と引き替えに飛行船を墜落させるのですが……
 飛行船のテロリスト達が頼りにしていたのは、偶然手に入れたとある「爆弾」のようなもの。テロリスト達もその実体はまるで理解できていないのだけれど、それが壊滅的な被害を及ぼすということは仲間の身をもって分かっていました。
飛行船のテロリスト達が頼りにしていたのは、偶然手に入れたとある「爆弾」のようなもの。テロリスト達もその実体はまるで理解できていないのだけれど、それが壊滅的な被害を及ぼすということは仲間の身をもって分かっていました。
こいつを一発ぶっ放せば(それで手札は無くなるのだけれど)、その悲惨な結果に恐れて、政府は要求を呑むだろうと考えたわけですね。もう、最初から投下するつもりだったんです。
いきさつはテロリスト達の思惑とは違うけれど、そしてテロリスト達も死んじゃうけれど、でも、その「爆弾」は高々度上空で破裂し、その中の「物」は気流に乗って世界中にばらまかれたのでした。

中に入っていた物は何?
テロリスト達が持っていた「爆弾」とおぼしき物の中に入っていたのは、タキス星で作られたウィルスでした。
タキス人は、自分たちのさらなる生態向上を考えていて、それに資するようなウィルスを開発していたのですね。様々な特殊能力を誘発するようなウィルスとでも言えば良いでしょうか。でも、まだ開発途上なので、「臨床実験」が必要でした。とは言え、副作用が恐ろしすぎるので、自分たちで試すわけにもいかず、タキス人と生体構造がほとんど同じ地球人をモルモットに選んだというわけです。
そのためにウィルスを仕込んだ「爆弾」を持って地球まで遠路はるばるやってきたわけですが、これって地球人から見たらすっごくひどい話じゃない? 僕た ちはモルモットかい!ですよね〜
ちはモルモットかい!ですよね〜
そのとんでも無さに反抗するタキス人もいました。後に、地球上では「Dr.タキオン」と呼ばれることになるタキス人ですが、彼はどうしてもこのやり方に納得できず、単身宇宙船を操って地球に飛来します。
タキオンの努力も虚しく、ウィルスが入ったカプセルはテロリスト達に奪われ、結局地球全体にばらまかれてしまったのです。
この日が「ワイルド・カード・デイ」となりました。
この猛烈なウィルスの効果により、多くの地球人は異形な物となり死んでいきました。
感染した100人のうち、90人は「黒の女王」のカードを引き、死に絶えます(普通に死ねないのですよ。恐ろしいカタチに変わった挙げ句、苦しみながら、ある人は溶けてし
まい、ある人は爆発してしまうような、そんな悲惨な死に様)。
 生き残った10人のうち、9人は、人間とも思えないような異形の物に変化してしまいます(それは見るもおぞましいような)。この騒ぎの後、生き残った彼等は「ジョーカー」と呼ばれ、迫害されてしまいます。こんな身体になって生きていくよりも「黒の女王」を引いて死んでしまった方がどれだけ良かったかと思ったジョーカーも沢山いたことでしょう。
生き残った10人のうち、9人は、人間とも思えないような異形の物に変化してしまいます(それは見るもおぞましいような)。この騒ぎの後、生き残った彼等は「ジョーカー」と呼ばれ、迫害されてしまいます。こんな身体になって生きていくよりも「黒の女王」を引いて死んでしまった方がどれだけ良かったかと思ったジョーカーも沢山いたことでしょう。
そして、最後の1人は「エース」のカードを引き当てた人たちです。
特殊能力を得る事に成功したわけですね(タキス人達は、この能力を開発しようとしてワイルド・カード・ウィルスを作ったのですが、実際に地球人をモルモットにして試してみたところ効率悪すぎ)。
エース登場!
 最初に人々の前に姿を現したエースは「タートル」でした。
最初に人々の前に姿を現したエースは「タートル」でした。
彼は、シャイな冴えない男の子でしたが、テレキネシス(思考で物体を操れる能力)を得たのですね。
でも、引っ込み思案で、とても生身でその能力を使えるような胆力も持ち合わせていませんでした。
ワイルド・カード・デイ以後の社会は混乱の極みです。暴力がまかり通り、ジョーカーとなってしまった者達は達は、その外見から理不尽に迫害され……それでも彼等なりのコミュニティーを形成し、それがまた逆に一つの勢力を形成していたりして。
あちこちで暴動が起こり収まりがつきません。
その混乱時期に登場したエースが「タートル」だったのです。
彼は、友達の協力も得て、スクラップ置き場からポンコツの車を選び出し、それに軍払い下げの装甲を施し、いくつかのセンサーを付けて、その「甲羅」の中に閉じこもって登場します。
念じれば、そのポンコツ車は空高く飛び上がることができます。
「タートル」はその力を使い、混乱した社会を沈静化することに協力し始めます。
暴徒の群れに出会えば、テレキネシスで穏やかに暴動の波を押さえ込みますし、 暴漢が女性を襲う場面に出くわせば暴漢を空高く舞い上げてノックダウンしてしまいます。
シャイな彼は決してポンコツ車から出てくることはありませんでした。エースなのにね。
それで、「タートル」はきっと異形のジョーカーなのだという噂がたちまち広がります(ジョーカーは、見た目は異形になっちゃうのだけれど、中には特殊能力を得た人もいます)。
これは、ジョーカー達にとっても、「タートル」は迫害されている自分たちの仲間だ、仲間がヒーローになったんだという感情を巻き起こし、熱烈な支持を受けることになります。
「タートル」自身の中身は、相変わらず冴えない男なんですけれどね。
Four Aces
エース達の力を使おうとした人が現れました。それは極めて政治的ではありましたが、対独裁主義ということで集まった4人のエースがいました。
ジャック・ブローンは鋼鉄の身体と百人力を持ったエース。アール・サンダスンは空を飛ぶ黒人のエース。ディビッド・ハースタインは、何て言えばいいかな、催眠術でもないのだけれど、その場、その人の思考を自由に操れる能力を持ったエース(作中ではフェロモンみたいな感じとして描写されています)。彼は使者(エンヴォイ)として働きます。そして、最後はブライズ・ヴァン・レンスラーという美貌の人妻さん(夫が政治家で、まぁ、げすな奴なんですわ。それで、愛情は冷め切っていました)。彼女はどんな人の思考でもすべて自分のものとしてしまえる能力がありました。
そうそう、タキオンは、とっても女好きなのですが(それはタキス星ではあったりまえのことだそうですが)、ブライズと本気で愛し合うようになっちゃったんですね。
4人のエースは素晴らしく活躍したのですが、その後、エース達に対する弾圧が始まります。並(ナット)の人たちにとっては、エースは脅威でもあったのかもしれません。
政治的に追いつめられて、査問委員会にまでかけられてしまいます。
ディビッド・ハースタインは、査問委員会の空気を変えてしまい、いわば無罪評決を言わせて意気揚々と引き上げますが、彼の能力の届く範囲は限定されており、査問委員会の部屋から出た途端に、件の評決は覆されて拘禁されてしまいます。
アールは、そもそもこんな茶番の査問委員会を相手にするつもりはなく、どこかに飛んで行ってしまいます(その後、消息不明)。
悲惨だったのはジャックかもね。彼は強制された挙げ句、ブライズや他の3人のことも話してしまい、それと引き替えに自由を得ます。ですが、その後、裏切り者の「ユダ」と呼ばれ続け、姿を消してしまいます。
ブライズも可哀想です。査問委員会で良いようにいたぶられた挙げ句、神経を病んでしまい、精神病院に収容されて亡くなります。
愛人だったタキオンはその後廃人になるくらいまで行きましたが、何とか立ち直り、ジョーカー達を治療する病院を造り、基金ももらえて、その病院にブライズの名前をつけました。
次のエース達
新たなエース達も登場してきます。ヨガの極意を身につけ、時を止め、空間を歪ませるフォーチュネイト。彼はゲイシャ置き場を経営する、まぁ、ポン引きなのだけれど、女性との交わりからパワーを得るというとんでもな奴。
エースじゃないのだけれど、強力な存在も出てきます。完全なアンドロイドで破壊的な力を持つモジュラー・マン。彼は人間的な感情とペニスも持っちゃってるの(彼を作ったのはまぁ、マッド・サイエンティストなのですが、そんなものつけなくても……)で,あちこちで、おにゃのこさんと色々しでかしたりします(美形に作られているので結構モテるんだわ、これが)。彼が悲しいのは頭が機械剥き出しになっていることで、「あの、教授。帽子を被っても良いですか?」とか聞いちゃうのが可愛いと言えば可愛い。
あるいは、完全な「並」(ナット)なんだけれど、戦場をくぐり抜けてきたヨーマンが、「禅」でパワーアップして弓使いとして活躍したりもします。
はたまた、「バッグレディ」のバガボンド。まだ若い綺麗な女性なのだけれど、ホームレスになっちゃってます。心に深い傷を負っているのです。誰も信じられない。彼女がワイルド・カード・ウィルスから得た力は、動物たちの声を聞き、お願いができること。
バガボンドを何とか助けようとするマフィアの令嬢が登場したりします(彼女はその後、検事補になっちゃったりするのだけれど、あちらの国の制度はどうなってるんですかね)。
自分ではどうにもできないのだけれど、いきなり巨大なワニに変身してしまい、地下鉄の深い迷宮をさまようジャックとか。
群れ子
地球をものにしようと思っていたのはタキス人の他にもいたのでした。「母」と呼ばれるマザー・シップ内で増殖を繰り返す「群れ子」達。
最初は原初的な生物でした。それでも人類にとっては恐ろしい存在です。それが、莢に守られて地球に飛来します。
この辺りからが第2シリーズの「宇宙生命体襲来」に入ってきます。
最初はすごくプリミティブな生態なのだけれど、それでも人類にとっては脅威です。何て言うんだろう、芋虫みたいなものが宇宙から飛来して暴れ回っちゃうのです(う〜、キモい)。軍も出るのですけれどどうにも旗色悪いです。
ここはやはりエースの出番ですかね。タートルはとても効率よく群れ子達を片づけていきます。モジュラー・マンも大活躍。
群れ子の第一波はなんとか撃退できたのですが、彼等の胞子は地下に潜りさらなる進化を続けます。
人類側にもやっかいな存在が登場します「天文学者」(アストロノーマー)と自称する、ちびで、頭だけがでかい醜悪な男。彼も特殊能力を持っているエースなのです。
彼は女性を性的にいたぶり、虐殺することによってパワーをためるという極悪非道な奴です。
アストロノーマーは、フリーメイスンの組織を使い、手下を集めていきます。色んなところで虐げられたエース達などを(エースも虐げられるのです。力を持っているばかりに)。
敗れ去るエース達
そして、第3シリーズ「審判の日」は、アストロノーマーvs正義のエース達という構図となり、アストロノーマーは正義のエース達の虐殺を企て、実際に次々とエース達が倒されていきます(誰がやられちゃったかは書きません)。
アストロノーマーの能力は圧倒的なのですよ。「午前4時までに皆殺しにしてやる」との予告の下、次々とエース達が狙われていきます。
この様子を複数の作家達が書き綴っていくのですが、単なる複数作家による短編集ではなく、「モザイク・ノベル」と呼ぶのも分かるように、まるで1本の長編小説のように書かれています。
というわけで、現在日本語に翻訳されているのは第3シリーズの「審判の日」まで(それぞれ文庫で上下二冊の計6冊)です。
6冊目の後書きには次のシリーズの予告まで書かれているというのに、それ以来ぱったり止まったままです。私が持っている文庫(初版です)の奥書を見ると、6冊目が発行されたのは1994年なんですけれどねぇ……
どうなっちゃったんでしょう、創元さん。もちろん原書ではさらに先まで書かれているのに。
今回再読してみても面白いと思ったので、是非続編を出版して欲しいものです。
087「宇宙を織りなすもの」/ブライアン・グリーン
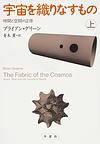 これは難物です。上手くご紹介できる自信などまるで無いのだけれど、是非ともお勧めしたい本なので、無謀にも敢えて挑戦してみることにしました。
これは難物です。上手くご紹介できる自信などまるで無いのだけれど、是非ともお勧めしたい本なので、無謀にも敢えて挑戦してみることにしました。
とは言え、体系的な説明は極めて難しいし、それをするには決定的にスペースが足りません。そこで、いくつかのエピソードを取り上げてご紹介することにします。
この本の一番コアな論点は、「空間とは何か?」、「時間とは何か?」です。この一見素朴な疑問、ある意味「そんなの簡単じゃない」と思ってしまうような疑問ですが、よくよく突き詰めて考えてみるとこれがまるでよく分からない。
「そんなことないよ。空間というのは自分たちの周り全部じゃない」、「時間は時間でしょ?」となりそうなのだけれど、じゃあ、空間や時間というのは、何か物理的な「実体」があるものなのか、それとも人間が概念的に構築しているだけの存在なのか?と問われると、ほら、ちょっと困ってきちゃうでしょ?
本書はそんな疑問を解くべく、ニュートンの古典物理学からアインシュタインの相対性理論を経て、最新のひも/M理論までを概観しつつ、数式を極力使わずに平易に解説してくれるものです(平易ったってそれほど簡単ではないけれど)。
 空間と時間
空間と時間
さて、それではニュートンは、空間や時間をどう取り扱っていたかというと、それは全宇宙に広がる絶対的なものと考えていました。
全宇宙にはまるで方眼の目のように一様に空間が広がっており、そのどの地点でも時間は同じように普遍的に流れていると考えたのです。
この考え方は、私たちの素朴な感覚に非常にマッチする理解しやすい考え方ですよね。
ところが、その後、アインシュタインが相対性理論によってこの考え方を根底から覆してしまったわけです。
まず、空間と時間というのは別々のものではなく、それは分かちがたく一体として捉えられるべきもので、「時空」なのだと説きます。
一見平坦に思える空間も、重力によって歪み、誰にとってもどの場所でも同じように流れると感じられる時間も、それぞれの「観測者」ごとに個別に流れるのだということが明らかにされました(このことは、多数の実験によって既に証明されています)。
空間が歪む例としては、例えば太陽などの極めて大きな質量を持つ天体の周囲では空間が太陽の重力によって歪まされており、それは、遠くの星の光が、太陽の近くを通って地球に達する時、その光の軌跡が歪んだ空間に沿って「曲がって」いることが観測されています。
時間について言えば、高速で移動している者にとっての時間は、静止している者から見れば遅く流れていることが証明されています。例えば、超高速で飛行するロケットの中にいる人にとっての時間は、地球で見守る人からみれば遅く流れているのです(もちろん、ロケットの中のパイロットにとっては通常通りの時間の速さなのですけれどね)。その時間のスピードの「遅れ」は、速度が上がれば上がるほど増すのでした(ですから、超高速で宇宙旅行をして地球に帰ってきた双子の兄は、地球で待っていた弟がひどく老け込んでしまったのを目撃することになります……これが有名な「ウラシマ効果」というやつです)。
じゃあ、ニュートンの説く分かりやすい空間、時間の概念はもう使えなくなってしまったのかと言えばそんなことはなくて、日常生活における理論としては今でも立派に役にたつし、正しいのです。アインシュタインは、本質的に正しいのですが、ニュートンとの違いが生ずるのは極めて大きな宇宙的スケールで物事を考える場合においてであって、日常の出来事を測るにあたってはニュートンの古典物理学で十分なのですね。
シュレディンガーの猫
一方では、アインシュタインが取り扱ったような非常にスケールの大きな世界とは対照的に、非常に微小な世界を取り扱う分野があります。その一つが量子力学です。
物質の最小単位は何でしょうか? ある時代には分子までたどり着き、さらに分子は原子からできている事が分かり、その原子は、真ん中にある原子核とその周りを回る電子からできていることが分かりました。さらに、原子核は陽子と中性子という粒子から構成されており、その陽子と中性子もさらに微小なクォーク(3種類あります)から構成されていることが分かっています。現時点では、物質の最小単位(素粒子と言います)は、電子(その他のニュートリノなども含んだレプトン)とクォークであるとされています。従来、これらの素粒子は、点状のものであると考えられてきました。
ところが、これらの粒子を調べてみると不思議な性質が分かってきたのです。これらの粒子を二本の切れ目を入れたスリットに当てて、その先にあるスクリーンに投射してみると縞模様ができるのです。これは「干渉」が生じている証拠で、干渉は波に特有の現象です。点だと思われていた粒子が何故波を形成しているのか?その過程を省略して答を書いてしまうと、粒子は、ある特定の場所に存在しているのではなく、この世界のどこにあるかは実ははっきり決まっておらず、どこにどの程度の割合で存在し得るかという確率でしかないということなのです。あそこにあるかもしれないし、ここにあるかもしれないという、極めてもやもやっとした存在で、それは「確率波」と言われています。その確率波が干渉を引き起こしているのでした。
それでは、粒子の位置は決して特定できないかと言えば、できます。しかし、それは観測者が観測することによってある位置に特定させてしまったということであって、その直前に粒子がどこにあったかはやはり確率でしか言い表すことができないのでした。
そしてまた、粒子の位置を特定してしまうと、その速度(スピン)は測定不能になってしまうのでした(逆もまたしかり。速度を測定してしまうと位置が特定できなくなるのです)。
何とも不思議としか言いようがありません。
この粒子の不確定な振る舞いについての有名な思考実験が「シュレディンガーの猫」と言われているものです(上記のお話とは若干違いますが、根っこは同じ話です)。
中が見えない箱に猫を入れます。この箱の中にはラジウムと、α粒子(陽子2個と中性子2個が組み合わさった物)を検知すると毒ガスが発生する装置が備え付けられています。α粒子はラジウムがアルファ崩壊すると発生する粒子なのですが、一定時間にラジウムが崩壊してアルファ粒子が出る確率が50%だったとしましょう。さてここで問題です。その一定時間後に箱の中の猫は生きているでしょうか、それとも毒ガスにやられて死んでいるでしょうか?確率的には五分五分ですが、箱を開けてみればどちらの結果になったかが分かります。しかし、それは箱を開けたという「観測」をしたから粒子の振る舞いが決定されて分かったことなのであって、箱を開けない限りは粒子の振る舞いは不確定でしかなく、中の猫は生きた状態と死んでいる状態が重ね合わされている存在になっているというものです。何とも不思議なお話ですね(「シュレディンガーの猫」の思考実験は、極微小であって、目にはもちろん見えないし観念することも難しい粒子の不思議な振る舞いを、可視的な猫の生死に結びつけてその不思議さを強調したものとも言えそうですね)。
次元のお話
ここでちょっと「次元」のお話をしましょう。私たちのこの世界は何次元でしょうか?
3次元。うん、空間的にはその通り。ですが、そこに時間軸がありますので、その意味では4次元の世界に生きているわけです。
この4次元というのがワケワカランと感じられるかもしれませんが、実はそんなに難しいことではありません。
こういう例を考えてみましょう。私とあなたが待ち合わせをすることにしました。待ち合わせ「場所」(空間のとある一点を決めなければなりませんよね)は、○○ビルの5Fにあるカフェに決めたとしましょう。このカフェの位置は、まず、地図上で見ると、縦と横でそのカフェが入っているビルの場所(及びビルの中のカフェの場所)を特定できますよね。この縦と横で一つずつ次元が必要になるので平坦な地図上での情報は2次元情報になりますね。
さらに、高さの情報が必要になります。カフェがあるのは5Fなので、この高さの情報も加えると3次元ということになります。私たちの空間は3次元であるというのはこういう意味ですね。しかし、これだけでは待ち合わせはできません。「時間」を決めないとね。この時間も一つの次元ですから、実は私たちは4次元の世界に生きているということになります。
ところが、最新の「ひも/M理論」によれば、この世界は4次元どころか、実は11次元でできているかもしれないということが分かりました。
「ひも/M理論」というのは、素粒子とはどのようなものかに関する理論で、実はそれは「ひも」のような形状をしており、それが振動することによってさまざまな素粒子の性質を持つのであると考える理論です(全ての素粒子の性質の違いは、実はひもの振動数の違いに過ぎないとされます。それはあたかも、弦楽器の弦の押さえ方によって振動数が変わり、違う音が奏でられるかのようなことです)。
本書でも、この「ひも/M理論」については詳しく解説されていますが、著者の処女作である「エレガントな宇宙」は、まさにこの「ひも/M理論」を中心に紹介した本です。
この「ひも/M理論」による計算では、この世界は11次元であるという帰結になるそうです。私たちは、先ほど書いた、「縦、横、高さ」に「時間」を加えた4次元を知覚できますが、残りの7次元は知覚できません。その他の7次元は、「縦、横、高さ」の空間座標の全ての位置に小さく(10のマイナス33乗の大きさだそうです)まるまって存在しているのだとか。
何だか気が遠くなるような話ですね。そもそも7次元ってどんな形なの?って思ってしまいます。
実は、この7次元図形という物が「ひも/M理論」ができる以前に、既に描かれていたのですね。それが「カラビ=ヤウ図形」と呼ばれている物です(勿論、模式的に2次元化して描かれているのですよ)。
カラビ=ヤウ図形
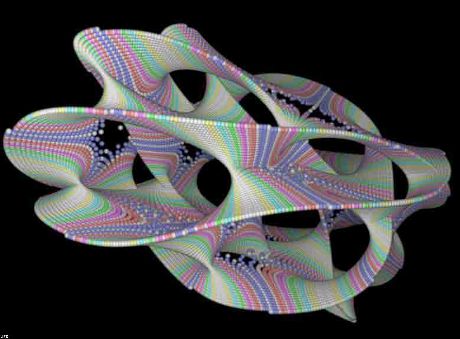 とにかく見て頂きましょう。左図が「カラビ=ヤウ図形」です。
とにかく見て頂きましょう。左図が「カラビ=ヤウ図形」です。
カラビ、ヤウというのはこの図形を考え出した2人の学者さんの名前です。
どこがどう7次元なのかさっぱり分かりませんが、こんな物らしいです。
しかも、「カラビ=ヤウ図形」は1種類だけではなく、いくつも発見されているそうです。
こんなものが、この世界の全ての位置に巻き上げられて存在しているのだとか。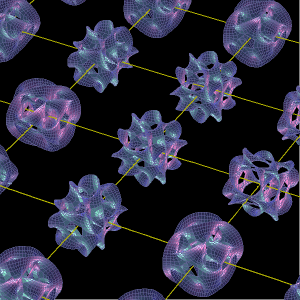
右の図がそのイメージです(アニメーションしているはずですが、見えますかね)。
宇宙の始まり
で、「ひも/M理論」は、何でこんなことを考えているのかと言えば、それはひとつには「大統一理論」のためなのです。多数の実証実験によって、大きなスケールを取り扱うアインシュタインの相対性理論も、微小な世界を取り扱う量子力学も、どちらも正しいことが証明されています。
ところが、この二つを一緒にすると(相対性理論の数式と量子力学の数式を一緒に使うと)、その答は無限大となってしまい、計算が破綻してしまうのです。これはどうしたことでしょう?
何とかこの二つの理論を統一する理論はできないものかと頭を悩ませているところに登場したのが「ひも/M理論」なのでした。
この「ひも/M理論」によって、宇宙論も書き換えられることになります。
いや、実は、その前から書き換えられているのですが。よく耳にする「ビッグバン理論」というのがありますよね。この宇宙の始まりは、大爆発が起きてそこから様々な物質が宇宙全体に広がり、いや、宇宙自体が膨張し続けているのだという理論。
実は、この理論も既に不完全であるとされており、現時点での最新理論は「インフレーション仮説」というものに取って代わられているのですね。
あ、いや、別に「インフレーション仮説」は「ビッグバン理論」を否定しているわけではなくて、それはそれで正しいとしているのですが、「ビッグバン理論」が言うところのその最初の大爆発って何よ?というところを解き明かす仮説なのでした。
「インフレーション仮説」は、原初の大爆発の理屈を解き明かしたわけなのでした。
で、そこに「ひも/M理論」が組み込まれると……というのが、この本が書かれた時点での最新の状態なのですね。
その答はまだまだ分からないのですが、一つの考え方として「多元宇宙論」も登場してきます。
時間の矢
で、この宇宙の始まりのことが、実は時間とは何かという問題に深く関わってくるのですね。
時間に関する論点の一つとして、「時間の矢」と呼ばれる問題があります。
平たく言えば、どうして時間は一方向にしか流れないのか(矢の向きは一方向だけを向いているのか)という問題です。
そんなの当たり前じゃないって思うかもしれないけれど、物理学的には大問題なのです。
物理法則は、時間の未来においても過去においても全く同じように作用しますし、時間軸を逆にしてもそれは変わりません。そうであるならば、時間は一方向に(つまり未来に向かって)進まなければならない理由はなく、そうなっているのだとしたらそこには何か原因があるはずだと考えます。
これはまだ解明されていない問題なのですが、仮説として非常に有力なのが、先ほど出てきた「インフレーション仮説」から導かれる議論なのですね。つまり、時間の向きが一定になっているのは、この宇宙が生まれた時に原因があるということです。その考え方によると(細かいことははしょりますが)、宇宙の始まりは重力場をも考慮するならば、非常に斉一な整った状態にあったとされます(つまり、エントロピーが低い状態です)。この世界の物はすべてエントロピーが低い方から高い方へと移ろいます(エントロピーが高いというのは、より乱雑な状態ということです。斉一な状態よりも乱雑な状態の方が選択肢が増えるので、当然エントロピーは低い方から高い方へと移ります)。
部屋がいつの間にか散らかってしまうのも、エントロピーが高い状態に移って行ってるのですよ。
で、このエントロピーの増大こそが、時間の向きを決定づけているのです(複雑、乱雑な方から整った方へ逆に流れることは絶対に有り得ず、宇宙の始まりがそもそも非常に斉一な状態だったので、そこから始まった時間も不可逆なのだということです)。
ハンプティ・ダンプティではありませんが、割れてしまった卵(エントロピーが高い状態です)は決して元へ(割れていない卵のエントロピーは低いです)は戻らない、つまり時間は戻らないのですね。
ぜいぜい。ここまで一気に書きましたが、ワケワカランですよね〜。
でも、何だかとっても不思議な感じがしませんか?
全てを理解できなくても、こんなことが考えられているんだとか、こうなっていたの?というような素朴な驚きが満喫できる本です。
著者は量子物理学者なのですが、「例え」の使い方が大変お上手です。難解なことを、結構平易に説明してくれる手腕は見事です。
軽く読むというわけにはいかないでしょうけれど、物凄く面白いことは保障します。上下二冊の分厚い本ですが、読んで損はないですよ〜。
「ひも/M理論」のことをもっと詳しく知りたいという方は、本稿中でご紹介している同じ著者の「エレガントな宇宙」もオススメです。
086「大地」/パール・バック
 舞台は中国。年代は、作中でははっきりとは記されていませんが、解説によれば日清戦争(1894〜1895)、義和団の乱(1900)、辛亥革命(1911〜1912)、清朝の滅亡(1912)、中国国民党の成立(1919)、南京事件(1927)等を題材にしているとのことであるので、時代背景としてはその頃と考えても良いのでしょうか。
舞台は中国。年代は、作中でははっきりとは記されていませんが、解説によれば日清戦争(1894〜1895)、義和団の乱(1900)、辛亥革命(1911〜1912)、清朝の滅亡(1912)、中国国民党の成立(1919)、南京事件(1927)等を題材にしているとのことであるので、時代背景としてはその頃と考えても良いのでしょうか。
親族3代に渡る物語です。
作者のパール・バックは1892年にアメリカ(ウェスト・ヴァージニア)で生まれたアメリカ人女性なのですが、その父親は宣教師であり、生後3か月で両親に連れられて中国に渡り(彼女の母親は中国で亡くなったそうです)、25歳の頃帰国したそうです。そのような彼女だからこそ、このような中国を舞台にした小説が書けたのでしょう。
「初代:王龍(ワンロン)の時代」
王龍は貧しい農民でしたが、村の富豪である黄家から奴隷(当時はそういう風習が普通にあったのです)の阿藍(アーラン)を妻にもらいうけることになりました。とにかく結婚さえできればまだ良いのです。阿藍は、決して美しくはないものの、黙々と働く芯の強い無口な女性でした。王龍は一生懸命働き、妻との間に3人の男の子と精白の女の子(もう一人女の子がいたかしら?)をもうけます。阿藍がしっかり者だったこともあり、徐々に暮らし向きも良くなっていきましたが、ある年、洪水による飢饉に見舞われます。多くの農民は土地を捨てて豊かな南方へと移動していきますが、王龍ら一家は最後まで踏みとどまります。とはいえ、それも限界となり、仕方なく一家で南に向かうことにしました。
南には、王龍達と同じ境遇の農民達が物乞いなどをして、また、金持ち達の施しである、今で言うなら難民救済所の食事の様な薄粥を食べながら、かろうじて日々を暮らしていました。王龍達一家も同じ事で、むしろで囲った壁沿いの場所を家として、阿藍と子供達は物乞いをし、王龍は車夫をしてその日その日をかろうじて生きていました。
しかし、この地方にも戦火が及ぶようになり、その混乱に乗じて王龍らは富豪の家から沢山の銀貨を盗み出すことに成功します。金を手にした王龍らは北の自分たちの土地に戻り(豊かな南にとどまる道もあったのではないかとも思いますが、王龍には北の土地への強い思いがあったのでしょうね)、あばら家を整え、種や農具を買い、再び農民としての生活を始めました。王龍らは手に入れた金で次々と土地を買い、前にも増して働くようになり、その甲斐もあってか、次第に裕福になり、人を雇い、仕舞いには今や零落した黄家の邸宅を買い取るまでになりました。阿藍も、余剰の金があると土地を買うことを勧め、王龍は、土地こそが最後まで頼りになるものなのだ、土地さえあれば何とかなると深く信じるようになります。
ですが、年を取ってから遊びを覚えると何とやらと言いますが、王龍もその例に漏れずでした。初めて行った娼館で買った蓮華に首っ丈になり、ついには金に物を言わせて第二夫人として家に迎え入れ、贅沢三昧の生活をさせるようになります。蓮華が望む物は何でも与え、ついには、阿藍が南方の戦乱のどさくさに紛れて手に入れ、その後肌身離さず持っていた真珠すら無理矢理取り上げて蓮華に与える始末(とはいえ、美しかった蓮華も最後にはぶくぶくと太った醜悪で淋しい女性に成りはててしまうのですけれど)。
他方、王龍にはだらしない叔父がおり、当時の中国の習わしから、王龍は零落した叔父一家の生活の面倒をみなければなりませんでした。叔父一家は王龍が裕福になったのを良いことに、全く働きもせず、贅に飽かした生活を送ります。いい加減嫌気がさした王龍は、ある時叔父一家を排除しようとしましたが、その時、叔父が近隣を荒らし回っている匪賊の幹部であることを知らされます。道理で匪賊らは王龍の家だけは荒らしに来なかったわけです。叔父一家を排除しようものなら、たちまち匪賊の餌食になることは目に見えていました。泣く泣く叔父一家の面倒を見続けざるを得ない王龍でした。しかし、いつまでもそんなことに耐えることはできず、遂に叔父らに阿片を与え(当時、阿片は高価な嗜好品として珍重されており、叔父らも喜んで自ら阿片に溺れていきます)、ついには廃人にしてしまいます。
「2代目:王大(ワンター)、王二(ワンアル)、王虎(ワンフー)の時代」
物語は、王龍の三人の男の子供達の代に移ります。幼かった頃はともかくとして、その後は裕福になった王龍のもとで育った3人の男子は、それぞれ別の道を歩み始めます。長兄の王大は、学者の道を選びますが、結局は酒色に溺れ、美しい妻を娶るも自分は醜く太り、優柔不断な男となり下がります。次男の王二は、商人となりましたが吝嗇家であり、利を貪る悪徳商人となります。妻に対しても女性的な魅力は求めず、しっかり者の農民の女性を選び子供をもうけます。三男の王三はその激しい気性と険しい容貌から王虎との異名を取り、軍人になります。
王虎は家を飛び出してしまい、しばらくはその行方が分かりませんでした。その間、王大は女性にだらしない贅沢三昧の生活を送り、亡くなった王龍が厳に戒めていたにもかかわらず、その贅沢な生活を維持するために、土地を切り売りし始めます。王二もさらなる富を狙って、投資資金を得るためにやはり土地を切り売りし始めるのでした。
軍人となった王虎は、貧しい農民達の境遇を改善してくれると信じていた将軍の元でめきめき頭角を現していきますが、ある程度の地方を平定してしまうと、将軍は安逸な生活に溺れだし、王虎から見ればただの腑抜けの老将軍に成り下がります。真っ当な世の中を作りたいと強く願う王虎は、遂に将軍を裏切る決意をし、自分を信じてついてきてくれる100人ばかりの兵と共に脱走し、一軍を起こします。手始めに、ある地方を牛耳っていた匪賊を打ち破り、公正な政治を行いました。軍も増強し、さらに多くの地方を平定しようとしますが、軍の維持費もばかにならず、裕福な王大、王二に資金的援助を請います。
王虎の名前はそれなりに有名になっており、また、この時代には主として北と南との間で戦争が絶えなかったこともあって、自分たちの保身を計るため、王大、王二の兄弟は王虎に喜んで資金援助をします。
王虎は、跡取りが欲しいとの理由のみから2人の妻を娶り(誰でも良かったのです、それぞれ、王大と王二が勧める二人の女性を妻にしたのです)、西欧思想を有する美しい妻との間には美人の女の子(愛蘭)を、伝統的な中国女性との間には男の子(王淵)をもうけます(この二人の妻の名前が思い出せない……というか、作中では「学問のある妻」、「そうでない方の妻」みたいな書き方しかしていなかったんじゃないかしら……違ってたらごめん)。
裕福な家に生まれ育った学問のある美しい妻は、その後、愛蘭を連れて南に行ってしまい、王虎とは別居するに至るのでした。
王虎は、男の子の王淵を跡取りと決め、幼い頃から柔弱と考えていた女性との接触を断たせ(それが淵の人格にも影響したのでしょうね)、軍事教育を施しますが、王淵は、祖父王龍の血をひいていたのでしょうか、農作業に心惹かれており、農民として生きたいと願っていました。しかし、峻厳な父である王虎の前ではそのようなことは言い出せず、言われるままに軍事を学びます。王虎も西欧の軍備が進んでいることは承知しており、南から白人の教師を招聘し、王淵の家庭教師につけます。優れた軍人となり、跡を継いで欲しいとの気持ちからですね。
時が経ち、王淵の家庭教師が進言しました。これ以上の教育をお望みなら、南の軍事学校で学ばなければなりません、と。王虎は子供を手元から離すことに抵抗ががありましたが、優れた軍人に育って欲しいという気持ちが勝り、部下をお供に付けて王淵を南に行かせます。
しかし、実はこれには策謀があったのです。当時、南を中心として革命気運が盛り上がっており、この白人家庭教師も、実は革命思想を持っており、王淵を革命軍に取り込もうという魂胆だったのです。次男王二の子供である猛も革命思想に染まっており、とうに家を出て革命軍に身を投じていたのでした。
「3代目:王淵(ワンシュァン)らの時代」
南の学校で学ぶ王淵は、虐げられた農民達を見るにつれ、確かに今の世の中はおかしいと考えるようになり、革命思想に傾いて行きます。革命思想はともかくとしても、南では西欧化された思想が主流であり、誰もが親が勝手に決めた相手と結婚するなどということは拒否しており、女性は自立すべきだとの思想が若い世代に確立していました。裕福な人々はスーツやドレスを身にまとい、ダンスパーティーに興じ、「自由恋愛」を楽しんでいました。
愛蘭は素晴らしく魅力的な女性に成長しており、ぎこちない淵を社交界に連れ回します。また、そこには、愛蘭を連れて出た王虎夫人が庇護する貧しい出自の美齢が甲斐甲斐しく働いていました。夫人は、ある時まで自分も学んでいた医学をゆくゆくは美齢に学ばせたいと考えていたのでした。
そして、淵は革命闘士となっていた猛と再会し、強く革命勢力に加わることを求められます。最初は煮え切らない淵でしたが、ある時、革命組織の物静かな女性と知り合います。勉強ができた淵に、その女性は勉強を教えて欲しいと願い出たのがきっかけでした。その後、徐々に二人は親しくなり、淵は、その女性から、愛の告白を受けるまでになります。ですが、どうしても煮え切らないのでした。その女性のこともあり、革命組織には加わることにしました。それなりの活動もしていたところ、弾圧が始まったのです。有無を言わせず多くの革命に加わっていた者が逮捕され、処刑されていきました。淵もその女性も例外ではなく、投獄されてしまいます。
これを知った王虎は、兄達からの援助も得て、莫大な金を使い、何とか淵だけは助け出しますが、女性は……おそらく殺されてしまったのでしょう。最後に淵と目を合わせるシーンがあります。
このままとどまるわけにも行かなくなった淵は、アメリカに逃亡します。そこで、王虎らからの資金援助を得て学問に没頭するのでした。
初めて見る西欧社会の進歩に驚愕する淵。コンプレックスもあるのでしょう。誰とも交わらず勉学に没頭し、優秀な成績をおさめます。西欧社会の進歩を認め、うらやみつつ、母国中国の後進振りに怒りを覚え、帰国後は必ず改革のために働くと決心するのでした。
ある時、教会で宣教師が中国の現状について話をする場に居合わせました。宣教師は、中国の貧民達の写真をスライドで映写しつつ、その悲惨な有様を語るのでした。恥辱にまみれた淵は、思わず大声で、それは嘘だ、そんな者は中国にはいないと怒鳴ってしまいます(内心では、確かにそういう貧しい農民達がいることは痛いほど分かっていたのに)。宣教師は、おだやかに、「あなたが暮らしていた場所にはいなかったのかもしれませんが、それよりもっと奥地に行けば目にすることができます」と諭します。泣きながら飛び出す淵。
アメリカ人の女性のメリーとの淡い心の交換もあります。淵が師事していた老教授の非常に真面目な娘さんがメリーです。最後にはKissを求められるところまで行くのですが、自分は帰らなければならない身であること、どうしても西欧的な自分になりきれないこと、その他様々な感情からメリーの気持ちを受け入れる事ができなかったのでした。
淵は6年間アメリカで過ごし、学位も得て中国に戻ります。
その道中、汽車の中で不潔でだらしない同国人の姿を見て、思わず怒鳴りつけてしまう淵なのでした。こんな奴らのために闘うのか?
家に戻ってみれば、老いて駄目になってしまった王虎を見ることになるのでした。不潔な家、ろくに家臣も残っておらず、老衰した父の姿に愕然となりました。
子としての礼を尽くした後(こういう中国的なことは、淵はどうしても捨て去ることができなかったのでした)、淵は南に出奔していた西欧思想のある王虎夫人の元に身を寄せることになります。そこで、美しい愛蘭が×イチ男とどうしても結婚するとすったもんだの場面に出くわします。既に子供を身ごもっていたという理由もあるのですけれどね(当時としては、それはそれはということだったのでしょう)。
愛蘭の母は嘆息します。愛蘭は確かに美しい。ですが、美しさを支える心が無かった。それは彼女の不幸なのだと。
愛蘭の結婚式の日、淵は、初めて美齢の静かな美しさに気付きます。美齢って覚えていますか?愛蘭の母親が庇護した娘で願い通り医学の道に進ませた女性です。
愛蘭は、それこそ咲き誇る花のように派手やかで美しいのですが、美齢には静かな美しさがある、と、淵には思えたのですね。
美齢は、やはり完全には西欧化していない女性に、淵には見えたこともあります。伝統的な中国人としての美徳も備えている女性と、淵には映ったのですね。
例えば、メリーと結婚することになったとして、老醜の身となった父親の王虎を見せられるかと言えば、それは淵には到底できないことでした。しかし、美齢にならそれは見せられると、そういう思いを抱いたのでした。
それで、淵は、結局、庇護者である夫人にその思いを伝えます。夫人は、淵の思いを美齢に伝えることを承諾するや否や、すぐに美齢をを呼び、ただただ客観的に淵の思いを美齢に伝えたのでした。何ていうことをするんだ!と淵は思ったんですね。もう少し、何て言うんでしょう、お膳立てなりなんなりがあっても良さそうなものなのに、こんなにストレートに……
美齢の答はこうでした。「それは、お受けしなければならないことなのでしょうか?」
夫人は言います。。「今は、自由恋愛の時代ですから、あなたが決めて良いのですよ。」
美齢は、医学を学びたい、そのためには結婚は考えていないと断ります。
夫人は、「でも、あなたは淵のことは好きなのでしょう?」と尋ねます。 「はい。お兄様として敬愛しています。」と答える美齢。
その後……
随分と長く書き連ねてしまいましたが、これが、「大地」の概ねのストーリーです。細かいところは記憶違いがあるかもしれませんが、勘弁してください。
こういう、中国のお話を、当時の西洋世界に読ませたというのは大きかったのではないかと思います(実際、相当に売れたそうですし、パール・バックはノーベル賞も受賞しています)。
この時代の本を読むと、今の作品に比べるとどうしても陳腐に思える部分があるのはやむを得ないことだと思います。
それを引き算したとしても、面白く読める作品であることに、今でも変わりはないと、再読(再々読かな?)でも思いました。
私が読んだのは、古い新潮文庫全4冊で、大作ではありますが、一冊ずつは比較的薄いので、是非チャレンジを。
085「老人と海」、 「誰がために鐘は鳴る」/ヘミングウェイ
手持ちのヘミングウェイの何冊かを再読してみました。どちらも有名な作品なので、既に多くの方がお読みになっていると思います。
ええ、僕ももちろん大分前に読んではいたのですけれど、情けないほどに記憶に残っていませんでした。
一番覚えていたのは、「老人と海」でしょうか。
では、僕と同じように、忘れてしまった人のために、「老人と海」辺りからいきましょうか。
 「老人と海」
「老人と海」
僕の手元にあるのは、新潮社文庫で、福田恒存(本当はもっと難しい字なのですが出ないので勘弁)さんの訳のものです。
表紙も、この現在の文庫の表紙とは全く違っていて、当時の新潮社文庫の表紙絵はヘミングウェイの顔が描かれていました。
さて、僕の中に残っていた「老人と海」は、年老いた漁師が一人で漁に出て、カジキマグロの大物を釣り上げる死闘を描いた……という印象、記憶でした。
それはそれでその通りなのでしたが、サンチャゴ少年のことが全く欠落していたのでした。
主人公の「老人」は、かつてはマグロ捕りの名手でしたが、今は年老いてしまい、お金もなく、うらぶれてしまっていました。ですが、漁師見習いみたいなサンチャゴ少年は、老人のことが大好きで、何くれと無く世話をしてくれていました。サンチャゴ少年も今では「老人」とは別の船に乗り込む漁師の端くれです。
「老人」は、かつてのように大物のカジキをつり上げることを願い、ある日、一人で漁に出ます(漁ったってボートのような船ですよ)。そこで、大物のカジキをつり上げ、その後の死闘が描かれるという物語でした。
幾日にも及ぶ死闘で、年老いてもうしびれて駄目になってしまった片腕を叱咤しながら何とか浜にカジキを持ち帰ろうとする「老人」が描かれます。
「老人」は大リーグの野球が大好きだったんですねぇ(すっかり忘れていました)。
大好きだったディマジオのことを考えながら自分を励ましたりもします。
「魚類」との壮絶な戦いと言えば、すぐに思い浮かぶのは「白鯨」(鯨は「ほ乳類」ですね)ですが、あれとは全く違うテイストの作品となっています。
悲壮さがないのですよ。いえ、確かに壮絶な戦いなのですが、何故か乾いている……つまり、カラっとしているように感じました。
結末はすっかり忘れていました。あぁ、こうなっちゃうのね。
短いお話ですので、僕のように忘れてしまった方は是非読んでみてください。敢えて結末は書きませんので。


「誰がために鐘は鳴る」
「Kissするとき、どうして鼻は邪魔にならないの?」この有名なセリフが登場するのがこの作品です。
スペイン内戦を舞台にしたのが「誰がために鐘は鳴る」です。ヘミングウェイ自身、この内戦には資金援助等で関わったのだそうですね。
物語は、共和主義者の主人公であるロバート(スペイン読みすればロベルト)が、友軍の総攻撃に呼応して橋を爆破するという任務を負ってファシストに敵対している人民政府の非正規ゲリラ達の根城を訪れるところから始まります。
そこの長はパブロ。かつてはファシスト達と徹底的に闘った勇者だったのに、今では酒に溺れているふぬけに成り下がっていました。代わってみんなを率いていたのはパブロの妻である剛毅なジプシーのピラールでした。
ロバートは、そこで、マリアと出会います。マリアは、ファシスト達に蹂躙され、髪を刈り取られまでしていたところをピラール達に救われ、今では一緒に生活していた19歳の女性でした。
ロバートの作戦行動までに残された日はわずか。その間に、ロバートとマリアは運命的な恋に堕ちます。
初めて結ばれる夜、マリアが囁いたのが冒頭の台詞でした。
さて、物語についてですが、率直な感想を言えば、これは、まるで「深夜プラス1」や、過日読了した「鷲は舞い降りた」と同様のテイストの作品に感じました。
ヘミングウェイって言うと、何だか純文学、世界の名作みたいなイメージありませんか?
それ、違うと思う。
今回再読して思ったのは、これは、「娯楽小説」であるということです。いえ、「娯楽小説」=低俗なんていう馬鹿なことを言いたいのではありませんよ、念のため。
そうではなくて、サスペンスやハードボイルドのテイストを満載した、楽しんで読める小説なんだということなんです。
どうも、ヘミングウェイという名前が大きく成りすぎている感があるのですかねぇ。そのため、余計敬遠されているのではないかと感じました。
もっと、もっと軽い読み物だと思いました。
そう、「武器よさらば」も読み直しましたが、やはり、「軽い」です。
軽いのは、決して悪いことではありません。何よりも、それが持ち味のヘミングウェイから軽さを取ってしまったらどんなにつまらなくなってしまうことでしょう。
あまり構えずに、ちょっと面白い本はないかな?と思ったら、そこでヘミングウェイですよ!
084 「隠し部屋を査察して」/エリック・マコーマック

非常に奇怪で不思議な作品を集めた短編集です。中には極めてグロテスクだったり、エロティックな描写も結構出てきます。
ですが、この感性は特筆に値すると思います。最近、再読しましたので、いくつかの作品をご紹介しましょう。
「隠し部屋を査察して」
表題作です。主人公は、とある入植地に赴任した査察官です。この入植地には6軒の家があり、それぞれの家には夫婦の管理人が住んでいます。そして、その地下には「隠し部屋」があり、囚人が一人ずつ収容されています。査察官は、月に一度、隠し部屋を査察して、それぞれの囚人が無事でいるかどうかを確認しなければならないのですが、囚人がすこぶる付きの奇怪な人達です。例えば、魔女だと告発されたために裁判にかけられたところ、判事の前で4時間に渡りとんでもない物を嘔吐し続けた女性.。嘔吐したものはと言えば、ウツボ4匹、44口径の巨大なピストル、花崗岩のいくつかの塊、1ダースもの動物の毛玉、文字が書かれた羊皮紙等々。あぁ、判事が目を背けずにその羊皮紙に書かれている事を読んでいたら命を落とさずに済んだかもしれないのに……とか、森の空き地に勝手に実物大(!)のガレオン船(奴隷船ですね)の精巧な模型を作り上げてしまった男とか。そんな囚人達を査察していた査察官ですら、この後……。
「パタゴニアの悲しい物語」
パタゴニアにいるというミロドンという不思議な動物を捕獲するために上陸した船乗り一行の物語です。明日はミロドンを探しに行くという晩、船乗り達は慣例なのでしょうか、各々物語を語り合い、評価し合うということを始めました。その物語がそれぞれ怖いのです。例えば、船長の物語は、南ボルネオに行った時の体験談でしたが、とある村では蜘蛛の神を崇拝していたそうです。その蜘蛛を奉った神殿の守護者(と、その予備)を養成するため、呪術師達は、近隣の村から男の子の赤ん坊をさらってきては何年もかけて守護者に育てたのだそうです。それが強烈で。さらってきた赤ん坊を、幼い頃から少しずつ上半身をひねっては固定していき、ついには上半身が真後ろを向くようにしてしまいます。そしてその後、手と足の間に膜を移植してしまうことから、その者は蜘蛛のように四つんばいにしか歩けなくなります。つまりは、顔は下を向いていて、剥き出しの生殖器が上を向いているという異形の者になり……
「刈り跡」
私が、初読の時も再読の時も、やはり一番印象に残った作品です。7月7日午前6時、カナダのサスカチュワンにある村から、それは始まりました。風のような音と伴に、突然大草原の表面に亀裂が走り始めたのです。その亀裂は幅100メートル、深さ30メートルの溝で、断面は人工的としか見えない程に極めて滑らか。その溝が時速1600キロの猛スピードで走り始めたのです。行く手にあった物はことごとく消滅してしまいます。とある農家はその溝の進路に半分だけかかっていたのですが、ちょうど半分がすっぱりと消滅してしまい、消滅した側にいた人々もいなくなってしまいました。この溝は「刈り跡」と呼ばれるようになりますが、これが世界中を走り始めたのです。ものすごいスケールの話ですよね。もちろん、軍もマスコミもも追いかけまくります。でも、ここに作者の、何だろう、アイロニー? じゃなければ何と表現したら良いのだろう。すごく不思議な感覚が盛り込まれています。悲惨さは何もないのです。あまりにもきれいに、スパっと「刈り跡」が作られていくことに、人類はどう対処したかというと……。
「趣味」
鉄道会社を退職した老人は、自分の趣味に没頭したいという理由から旅に出た挙げ句、見知らぬ町のとある夫婦が住む家の地下室に間借りしました。老人は、来る日も来る日も鍵をかけた地下室で長時間作業を続け、完成するまでは地下室に入らないように夫婦に言い渡します。どうやら精巧な鉄道模型を作っている様子です。家主の夫婦は老人のこれまでの仕事のこともあり、その夢にも理解を示し、全面的に協力します。が、老人が余りにも作業に没頭するのでその健康を心配し始めたところ、突如、大音響が地下室から響き渡ります……
といった感じの作品が多数収録されています。一つの作品の長さはかなり短めですが、どれも奇妙な味わいを有しています。
私は、かなり好きだと思います、こういうタイプって。
残念ながら、著者の作品で、現在普通に入手できるのはこの一冊だけのようです。
もう少し、こういう作品も評価されてもいいのになって思います。
083 「阿房列車」/内田百饟
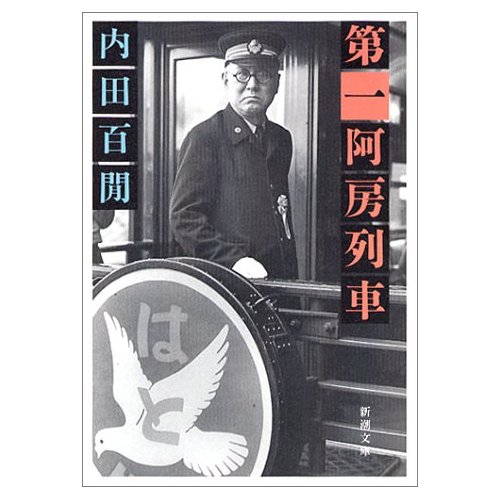
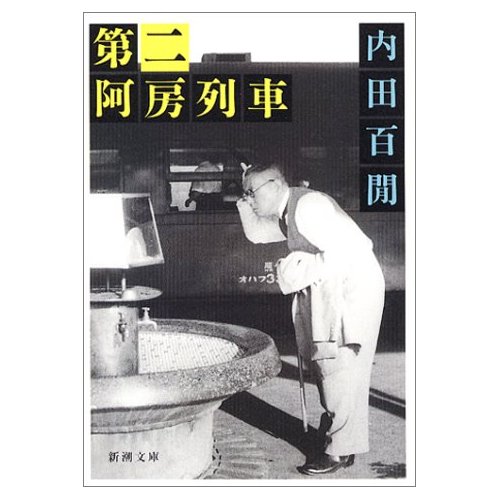
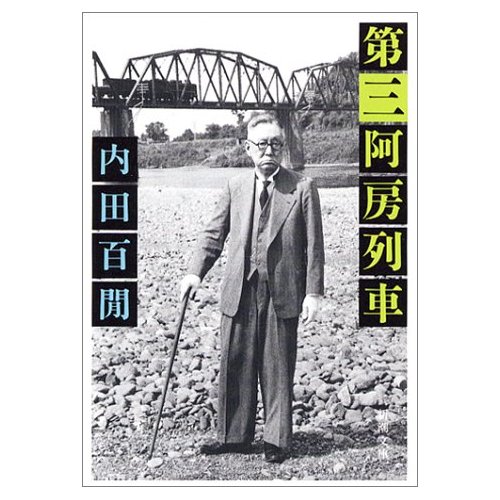
内田百饟(「饟」の字は機種依存文字なので、お使いの機種によっては表示されないかもしれません。門構えの中に月を書いて「けん」と読ませます)を読みたいと思っていましたが、さて、どこから読みましょうかと迷っていました。やっぱり「阿房列車」からかなぁ、と考えましたが、次に困ったのは、色んな出版社から色んな本が出ているのだけれど、どれが良いのだろうかということでした。
文庫で、現在入手し易いところで言えば、写真の新潮文庫とちくま文庫があるようです。新潮文庫の方は「第一阿房列車」〜「第三阿房列車」までの全3冊なのに対して、ちくま文庫の方は、「内田百饟集成」として出ている中の第1巻目です。他の百饟の作品も読みたいので、ちくま文庫の方が揃いで手に入るから魅力的でしたが、他方、新潮文庫が3冊に別れているけど、その全てがちゃんとちくまの1冊に収録されているのかなぁとの不安もありました。色々調べてみたのですが、どうにも分からなかったので、「えいやっ」という感じで新潮文庫全3冊の方を選びました。買ってみて分かりましたが、やはり、ちくま文庫の方には全部は収録されていませんでした。
煩を厭わずにご参考までに書いておきますと、ちくま文庫に収録されているのは、「特別阿房列車―東京・大阪」、「区間阿房列車―国府津・御殿場線・沼津・由比・興津・静岡」、「鹿児島阿房列車前章―尾ノ道・呉線・広島・博多」、「鹿児島阿房列車後章―鹿児島・肥薩線・八代」、「東北本線阿房列車―福島・盛岡・浅虫」、「奥羽本線阿房列車前章―青森・秋田」、「奥羽本線阿房列車後章―横手・横黒線・山形・仙山線・松島」、「雪中新潟阿房列車―上野・新潟」、「春光山陽特別阿房列車―東京・京都・博多・八代」です。
新潮文庫版にはこれらに加えて、さらに「雪解横手阿房列車」、「雷九州阿房列車前章」、「雷九州阿房列車後章」、「長崎の鴉」、「房総鼻眼鏡」、「隧道の白百合」、「菅田庵の狐」、「時雨の清見潟」、「列車寝台の猿」が収録されていました(新潮文庫版にも、それぞれの行き先である地名が付記されていますが、面倒なのでそこは省略)。
さて、「阿房列車」とは一体何でしょうか。くれぐれもご注意下さい、「あぼう列車」ではなく、「あほう(阿呆の意味)列車」なのですから。
これを説明するには、記念すべきシリーズ第一作目の有名な書き出しを引用するのが良さそうです。「阿房と云うのは、人の思わくに調子を合わせてそう云うだけの話で、自分で勿論阿房だなどと考えてはいない。用事がなければどこへも行ってはいけないと云うわけはない。なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行って来ようと思う。」ということです。つまり、百饟先生は、本当に用事は何も無いのだけれど、ただただ大好きな汽車に乗って旅をしたいというだけの気持ちから、借金までして旅費を工面して旅に出るのでした。その時に乗る汽車を「阿房列車」と呼び、様々な旅のことを書いた紀行文が「阿房列車」シリーズなのでした。
百饟先生ってどんな人かと言えば、夏目漱石の弟子です(詳しくは、Wikipediaなどをご参照下さい)。大変文章に厳しい方だったようです。……「あれ?さっきの引用文は現代かな使いだったけど?」と気付いたあなたは鋭い!そうなんです。もちろん、原典は旧字、旧仮名遣いなのですが、どうも現在市販されている文庫は、御遺族の承諾を頂いて、基本的に現代仮名遣いに直してあるようです(ただし、例えば、「著く(着く)」、「這入って(入って)」などの表記は一部残されています)。原典の味わいが無いとの批判もあるようですが、読みやすいことは読みやすいです。でも、百饟先生がこれを読んだら怒るでしょうねぇ。
さて、「阿房列車」に戻りましょう。そんなに汽車の旅が好きなら、きっと、事前に色々入念に準備して……などと思うのが普通ですが、これが全然! 一応、ルートだけは念入りに考えているようですが、何事にも縛られるのが嫌いで、特に用事もないけれど、ふらっと旅に出るというのがお好きだったようで、切符も事前に買ったりせず、敢えて当日買うことにこだわります(前日、乗車駅まで行って混雑具合を確認までしているのだから、その時に切符を買えば良いものを買わないのですね)。当日満席だったら行くのをやめれば良いなどと平気で言います(それが阿房列車なのだそうで)。また、乗り換えの接続が一番良い列車を選んで、その時間に合わせて旅程を組むのが普通ですが、百饟先生は朝が大の苦手です。夜更かしをするせいもあるでしょうけれど、百饟先生の時計には「午前中」などという時間は無いのです。そのため、ものすご〜く不便になるのを承知で、敢えて遅い時間に出発する列車にしか乗りません(そのために、無駄に一泊しなければならなくなったとしても)。そしてまた、百饟先生は、「乗り鉄」ですね。列車にもこだわりがあって、1等車が一番えらいから1等車が大好きです(お金が無いっていうのに!)。列車編成によっては1等車が無い場合もあるのですが、じゃあ、その場合は2等車に乗るかと言えば、2等車は嫌いだそうで(どうも2等車に乗ってくる乗客の顔つきが気にくわないそうです)、2等車に乗るくらいなら3等車の方が良いのだとか。まったくワガママな爺さんでしょ?(もっとも、この辺りのこだわりは、「阿房列車」の旅を重ねていく内に、徐々に緩和されてくるようで、最後の方になると文句を言いながらも朝出発する列車に乗ったりもしています)。
もう一つのワガママと言えば、百饟先生は一人旅は絶対に嫌なのです。それで、いつも「阿房列車」の旅に同行するのが、当時、国鉄の職員だった弟子の「ヒマラヤ山系」氏なのです。「ヒマラヤ山系」ってすごい名前でしょ?これも百饟先生がつけたあだ名なのです(その正体は、作家の平山三郎氏だそうです)。この「山系」氏が良い味を出してるんですよね〜。百饟先生はひどいですよぉ。先生を待っている「山系」氏を見つけると、後ろからステッキで頭をコツンと叩いたり、「どぶ鼠」呼ばわりしたり、旅先の宿での待遇が気にくわなかったりすると、それは「山系が持ってきた猫の死骸のようなきたない鞄のせいだ」と決めつけたりします(でも、そういうのが嫌らしくは感じなくて、なんともほのぼのとユーモラスなのです)。
道中での百饟先生と「ヒマラヤ山系」君の会話がまたゆる〜くて良いんだわ、これが。ちょっと引用してみましょうか。
「いい景色だねえ」
「はあ」
「貴君はそう思わないか」
「僕がですか」
「窓の外のあの色の配合を御覧なさい」
「見ました」
「そこへ時雨が降りそそいでいる」(「そそぐ」は小難しい漢字なのですが出ないので勘弁)
「そうです」
「だからどうなのだ」
「はあ。別に」
何とも張り合いのない、つまらない会話のように思われるかもしれませんが、この味が良いんだなぁ。「ヒマラヤ山系」氏という絶妙なパートナーがあってこその「阿房列車」だと思うのですね。
で、この二人は旅に出て何をするかというと……何もしないのです。列車に乗り込み、件の様な会話をしたり、あるいは二人とも黙っていたり。百饟先生は「乗り鉄」ですから、車窓の眺めを楽しんだり。二人ともお酒が大好きなのですが、百饟先生は昼酒はお嫌いなようで。いや、実は大好きなのだけれど、これは控えていて。だから、昼の間は食堂車には行かないのです(他の乗客がお酒を飲んでいたりするとたまらなくなるから)。でも、早くお酒を飲みたくて仕方がないので、早い時間から二人で食堂車に行き、そこで長尻をを決め込んで飲み続けます。宿に着いても別に何をするわけでなし。どこへ行くわけでもありません。もてあますほどの時間があることはまったく苦にならず、それを楽しんでいます。温泉地に行ったからと言って風呂に入ることもせず、観光地の見物をするわけでもなし。二人してぶらりと宿を出てタクシーに乗り込むことがありますが、行き先なんて決まっていないので、「どこへ行きますか?」との運転手さんの問いに対しても、「どこでも良いんだ」と答える始末。運転手さんが、地元の名所に案内しても、ろくに見もせずに引き返したり、ひどい時には車から降りもせず、ただぐるぐる回って帰ってくるだけ。ただただ、宿で夜のお膳が出るのを楽しみにしています(そこでまた酒を酌み交わすのですね)。
用事の無い「阿房列車」ですから、もちろん基本的に人を訪ねるようなこともしないのですが、百饟先生は有名人なのでしょうね。行く先々でマスコミに追いかけられ、インタビューされることも度々。すげなく断るかと思えば、嫌々ではありますが、あちらも仕事で来ているのだろうから、まぁ、無駄だがと思いながらも答えてあげたりします。はたまた、国鉄サイドも随分と気を遣ってくれるようで、行く先々の駅では駅長室をよく訪れて歓待され、車や宿の手配をしてもらいます。国鉄職員と一緒に飲むこともしばしば。百饟先生は愛されていたのでしょうね(法政大学で教鞭を執っていました)。全国にいる教え子(この「教え子」っていう言葉が大嫌いだそうですが)達が会いに来てくれたりもします。
「阿房列車」を読み始めて、しばらくして気付いたことの一つに、やたらに雨が降る旅だなぁということでした。毎度といって良いほど雨が降ります。百饟先生は、そのことにも途中で触れています。何でも、「ヒマラヤ山系」君は稀代の雨男なのだそうで。どうりで。九州に出かけた時など、記録的な豪雨に見舞われ、鉄道も不通になりまくりますが、何とも運の良い2人でして、何とかすり抜けて帰京します。
百饟先生は、八代がお気に召したようで、シリーズの中で4回も訪れます。いつも同じ旅館に泊まるのですが、最後の時は、その旅館の池を楽しみにしていて、事前に池に水を張っておくようにと言いつけるほど。ところが、どうしたわけか、この旅行の時は「山系」氏の神通力も失せたようで、良いお天気続きで、池の水もすっかり干上がっていました。それを見た百饟先生曰く、「つまんないの」。何とも可愛いじゃありませんか(でもこの後、「山系」氏の神通力が発揮され、大雨になって池の水が溢れてきたりします)。
なんとも、のほほん、ほのぼのとした、うれしくなるような旅行記です。
書いていることは、同じ様なことの繰り返しで、毎度持ってくる2本の魔法瓶に詰めた熱燗だけでは足りなくなって、ボイ(ボーイ、給仕)に頼んでお酒を買ってきてもらったり、辞退しているにもかかわらず、「阿房列車」が出るとなると何をおいても見送り、出迎えにやってくる弟子のこと。
何をするでもない、用事のない旅って、何て贅沢なんでしょう、って、少しうらやましくなってしまいました。
082 「大聖堂〜果てしなき世界〜」/ケン・フォレット
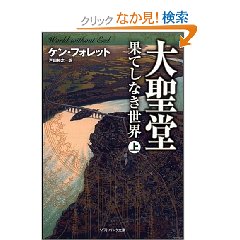
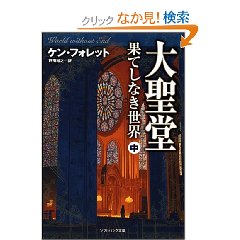
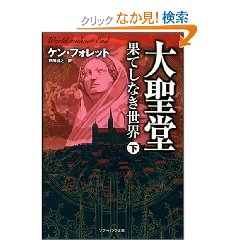
この本は、寝る前に寝床で読んだりしない方が良い。物語の続きが気になって、必ず眠れなくなるから。
本書は、039で紹介した「大聖堂」の続編である。
実に18年かかってようやく書き上げられた続編なのである。
世に数多ある「続編」というものの中には、前作と違った趣向にしようと考えてか、あるいは「二番煎じ」、「安易な水増し」との誹りを免れようとしてか、時として前作のテイストとは全く違ったものになってしまう作品もあるが(その多くはがっかりするのだが)、この作品に限って言えば、その様な心配は全く無用である。
大体、続編を読もうと思った読者というのは、前作がとても面白いと感じた人達なのであって、もう一度前作のような話を読みたいという気持ちを強く持っているはずだと、私は思う。
前作の「大聖堂」を面白く読んで下さった方は、安心してこの続編のページをめくって欲しい。あなたの期待は決して裏切られることはないと保障しよう。
前作の「大聖堂」は(039の紹介にも書いた通り)、1123年〜1174年までの出来事を描いていた。
本作は、その後の1327年〜1361年までを描く。舞台は、前作の主人公であったトム・ビルダーとその息子達が念願叶って建設した大聖堂があるキングスブリッジである(もちろん、キングスブリッジ大聖堂も健在である)。その後のトムの血をひく者も登場する人々の物語である。
物語の中核をなすのは、マーティンとラルフの兄弟。そしてそこにからむカリス、グウェンダらの女性達。
マーティンは自分で工夫して弓を作るような才能を持ち、ラルフは粗暴ではあるが運動能力に優れた弟。彼等の父親は騎士であったことから、二人の息子にも騎士になってもらいたいと願っているが、今は没落している。
その後、ふとしたことから、ラルフはシャーリング伯のスクワイア(作中では「騎士見習い」と訳されているが、一般には「盾持ち」などと言われる立場)に取り立てられる。兄のマーティンも志願するが、「お前は職人になると良い」と言われてしまう。
騎士になる夢を断たれたマーティンは、仕方なく大工の親方であるエルフリックの下で徒弟として働くが、元来才能があったのだろう。めきめきと腕を上げていく。しかし、父親は自分の夢を担ったラルフに大きな期待をかけるばかり。それでもマーティンはエルフリックの理不尽な仕打ちに耐えながら、あと少しで徒弟期間を明けるまでに勤め上げていたのだが……。
一方、女性達はと言えば、裕福なギルドの長老(オールダーマン)の娘カリスは、聡い子供で、父親をよく助け、医学に興味を抱く。しかし、当時は医術を行うことが出来るのは男性修道士に限られており、かろうじて修道女が看護婦(古い言い方だが)として働くことが出来る程度。けれども、修道士達の「医術」とは、古い言い伝えを墨守するだけのもので、中には多少効き目がある治療法もなくは無いが、多くは、何でもかんでも瀉血し、動物の糞を与えるなどの何の効能も根拠もない、有害なものでしかなかった。カリスは、自分の未来に対して確たる進路も定まらないまま、しかし、男性に縛られることを拒否しつつも、マーティンに魅かれ、二人は愛し合うようになる。
カリスと親しいグウェンダは自由労働者の家の子供。自由などと言えば聞こえは良いが、要は土地を持つことも出来ず、何の資産もなく、ただ自らの労働力を、土地を有する農民に提供してわずかな賃金を得るだけの搾取された貧しい生活を強いられる立場であった。
グウェンダの父親は、農作業の無くなる冬を越すために、子供達に盗みをさせて一家の生計を維持している。しかもとんでもないことに、ついにはまだ幼い娘のグウェンダを牛と交換に売り飛ばしてしまうような卑劣な奴である。……まぁ、卑劣と言えば簡単だが、一家を養っていくためにはそれも仕方がない時代だったのかもしれない。売り飛ばされたグウェンダは売春を強要させられそうになるが、すんでの所で逃げ帰り、母親に助けを求めるのだが、母親は父親(つまり、彼女の夫)を非難するどころか、「仕方なかったんだよ。それより只で牛が手に入ったっていうことじゃないか。」などと言う始末。重ねて、父親は再びグウェンダを売り飛ばそうと画策する。あぁ……
家を飛び出したグウェンダは、綺麗な顔立ちの農民のウルフリックに恋をする。グウェンダは自分の器量が良くないことは自覚していながらも、必ずウルフリックを自分のものにすると誓う。しかし、ウルフリックは、美人のアネットにぞっこんであり、アネットもウルフリックに媚びを売っている状態。こりゃあ、結構望み薄かも……
とある日、スクワイアとなったラルフがやってきて、美人のアネットに目を付ける。傲慢なラルフは衆人の前でアネットの身体をまさぐり、強引にものにしようとする。これを見ていたウルフリックは、ためらわずにラルフの顔面に一発お見舞いし(当時の身分関係から言えば、農民がスクワイアに手を出すなど考えられないこと)、その鼻をへし折ってしまう。この一件が後々までたたるんだが。
さて、キングスブリッジ大聖堂にいる聖職者達はどうだろうか。この時代には修道院も併設されており、修道女達も一緒に暮らしている。
院長アントニーは、保守的かつ優柔不断な性格で、オールダーマンらが建設的な意見を具申してもことごとく却下する始末。商人達からすれば、キングスブリッジの繁栄をことさら邪魔しているようにしか思えない。若き修道士であるゴドウィンは、そもそも修道女との生活圏があいまいな現在の大聖堂のあり方自体に危惧感を抱いている上、アントニー院長のような財政のやり方ではキングスブリッジは没落していく一方だと考えており、閉塞した現状を何とか打開したいと願っていた。そして、ゴドウィンが愛してやまない母親の勧めもあり、グウェンダの兄であり、どういうわけか大聖堂に憧れて勝手に下働きをしていたフィルモンに目をかけてやるようになる。
続編には、様々なエピソードと共に、登場人物達の愛憎劇も描かれる。マーティンとカリスの関係も然り。
この二人のやりとりを読んでいて、マーティンに同情してしまうのは私が男性だからだろうか。カリスの選択や行動に、時として身勝手な、理不尽なものを多く感じてしまったように思える。女性の読者は、この辺りはどう感じるのだろうか?
そうそう、女性の読者と言えば、もう一つ気にかかることがある。
私がこの続編を読んでいて、一つ、とても気になったことがある。それは、性描写がかなり露骨に繰り返されたことである。このような時代であり、ある意味奔放なところがあったのかもしれないし、それを描き出すためには生々しさは効果的ではあったのかもしれないが、それでもその描き方が私には好きになれなかったのである。同じ事を書くにしても書き方はあるだろうと正直思ったのだが、女性読者はどう感じるのだろうか? というのは、かなりの部分は女性から見た「性」の描き方をしているからである(別に、女性は性描写をいやらしく感じるだろうなどという、皮相なことを言っているのではないのでご了解を)。
ストーリーの紹介はここまで。
どうだろうか、前作の「大聖堂」を読んだ方は、「うん、まさしくあの通りだ!」と納得して頂けただろうか。
もちろん、ここで紹介したストーリーはさわりもさわり、ほんのはじまりの部分であり、この先沢山の出来事が連なる長い物語が待っている。
1冊約650ページ前後の分厚い文庫本で3冊であるが、怖じ気づかないで欲しい。今時の文庫本の活字は大きいので、昔の文庫本を知っているのであれば、ページ数に恐れをなすことはない。加えて、以下に書くように、気付かないうちにどんどんページはめくられていくので、どうか、外見の分厚さに恐れをなさずに手に取って頂きたい。
冒頭で、この本を読むと眠れなくなると書いたが、その理由はいくつかあるように思われる。私が思うところのいくつかを挙げてみると……
1 次々に起きるエピソードが、いくつか多重並行的に進んで行くが、しばらく読み進むと、現在進んでいるエピソードは良いところで「おあずけ」をくい、以前気になっていた別のエピソードが語られるという構成になっている。従って、どこまで読み進んでも、次々と現れるエピソードの結末が気になってしまい、ついついページをめくることとなる。
2 登場人物のキャラクターがはっきりしており、悪い奴はとことん悪い。ほんとうに腹が立つ位、悪辣である。その力は計り知れず、善玉の登場人物がなんとかこしらえたものが、あっという間に瓦解させられることが度々である。あるいは優柔不断な奴はどこまで行ってもそのままであり、はがゆさ満点である。
3 1とも関係するが、章の長さが絶妙である。長すぎることは決して無く、良いタイミングで切り替わる。
その他にも上手なところはいくつもあるだろうけれど、これらのことが作用して、次を読みたくなってしまうようだ。
前作の「大聖堂」はとても力を入れて勧めたが、本作も同様にお勧めできる作品である。
前作を読んでいる方は、心おきなく本作を楽しんで欲しい。
前作を読んでいない方も、本作は、「続編」ではあるが、前作とは別のストーリーであるので、望むなら本作から読み始めても構わない。その場合、多少知らない名前も出てくるが、構わずに読み進んで頂いて一向に差し支えない。……ではあるけれど、やはり、前作から読み始めることをお勧めするが。
081 「通訳」/ディエゴ・マラーニ

語学って、ものすごーく苦手なんです。もう、それは本当にキライだぁというレベル位に。
でも、仕事で、数年前には国際会議に頻繁に行かなければならない時期もあって。私が行っていた一般の会議だと、大体1回が2週間のセッションなんですね。その間、毎日会議に出るわけですが、議事録のようなものも記録するわけです。最初はもちろん日本語で書いていましたが、これは、どうしても脳内翻訳のワンクッションを必要とするので遅くなるんですね。とはいえ、最初の頃にはそれしかできなくて。
でも慣れるもんですねぇ。何回か参加しているうちに、英語でメモを書き始めるようになりました(これは自然に)。その方が全然早いし、それに慣れてくると発言者の言ったジョークまで英語でメモしていたりしました。きっと、その時、自分の思考も英語になっていたんじゃないかなぁと思います(今ではそんな仕事からもすっかり離れてしまったので、まったくできなくなっちゃいましたよん)。
そう、言葉って、思考を拘束するのです。
これを読んで下さっているみなさんも、色々脳内で考えたりしているけれど、それは日本語で考えているでしょ?
でも、別の言語を使う時には、それに馴染んでいたら、思考もその言語でしているんですよ(もっと大昔、英語圏の国に滞在していた最後の頃、英語のTVドラマを見ていた時、「あ、英語で考えていた」って実感したこともあります)。
この作品は、国際会議のスタッフが主人公です。仕事柄、何カ国語かできるのですけれど、自分が管轄しているセクションの通訳にちょっと変な人がいてトラブルが発生します。
モニターしてみると、確かに問題がありそう。
で、結局解雇しなければならなくなり、そのことを通告しますが、当の通訳人は解雇しないでくれと哀願すらします。
ですが、そういうわけにもいかず……
その時、通訳人が、何語か分からないのですが、不思議な言葉をしゃべります。
その言葉が耳に付いてしまって、それからというもの……
という、ある意味とても怖いお話です。
作者さんも、そういうお仕事をされていたそうです。
佳作だと思います。
080 「禁色」/三島 由紀夫
 な〜んで、三島の最初の紹介が「ホモ本」(いやらしい書き方ですみません、敢えてです)の「禁色」(「きんじき」)なの! という声が聞こえてきそうではあります。
な〜んで、三島の最初の紹介が「ホモ本」(いやらしい書き方ですみません、敢えてです)の「禁色」(「きんじき」)なの! という声が聞こえてきそうではあります。
うん、なんで、だろうね。
三島由紀夫って、結構好きなんですよ。何ていうのかなぁ、すごく論理的だと感じます。構成もきっちりしているし、「法律屋」としては、すっと分かる文章なんですよね。
いえ、それは、私が、法律屋になる前から、好きだったんですよ。中学、高校生の頃から沢山読んでいました。
法律屋になった今、読み直してみても、やっぱり好きだし、より以前より、そのクリアな論旨に惹かれるように思います。
さて、それで何故最初が「禁色」かですよね。
あのね、本当は、「真夏の死」に収録されている「翼」という作品が大好きなのでした。
だけど、今回は「禁色」にすることにしました。
「禁色」というのは、読んで字の如しで、禁じられたセクシュアリティのことを描いているわけです。
それは、一つには、ホモ・セクシュアリティのことです。
「悠ちゃん」(本名は悠一ですが、「その世界」では○○ちゃんと呼ばれるのが、当時は、そうだったのかな。彼も「悠ちゃん」です)という、絶世の美青年が主人公……いや、主人公は、老醜の作家である檜俊輔ではないのかな?
悠ちゃんは、とても若くて美しい康子さんに思われていて、康子さんに請われて二人して泊まりがけの旅に出ます。
康子さんは、その幾日かの旅の間に、結ばれることを願っていたのですけれど、悠ちゃんは、男性しか愛せなかったので、辛くて仕方がない旅だったわけですね。
そんな時、老醜の作家俊輔と出会い、思わず自分の秘密を明かしてしまった悠一。
俊輔も屈折しまくっていて、とある女性に対する復讐心のような、根にしこったことを悠一に仮託しようとします(大金を援助してでも)。
という、かなりなお話。
これ、俊輔って、三島自身を仮装しているのではないのかしらん……
さて、洋の東西を問わず、世の文豪、偉人には、ホモ・セクシュアリティの方は数多います。
そういうことは、色々な作品や評論を読んでいけば、いやでも分かります。
私は、残念ながら、そちらの方はどうにも趣味に合わないので、多分どうにもできない領域なのですけれど、少しだけ、精神論みたいなところでは、分からなくもない、かもしれません。少なくとも、例えばこの作品を読んで、嫌悪感みたいなものは一切ありませんですよ。
途中まで読んできて、すごく共感できたのは、康子さんのキモチなのでした。
ええ、悠一と結婚して、子供も出来た後、とある悪意の手紙が届き、悠一がホモ・セクシュアルだという暴露をされるのですが、それはほとんど堪えないのね、康子さんにとっては。
その気持ちがとても理解できるように思えました。
むしろ、悠一の放蕩の相手が女性ではなかったということが、救いだったのかもしれない。
そういう人なのだから、と。
でも、これは残酷な物語だから、そのままにはしてくれないのですけれど。
あらすじを追うようなご紹介は控えたいと、前々から思っているので(でもやっちゃうんだけどね)、ここでも自制して少し方向を変えますね。
ひとつだけ、「彼等」の思想に違和感を抱くところと言えば、女性をあまりにも醜悪な、「なまもの」みたいに感じる感性でしょうか。
それは、あぁ、それは分からなくもないのですけれど、でも、「お前だってそうだろ」と、還元しちゃうみたいです。
きれいごとに、し過ぎているようにも、思えるのですね。
おっと、別に、ここでホモ・セクシュアリティのことを書こうと思ったわけではないのです。
そういう主題ですけれど、しっかり書き込まれた小説として、「禁色」という作品もありますよ、というご紹介でした。
構築美というか、どうにもしっかり組み立てられているのが、息苦しくなければ(私は、そこが美しいと感じますけれど)、読んでご覧になってはいかがでしょうか?
079 「ナジャ」/アンドレ・ブルトン
 アンドレ・ブルトンは、シュルレアリスムの総帥などと言われています。
アンドレ・ブルトンは、シュルレアリスムの総帥などと言われています。
そうそう、ここが肝心。日本では、よく「シュール・レアリズム」などと書かれていたりしますけれど、これは、とんでもなく間違い。
「シュールな」みたいな、形容詞を使うことがあるけれど、それも、かなり間違い。そこで言おうとしているイメージと、シュルレアリスムとは、おそらくとてもかけ離れたものじゃないだろうか、と感じています。
この辺のことは、巌谷國士さんなどの丁寧な解説を読んで頂けたら了解して頂けるように思います。
で、そのシュルレアリスムの総帥たるアンドレ・ブルトンが書いたのが本書です。
アンドレ・ブルトンの文章って、すっごく読みにくいのです。
「わざと」なのかも知れないけれど、文章を区切らないのね。だらだらと、しかも違うテーマだって一緒くたにして一文の中に垂れ流しているような……
長いし、非常に観念的だし。
このHPの「今年読んだ本」などを見て下さっている方ならお分かりの通り、「アンドレ・ブルトン集成」(既に絶版)なども頑張って買い集めて読んではいるのですけれど、とても読みづらいです。
そんなブルトンの中で、かなり読みやすく、しかも、ある意味代表作の様に扱われているのが、「ナジャ」じゃないかな。
ブルトンが、パリの街を歩いていた時、何だか奇矯な格好をした、貧しい若い女性と出会います。
声をかけてみて、カフェでお茶したりします。
魅かれたのでしょうね。
ナジャに会いたくて、また、同じ場所などを彷徨ったりします。
また、出会えて、そうして、一緒にいる時間を沢山持つようになります。
あ、もちろん、このころは、ブルトンだって結婚していて奥様もいらっしゃいますけれど。
こう言っても良いのなら、「恋愛感情」(あー、嫌だな、この言葉)はあったと思いますよ。
二人で、あてもないような長い(短い?)列車の旅などもします。
そんな、逢瀬を書いているのが「ナジャ」なのでした。
その時々の、壊れやすいような気持ち、みたいなのが良いなって感じました。
ブルトンが書くところによれば、ナジャは精神を病んでいたようです。
それ故の、繊細さ、壊れやすさなどが、ナジャには見えたように読みました。
最後は、病院に行ってしまうのですけれど。
それまでの間の、はかないような逢瀬を書いています。
どこかのブログで読んだ話なのですけれど(私が色々読んだ範囲では確認できない話ですが)、ブルトンが、パリの街を歩いていた時、一人のうらぶれた物乞いの男を見たそうです。
目が、見えないのでしょうか。首からかけていた紙に、「わたしは目が見えないのでお恵みを」というようなことが書いてあったそうです。
ですけれど、その男の前を通り過ぎる人達は、まるでお恵みなんてしてくれないようで、空き缶にはいくらのお金も入っていなかったそうです。
詩人でもあるブルトンは、その男の「看板」を書き換えてあげたそうです。
「わたしは、目が不自由なので、新しく来る春が見えません。」みたいに。
そうしたら、たくさんのお金をもらえたのだとか。
あざといなぁ……とも感じますけれど、素直に読めば良い話かも?
078 「嵐が丘」/エミリー・ブロンテ , 「ジェーン・エア」/シャーロット・ブロンテ
 ブロンテ姉妹の、世に言われる「名作」を二つ取り上げさせていただきます。
ブロンテ姉妹の、世に言われる「名作」を二つ取り上げさせていただきます。
再読(再々読かな?)させていただきましたが、「時代が違う」で、終わりで良いでしょうか?
いえ、いわゆる「少女らしい」夢や冒険などは、特に、「ジェーン・エア」などには色濃くあるのかしらん?
でも、お金も何も持たずに、極めて無計画に放浪に出てしまい、その後、みなさんのとても(作者にとって?)都合の良い善意で物乞いのようにして生きていけるというのは、今ではあり得ないよね。
ジェーン・エアで書かせて頂くのなら、それほどに思い焦がれたロチェスターなら、どうして飛び込んで行かないの? その結果、「ハッピー・エンド」なんだかどうだかわからないけれど、ロチェスターは片目を失い、片腕を失っちゃうわけですよ(事故ですけれどね)。
まぁ、ロチェスター氏も、狂人の妻を抱えちゃって、それを隠してまで結婚しようとしたという、とんでもなことをしてるから同罪か。
二人とも、ちゃんとお話をすれば良いのに。どうして、ちゃんと話し合わないのだろうと、歯がゆくて仕方なかった。

そう、「嵐が丘」だって同じ。
大体、あれほど怪しいヒースクリフの家に、何であんなに無警戒に、というか、繰り返し繰り返し行くのですか?
結末は、作者なりにつけているとは思うけれど、読んでいる途中で、「何でそんなところに行くの?」って、ずっと思ってた。
これも、「歯がゆい」と言えばそうだし、何よりも、「あなたは何をどうしたいの?」と思っちゃうかも。
本当にヒースクリフが好きだったのなら、愛していたのなら、もっと早くきれいに決着できるでしょうに(いや、確かに、エミリーが書いているヒースクリフの性格はとんでも!なので、あいつと折り合いが付けばということですけれど……だって、最後には折り合いついちゃうわけでしょ? どうしてそうなるのかが、あんまり納得しないのだけれどね)。
そもそも論を書けば、ヒースクリフって、何であんなに執念深いの?
もう、放っておいて、自分が好きに生きれば良いのに、執念深いよね。まぁ、そうしたかったのかもしれないけれど、そこに「強引に」割り込んできたキャサリンって、何で関わらなくても良いことに関わるの?
「好きだったから」というのが答なら、もう少し、気持ちを伝える術はあったよね。
「名作」として、今の子供達にも勧められている本なのかなぁ。
はっきり言って、子供達に読んでもらいたい本としては、私は推薦しません。
先ほど書いたとおり、今の感性で読むと、余計に「変」としか思えないし、ましてや子供達に、まずこれを読んで欲しいとは決して思えません(何だら教育委員会の推薦図書とかにまだこういうのが上がっていますか?)。
すっごくきつい「本棚」になってしまいましたが、そういうのもあるよね。
いえ、物語としては、それなりに書いてあるので、いいかもね。
決して、私は好きじゃないけど。
077 「澁澤龍彦全集」/澁澤龍彦
 全22巻、読み終えるまでは書かないことにしようと、思っていました。
全22巻、読み終えるまでは書かないことにしようと、思っていました。
別巻もあるのだけれど、そこまでの興味はないので、それは買いませんでした。
全22巻、読了しましたので、書かせて頂きます(ちなみに、画像はアフィリエイトしているAmazonのものを使わせて頂いていますが、これ、間違っていると思います。この画像は「翻訳全集」の方じゃないかなぁ。何よりも、本の表紙が赤いのは翻訳全集の方ですね。普通の全集の本の表紙は銀色です。箱の背表紙の文字部分も赤く映っていますが、これも「翻訳全集」の方の色です。「全集」の色は黒です)。
タイプとしては、好きだったと思います。
そうでもなければ、お高い全集を買い揃えようなどとは思わなかったことでしょう。
時代も考えれば、あの時に、このジャンルをここまで書いてくれた(紹介してくれた)というのは、とても素敵です。
最初に、文庫で、そうですね、例えば「手帖」シリーズなどを初めて読んだ時、こんなことを書いてくれている人がいるんだ!と嬉しくなりました。
ええ、澁澤さんが紹介してくれることどもは、私的にはとてもつぼにはまる分野なので、情報がとても少なかったであろうあの時代にここまで書いてくれたのは狂喜乱舞ものです。
澁澤龍彦と言えば、一般に一番有名なのは、マルキ・ド・サドを本邦に紹介した仏文学者(?)ということでしょうか?
彼が翻訳したサドの「悪徳の栄え」は、いわゆる「わいせつ本」として発禁処分を受け、刑事裁判にかけられもしました。
今の基準で見れば別に何ていうこともない本なのですが、当時はこれでもわいせつとの非難を受けたのでしょう(今は、全文読めますよ)。同様の裁判例としては「チャタレイ夫人の恋人」事件(原作はD.H.ロレンス)だとか、「四畳半襖の下張り」事件(原作は野坂昭如)だとかもあって、「悪徳の栄え」事件と並んで、法律の勉強をした人であれば必ず学ぶことになる、「わいせつ」概念に関する判例ともなっています。
こういう「わいせつ」に関する問題(個人的には、この手の問題は全くむなしいことだと思っているのですけれど)はさておき、当時、サドに着目したというのもセンスが良かったのだろうと思います。
あ、もしかしたら、今でも、「サドなんて、いやらしい猥褻本なんだ〜」とか思っていらっしゃる方がいますか? だとしたら、それはとてもナンセンスです。
澁澤も書いていますが、サドというのは、わいせつというよりは(ええ、もちろんそれなりの性描写がありますが)、むしろアナーキストなのではないでしょうか?
好き嫌いは別にして(それはとても尊重します)、それを、「いやらしい」とか「Hだ」としか読めないのだとしたら、自分の感性をこそ疑うべきとまで、言うかも知れません。
その辺の思想を読むことに意味があるように思えて(その意味で、日本では「サド・マゾ」などと一緒くたにされているマゾッホの方には思想ががそれほど無いのでサドほどには高く評価できないわけです)。
こんなことから書き出すと、どうにもキワモノ的に思われてしまうかも知れませんが、ある意味、それは正しい。
当時、それほど注目されていなかった作品や作者を、彼の美意識で紹介したのが澁澤だったのではないかと思うのです。
彼が愛した領域は、オカルティスムやマニエリスム、シュルレアリスムなどであり、それは、ある立場の方々から見れば、キワモノと言えばキワモノかもしれない。
だけど、私のつぼでもあったわけですね。
そんな意味で、彼が愛した領域をとても楽しく逍遙させていただいたのです。
澁澤は、私の個人的評価では、あくまでもガイドだったのではないかと思います。それ以上では決して無かった。
彼のエッセイなりは、はっきり言って「切り張り」であり、その先の深みは乏しいと言わざるを得ません。
はたまた、彼の翻訳も評価は低いようです(ですが、何を取り上げて翻訳したかという点においては、個人的には星5つです)。
読売文学賞を受賞した「高丘親王航海記」だって(割と一般には評価されているようですが)、要は彼が愛したプリニウスやその他諸々の伝承などの焼き直しに過ぎないように感じられます。
さほどの厚みはなく、せっかく魅力的な人物を配しているのに、その人物描写なども淡泊で、ただただ、表面的な出来事の羅列であります(薬子や秋子、春子のエピソードなどもありますが、所詮その程度)。
随分、辛辣なご紹介となってしまっていますが、ですが、私は澁澤が好きだったんですね。
彼の感性、彼が良いと思った物は、確かに、私にとっても良いものだったのです。
それは、彼の残した仕事がどうとかという評価とは全く別の次元で、とにかく好きだったとしか言いようがありません。
彼がガイドとして紹介してくれた領域を漁り、そこからさらに発展して私自身の領域を形成するにあたり、とても与ったと思っているのです。
「波長」が合ったということでしょうか。
今、私の部屋にあるいくらかの本の背表紙を眺めてみると、とある傾向が顕著に読みとれるように思われます。
それは、私がもとより持っていた趣向ではあるのですが、それを発展させ、充実させるに当たり、澁澤さんには随分教えられたと思います。
澁澤さんの本で初めて知ったという事も多数これあり、その意味では随分と影響されたようです。

全集を読み終えてしまうと、もう、これ以上、澁澤作品は無いのだなぁという、ちょっとした淋しさを感じたりもします。
今は、彼の作品の中で紹介された様々な作品に触手を伸ばしたり、はたまた、彼の蔵書目録(←「書物の宇宙誌」という本になっています)から、興味深そうな本を探したりしてます。
私が全集をコンプリートした作家さんは、エドガー・アラン・ポオ、稲垣足穂に続いて三人目です(部分的な全集であれば、「エリアーデ幻想小説全集」とか「ナボコフ短編全集」、「生田耕作評論集成」、そうそう、こちらでもご紹介した「バルトルシャイティス著作集」などなども読了していますが、全著作集というのはこの3人だけです)。
辛辣なことも書きましたが、好きだったのだと思います。
076 「去年マリエンバートで」/アラン=ロブ・グリエ
ようやく読むことができました。ずーっと気になっていたのですけれど、原作は絶版。
映画で有名になった作品ですが、こちらも全くと言って良いほど販売されていませんでした(何だか復刻版というのがあるような記事も読みましたが、とってもお高かったです)。
映画は、アラン・レネ監督が撮ったのですけれど、とても難解だという噂。
原作を、古本でようやくみつけて、買い込みました。
1969年版の第2刷。筑摩書房から、当時の価格で780円で出ていたようです(古書の買値は5000円しちゃいました)。
前書きを読むと、映画のために書いた作品のようです。
ですから、小説の形にはなっていないのですね。コンテです。
撮影を意識しての指示(ト書きとはまた違います)が頻繁に出てくるし、心理描写などもおそらく小説に書いたならもう少し書いてくれたかも知れないという感じで、読みにくいことは読みにくかったです。
ストーリーはというと、名前も付けられていない男性(Aと表記されています)が、とあるホテルに現れます。
そこでは、タキシードやドレスを着た人達が、何だか時間が止まってしまったかのようにたたずんでいます。
その男性は、主人公の女性(Mです)に近づき、「忘れてしまったのですか?」というように話し始めます。
コアのストーリーだけを書くと、男性が言うには、去年お会いしたじゃないですかということ。
その逢瀬があって、女性から、「1年だけ待ってください」と言われて、その1年が過ぎて会いに来たのですよ、と、まぁこういうお話です。
でも、その女性は、最初は(故意にでしょうけれど)、「どなたですか?」という態度をとり続けます。
その女性のご主人らしき人(Xです)もちらちらと出てきます。一緒にホテルに来ていたようです。
まるで、時が止まってしまったかのようなホテル。
演劇が上演されたり、ダンスの時間があったり、はたまた、テーブルではカードが行われていたり。
象徴的に出てくるゲームがあります。主人公の女性の旦那と思われる人が好んでやるゲームです。
それはこういうもの。
○
○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
こんな形にカードでもマッチでも良いのですけれど、並べてみて下さい。
旦那さんは、お相手のプレイヤーに言います。
どれでも好きな列のカードの、好きな枚数だけ取って下さい。一度に取れるのは一つの列にある任意の枚数のカードだけですよ。
その後、私も同じように取りますので、それを繰り返しましょう。
最後に残ったカードを引かなければならなくなった方が負けです。
これ、分かりますよね。必勝法があるゲームです。
旦那さんは、1年越しで現れた男性に対してもこのゲームを何度か挑みます(すべて勝つのですけれどね)。
そんなことをしつつ、男性は、女性に対して、「1年待って来たのですよ」と迫ります。
女性は、「どこでお逢いしたのかしら?」と、言うわけです。拒否しているのですね、最初は。
でも、本当に会った記憶などないようにも読めます。
男性が言うには、「○○か、××か、あるいはマリエンバートでか、お逢いしましたよね。」と。
マリエンバートというのは地名です。
どうやらチェコにある今では温泉保養地になっているところだとか。Marienbadと書くようですけれど、ドイツ語読みだそうです(そうかなぁ? ドイツ語ほとんどできないけれど、ドイツ語読みすると、むしろ「マリエンバット」とか読みそうな気もする)。
「去年マリエンバートで」というタイトルが秀逸だと思います。
何よりも、音の響きが素敵じゃないですか?
私が、この作品にこだわった理由の大きな一つは、このタイトルのせいだったかも知れません。
さて、Mは段々記憶を甦らせてきます。
その間の心象風景が映画で多く語られているのかなと、想像します。
心に浮かぶイメージを連ねているわけですから、これは第三者からすればとてもわかりにくい。
時間や場所を何度も経巡るわけですし、前後の脈絡もないですから、これは辛い。
そんな回想の狭間に、今あるホテルの風景が挟まれるので、なおさらわかりにくいのかも知れません。
原作(コンテ)では、まだ少しの指示から何をしようとしているのかを読みとれる部分もあるのですけれど、これを全て映像で描かれたらかなり難解になるかもしれません。
原作も、とても象徴的なシーンを沢山書いていますので、それだって難解と言えば難解かもしれませんが。
でも、ストーリー的にはかなりシンプルなんですよ。
Mは、自分の記憶(はたして、そうなのだろうか?)を甦らせつつ、最後には、Xを捨ててAについていく決心をします。
このホテルから一緒に出るために、0時にホテルの廊下で待ち合わせをします。
そこに、AもXもやって来るのですけれどね。
余韻〜という感じがします。
うん、ようやく知ることができて、とても嬉しかったです。
いつか、機会があったら、映画の方も見たいなと、思いました。
075 「反復」/アラン=ロブ・グリエ
 作者の、アラン=ロブ・グリエは、「去年マリエンバートで」の原作者です。
作者の、アラン=ロブ・グリエは、「去年マリエンバートで」の原作者です。
アラン・レネ監督が映画にしていますが、これが相当に難解な映画だとか。見たことはないのですけれど。
でも、何とも気になる映画で、是非見てみたい、できるなら原作本を読んでみたいと思っていたのですが、どちらも相当に困難。
原作本は絶版ですし、映画の方も、DVDなど探して見たのですけれど概ね無いようです(復刻版というのを見かけたのですがとてもお高くて)。
で、そんなときに目に留まったのが本書でした。
「あ、ロブ・グリエの本だ」というわけで、迷わず購入して読んでみました。
とっても不思議なテイストの作品です。
主人公であり語り手であるのは、アンリ・ロバンという名の40代の男性。とある密命を帯びて戦時下のベルリンに向かいます。
混雑した列車。ふと席を離れて戻ってくると、自分とそっくりな男が席を占領している。
ここから、作中何度も繰り返されるダブルイメージです(これも仏語で「リプライズ」と題されている「反復」ですよね)。
ようやくたどり着いた駅で、同じ組織の仲間であるピエール・ギャランと合流し、廃墟の建物に案内され、「今から表の通りである男が暗殺される。その様子を観察して報告書にまとめてくれ。」との指令を受けます。
本書は、アンリ・ロバンの報告書というスタイルで書き進められていきます。が、初めは1人称物語風に書かれているので、およそ報告書らしくもない体裁。
しかも、その報告書を読んでいるであろう「誰か」による原注がつけられているのですが、本文である報告書の欺瞞を指摘する内容なのです。
つまり、読者は、ロバンが書いている報告書に沿って物語の筋を追っているわけですが、時折現れる原注によって、「それは間違っている」との指摘を受けるのです。
しかも、状況によっては原注が長く続き、さらに勝手に先のストーリーまで語り始めるため、どこまでが原注でどこからが本文なのかを見失うことにもなります。
アンリ・ロバンは3通の偽造パスポートを持参しており、状況に応じて偽造パスポートに記されている偽名を使います。
すると、作中のロバンの名前が勝手にその偽名で書かれ始めたり、あるいは、「旅人」なり「彼」なりの3人称になったりするので、一体、今誰がこの物語を語っているのかが分からなくなります(ロバンとそっくりな男のことも「旅人」なり「彼」と呼称されていたりもしますので)。もちろん、そもそも原注を書いているのが誰かも。
ピエール・ギャランが言ったとおり、廃墟の前の通りで、とある男性が狙撃されてしまいます。しかし、どこから撃たれたのかはロバンには判然としません。
それをしっかり観察したロバンは、死体のそばに行き、脈が無いことを確認して再び廃墟の部屋に戻るのですが、そこに住み着いていたらしい老婆に目撃されてしまいます。
あんまり書くとネタバレになるのですが、どうにも変な感じがつきまといます。
狙撃したのはロバン自身じゃないのか?という疑惑が……
読者は、あくまでもロバンが書いている報告書を読まされているだけなので、そこに真実が書かれているとは限りません(原注は、まさしくその報告書が虚偽であることを折に触れて主張します)。
その後、少女売春婦の館に紛れ込み、薬をもられたか何かして朦朧とした意識の中で様々な出来事が起こります。
同じシチュエーションが、人を変えてまさに反復されたりもして、ロバンの名前もころころ変わっていきます。
時間のことは最初からぼかされていて、今いつなのかが分かりません。
報告書は5日間の出来事としてまとめられていて、1日ごとに章立てされてはいるのですが、本当にそれは1日の間の出来事だったのかすらあやふやでしかないのです。
自分の認識がぐらぐらさせられます。
映画的と言えば映画的ですが、これを映画にしたら相当に難解なものになりそう。
おそらく、「去年マリエンバートで」も、そういう映画だったのかもしれませんね。
そうそう、その後、ネットで古書ですが「去年マリエンバートで」が売りに出ているのを発見してようやく手に入れることができました。
ちょっとお高かったですが、ゆっくり読んでみようと思います。
こういうタイプがお好きでしたら、良い作品だと思います。オススメ。
「反復」/アラン=ロブ・グリエ
平岡篤頼 訳 白水社
ISBN4-560-04779-0
074 「青ひげ」/カート・ヴォネガット(・ジュニア)
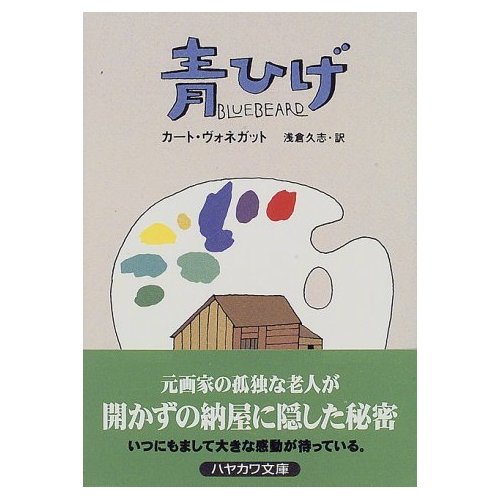 軽妙洒脱というのが、カート・ヴォネガット(・ジュニア)の持ち味でしょうか。
軽妙洒脱というのが、カート・ヴォネガット(・ジュニア)の持ち味でしょうか。
最初に、お読みの方が多分気になっているであろう括弧書きの(・ジュニア)のことから書いておきますね。
「ジュニア」が付いた名前でも著作を残しているのですけれど、お父様が亡くなった後はジュニアを取った名前で書いているのだそうです。それで、両用の表記があるということでご了解を(「ジュニア」あるなしにかかわらず同一人物なのだ)。
まぁ、飄々とした文体です。
一つの章(これだって結構短いです)の中でも、短い文章の塊でアスタリスクを入れて休符し、また続けるような。
シニカルであり、ユーモラスであります。「まぁそういうものだ」などという言葉が、短い文章の塊の最後に繰り返されたりもします。
私が最初にこの作者の作品を読んだのは、何と今年になってからであり、しかもそれは「スローターハウス5」でした。
作者の名前は知っていました。それとなく興味はあったのですが、色々な書評を読んでみても今ひとつピンとこなかったこともあり(あ、読み終えたから言えますが、これは書評が悪いのではなく、こうとしか書けなかったのだろうと納得しています)、ずーっと手を出さずにいました。
でも、気にはなっていたのですよ。
それで、この度読んでみることにしたのですが、さて、何から読もうか?
「スローターハウス5」は、映画化されています。それは大分昔、確か私が中学生だった頃に、「スクリーン」だか「ロードショウ」だかの誌面で紹介されていたことを記憶しているので、多分その頃……今、調べたら1972年に映画化されていました。何にしても、それは覚えていたので、まずそれを読みました。
う〜ん、これをよく映画化したもんだ。
それよりも何よりも、この作品は、それまでにカート・ヴォネガット(・ジュニア)が書いてきた様々な作品の登場人物があちこちに散りばめられているという趣向。
これを最初に読むのはいかんですよねぇ(面白さ半減になっちゃう?)。
では、ということで次にとっかかったのが「青ひげ」でした。
「青ひげ」(Barbe-Bleue)ってご存知ですか?
一般には、童話で取り上げられているあのイメージかもしれませんが、モデルはジル・ド・レイという貴族であるという説もあります。
ジル・ド・レイについては澁澤龍彦が大好きだった様で、散々書いているのですけれど、澁澤が書く「青ひげ」は猟奇的な方。
主たるストーリーは、何度かの結婚歴がある侯爵だか伯爵だかの青ひげが、城中に初々しい新妻を迎えるお話だったと思います。
広い城の中の全ての鍵を渡し、この城のどこでも自由に見てよろしいと言います。しかし、ただ一つの部屋だけは開けてはいけないと。
こう言われると余計に開けたくなるのが人情ってもので(この辺はカート・ヴォネガットも皮肉っているのですけれどね)、新妻は青ひげの留守の間についにその部屋を開けて中を見てしまうのですよ。
その中には、これまでの青ひげの妻たちの白骨化などした死体がごろごろと……(きゃー!)
で、お約束です。そこに青ひげが現れ、「お前は、見てしまったのだな」と……
というのが、オリジナルの「青ひげ」なのですが、今回ご紹介する青ひげはそんなのとはぜ〜んぜん関係ない(あ、換骨奪胎的テイストは散りばめてあるのですけれどね)です。
主人公は、老齢の域に達した画家であった復員兵です。
2度目の結婚で得た(奥さんは亡くなってしまってその遺産を相続したのですね)海辺の広壮な屋敷にしょぼくれて住んでいたおとこやもめです。
彼は、若い頃非常に絵画の素養があり、まぁ、すったもんだの末、極めて写実的な絵を書く有名画家の弟子になります。
しかし、その後、紆余曲折あり、彼自身素晴らしい写実的技術を持っていたのに、抽象絵画の道に進んでしまいます。
そこでもそれなりの成功をおさめたのかも知れませんが、悪いことに粗悪な塗料を使っていたため、高額で買い取られた彼の作品があちこちで一夜にしてはがれ落ちる始末。
もう、絵なんか描かないぞ〜というわけで、当時のアトリエにしていた(今は亡き妻の相続で自分の物となっている)ジャガイモ貯蔵納屋に「ある物」を入れて固く封印してしまいます。
その後は、同じ復員兵の作家と広壮な屋敷で共同生活をしてうだうだと暮らしていたのですが、ある日、プライベートビーチに30代なんですかね、魅力的な女性が入り込んでいるのを見つけます。
まぁ、とがめることもないけれど、一応挨拶でもと声をかけたところ、その女性曰く「ねえ、あなたのご両親はどんな死に方をしたの?」
それがきっかけで、彼女(未亡人ね)に、有り余っている部屋を貸して一緒に生活することになります。
彼女は、その地(実は今では結構なリゾート地になっていて、若者達が来たりもするようです)を舞台にして小説を書くつもりでいたようです。
同居していた仲間の復員兵作家は、素人が何でも書けると思ったら大間違いだよみたいな警句をやんわりと与えたりしますが、が!
実は、彼女は大ベストセラー作家だったのでした!
しかも、好奇心旺盛。勝手に主人公の家の隅々まで、あるいは使用人のプライベートまですんなりと調べ上げてしまいます。
そして、しょぼくれていた主人公には、自伝を書くように勧め、その結果書かれたのが本書という構成になっています。
著者のカート・ヴォネガット(・ジュニア)は、冒頭で謝罪を書いています。「青ひげ」という物語を書くつもりだったけれど、書いてみたら結局はしょぼくれた老人の自伝のようになってしまってすまそ、と(まったく人を食った謝罪ですこと)。
もう、にやにやしちゃいます。
いいえ、もちろん、この作品は「青ひげ」なのですよ。
カート・ヴォネガット(・ジュニア)は、ちゃんと伏線(というよりもっと分かりやすいですけれど)を書いています。
一番分かりやすいのは、この物語の感動的なエンディングにも使われている「ジャガイモ貯蔵納屋」のことです。
ベストセラー作家の彼女は厳重に閉ざされているこの納屋を開けたくて仕方ないのです。
それはまるで、青ひげが開けてはいかんと厳命した部屋のようではありませんか。
それが、最後の数頁に描かれていて、とても良かったなぁという読後感を与えるところなのですが、いいえ、それだけじゃなく、あちこちに「青ひげ」がありますよ。
今回、一読しただけですが、カート・ヴォネガット(・ジュニア)の作品は、結構凝っているかもしれないって感じました。
もっと読み込んでみたら、沢山の「仕掛け」に気づけるかもしれないね。
テイストは軽く。でも良い作品だったのでご紹介させていただきました。
「青ひげ」/カート・ヴォネガット(・ジュニア)
浅倉久志 訳 早川書房
ISBN-4-15-011205-9
073 「君のためなら千回でも」/カーレド・ホッセイニ


最初に目を引いたのは、本書のタイトルでした。「君のためなら千回でも」なんて、素敵なタイトルじゃないですか。
書評を読むまでは、みずみずしいロマンスだろうかなどとも想像しました。
ですが、まったく、そういう作品ではありませんでした。
それでも、本書を読もうと思い、購入して読んでみて、あぁ、素敵な、良い本だなって、思いました。
物語の部隊はアフガニスタンです。しかも、主人公が生まれたのは1963年。
つまりは、僕たちが日本で生まれたちょっと後のアフガニスタンの事柄から、この物語は始まるのです。
私も、アフガニスタンの歴史については無知も良いところです。
昨今の事情から、民族紛争や、テロ、タリバーンのことや、いえ、例の911のこと、その後続いている混沌とした状況程度の知識しかありませんでした。
作者のカーレド・ホッセイニは、1965年にアフガニスタンに生まれたそうです。1976年(作者が11歳の時)父親が在仏アフガニスタン大使館に赴任したのを機にパリに移住。
数年後にアフガニスタンに帰国する予定でしたが、ソ連によるアフガニスタン侵攻が始まったため(このことは作中でも描かれます)、家族はアメリカに亡命します。
その後、作者はカリフォルニア大の医学部を卒業し、1996年から内科医として勤務をしているとのことです。
この経歴を読むと、この作品は、作者の自叙伝的なテイストも少なからず生かされているのかなと思いました。
物語のことをお話しします。
主人公はアミール。
彼の父親であるババは、男らしい男、情味にあふれ、勇敢で人望があり、「熊と闘った男」、「トゥーファン・アハ(Mr.ハリケーンの意)」と呼ばれた誰にでも尊敬された男。
そびえるほどの大男であり、商売もうまく行き、しかも、孤児院を自分の手で建てるような男。
ですから、アミールは、何不自由のない、非常に裕福な家の子供として育てられていました。
アミールの母は、アミールを生んだ時に亡くなってしまいました。
アミールの家には、下働きをするアリ親子が別棟に住んでいました。何故下働きをするかと言えば、それは「ハザラ人」であるから。
ごめんなさい。作中ではそういうことだと書かれていますし、それに関することも少しは書かれていますが、私は、知識が足りなくて、何故そういうことになったのかを、ここでちゃんと書くことが出来ません。
父親のババと同年代であるアリは、片足が不自由でした。
子供は残酷です。アミールは、アリと一緒に買い物に出かけた時、アリの不自由な片足の動かし方をまねしたりしました。
アリにはアミールと同じ位の年のハッサンという男の子がおり、アリと一緒にババの家の下働きとして働いていました。
アミールと同年代で、一緒に遊んだりもするのですけれど、アミールからしてみれば、下男のようなものだったのでしょうか。
いいえ、決してそうじゃなく、本当は友達だったのですけれど、「ハザラ人」は友達ではないのです。
そういう文化だったようです。
ですから、子供心に残酷なこともあります。
アミールは読み書きができますが、ハッサンはできません。それでも、二人は仲良しですから、ハッサンの求めに応じてアミールは本を読んであげたりもします。
でも、子供は残酷です。ハッサンが字を読めないことを良いことに、「○○ってどういう意味ですか?」と聞かれた時、真反対の意味を教えて遊びふざけるなどということもします。
……そういう、子供の残酷さは、私にも経験があります。
ひどいことをしてしまったと、今でも忘れることができない悔悟が、私の心の中にも、あるのです。
いえ、もっとひどいいじめをする悪ガキがいて、アミールとハッサンをメリケンサック(手に鉄の輪をはめて使う殴打するための凶器とでも思って下さい)で殴り倒す寸前まで行ったことがありました。
その時、身を張ってアミールを守ったのはハッサンでした。
得意のパチンコで悪ガキの目に照準を狙い、目を潰されたくなかったら止めろと言って、アミールを守ってくれました(本当は、本人だってがたがたぶるぶるだったのにね)。
その悪ガキは、パチンコにおそれをなして、「覚えていろよ」という棄て台詞を残して逃げていきました。
……こういう悪ガキも、私が子供のころには確かにいました。
私は、そうですね……色々な、当時の「子供の間の理屈」で、いじめられるままになっているような、、、子供だったと思います(ええ、私は、当時は、とんでもない、いじめられっこだったのですよ)。
アミールは、父親のババを尊敬していました。
少しでも、ババの歓心をかいたい、二人だけで一緒にいたいと願っていたのですが、思うようにはならないのでした。
ババは、アミールに対してと同じように、あるいはそれ以上にかもしれませんが、ハッサンも慈しみ、大切にしていました。
それが、アミールにとっては、不満というか、自分は認められていないという気持ちになったのかもしれません。
確かに、アミールは本ばかり読んでいる柔弱な少年で、剛胆な父親が勧めるサッカーも下手くそ、運動もまるで駄目という少年だったこともあったのかもしれません。
この後のエピソードはかなりネタばれになるので、本編を読んでみたいと思って下さった方は、以下読まないで下さい
当時のアフガニスタンでは、凧揚げ競技が盛んでした。
沢山の子供達が自慢の凧を空高く上げ、ガラス糸で手を切り、血を流しながら凧を操り、他の凧の糸を切って落とすという競技でした。
アミールも、ハッサンもこの凧揚げには夢中で、アミールもかなり良い凧使いでありました。
ハッサンは、凧追いの名手だったのです。
凧追いと言うのは、この競技で負けて落ちてきた凧を町中を駆けめぐってでも探して取るということ。
中でも一番の名誉は、最後に残った二つの凧のうち、負けてしまったNo.2の凧を取ってくると、それはその年一年の家宝のようなものだったそうです。
この凧追いって言ったって、日本人が想像するような、広い野っ原に落ちてくる凧を拾うなんていう生やさしいモノじゃなくて、入り組んだ街の路地の中にさえ落ちてくるかもしれない、あるいはどこか知れない広っぱらに落ちてくるかもしれない凧を取ってくるということです。
ハッサンは、風を読めたのでしょうか?
いつも、いつも巧みに凧の落ちる場所に先回りして凧を取っていたのでした。
ある年、これまでの一つの町単位の凧揚げ競技だったものを、多くの町を合同して開こうという企画がが持ち上がり、開催されることになりました。
アミールは、ババから、お前は、勝つと思うと言われます。
それは、親の期待だけの言葉だったのかもしれませんが、アミールとしては、今ひとつ自分に冷たい、ハッサンにさえあのようにやさしい父の気持ちを、期待を得られる場所であると、そう思いました。
その気持ちは、もちろん、ハッサンにも分かっていました。
何度も練習し、アミールは、最後まで残る凧になること、そして、自分が落とした最後のNo.2の凧を、パートナーでもあるハッサンが、獲得して戻ってくる事を願っていました。
アミールは、言います。「あの落ちた凧を取って来い!」と。
素早く駆けだしたハッサンは、振り向きながら(おそらく笑顔だったのだろうと思います……)言います。
「君のためなら千回でも!」と。
その大きな凧揚げ競技の当日、アミールは遂にやり遂げました。
最後まで残った敵の青い凧を落とし、手を血だらけにしながら優勝したのです。
後は、あのNo.2であった青い凧を拾ってくればパーフェクトです。
ハッサンは、任せて下さい!と駆け抜けていきました。
アミールは、これでようやく父親ババに認められる男になれるのだ、と高揚した気持ちでいました。
……ところが、いつまで経ってもハッサンが戻ってきません。
心配になったアミールは、一生懸命ハッサンを探して町中を駆けめぐります。
そこで見てしまったんですね。
あの悪ガキ連中がハッサンを取り囲んでいる場面を。
ハッサンは、青い凧をしっかり手にしていました。
そこで、悪ガキは、その青い凧を寄こせと言います。
ハッサンは、その凧の意味することを痛いほど分かっていたので拒否しました。
悪ガキというのは、性根から腐っている奴というのは、どうしてこういうことを言うのかなということを、ここでも言います。
「分かった。その凧はくれてやろう。しかし、ただじゃないぜ。」と。
アミールは、そこで助けに行こうと思ったのです。思ったのですが、恐くて、行けませんでした。
そこで、どんなに屈辱的なことが行われるか、そして行われたことかを半ばまで見たのに、そこから逃げ出したのでした。
しばらく後、アミールは、今着いたばかりという風を装って、ぐったりしているハッサンの元に戻って来ました。
ハッサンのズボンの尻の辺りにどす黒い赤黒い染みがついているのを見ました。
……
その後、アミールは、ハッサンの友情と献身に応えることが辛くなる自分に嫌気がさし、遂に、ハッサンとその父親であるアリを家から追い出してしまうかもしれないようなことまでしてしまいます……それは、アミールが本当に望んだことなのか、そうではなかったのか……
いずれにせよ、アリとハッサンは、家から出て行くことになります。
大分、ストーリーを詳しく書いてしまいました。
ですが、問題はこの後なのです。
この後のことを「読んでみたい」と思って頂けたらいいなという気持ちだけのめに、今回は書き過ぎも良いところ。本当に上巻のほとんどのストーリーに近い所まで書きました。敢えてです。
もちろん、アミールは、この事を深く恥じています。
それは、それはとても。
ここまででも書き過ぎではありますが、でもこのエピソードは、アミールがまだまだ子供と言っても良い時代のこと。
この後、祖国であるアフガニスタンがとんでもないことになり、ソ連やタリバーンや……まるで地獄絵図のような状況になり、アミールもアメリカに移住します。
でも、ハッサンとのことはアミールの心の奥にあって、それが……この後の、これまで書いてきた以上の長さと重さの話になっていきます。
とても下手なご紹介でごめんなさい。
それほど、長い作品ではないので、よかったら、読んで下さい。
「君のためなら千回でも」/カーレド・ホッセイニ
佐藤耕士訳 早川書房
ISBN978-4-15-120043-4
ISBN978-4-15-120044-1
072 「ポオ全集」/エドガー・アラン・ポオ
 ポオについて、これまで書かずにいたのにも程がある、と、思っています(すんまそん)。
ポオについて、これまで書かずにいたのにも程がある、と、思っています(すんまそん)。
これだけの数の本をご紹介しておきながら、ポオが出てくるのが72番目とは!
おそらくみなさんも、どのような形にせよ、一つくらいはポオの作品を読まれたことがあるのではないかと思います。
エドガー・アラン・ポオ(1809.1.19〜1849.10.7)。アメリカ合衆国ボストン市生まれの作家さんです。
代表作としては、「マリー・ロージェの謎」、「モルグ街の殺人」、「盗まれた手紙」などの推理小説の創始ともなった作品や、暗号物の名作である「黄金虫」(後に、コナン・ドイルがホームズにやらせた「踊る人形」の謎は、すでにこの「黄金虫」で解かれています)、耽美的な怪かしの「ベレニス」、「リジイア」、「モレラ」、じっくりと恐い「早すぎた埋葬」、「アッシャー家の崩壊」、「黒猫」、「赤死病の仮面」、「陥穽と振り子」。
はたまた、緻密な論理的作品である「メルツェルの将棋差し」、壮大な「メエルシュトレエムに呑まれて」、「ユリイカ」。
ユートピア物でもある「アルンハイムの地所」。詩作では、「大鴉」(「……Nevermore」を「またとなけめ」と訳した日夏耿之介訳はあまりにも有名)、その他沢山の名作目白押しです。
ここまでご紹介が遅くなってしまったのは、とにかく作品が幅広すぎて、どうにも手に余ったというのが正しいところだと思います。
今回、筆を取ったものの、さてどこからどう書いたら良いかと悩んでいる位です。
まずは、分かりやすいところから入りましょうか。
推理小説の創始者であるポオのこと
この世に生まれた最初の推理小説は、ポオが書いた「モルグ街の殺人」であるとされています。
単に犯罪を題材とした小説はそれ以前にもありましたが、論理的推理により、犯人を明らかにするという小説、そして、その論理的推理の過程を主題とする小説は「モルグ街の殺人」が嚆矢とされています。
しかも、記念すべき世界初の推理小説において取り扱ったトリックは、いきなり「密室犯罪」であり、「意外な犯人」のテーマだったわけですね(推理小説の王道とも言うべきこの2つのテーマが、第一作において既に語られているすごさってありますよね)。
しかも、この作品において、後のシャーロック・ホームズにもつながる「名探偵」像を描き出してもいます(オギュースト・デュパン登場!)。
う〜ん、「密室犯罪」の点では、ややアンフェアな部分もあるのですが、それは一つの心理的トリックでもあり、私は許容されるのではないかなと思っています。
はたまた、「盗まれた手紙」では、極めて心理的なトリックを創案しています。コアな謎の部分を書いてしまうとネタばれになるので、デュパンが解説した中に出てくる「地図帳地名当てゲーム」のことに触れてみましょうか。
こういう遊びがあります。任意の地図を開き、プレイヤー1は、その地図上に記載されているある名前(都市の名前でも良いですし、山や湖などの名前でも構いません。とにかく、その地図に書かれている言葉なら何でもOKです)を提示します。プレイヤー2は、示された名前がどこにあるかを当てるというゲームです。
オギュースト・デュパンが指摘したことは、初心者はなるべく細かな文字で書かれている言葉を選びがちであるが、上級者になるとそういうことはしないということ。上級者が選ぶ言葉は、例えばその地図の端から端にわたって長〜く書かれている「○○山脈」のような言葉であると。
なるほど!ですね。 たしかに、大きく書かれた文字は見えにくく、探しにくいものであります。そういう心理的盲点のようなことに触れている作品です。
「盗まれた手紙」の謎の主題は、とある手紙の捜索に尽きます。状況から言って、この部屋の中のどこかにあるとしか考えられないのですが、徹底的に捜索したにもかかわらず見つけられないという謎を、デュパンがさらっと解き明かします。
これに似たテイストのトリック(裏から書いているような)は、その後、G.K..チェスタトンがブラウン神父物の中で使っていますね。
「死体を隠すにはどこが良い?」 答は「戦場」。そりゃあ、沢山の死体がごろごろしていますから、見つかりにくいでしょう。
では、戦場が無かったとしたらどうする?
というブラウン神父の知恵により、歴史上の不思議の一つが解き明かされるという内容でした。
とっても恐かったこと
私が「陥穽と振り子」を初めて読んだのは、多分中学生の頃だったのではないかと思います。
今でも覚えていますが、それは、すっごいショックでした。
大体、この物語の始まりが極めて異常で不条理です。その不条理さについてもろくな説明もされません(こういうところは、まるでカフカのようでもありますね)。
主人公は、真っ暗な部屋に閉じこめられています。出口を探そうにも光一つ入ってこないため何も見えません。
主人公は、壁に手を置いて、手探りのようにして部屋を歩き出し、出口の有無や部屋の広さを測り出します。
部屋を一周してみて大体の部屋の大きさは分かりました。そして、出口らしい出口がないことも。
でもこれは、壁沿いに一周してみただけのこと。今度は部屋の中央に歩き出してみます。
部屋の真ん中手前辺りで何かにつまづき、主人公は俯せに倒れてしまいます。
その時、分かったのです。自分の顎の下には何も無いということが(ぞぞぞ……)。
つまり、部屋の真ん中に大きな孔が開いていたのです!
なにも分からず、部屋の中をうろうろ歩いていたなら、いつかきっとこの孔に落ちてしまった事でしょう!(何という恐怖)。
その後、主人公はまた眠らされてしまい、次に目が覚めてみると大きなベッドのようなものの上に仰向けで革のベルトで縛り付けられているのが分かります。
天上を見ると鋭い刃がついた巨大な振り子が左右に揺れています。
「何なんだ!これは!」と振り子を見つめていたところ、その振り子がゆっくり、ゆっくり、少しずつ下がってくるのに気づきました。
シュッ、シュッと、鋭い刃がついた振り子が空気を斬って左右に揺れながら、自分の胸目掛けて少しずつ降りてくるのが分かりました。
その振り子の鋭い刃は、動けない主人公のシャツを切り裂き、少しずつ皮を断ち、肉に迫ってきます。
何と恐ろしいことでしょう!
主人公は、その境地からなんとか脱出するわけですが、その過程までを書いたお話。恐いよ〜!
はたまた、「ベレニス」、「リジイア」、「モレラ」のような耽美的な恐怖を描いた作品もあります。
こちらはまさに病的で耽美的。
母親と娘、死に至る病、墓暴き……それぞれの作品が、そんなことに触れられていきます。
ある作品で、主人公が墓を掘り返して持って帰ってきたのは、真っ白な「歯」なんですよぉ(何と恐ろしくも美しい!)。
「アッシャー家の崩壊」も有名な作品なので、お読みになられた方も多いかもしれません。
このお話の何が恐いかって、それは、朗読している本の通りに音がして、本そのままの状況が現出してくることでしょうか?
アラン・パーソンズ・プロジェクトというロック・バンドがありましたが、彼等は、こういうポオの世界をプログレで表現しようとしていました。
結構、良かったですよ。
さらに、「赤死病の仮面」に至っては、数多ある世界の名作などと称される作品にもよく引用されています。すごくビジュアルな恐怖を描くんです。
この作品では、「色」がポイント。それぞれの色で整えられた部屋を経巡って、やってくるものは……という怖さがあります。
単なる「スリラー」だけではない
じゃあ、ポオはそういう「恐怖」を主だって書いていただけなのでしょうか? いいえ、そんなことはありません。
ユーモラスに、でも極めてシニカルな味わいの作品(「タール博士とフェザー教授の療法」、「アモンティリヤアドの酒樽」、「不条理の天使」等々)も多数ありますし、冒険小説のようなテイストの作品(例えば、「ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピム」など)もあれば、冒頭で書いた「アルンハイムの地所」や「庭園」などは、後に江戸川乱歩が書いた「パノラマ島奇譚」のネタ元であります。宇宙の不思議、そもそものこの世界の始まりについてまでも言及しており、あの時代にしては結構良い推測もしています。宇宙物と言えば、H.G.ウエルズが思い浮かびますが、ウエルズは1866年生まれですから、それより先に没したポオの方がとっくに早く宇宙旅行物の先鞭をつけていたのですね(「軽気球夢譚」がそうだった記憶です)。……あ、そうだね。ジュール・ベルヌもSFの創始者だけど、彼が書いた最初期の「気球に乗って5週間」だって1863年作ですから、ポオの方が早いのではないかなぁ。
とにかく、よくもまあ、これだけ様々なジャンルで、しかも素晴らしい作品を残した物だと驚愕してしまいます。
ポオの全集としては、私も持っている冒頭の写真の物(東京創元社刊のハードカバー全3巻もの)が定番だろうと思うのですが、この度出版社のHPで確認したところ、在庫無しになっていました。
ありゃりゃ。
お求めやすいところでは、同じく東京創元社の創元推理文庫から、「ポオ小説全集」全4巻が出ていますので、今入手するならこれですかね。
とりあえず、そちらの情報を書いておきますね。
「ポオ小説全集」/創元推理文庫
ISBN:978-4-488-52201-8
ISBN:978-4-488-52202-5
ISBN:978-4-488-52203-2
ISBN:978-4-488-52204-9
071 「魔の山」/トーマス・マン
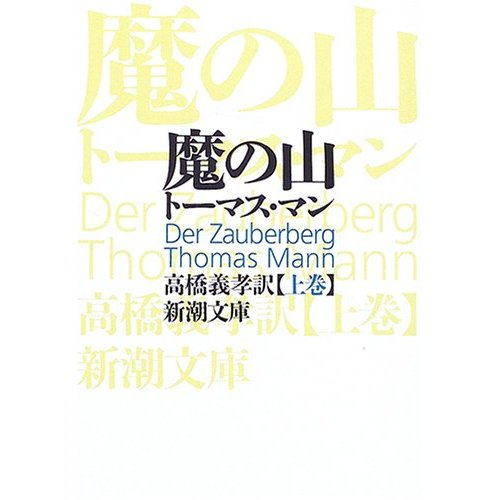
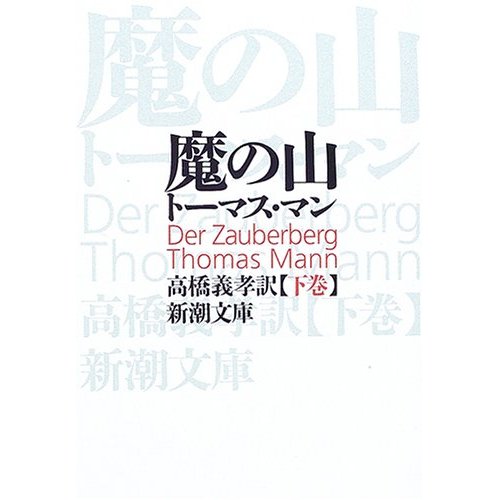
3度目の正直!
どーしても、どうしても読めなかった本ってありませんか? その一つをようやく読了できました。
私は、結構しぶとく読み続けるタイプなのですけれど(それは良くないという指摘も分かるのですけれど)、そうやっていても、今までにどうしても読めなかった本がいくつかあります。
その一つが、このトーマス・マンの「魔の山」でした。
最初にトライしたのは、いつの頃だったかしらん。高校生位だった記憶です。はい、挫折しました。
その後、多分、大学生だった頃か、就職した後に、もう一度トライしたと思うんですね。
でも、やっぱり、あえなく再度挫折しました。
で、その本は、「実家送り」になっていて、もう、何年もお蔵仕舞のままでした。
だって、な〜んにも起こらないんですもの。いえ、それなりの出来事はあるのですけれど、なんていうか、結末に向かっての一貫した「流れ」のようなものはなく、ただただ、時が過ぎていくだけ。
えっと、「えふの本棚」を読んで下さっている方で、「今年読んだ本」なんかも見て下さっている方は何となく気づかれていたかもしれません。
最近、私の読んでいる本って、いわゆる古典名作辺りが多いって。
うん、そうなんです。
実は、実家を改築するという話が出て、中学生〜高校生、大学生の頃までに、私が買った本が実家に溜まっていたのですけれど、その中で、必要な本だけ引き上げてきたのでした。
その時の本を、最近読み直していたりします。
「魔の山」も、そうやって戻ってきた本で、今回が3度目のトライ。
目出度く読了できました。
主人公、というか、このお話の軸として描かれているのは、ハンス・カストルプという、何の変哲もないふつーの青年です。
いとこのヨーアヒム・ツィームセンが、高い山にある国際療養施設、サナトリウムですね、「ベルクホーフ」に入院していました。
ハンスは、これから造船会社に就職することが決まっていたのですが、ちょっと体調を崩したこともあって、いとこの見舞いがてらにこのサナトリウムで3週間の休暇療養を過ごすために高地を訪れました。
ベルクホーフは、いたれりつくせりの施設です。
毎日5回の、滋養に溢れる、贅沢な食事が振る舞われ、絶妙の寝心地を提供する寝椅子に、毛布にくるまって横になり、「水平生活」と揶揄されるような、穏やかな療養生活を送ります。
滞在者は、みんな病気を抱えており、時々亡くなってしまう人のことも描かれますが、総じて「病人」というイメージは湧いてきません。
多少の熱がある人でも、通常人と同じような生活(それも、とても贅沢な)を送り、優雅に暮らしている様が描かれます。
それは、「下界」のことを忘れさせるような、素晴らしい体験であるように、「外来者」のハンスには思えました。
しかし、いとこのヨーアヒムは、軍人志願で、もう、入隊が決まっていたのに、病気のためにそれも叶わず。
ヨーアヒムとしては、病気を治すために与えられた日課をきっちりとこなし、一日でも早く「下界」に戻り、軍人としての生活を全うしたいと誠実な暮らしをしていました。
最初は、「外来者」であったハンスですが、ここで、発病してしまうのですね。
熱は下がらず、専門医の診断では間違いなく肺病だとか。
最初は、3週間の見舞い療養だって長すぎると思って訪れたのに、ここで数ヶ月過ごすようにとの診断を下されてしまいます。
さて、ここからが、「魔の山」の世界になっていくのですね。
な〜んにも起きません。
いえ、起きますよ、日常生活の細々としたこととか、ハンスが知り合いになるセテムプリーニというイタリア人との形而上的な会話(……これは、その後、セテムプリーニの論敵であるナフタとの論争に発展します……その結末は……)、あぁ、クラウディア……いえ、ロシア人であるショーシャ夫人に惚れ込んで、恋してしまうハンスとか。
それなりのエピソードはありますが、でも、物語の「筋」というものがないのです。
最後まで読みましたが、最後のシーンに連なる伏線、あるいは、そこに導くためのストーリーなど、なにもありません。
ただ、ただ、雪に覆われ、薄い空気を吸い、下界と隔絶された、サナトリウムの中の日々が連綿と綴られていくだけです。
この作品は、丹念に「時間」を書いているように思えました。
ええ、作者も、読者に向かって、そういうことを書いていますし、ハンスの口や思考を借りて、そのテーマを論じてもいます。
ベルクホーフ周辺の季節感もその伏線になっているように感じられます。
季節感、と、書きましたが、これが無いのです。夏のような、真っ青な空が広がる日々があるかと思えば、季節的には夏なのに、ひどく冷え込み、雪まで降ってしまう日もある。
私たちが、時間を感じるよすがの一つでもある季節感が完全に狂わされています。
そして、ベルクホーフの滞在者達も、そのような時間の流れに身を浸しきっているのでした。
後半に出てくるちょっとしたエピソードですが、ハンスは、ある時、時計を落として壊してしまったのですが、もう、それをなおそうともしません。
時間など、無くなってしまう世界なのかもしれませんね。
私たちが、小説を読む時に費やす時間があるじゃないですか。
でも、おそらく、時間軸で比べたなら、要領よく描かれている作中の人物達の時間の方が早く過ぎていくことでしょう。
それは、「小説」というスタイルを取る以上、仕方のないことなのですが、何だか、この作品は、ところどころで、そういうことに反旗を翻し、たとえば、セテムプリーニとナフタの難解な議論を丁寧に追って書き込んでいたりもします。
でもね、いくら書いてみたところで、それは、彼等の思考の速度には追いつかなくて、だからどうしてもはしょらざるを得ないから、やっぱり作中の時間の方がどうしても早く流れてしまうのだけれど。
作者が、そういう時間に論及するところもいくつかあります。
特に、初期の頃など、そういう作品を目指していたのではなかったのだろうか、と思わせたりもします。
何と、この作品を書き上げるまでに要した時間は11年程だったとか。
ラストは、それなりの描写がありますが、やや強引に「閉めた」とも感じられます。
きっと、そのままにしておいたら、「魔の山」は、いつまでも続く物語だったのかもしれません。
表紙絵は、おそらく現在出版されているであろう、新潮文庫の改訂版の方です。
もちろん、私が読んだのは、当時の自分の少ないお小遣いで買った、実家に残されていた文庫本です。
長い、長い物語ですが(当時の細かい字で書かれた文庫で、上下それぞれ650頁前後のものです)、じっくり読んでみると良い作品です。
ようやく、読了できた記念で書いてみました。
「魔の山」/トーマス・マン
高橋義孝 訳 新潮文庫
ISBN:13-978-4002022023,13-978-410202230
070 「オトラント城奇譚(オトラントの城)」/ホレス・ウォルポール

ゴシック・ロマンス、ゴシック・ファンタシーの創始と言われる作品です。
そういう、文学史的にはそれなりに重要な作品なのに、実は今、日本で読もうとすると、すっごく大変。
誰も顧みてくれないのかなぁ。過去に出ていたのは全部、絶版になっちゃっています。
今回、探してみたのですけれど、やっぱり表紙絵でご紹介できるのは、今はこれしかないようです。学研M文庫なのですが、これは擬古文で書かれていて、ちょっと読みにくいのです(私も持っていますが……)。
もう、一冊、絶版承知で買い求めて持っている本があるのですけれど、そちらは入手困難なのでちょっとご紹介するにはふさわしくない、ですね。
ちなみに、それは、国書刊行会の出版で井出弘之さんが訳してくれています。
物語は、オトラント城の当主であるマンフレッド公の息子のコンラットの結婚式を翌日に控えた日から始まります。
病弱な息子で、あんまりぱっとしなかったのですけれど、マンフレッドとしては跡取り息子なので、何とか家督を継いで欲しいとの思いでした。
迎えた花嫁は、ヴィチェンツィア公の息女イザベラ。実は、彼女としては望まない結婚なのですが、半ば強引に……というか、ほとんど略奪のようにってなもんです。イザベラは、今は行方が分からなくなっている父親のヴィチェンツィア公が助けに来てくれるのを待ちわびています。
ですが、現実は、コンラットが華燭の典を挙げられるだけの体調になったら、すぐにでも式を挙げられるように、と、既にお輿入れしていたというわけです。
イザベラは、気が進まない結婚ではありましたが、それでも、将来義母となるであろうやさしい母親のヒッポリタや、義姉となるマティルダとは仲良くやっていました。
しかし! 異変が起こったのです。
実は、マンフレッド公は、オトラントの領地を横紙破りのようにして奪い取った男で、正当な領主ではありませんでした。そのため、「オトラントの城館と領主権は、真の所有主が住まいきれなくなるほど大きくなった暁には、現在の一族の手を離れるであろう」という不吉な言い伝えが残されていました。
ですから、余計に病弱な一粒種でもあるコンラットに早く家督を譲れるようにしたかったのでしょうね。
でも、それも叶わなくなります。予言が、実現してくるのですね。
巨大な兜がどこからともなく現れ、空に浮かびます。
あれよ、あれよと言う間に兜は城の庭先に激突します。
そして、コンラットは、その下敷きになってあえなく絶命してしまいます。
城中は大騒ぎ。
何だ、あの巨大な兜は! 呪いだ、予言だとの声が充ち満ちる中、激怒したマンフレッドが見分に現れます。
横死してしまった息子の遺体などそっちのけで、「何だ、これは!」という憤りだけ。
その時、城に集まった野次馬連中の一人から、「あの兜はアルフォンソ様の黒い兜にそっくりだ……」と漏らされたつぶやきに激高します。
アルフォンソとは、オトラントの正当な領主であった人で、その像が、今は領地内の聖ニコラス教会堂に奉られていました。
その後、見てみたら、確かにその像から兜だけ無くなっていたのですけれどね。
自分のもくろみを打ち砕かれたマンフレッドは、その言葉をもらした、一見、農民の息子に見えるような男を召し捕り、「お前が兜を落としたのだ!」と決めつけ、処刑するために拘束します。何というご無体な。
実はこの若者、むにゃむにゃむにゃ……その正体は、なのですけれどね。
んで、ひどいのはマンフレッド公。
跡取りを残せなくなったので、自分で作っちゃおうという、何だ、このおやじは!
あろうことか、息子の嫁にということで手元に引き寄せていたイザベラと結婚しようとします。
はい、賢明な妻のヒッポリタと離婚してまで。
そんなことは通るわけもなく、聖ニコラス教会の神父、ジェロームに厳しく諫められます。
そのような人倫にもとる振る舞いなど、神はお許しになりませぬ!
だけど、そんな忠言なぞ、聞く耳持ちません。
たたるんですよぉ、この後も。
肖像画が動いて、その主がさまようとか、すっごく大きな籠手や足が城に現れたりとか(兜のサイズと、多分同じなんだろうね)。
一方、イザベラは、「俺とけっこんすれ〜!」と迫るマンフレッド公から逃れるため、教会へと続く地下の秘密の通路に逃げ込みます。
そこで、捕らわれていた一見農民の息子さんと出会い、辛くも追っ手から逃れ、教会に逃げ込みます。
最初に書いた、ゴシック・ロマンスって、今ではかなり陳腐化したこういうお話のこと。
でも、こういうお話のスタイルが出来上がるまでには相当長い時間がかかったのですね。
確かに、今さらこんなお話を読みたいという奇特な方もいないかもしれないけれど、でも、これがエポック・メイキングな作品だったって言われると、ちょっと読んでみたくはありませんか?
この後、多くの同じような作品も書かれるようになっていきます。初期の頃だと、ルイスの「マンク」とか、マチューリンの「放浪者メルモス」、ベックフォードの「ヴァティック(ヴァセック)」、カゾットの「悪魔の恋」なんかが有名どころ(と、言っても、すっごく濃ゆいお話なので、普通の文学史などには全く載っていないとは思いますが)。
もう少し有名なところだと、メアリー・シェリー(シェリー夫人と言った方が通りが良いでしょうか?)の「フランケンシュタインの怪物」なども書かれるようになりました(「オトラントの城」が書かれたのは1764年、「フランケンシュタイン……」が書かれたのは1818年です)。
作者のホレス・ウォルポールは、イギリスの国会議員です。
名家の出でございまして、裕福にあかして、実はストロベリー・ヒルという地所を買い込み、そこにゴシック趣味の城まで建設しちゃったのでした。
建物をを造った……と言えば、先ほどご紹介したベックフォードも、フォントヒルという地所に僧院を建ててしまったりします。
約84メートルにも及ぶ塔を建てたのですけれど、これが2度に渡り崩壊するんですね。
どうも、当時の建築技術を無視して、高く作りすぎたのではないかと……
ホレス・ウォルポールの息子であるヒュー・ウォルポールも、一つだけ良い作品を書いています。
ついで、というわけではありませんが、ご紹介しておくと、それは「銀の仮面」という作品です。
これは恐いお話ですよ。
年老いた、一人暮らしをしている品の良い裕福なご婦人のお話です。
健康にも気を配っていて、静かに暮らしています。
と、ある夜、家の扉をノックする音が聞こえました。
「何かしら?」と、思って出てみると、とてもきれいな顔をした若者が立っていました。
彼は、とても貧しくて、食うや食わずの状態のようです。
ただ、ただ、情けを請いにやって来たのでした。
その晩、彼女は、豪勢な夕食を済ませていました。
どうして、家の中に入れてしまったのでしょう。
サンドイッチを出してあげました。
彼は、彼女の家の中の趣味の良い美術品の中から、壁に飾られていた銀の仮面の前に立ち、とても良いですね、と言います。
彼は、その夜は、丁寧に礼を言って帰るのですが、しばらくすると、今度は、子供と妻を連れてやってきました。
ひもじそうな子供達を見て、善意からまた家に通してしまう彼女。
それからはどんどんエスカレートするばかりです。
好きなように家の中で振る舞う家族。
彼女は気苦労でどんどんげっそりして、しまいには寝込んでしまいます。
「出て行って!」とすら、もう言えなくなってしまって。
最後は、恐いですよ。
彼女が寝込んでいる寝室で、彼は、「寂しいでしょう?」と言って、銀の仮面を壁にかけて、そして……寝室の鍵をかけて出て行ってしまいます。
「オトラント城奇譚」/ホレス・ウォルポール他 ゴシック名訳集西洋伝奇物語(7) ISBN10-4059-00297-6
「銀の仮面」/ヒュー・ウォルポール 国書刊行会 ISBN4-336-4244-6
069 「白鯨」/メルヴィル
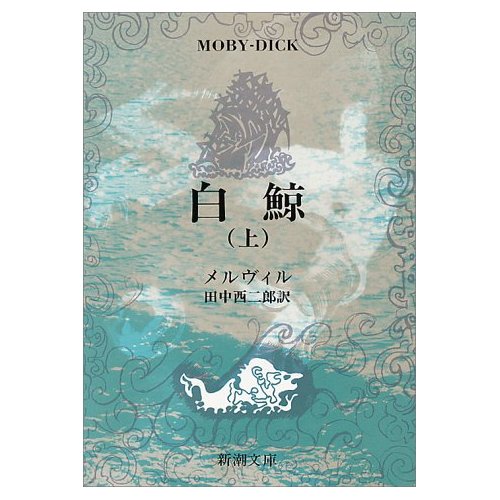
エイハブ船長の執念の物語、白鯨です。
主人公、というか語り手はイシュメールという名の、まだ経験も浅い船乗り。
職を探して、港町の旅籠を訪れます。「汐吹亭」という旅籠に何とか潜り込み、相部屋となったクィークェグと一夜を共にします。
このクィークェグ、見た目は恐ろしいし、何ともおっかない感じなのですが、実はとても良い奴で、これから先の航海でも頼りになります。銛手です。
で、イシュメールとクィークェグはピークォド号に船乗りとして乗り込むことになります。
この船の船長が、エイハブ船長。片足をモビー・ディック……つまりは、巨大な白鯨(マッコウクジラです)に食いちぎられ義足となっています。何としてもあいつを仕留めてやるという執念にかられた船長です。
商業捕鯨ですから、それなりの数の鯨を捕獲して帰らなければ船主は満足しないのですが、エイハブ船長の頭にあるのは白鯨のみ。
表面上は、一応、商業捕鯨に出かけることにしていますが、願いはただひとつ。あの、モビー・ディックを仕留めることだけ。
ピークォード号に乗り組む面々も個性的です。
冷静な一等航海士、スターバック。血気盛んな(いや、これは…)二等航海士のスタブなどなど。
「誰でもよい。額に皺があって、顎のまがった白いあたまの鯨を見つけてくれたやつには─あの白頭の、右舷の尾に三つ孔のあいた鯨をみつけたやつには─これ、みろ、その白鯨(しろくじら)みつけたやつにはな、この金貨をくれてやるぞ!」
エイハブは全船員を前にして、大帆柱にスペイン金貨を打ち付けます。
作者のメルヴィルも、船員としての経験もあり、その辺の知識もふんだんに活かされて描かれた海洋小説ということでしょうか。
おそらくは、教科書的に「まとめ」られているお話としては、執念のエイハブ船長が最後には白鯨と相見舞える物語ということになっているのだろうかとは思いますが、実際に読んでみると、主たるストーリー以上に細かく語られている、捕鯨や鯨の生態学、博物誌的なところが大きなヴォリュームを占めています。
私は、博物誌とか大好きなので、その辺りもとても興味深く読ませて頂いたのですが、ストーリーを追いたいという方には、ちょっと、うっとおしいかもしれませんね。
そんな部分も挟みつつ、最後はモビー・ディックとの決戦になります。
……ここで余談なんですが、今年、何故かおおはやりした「蟹工船」。
私は、あれ、まったく偶然に、マスコミなどに取り上げられる前に、今年、「青空文庫」で読んだのでした。
「青空文庫」は、御存じだと思うのですが、著作権が切れた作品をデータとしてUpしてくださっている、とても素晴らしいサイトです。
私は、このデータを取り込んで、通勤途中などに携帯で読んでいるのですが、なかなか趣味に合う作品が無いと言えば無いです。
ですが、今まで読まなかった作品を読むという意味ではとても良いかも(以前、三中の板にも書きましたが、「源氏物語」もこれで通読しました)。
そんなノリで、実は、蟹工船も読んでいたのですね。
そうしたら、それからしばらくして、あれよあれよと大ヒット? 分からないものですね。
いや、横道にそれてしまいました。うん、蟹工船も、漁師さん達の苦闘が描かれています。それはそれは残酷なほどに。その先のお話もある蟹工船ですけれど、白鯨はそういう思想的なことは抜きにして、そう、先ほどお話しした、エイハブ船長と白鯨との死闘につながっていきます。
スターバック、クィークェグ、スタブ……それぞれの思いも巻き込みながら、眼前に現れたモビー・ディックとの戦いに否応なしに巻き込まれます。
文学的に、名作としてあげられるアメリカの作家さん(実は、あんまり好きな人がいないんですよね、アメリカの作家さんって。ポーが一番かなぁ。)の作品ですが、そういうことじゃなくて、作品として、読んで、うん、なかなか良いじゃないって思える感じです。
*追記
カミュは、その作品である「シーシュポスの神話」の中で、「不条理」な作品の例として、「白鯨」を挙げています。
訳者によれば、カミュはここで、「不条理」という言葉を特殊な意味に使っており、それは、「この世界が理性では割り切れず、しかも人間の奥底には明晰を求める死に物狂いの願望が激しく鳴りひびいて、この両者がともに相対峙したままである状態」のことを「不条理」としているそうです。
なるほどね。
「白鯨」/メルヴィル
田中西二郎 訳 新潮文庫
ISBN4-10-203201-0
ISBN4-10-203202-9
068 「法王庁の抜け穴」/アンドレ・ジイド
ジュリアン・ソレルは、「赤と黒」。
ラスコーリニコフは「罪と罰」。
ドリアン・グレイは、その名のとおり、「ドリアン・グレイの肖像」。
えっと、あとは……そうそう、ハンス・カストルプは、「魔の山」。
私たちが、主人公の名前で作品を語らなくなって、どれだけ経つでしょうね。
主人公の名前さえ、あんまり記憶に残らなくなったのかもしれません。
そういう、主人公の名前が、残る小説のひとつだと思います。「法王庁の抜け穴」は。
この作品の主人公の名前はラフカディオ。
不条理、といえば、不条理なことをしてしまいます。
無機質めいたところもあって、それは、つい先日再読した、カミュの「異邦人」の主人公であるムルソーと、少しだけ似ているのかもしれない。
アンドレ・ジイドっていうと、一番に思い浮かぶのは「狭き門」じゃないですか?
この作品も、再読しなければって思ってはいるのですけれど、今のところ、私の記憶の中にある「狭き門」の印象は、「どうして?」ということかもしれません。
個人的な感想ですが、おそらく、ジイドの作品としては、「狭き門」じゃなくて、「法王庁の抜け穴」こそがベストではないかと(ジイド、全部読んでいないので、ベストというのはおこがましいですが、それだけインパクトがある作品に思えます)。
冒頭に書いたように、主人公であるラフカディオのことが、とても印象深く残ります。
物語の前半は、結構「たるい」かもしれません。何をどうしたいのかなぁ……と、読んでしまいました。
しかし、とある時から、ぐっと引き締まってきます。
あぁ、前半であんな風に描かれていたラフカディオは、こうなっちゃうのかって。
「えふの本棚」は、いつもは、粗筋ばかり書いていて、とても下手なコメントなのですが、今回は粗筋は書かないようにしました。まぁ、どうやっても下手だなぁとしか思えないのですけれども。
でも、下手なのは、私のご紹介だけにとどめていただいて、是非、「法王庁の抜け穴」をお読み下さい。
まだ、読んでいらっしゃらない方、読まないと、きっと損しますよ。
不条理加減と、そこにある弱さのような感覚が、良いかもって思いました。
その辺の、感性を読んで頂けると、すっごくいいですよ。
「法王庁の抜け穴」/アンドレ・ジイド
石川 淳 訳 岩波文庫
ISBN4-00-325583-6
067 クラフトエヴィング商會のこと
クラフトエヴィング商會のネームで沢山の本が出ています。
とても、ファンなので、結構買い込んで読んでいます。
え? どんな本なのかですって? たとえば……
「クラウド・コレクター」
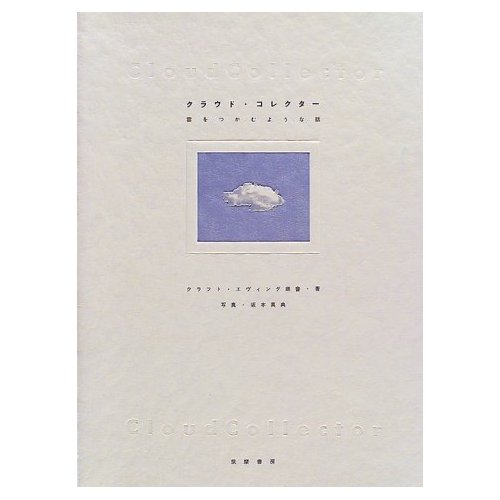 昭和9年、とある科学雑誌のそこだけ紅色が使われた広告頁に「雲、売ります」という広告が出ていたそうです。
昭和9年、とある科学雑誌のそこだけ紅色が使われた広告頁に「雲、売ります」という広告が出ていたそうです。
広告主はクラフトエヴィング商會。
現在のクラフトエヴィング商會の祖父である吉田傳次郎が出した広告なのです。
本当に雲なんて売ってたの?
あるとき、商會の倉庫を整理していた時、祖父が使っていた古い革の鞄が見つかりました。
中を開けてみると、数十本の小瓶が入っていました。どの小瓶にも見たことがないラベルが貼り付けられていました。
これは一体?
というわけで、本書は、一つ一つの小瓶に入っていた物をご紹介するという仕掛けで進みます。
……たとえば、No.2のラベルの瓶に入っていたのは「雲母酒」。とても柔らかな、でも、危険なお酒のようです。
クラフトエヴィング商會の正体は、といえば、吉田浩美さんと吉田篤弘さんというブックデザイナーのご夫婦なのでした。
とても素敵なデザインをされるご夫婦で、ですから、クラフトエヴィング商會のご本には、手塩にかけて作られたさまざまなアイテムが満載です。
また、この写真が素敵なんです。
クラフトエヴィング商會の数々の商品?の写真をお撮りになっているのは、坂本真典さん。
透き通るような写真を撮影しています。
この辺が、とっても味なんですよ。
「どこかに○いってしまった○ものたち」
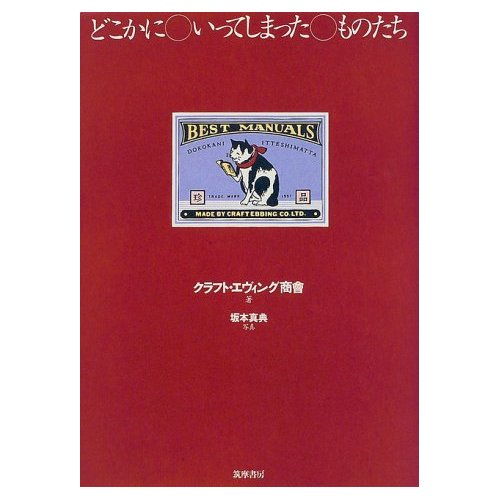 クラフトエヴィング商會にある、古い引き出しには色々な物が入っています。
クラフトエヴィング商會にある、古い引き出しには色々な物が入っています。
その中の一つに、商品目録があるのです。
この商品目録は、クラフトエヴィング商會がこれまでに取り扱ってきた不思議な物が沢山掲載されています。
たとえば……「記憶粉」なんていう物があります。
ひとは、色々なことを忘れてしまいますよね。そんな時に飲む薬、だったのでしょうか?
「ないもの、あります」
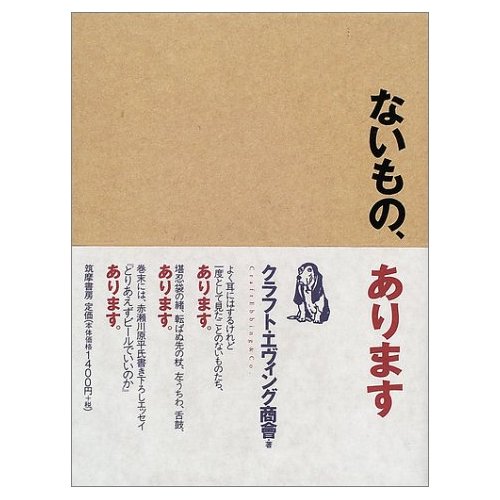
クラフトエヴィング商會が取り扱う商品はとても多彩です。
中には、良く耳にはするけれど、現物はついぞ見たことがない、などという物も、クラフトエヴィング商會では取り扱っているのですよ。
「堪忍袋の緒」なんてどうでしょうか? そうそう、切れてしまうあれですな。
お役に立ちそうなところでは「助け船」なんていうのもあります。
そうそう、「左うちわ」や、「口車」なども取り扱っておりますよ。

ところで、「AZOTH」という国のことは、お聞き及びになったことがありますか?
「アゾット」と読むんです。
現在のクラフトエヴィング商會の祖父である吉田傳次郎が残した物の中に、「アゾット事典」なるものがありました。
傳次郎が大切にしていた事典のようですが、記憶では、傳次郎は、「見るたびに中身が変わる事典」と話していたようでした。
アゾットという、どこにあるのか分からない、きっと遠いところにあるのかもしれない国の、諸々のことが書かれている事典なのです。
ちょっと、読んで見ますか?
「すぐそこの遠い場所」
その他にも、「アナ・トレントの鞄」、「テーブルの上のファーブル」、「らくだこぶ書房」、「じつは、わたくし、こういうものです」などなど、う〜ん、とても素敵な本が沢山あります。
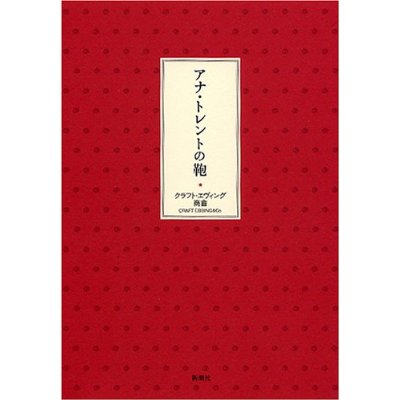
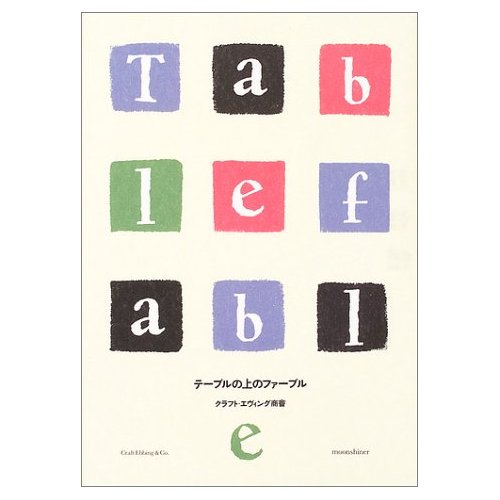

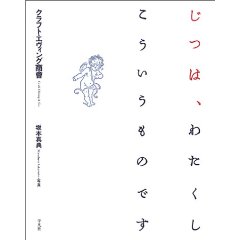
あるいは、吉田ご夫婦の娘さんである音(おん)さんも、才能を引き継いだのでしょうか。「Think」や「Bolero」などの「ミルリトン探偵局シリーズ」を出しています。猫がお好きな方にはおすすめですよ。
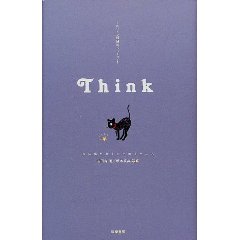
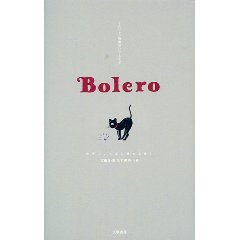
はたまた、ご夫婦がそれぞれ単独で作っている本もあります。
奥様の浩美さんは、「a piece of cake」、旦那さんの篤弘さんは「つむじ風食堂の夜」とか……(他にもたくさんあります)。


でも、どれも、やっぱりクラフトエヴィング商會のテイストが漂うんですよね。
ちょっと温かいお茶でも入れて、読んでみませんか?
066 「深夜プラス1」/ギャビン・ライアル
 主人公のルイス・ケインは、かつてカントンという名で闘った、レジスタンスの闘士。戦後の現在は、ビジネスエイジェントを生業としています。
主人公のルイス・ケインは、かつてカントンという名で闘った、レジスタンスの闘士。戦後の現在は、ビジネスエイジェントを生業としています。
あるとき、かつてのレジスタンスの同士で、現在はパリの腕利きの弁護士となっているアンリ・メランから、マガンハルトという大富豪をブルターニュからリヒテンシュタインまで車で送り届けて欲しいとの依頼を受けます。
間違いなくやばそうな依頼ですし、撃ち合いもあり得るとのこと。高額の報酬を約束されますが、とにかくやばそう。
とはいえ、昔の同士からの依頼でもあるので、いつも2人で仕事をすると言われているヨーロッパでNo.1とNo.2と評価されているボディガード(拳銃の使い手ですな)ペアをつけてくれるのならという条件で引き受けようとします。しかし、そのNo.1及びNo.2のガンマンペアとは連絡が取れないということなので、それではということでNo.3と言われているハーヴェイ・ロヴェルを指名し、OKをもらいます。
ロヴェルと落ち合ったケインは、マガンハルトの車であるシトロエンを受け取りに約束の場所に赴いたところ、バンパーの下に貼り付けてあるはずの車のキーが見あたりません。不審に思いながらもドアを開けてみたところ、開くではないですか。しかも、キーは差しっぱなし。
どうしたんだ?と思い、後部座席を見ると、運転手の死体が!
既に手が回っています。
とは言え、引き受けたものは仕方がない。とにかく死体を載せたままシトロエンを運転し、マガンハルトと落ち合う予定の海岸に向かいます。
夜の闇の中、ケインとロヴェルは運転手の死体を始末し、約束通り、沖合に停泊しているはずのマガンハルトを載せた船に向かって合図を送ります。
ほどなくして、船から船員に伴われたマガンハルトが上陸してきます。ところが女連れ!
何だ、この女は! 聞いていない話だ。
しかし、マガンハルトは、その女性も一緒にリヒテンシュタインに行くのだと言い張ります。
仕方なく、女連れでマガンハルトをシトロエンに載せ、出発する一行。
まず、間違いなく、こちらの状況は敵に察知されていると考えた方が良い。
とにかく、アンリに連絡して、運転手が殺害されていたこと等の状況を伝えます。
マガンハルトが何故リヒテンシュタインに行くのか、その目的はよく分からないものの、とにかく、早急に行かなければならないとのこと。
アンリの当初の依頼から、マガンハルトは婦女暴行の嫌疑でフランス警察に追われていることは分かっていますが、どうやらこれは濡れ衣くさい。
しかし、少なくとも警察に追われていることは事実。
夜通しシトロエンを運転し、明け方、とある村に着きます。朝食を取ることにし、村のカフェに入ります。
そこで流れていたラジオニュースによると、マガンハルトを載せて来た船が拿捕されて、その船員達が捕まったとのこと。
またしても、行動が読まれている。
船員達は、マガンハルトを上陸させたいきさつをしゃべっていることでしょう。
とにかく出発することにして、シトロエンを止めた場所に向かったところ、ロヴェルから立ち止まるなとの指示が。
ははぁ。シトロエンの前後を挟むようにして車が止められています。
うっかりシトロエンに乗り込もうとでもすれば、狙撃されるのは目に見えています。
立ち止まらずに裏通りに入り、マガンハルトと連れの女性を残し、ケインとロヴェルは戻ります。
この位置関係からすれば、向かいのカフェ当たりに張っているはず……いました、いかにも怪しい3人組。
何気なく、向かいのカフェに入るケインとロヴェル。あっという間に3人を組に銃を突きつけ、外に出ろと指示します。
3人組のリーダーらしい奴が抵抗しますが、ロヴェルは即座にその男の右手を潰してしまいます。
抵抗できずに外に連れ出される3人組。しかし、リーダーは左利きだったのです!
銃撃戦が始まりますが……
というような調子で、マガンハルトをリヒテンシュタインまで護衛するサスペンスが本作です。
この先、様々な出来事が起きますが、少しだけご紹介すると、実は、ロヴェルはアル中だったのです。
このミッションを引き受けた時から、酒を断っていたのですが、予定していた時間にリヒテンシュタインに着けずミッションが長引くに連れて手が震え出します。
頼りのガンマンがこれじゃあ…… 手が震えたガンマンが良いか、その先泥のようにダメになってしまうかもしれないけれど、とにかく酒を飲ませてしばらくの間だけでも使い物になるガンマンがましか?
その先も、ことごとく情報が筒抜けになるのは何故か?
マガンハルトの連れの女の正体は? この女、この先、禁じられているにもかかわらず、度々電話をしようとします(気付かない間にどこかと連絡を取り続けていたのかも)。
絶体絶命の一行を救う、昔のレジスタンス仲間達。ですが、その中の一人とはどうしても会おうとしないケイン。それは何故?
そして、遂に姿を現したヨーロッパNo.2と言われるガンマン(もちろん、敵に雇われていました)。ということは、ペアで仕事をすると言われているNo.1もいるのか?
フランス警察の執拗な追跡。
こんな感じでサスペンスとスピード感たっぷりに話が展開していきます。
一気に読み切ってしまえるおもしろさがあります。
銃や車に関するこだわりの描写もハードボイルドに薬味を添えます。
名作との誉れ高い作品です。
こういうタイプの小説はあまり読まないという方にこそ、是非お勧め。
実は、私もあまりこういうタイプは読まないのですが(それはこれまでご紹介してきた作品の傾向から言ってもおわかりになると思いますが)、それでも本書は面白い!とお勧めできます。
私が持っている本はISBN番号も違う古いものですが、今、入手できる物を挙げてみました。
「深夜プラス1」/ギャビン・ライアル
菊池 光 訳 ハヤカワ文庫
ISBN13- 978-4150710514
065 「残虐行為記録保管所」/チャールズ・ストロス
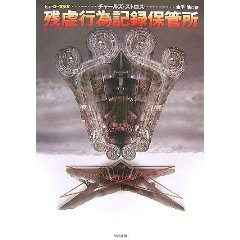 主人公は、イギリスの秘密組織「ランドリー」に所属する冴えないコンピュータおたく。のっけから、ほとんど侵入盗のようなミッションを与えられ、雨でずぶ濡れになりながら、何とか目的を達成してすたこら逃げ帰って来ます。
主人公は、イギリスの秘密組織「ランドリー」に所属する冴えないコンピュータおたく。のっけから、ほとんど侵入盗のようなミッションを与えられ、雨でずぶ濡れになりながら、何とか目的を達成してすたこら逃げ帰って来ます。
この「ランドリー」なる組織は、ちょっと変わった目的をもって設立された組織です。う〜ん説明は難しいのですが、一言で言うと、「オカルト・バスターズ」みたいな組織とでも言えば良いでしょうか。
本書の設定では、この世界は多元宇宙で構成されていて、この人間界の他にも、「魔」が巣くっているような別世界があります。で、数学者チューリングが基礎を築いた数学理論により、この人間界と魔界との交流が可能になっているのですが、そんな危なっかしいことを公にすることもできず、「ランドリー」はひたすらその秘密を保持し、時として人間界に出てきてしまった魔があるとすればそれを掃討する任務を負っています。
冒頭のコソ泥のような行為も、とある研究者が偶然多元宇宙に関する研究を成し遂げちゃったみたいなので、秘密保持のため、研究者がそれと気付く前にデータを盗み出しちゃえというなかなか乱暴なミッションだったわけです。
で、主人公の次なるミッションは、アメリカから出国を認められずにいるイギリス人の大学教授と接触し、帰国のためのアレンジのお膳立てをすること。この大学教授も、自分ではそれと気付かないまま、多元宇宙に関する重要な研究をしちゃっているため、それに気付いた米政府から出国できないようにされているというわけなのでした(知識を流出させることになるからね)。
その教授に接触してみたところ、何とまあ、赤毛のバツイチ美貌の女性教授ではないですか。
主人公はどぎまぎしながらもファーストコンタクトに成功し、ひとまず宿にひきあげます。
そうしたところ、宿には米政府の秘密組織の人間が入り込んでおり、「手を引け」と脅される始末。あちゃ〜……と思っていると、そこにさらに別の勢力が介入し、米政府のエージェントが殺害されてしまいます。
とってもヤバいっす。主人公は単なる帰国調整のためのアレンジがミッションでしたので、こんな事態になった場合はとにかく逃げ帰ることとランドリーの行動規範には定められていました。第一、主人公は別に戦闘等の専門家でもなんでもないしね〜。
というわけで、またすたこら逃げ出そうとしたところ、件の美貌女性教授からHelpの電話が!どうも彼女も襲われたらしい。
美人だしなぁ〜……と、いうわけでお目玉覚悟で救出に向かいます。が、やはり手に負えず。ぎりぎりのところで救助要請するのが精一杯で、主人公もやられちゃいます。
意識を取り戻してみると、イギリスの病院に収容されていたという次第。大学教授は何とか救出されたようですが、主人公は予想通りこっぴどく叱られた上、厳し〜い上司の下に異動させられてしまいます。
しかし、英米のほかにも大学教授を狙った第三勢力は一体何者なんでしょう?
そうこうしているうちに、徐々に事実が明らかになり、件の第三勢力はどうやら旧ナチスの残党がオカルティックな研究を遂げた上で現代に甦り、テロリストと手を組んでいるのではないかとの疑惑が。
このままでは後手後手に回るだけなので、この際、大学教授を囮に使い、逆手を取って第三勢力を攻撃しようとのプランが立てられます。
んで、主人公は表向きは調査名目で、大学教授を伴ってアムステルダムの国立博物館地下にある旧ナチスオカルトチームの資料が収蔵されている施設に向かいます。ここが作品のタイトルととなっている「残虐行為記録保管所」なのですね。
大学教授は、アメリカで拉致された際、テロリストが書き残した奇妙な図形を目にしており、それは魔との接触に関する図形と思料されたため、同様の図形が保管所にも残されていないかを調べに行ったわけですね。
で、そこで驚愕の事実が明らかになるのですが、テロリストというか旧ナチの残党も放っておいてはくれません。
「ランドリー」が厳重に警備していたにもかかわらず、どっひゃー!という手段により、再び大学教授を連れ去ってしまいます。
それは……え〜い、書いちゃえ! 大学教授が宿泊していたホテルの部屋に異変が起こり、主人公が駆けつけてみると、教授の姿が見えないばかりか、部屋の中には異次元に通じる穴が開いちゃってるじゃないですか!
どうも、教授は異次元世界に連れ去られた模様。こりゃ一大事! 集結するランドリーの特殊部隊。教授奪回と、そもそもこりゃどういうこったいを調査するためのチームが編成されます。
物語の冒頭では冴えないコンピュータおたくでしかなかったのですが、物語が進むに連れてどんどんたくましくなる主人公。この特殊チームにも志願します。
はたまた、単に厳しいだけの陰気な上司と思っていた人が、こうなると結構頼りがいのあるエキスパートだったり。
そして、異次元に通じる穴に入ってみると……
というお話。
かなり、マニアックな会話などがテンポ良く飛び出し、時にユーモラスでもある、SFではあるのですが、むしろサスペンスもの的な作品です。
やや、コアなテイストもありますが、一気に読めて楽しめる作品に仕上がっていると思います。
特に、コンピュータやオカルティックなお話に詳しい方は、作品のあちこちに散りばめられている隠し味にくすっと来るのではないでしょうか? ヒューゴ賞受賞作品です。
本書には、表題作のほか、同じ登場人物による「コンクリート・ジャングル」という中編も収録されています。続編という感じの作品なのですが、主人公がどんどん魅力的になっていくので、これ、シリーズ物にしても良いんじゃないかなぁ。
こちらでは、本編で「うっとおしいなぁ」という感じに描かれていた主人公の上司でもあるハイミス女史がやってくれちゃってます。主人公に与えられた最初のミッションは、「石になった牛を調査してこい」ってなもの。何ですか、それ?ですよね。はいはい、バジリスク、メデューサの類ですな。
描写もますます生き生きとしてきて楽しめます。「ランドリー」という組織の実態もさらに明らかになっていき、何ともわくわくしちゃいそうな秘密組織ぶりです(ランドリーへの入り口はロンドンの地下鉄駅にひっそり設置されている公衆トイレの奥にあるんですよ〜)。「謎の円盤UFO」というTV番組が昔ありましたが、あの秘密組織シャドーをちょっと思い出しました(あんなに格好良くは描かれていないですが。何というか、ちょっと二枚目半みたいな組織です)。
軽く楽しめる、結構おすすめな作品でした。
「残虐行為記録保管所」/チャールズ・ストロス
金子 浩 訳 早川書房
ISBN978-4-15-208880-2
064 「夏の涯ての島」/イアン・R・マクラウド
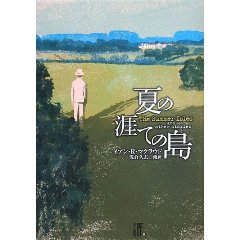 短編集です。一応、ジャンル的にはSFということになるのかもしれませんが(そう分類されています)、非常に叙情的で、中にはSFというジャンルでは語れない作品もあります。
短編集です。一応、ジャンル的にはSFということになるのかもしれませんが(そう分類されています)、非常に叙情的で、中にはSFというジャンルでは語れない作品もあります。
私の好きなブラッドベリなどのタイプにやや似ているかもしれません。
「帰還」は、宇宙の果てを目指した宇宙飛行士が、目的を達することができずに地球に帰還するというお話。ネタばれになっちゃうのでこれ以上書きませんが、帰還した宇宙飛行士が妻子の元に戻ったとき、そこで起きた出来事とは…。哀しい作品です。
「チョップガール」は、戦時中、とある爆撃機の基地で働く女性のお話。
「チョップガール」というのは、不幸を運んでくる女性とでもいう意味です。つまり、彼女と関わると戦死したりするという……。基地中からそのように見られている彼女の前に現れたのは幸運を絵に描いたようなパイロット。さて、この先は? これって本当にSFじゃないよね。
「ドレイクの方程式に新しい光を」。ドレイクの方程式というのは、この宇宙に知的生命体がいる惑星の数を割り出すための方程式です(実際にあります)。もちろん、様々な変数があるので、適切な変数を入れることができれば答が出るというものですが。SETIという活動は御存じですか?これも現実にある活動なのですが、宇宙に存在するかもしれない知的生命体を探そうというプロジェクトで、とにかくパソコンのパワーが必要なため、膨大な数のパソコンを並列的につないで解析しようという試みなどもなされており、個人のパソコンのパワーを少しずつ分けてもらうという活動をしています(私や、みなさんのパソコンも、このプロジェクトに申し込んで、あるプログラムをインストールすれば活動に加わることができます)。
主人公は、知的生命体の存在を強く信じ、長年に渡り観測を続ける男性。彼を愛するとある女性は、そのような彼の活動を温かく見守りつつも、彼女のキャラクターからとある旅に出ます。舞台は身体改造なども容易に行われるようになった未来世界ですが、ともすると、今現在であったっておかしくないと思わせてしまうような作品です。これ、本当に現代を舞台にして書いたら、別にSFじゃないよね。
表題作の「夏の涯ての島」は、いわゆる「別世界物」などと言われているSFの古典的なテーマを使っています。つまり、例えば第二次世界大戦でヒトラーが勝っていたらどうなるか?みたいな、実際の歴史とは異なった歴史を歩んだ場合の世界を描くやりかた。
舞台はイギリスで、異なる時間軸はまさにヒトラーが勝利した世界です。第二次大戦に敗れたイギリスで暮らす一人の男性が主人公。これも、古典的なSFテーマを扱っていますが、そのテイストは叙情的で、主人公の一生を哀切たっぷりに描き出します。
「転落のイザベル」は、架空世界を舞台にしています。この世界では太陽を世界の隅々に行き渡らせるため、光塔(ミナレット)が各地に立てられています。そして、ミナレットには、巨大な鏡が設置されており、その鏡を使って適切に世界中に光を運ぶ役割が「夜明けの歌い手」と呼ばれる女性達でした。
彼女達は見習いから始まり、選ばれた者だけが「夜明けの歌い手」になれるのですが、その代償として盲目になってしまいます(強い光を扱うことから)。
主人公のイザベルは、そのような「夜明けの歌い手」の一人なのですが、彼女は、「その時」に目を閉じてしまったのか、盲目になることを免れています。しかし、「夜明けの歌い手」は盲目であるものと定められていることから、イザベルは盲目のふりをするのでした(とはいえ、光を扱わなければならないのは間違いなく、徐々に視力は衰えていくのですが)。
そんなイザベルは、ある日、調子が悪くなった鏡を調べようとしたところ、偶然、塔の下で踊っている女性を発見します。その女性は、「言葉の大聖堂」に仕える司書でした。
2人は親しくなり、互いの世界を教え合います。そうこうしている内に鏡の調子は本格的におかしくなり……というお話。
タイトルの「転落」は、落ちてしまうフォールと、秋のフォールをかけています。
「息吹き苔」もとても切なくなるお話です。舞台となるのは、男性の数が圧倒的に少ない架空世界です。その世界の山間で生まれた主人公の女性ジャリラは、3人の母親(この世界では母親は複数います……少なくとも2人は)と共に、海辺の町へと引っ越すことになります。気候も風習も異なる世界に最初は拒否反応を起こしますが、徐々に馴染んでいき、また、珍しい同年代の男の子とも知り合います。この町の描写が美しいのですが、物語はこの町で育ち、独り立ちしていくジャリラを描きます。
タイトルの「息吹き苔」というのは、空気の薄い山間部で生活するために、必然的に体内に取り込まれた苔のことを言います。ジャリラは海辺の町に適応していく課程で、自分の身体の中に取り込んでいた息吹き苔を吐き出してしまうのですが。
ご紹介からも感じて頂けたと思うのですが、非常に叙情的な美しい作品が多く収められています。
こういったタイプがお好みでしたら、楽しめると思いますよ。
「夏の涯ての島」/イアン・R・マクラウド
浅倉久志ほか訳 早川書房
ISBN978-4-15-208887-1
063 「ナイフ投げ師」/スティーヴン・ミルハウザー
 スティーブン・ミルハウザーの短編集です。
スティーブン・ミルハウザーの短編集です。
とても不思議な味わいの作品が詰まっています。
表題作の「ナイフ投げ師」は、カーニバルの演芸芸人であるナイフ投げの達人を描きます。
もう、時代遅れの出し物になってしまったナイフ投げなのですが、その達人は「技巧的な傷」という「技」?を開発し、評判を博します。とある町にそのナイフ投げ師がやって来たからさあ大変。
住民達はこぞって見にでかけます。
古臭い出し物と行っても、技術は確かです。普通のナイフ投げだけでも驚くべき技を見せつけられます。
そして、問題の「技巧的な傷」。
……ショーを見終わった町の人達は、おそらく何らかの罪悪感の様な感情を抱えながら家路を辿るのでした。
「夜の姉妹団」も不思議なテイストの作品。
女の子達の秘密のグループがあったそうです。
そこで何をしているのかは秘密。
新しく姉妹団に入団を誘われた女の子は、そっと小さな紙切れを渡されます。その紙切れの半分は真っ黒で半分は真っ白なのだとか。
その姉妹団で起こった出来事を告発した女の子がいました。
忌まわしいことが行われているのだと。
そして、しばらくすると、その告発で名指しされた女の子の一人が自殺してしまいます。
やはり、そういうことが?
ですが、最初の告発者は自分の告発は嘘であったという第二の告発をします。
この姉妹団なるものは、そもそも存在していたのか、からして謎のまま。
「空飛ぶ絨毯」は、まさに題名の通りのお話。
空飛ぶ絨毯が普通にある世界。子供達は絨毯に乗って遊んでいるのだけれど、あんまり高い所や遠くに行ってはいけません。
でも、どうしても行ってみたくなった男の子のお話。
「月の光」はきれいなお話です。
私はとっても気に入りました。
ある夜、ふと目が覚めてしまった少年が外に出てみたら、芝生の上で女の子達が野球をやっていました。
白いシャツ、短パン、トレーナーを着て汗をかいている女の子達に混ぜてもらって、いっしょに月明かりの下で野球をします。
何とも詩情溢れる作品だと思いました。
「パラダイス・パーク」は、陳腐化してしまった遊園地を買い取って蘇生させるお話。
できあがったのは度肝を抜くような斬新な遊園地でした。
しかも、どんどん進化を遂げて、その度にお客さんをびっくりさせるような趣向が満載。
でも、その行き着いた先は?
スティーブン・ミルハウザーはこの本が初めてでしたが、なかなか面白い!
「マーティン・ドレスラーの夢」という本も買い込んでしまいました。
良い本をお探しでしたらいかがでしょうか?
「ナイフ投げ師」/スティーブン・ミルハウザー
柴田元幸訳 白水社
ISBN975-4-560-09203
062 「ラナーク〜四巻からなる伝記〜」/アラスター・グレイ
 本作は、とある男性の「四巻からなる伝記」です。とはいっても、本自体はとても分厚いのが一冊ですが。
本作は、とある男性の「四巻からなる伝記」です。とはいっても、本自体はとても分厚いのが一冊ですが。
まず、読者は、第三巻目から読むことになります。
どこか場所も分からないところで列車に乗っている主人公。
記憶もなく、自分の名前すら分からない。
着いた駅で降りてはみたけれど、どこに行くのかすら分からない。
そうしているところにやってきた一人の男性。
妙に馴れ馴れしくて、世話を焼いてくれるのだけれど、いけすかない。
とにかくどこに行けば金が手に入るのかと聞けば、保障局に行けと言われる。
そこで身体検査を受けさせられると、体にあった痣を見られて「竜」だな。と言われる。
とりあえずの金と住む場所を手に入れ、その後は怠惰な生活に沈んでいく。
しかし、ここは寒い。太陽がない。
誰も彼も、別に働きたくなければ保障局に行けば金はもらえるし……
ただ、理由は分からないけれど、時々消えてしまう奴がいるだけのこと。
そうそう、とりあえず、ここでは、主人公は「ラナーク」と名乗っています。
実は、この第三巻にはこの後に続くとても興味深いエピソードが語られるし、実は一番面白いところなのかもしれないのですが、そこはネタバレになるので飛ばします。
次に出てくるのは第一巻。
ダンカン・ソーという子供のお話。イギリスの町で育った感じなのかな。戦時中で、絵が好きで、でも自分がどうなるかなんて分からない子供のこと。
いじめられたり、裏切られたりして育ちながら、で、お前は大きくなったら何になりたいんだ?
そんなの、分からない。
屈折した心情がちょっとトゲのようで痛い。
そして第二巻へ。
話をすっごくはしょっていますが、結局、ソーは美術学校に通うことになります。
それなりの才能を示しはするのですが、天才?故か教師達に従順に従うことはしません。
親の期待もあっての途なのですが。
結構、ぼろぼろになりながら、とある教会の壁画を描く仕事を得ます。
お金とかが問題じゃなくて。
でも、凝りに凝ってしまうソーの理解者は減っていくばかり。約束の期限も過ぎていくばかり。
そして結局駄目になってしまって……
で、第四巻。
君は、あの時の!
とあるパートナー(これは冒頭の第三巻に出てくるあの人なのですよね)と暮らしていこうと思っていたのに、破局を告げられます。
彼女との間に息子も生まれているというのに、ほとんど、子供と接する機会ももてずに、次のステージに押し出されていきます。
そう、それは、彼が第三巻で暮らしていた町が、とある陰謀により危機に瀕している。
それを救うために、彼が市長に祭り上げられ、会議でその窮状を訴えるという役目を与えられます。
何で?何で?何で?
それはね……
紆余曲折あって、彼は、息子にようやく巡り会えます。
でも、その時にはね。
あぁ、ネタばれにならないように努力しているのですが、とても書きにくい作品です。
人間関係もはしょりまくっていますし、重要人物も書いていません。
とにかく、雰囲気だけでもというご紹介にすらならない落書き程度で終わってしまいました。
とても複雑な作品です。
好き嫌いも分かれそうです。
私は、キライじゃないけれど(特に冒頭の「第三巻」の雰囲気はとても面白かったのだけれど)、ちょっとダレたというか、焦点が拡散しちゃった感じもあって(それは私の読み込みが浅いせいもあるのですが)、ややどうかなという感じもします。
でもね、インパクトは確かにあったのですね。
これが気に入っていただけるのかどうか、それは、みなさん次第なのですが、悪くない!というご紹介でした。
「ラナーク〜四巻からなる伝記〜」/アラスター・グレイ
森慎一郎 訳 国書刊行会
ISBN978-4-336-04939-1
061 「ゴーメン・ガースト3部作」/マーヴィン・ピーク
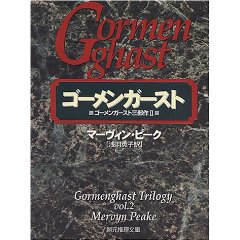


熱にうなされたねっとりした夜に見る悪夢のような作品です。
おどろおどろしいったらありゃしない。 舞台は、泥の底に沈み、時すら絡め取られてしまったような、天空まで届きそうな偉容を誇るゴーメン・ガースト城です。
城の周りにに住む人々はそれこそ本当に泥で作った家に、はいつくばるようにして生きているのです。
今日は、ゴーメン・ガースト城で開催される職人達の匠の技をたたえる儀式があります。
泥の中の人々は、木彫りの人形を精魂込めて作ります。
それが、城に飾られ、一番の栄誉を得た人形が城に収蔵されるのでした。
城に住んでいる異形の人々と言えば、偉大としか言いようのない体躯の、部屋には溢れるほどの鳥を飼っている王妃。
どこまでも永遠に続くような迷路の廊下を音もなく歩く執事。彼は固い石で敷き詰められた廊下でしか寝ようとしません。
城の料理番の、獣脂や腐った野菜の臭いにまみれた脂ぎった脂肪の塊のような調理長。
その下働きとして、泥の村から引き上げられてきたスティアスパイク。
このスティアスパイクが野心家で、城の秘密を探りにかかります。
どこまでも天に伸びそうなくらい高い城の尖塔をはい上がり、未だかつて誰も見たこともないであろう、中空にそびえる城の屋根に上り詰めます。
そこは、野草が生え、灼熱の昼と冷厳な夜が繰り返すだけの場所。
その気も遠くなるほどの高みに登る途中、手もしびれ、落下の恐怖におびえながら見た物は、尖塔にも負けないような大樹の木陰でお茶会をしている気のふれた貴婦人の姉妹。
尖塔の窓から狂気に歪んだ笑い顔を出して詩を吟じている詩人。
そんなものたち。
この3部作は未完です。
1作目の「ゴーメン・ガースト」は、そういう城の様を描いています。
2作目は「タイタス・グローン」。
城の跡取りとして生まれたタイタスの物語です。
スティアスパイクとの対決もあります。
城自体が水没してしまって、その水の中で女王やタイタスや、スティアスパイクが、お互いぬめる蛇のような様を見せます。
あぁ、何ていう悪夢を紡ぎ出してしまったのでしょうね。
そして「唐突」なのが3作目の「タイタス・アローン」です。
どこにあるのか、どの時代なのか分からないのですが、強いて言えば中世風だったゴーメン・ガースト城の世界から、じめじめとした地下水路を巡った果てに出てきたのは銀色が輝く未来世界。
このギャップには沢山の意見があります。
そりゃそうだよね、あんな中世風の悪夢にどっぷり漬かったあとにこれですか?だもの。
でもね、これは未完なのですよ。
作者のマーヴィン・ピークは、もう一つ何か書きたかったのじゃないのかなぁって、思うんです。
未完といってもあなどることなかれ。
少なくとも、2巻目までの、熱にうなされるような悪夢の物語は、ほかにはちょっとないですよ。
文字が、フィジカルに影響するのですね。
高みに登ってくらくらする足下や、黴臭い城の廊下で眠っていたはずなのに、すくっと起き上がる執事の目が見ていた先のこととか。
今晩、悪夢をみてみませんか?
「ゴーメン・ガースト」/マーヴィン・ピーク
浅羽 莢子訳 創元推理文庫
ISBN4-488-53402-3
ISBN4-488-53401-5
ISBN4-488-53403-1
060 「ドン・キホーテ」/セルバンテス
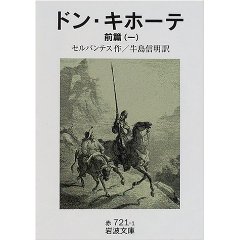
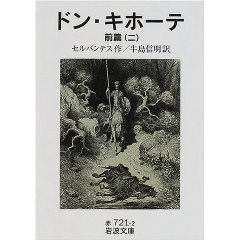
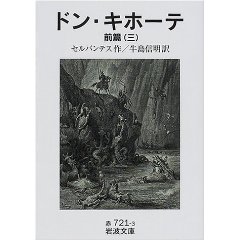
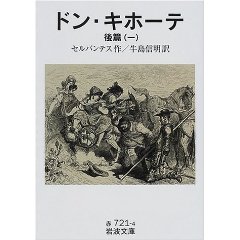
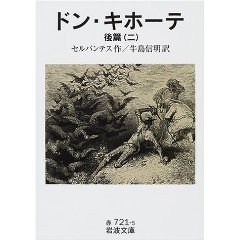
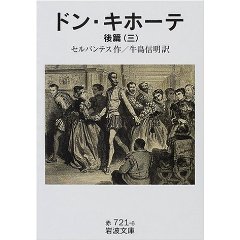
「ドン・キホーテ」って、ちゃんと読んだことありますか?
私は、「少年少女なんだら全集」みたいなので、子供の頃読んだことがあっただけでした。
それで、「ちゃんと読もう」シリーズで読んでみたのだけれど、思わず吹いてしまいましたよ(電車の中だったので辛かった〜)。
いやぁ、ユーモア小説というか、コミカルな味と割り切って読むのがおそらく大正解なのでしょうね。
作者セルバンテスの序文からしてそうですもの。
世界の名作○○みたいに構えてるから余計読まれないし、良くないのだろうなぁ。
名前からして思いっきり誤解されてますよね。
まぁ、それは「マック」なのか「マクド」なのか問題(?)でもあるのだけれど。
いえ、あの安売量販店のこと、みんな「ドンキ」って言うじゃないですか。
こんなこと承知の上でしょうけれど、敢えて書きますと、もちろん「ドン」は敬称です。Mr.(ミスター)と同じ。
騎士だから(自分で勝手につけた)「キホーテ」という名前の前に「ドン」もつけちゃったのね(ちなみに、イギリスだと「サー」という称号になることは御存じのとおり。あれと同じね。)。
あ、女性だったら「ドニャ」ね。
だから、「ドンキ」っていう略し方はとんでもなく中途半端なんだけれど、それはそれか。
(あ。もちろん、マックも「Mc.」という「誰々の息子」という意味の言葉がついていて、「ドナルド」の息子という意味だから、「マクド」っていう略し方は何だかな〜なのですけれどね)。
小説の内容は大体ご存知のとおり。
でも、通して読んでみると、昔読んだ「少年少女○○全集」でラストシーンに描かれていた風車との戦いなんて、結構序盤に出てきてしまうのにびっくり!(それだけ、「少年少女○○」が水で薄めきったようなものだったわけだ。こういうの「ジュヴィナイル」っていうのですけれど、質の悪いのに当たってしまうと、本当に面白い作品が台無しになりますね。)。
でも、風車との戦いって結構教科書レベルでも書いてませんか?
あんなの序の口ですお。
いわゆる「騎士物語」を痛烈に批判しているわけですね。
セルバンテスが生きていた時代の文壇というのもあるのでしょう。
はいはい、思いっきり引用されていた、「アーサー王伝説」も、アリオストの「狂えるオルランド」も読んでいましたので、余計楽しませて頂けました。
前編と後編では著しく趣を異にするのですね。
前編は、騎士物語に惑溺するあまり気がふれてしまったドン・キホーテが、自ら時代錯誤の騎士となり、少々頭の足りないお人好しのサンチョ・パンサを従者に仕立て上げてとんでもない「冒険」(と、本人だけが思いこんでいること)の旅を続けるという物語。
騎士は「思い姫」が必要なので、ろくに会ったこともない農家の娘さんを空想の中で絶世の美女の様に仕立て上げてしまうとか(後でたたるんだけれどね〜)。
回りの者ははらはらし通しで、何とか連れ戻そうとするのですけれど、その旅に及ぶこと3回というのが前編の構成なのでした。
で、後編になると(時間をおいて執筆されたのでした)、前編での冒険が世間で大評判となり、出版されているという構成(いや、事実そうだったんですけれどね)。
結構な数の人が「ドン・キホーテ」の物語を読んでいて、彼等のことを知っており、その奇矯なキャラを楽しみたくて、まぁ、いじることいじること。
偽の「ドン・キホーテ」物語まで出版されていて(しかも後編に起きる出来事が書かれているというメタフィジックな構成!)、そんな偽物の本のような冒険jはしたくない作中のドン・キホーテは、敢えて筋書きとは違う行動を取ったりもします。
キャラも前編とは少し変わってきていて、もう少し理性的になっているドン・キホーテなのでした。
サンチョ・パンサも知恵を見せたりします。
この辺が、前編の破天荒な痛快さを殺いでしまっているのが個人的には残念なのですけれど。
しっかし、凝った作りですねぇ。いわゆる「メタ」構造です。その辺が名作に祭り上げられている理由の一つなのでしょうね。
長〜い物語ですが、肩肘張らずに楽しんで読むのが正解と思います。
くすっと笑ってしまうような物語を名作でいかが?
「ドン・キホーテ」/セルバンデス
牛島信明訳 岩波文庫
ISBN4-00-327211-0(前編1)
ISBN4-00-327212-9(前編2)
ISBN4-00-327213-7(前編3)
ISBN4-00-327214-5(後編1)
ISBN4-00-327215-3(後編2)
ISBN4-00-327216-1(後編3)
059 「逆転世界」/クリストファー・プリースト
何とも奇妙なSFです。
ここは、宇宙のとある領域にある星です。
そこにある列車のようにレールに乗った都市が舞台です。
その都市は7層からなる大都市で、大勢の人達が住んでいます。
レールに乗っていることから分かるように、この都市は移動し続けなければなりません。
毎年、36.5マイルずつ、北へ北へと移動し続けます。
そんなレールなど敷かれているわけはないので、どんどんレールを作り続けていくのです。
その距離をかせげないと大変なことになってしまうのです。
過去、その都市が過ぎ去った後には、それまで移動してきた分だけのレールがあるので、それをはがして、都市の先に施設します。
一般人が都市の外に出ることは厳禁なのです。
ただ、レールを敷く作業員だけを除いては。
都市の住民は、一生を都市の中で過ごして死んでいきます。
都市の外に出ることはとても恐ろしいことなのです。
そして、都市がひたすら北を目指すのは、南は危険だからです。
主人公は、成人してレール施設員となります。
日々、都市の後ろに残されたレールをはがしては都市の前に新しいレールを敷く仕事です。
ある事情から、彼は、都市を離れて南に向かうことになります。
ええ、危険な南へ。
そこで彼が体験したことと言えば、それは……
彼は二人の女性と一緒に南へ旅することになるのですが、南に近づくほどに、段々女性が太っていく……というか、平べったく伸びていくのですよ。
これが南の危険なのです。
双曲線って覚えていますか?
数学で、グラフを描いたよね。
太陽が、まるで双曲線のように歪んでいくのが南の世界なんです。
重力異常が起きているのでしょうか。
だから、都市はどんどん北へと逃げなければならなかったのですね。
でも彼自身も、南にあまりに近づきすぎてしまったため大変なことになります。
一体どんな世界なんだっていう、ものすごいインパクトを感じた作品でした。
とても古い作品なのですが、いつまで経ってもその印象は残り続けています。
クリストファー・プリーストはとても素晴らしい作家さんで、色々な作品を今でも執筆中です(私も、今「双生児」っていう作品を読んでいる最中です……とても素敵な作品です。またいつかご紹介できるかもしれません)。
私が読んだのは「サンリオSF文庫」でした。今はこの文庫自体なくなっちゃっていますが、今は創元SF文庫から出ているようです(ぱちぱち)。
すごく不思議な感覚を味わえるとっても面白い作品です。
えっとね、敢えて書かなかったけれど、もうひとつ「でんぐりがえし」があるのですよ。オチっていう奴ですね。
唖然としました。
それだけ筆力のある作家さんなんですよね。
とっても好きな作品なので、ご紹介しました。
ISBNコードは、今入手できる創元推理文庫のものを挙げておきました。
「逆転世界」/クリストファー・プリースト
安田 均訳 創元SF文庫
ISBN13: 978-4488655037
058 「レベル3」、「ゲイルズバーグの春を愛す」/ジャック・フィニイ


ハヤカワ書房から復刊している「異色作家短編集」というシリーズがあります。
これまでにも、何作か「本棚」でご紹介しています。
全20巻なんですが、全巻揃えまして、少しずつ読んでいます。
しばらく前に読んだその第13巻目が「レベル3」でした。
読んでいて、ふっと「香り」のようなものを感じたのですね。
「あぁ、これって、いつか読んだ……何だっけなぁ……あの作品に似ている」って。
空気のような……そんな感じです。
「レベル3」には、「時間物」をいくつか収録してあります。
たとえば、ニューヨークのグランド・セントラル駅の地下には、過去に戻れるプラットフォームがあったとか(これが、「地下三階」である「レベル3」なんですけれどね)。
それを単に不思議なこととか、サスペンスとかで書いているのではなくて、やさしいのですよ。
それを、「空気」のように読めたということでしょうか。
全部読み終えて、巻末の後書き解説を読んだら! そっか!あの人だったんだ!
いえ、とっくに、僕はジャック・フィニイを読んでいたのでした。僕の本棚にありました。
それは「ゲイルズバーグの春を愛す」という作品で、これも良かったです。
そのテイストが、気持ちの中にはぐくまれていて、「レベル3」を読んだ時に共鳴したのでしょうね。
そういう経験ってありますか?
作者さんの、おそらく地でもっている感性を感じたようなこと。
「ゲイルズバーグの春を愛す」って、とてもきれいなタイトルですね。
これも「時間物」です。
手紙……のお話でもあります。
ネタバレになるので詳しくは書きませんが、何だか切なくなったですよ。
少しだけ、やさしい気持ちが必要になったら、ジャック・フィニイなんて良いですよね。
「ゲイルズバーグの春を愛す」/ジャック・フィニイ
福島 正実 訳 ハヤカワ文庫
ISBN4-15-020026-2
「レベル3」
福島 正実訳 早川書房
ISBN4-15-208758-7
057 「失われた時を求めて」/マルセル・プルースト













「失われた時を求めて」のことは色々なところで聞いたり読んだりして知っていました。
たとえば、こんな記事とか。
有名な作品でしたし、一度は読んでみたいと思っていましたが、上記の記事にもあるように、ハードカバーで揃えたら10万円以上という価格や、何よりもその長さ、それから「難解だ」との評価におそれをなしてこれまで手を出せずにいた作品でした。
ところが、集英社ヘリテージシリーズという文庫から、ハードカバーの内容のまま(鈴木道彦さんの訳で)全13冊の文庫として出版されるというニュースを目にし、「これは読むしかない!」と思い、昨年、全巻揃いでAmazonから買い込んでいたのでした。
とはいえ、そうそう気軽に読み始められるものでもなし、結局、昨年は手を出せずに終わっていました。
そして、今年に入り、年末年始に結構まとまったお休みをいただけたことから、1月3日からついに読み始めたのでした。
幸いなことに事件の発生もなく、ひたすらこの本を読み耽るお正月となりました。
それでも、正月休みだけでは読了できず、その後も読み続けていましたが、この度ようやく読了できたので、この機会に「本棚」にも書いておくことにしました。
まず、最初の感想は、やっぱり「長かった〜」です。
一つの作品としては、私がこれまで読んだ中で一番長い作品だったと思います。
よくもまぁ投げ出さずに読了したと、自分でも思います。
そして、実際に読んでみると、一般に言われていた「難解」などということは全くなかったのでした。
鈴木さんの訳が良かったのかもしれませんが、すらすらと読み進むことができました。
何故、そんなに難解だと言われるのかよく分かりませんでしたが、敢えて言うとすれば、非常に観念的な叙述が多数あることや、時制が行ったり来たりする場面があり、場面によっては「これはいつの時点のことを書いているのだろうか」と分からなくなるところもありました。
でも、そんなに神経質になる必要は無くって、プルーストの筆のままに身を任せてたゆたうのが良いのではないかと感じました。
さて、それでは一体どんな物語かと言えば、一言で言えば、語り手である「私」の少年時代から中高年に至るまでの物語ということになります(作者プルーストの自伝的小説とも言われます)。
「私」(名前も年齢もはっきりと書かれていないのです)は、裕福なブルジョアの家に生まれ育った病弱で神経質な人間であり、作家を志していました。
当時は(第1次世界大戦前から第1次世界大戦を挟んだ後までの時代を描きます)貴族社会が健在であり、色々な貴族が「サロン」を運営し、社交生活が繰り広げられている時代でした。
「私」も貴族ではありませんでしたが、そのようなサロンに出入りするようになり、大貴族達と親しく交際するようにもなります。フォーブール・サン=ジェルマンという1流中の1流の名門貴族だけで構成される社交界もあれば、格式はなく、場合によっては貴族ですらないけれどスノッブな婦人達が運営するサロンもあります。この両者の、時代を経ての変遷なども描かれます。
この物語の一つの大きな部分を占めているのは、そのような貴族達の社交界の物語です。
そしてそのような社交界をも巻き込んだ大きな事件として出てくるのが「ドレフュース事件」です。ユダヤ人のドレフュースが無辜の罪に問われたとのことで、当時のフランスを二分する大きな社会問題ともなった事件ですが、作家のプルーストもドレフュース擁護派として活動していたこともあり、この事件のことが多く語られます。
はたまた、プルーストの考える芸術論も大きな軸をなしています。そもそも、この物語の前身は、プルーストがとある自分とは立場を異にする作家が書いた文学論への反論だったのです。その文学論に、絵画や音楽などに対するプルーストの見解を加えて書かれたのがこの作品でもあったわけです(登場人物にも画家、音楽家が重要な役割を担い出てきます)。「私」が作家志望であるというのも、この辺りを書きたくての設定かもしれません。
あるいは、幾多の恋愛小説でもあります。それは「私」が異性に目覚め、欲望を感じ、何人かの女性と関係をもつお話もあれば、「私」の親友である若く美貌の貴族サン=ルーの恋愛、重要な登場人物であるスワンの恋物語もあります。
そしてそれに絡んで出てくるもう一つの大きな要素は同性愛です。プルーストもホモセクシュアルだったとのことですが、ホモセクシュアル、レズビアン両方についてかなりの描写がなされています。
そして、どうしても忘れてはいけない大きな軸は、「時間」や「記憶」のことです。
「失われた時を求めて」についての文章を読むと必ず触れられているエピソードに、「私」が紅茶に浸したプチット・マドレーヌを口にしたとき、一気に少年時代のことがよみがえってくるというのがあります。これは第1巻の前半に出てくるエピソードなのですが、これをきっかけに物語は「私」の少年時代に戻り、コンブレーという架空の町での出来事に筆が進みます。この辺りの自然描写はとても美しく、大好きでした。
さて、コンブレーからは2つの方向に道が延びており、その一つは重要な登場人物であるスワンが住んでいる家の方向への道であり、「スワン家の方へ」という第1,2巻のタイトルにもなっています。
もう一つの道はゲルマントという大貴族のお屋敷の方向に伸びる道であり、「ゲルマントの方へ」という第5,6巻のタイトルにもなっています。「私」は、このゲルマント公爵夫人にも恋をし、今で言えばストーカーのようなことまでしたりもします(時代もあるのでしょうけれど、「私」の恋愛に対する態度はものすごく嫌いです。身勝手で嫉妬深く、時には単なる欲望だけのために女性に手を出したり、まぁ、とんでもない奴ですよ。「私」に比べれば、放蕩者と描かれているサン=ルーの方がどれほど良いと感じたことか。)。
その他の巻も含めて全体の構成を書いておくと、1,2巻は先ほど書いた「スワン家の方へ」で、「私」の少年時代の事から始まり、スワンの恋愛と結婚までが描かれます。スワンは大貴族とも親交がある名流だったのですが、なんと高級娼婦(ココット)のオデットと結婚してしまい、それが機になって大貴族らとの社交生活から離れていきます。そしてまた、二人の関係に絡みつくのはヴァントイユが作曲したソナタなのでした(音楽論を導くことになります)。そして、伏線として、ヴァントイユの死後、その娘が亡父の写真前でレズビアンにふける場面を「私」が目撃するというエピソードも。
第3,4巻は「花咲く乙女たちのかげに」というタイトルで、「私」が幼い頃から憧れていた海辺のリゾート地であるバルベックの高級ホテルに祖母と長期滞在していた頃のことを描きます。「私」は、それ以前にスワンとオデットの間に生まれた娘であるジルベルトに幼い恋心を抱き、フィジカルな関係を望んでいたりもしたのですが、バルベックでは後に重要な役割を果たすことになる若いサン=ルー侯爵や尊大なシャルリュス男爵(パラメード)、アルベルチーヌという少女らと出会うことになります。バルベックでは、画家のエルスチールとも知り合いになり、芸術論の一つを形成します。
第5,6巻は先ほど書いた「ゲルマントの方へ」です。
第7,8巻は、「ソドムとゴモラ」というタイトルで、ここで同性愛の主題が取り上げられます。詳しく書くとネタバレになるので書きませんが、こんな人がそういう関係に……という辺りが徐々に明らかになっていきます。
第9,10巻は「囚われの女」というタイトルで、サブ・タイトルに「ソドムとゴモラ」の続編であることが記されています。ここで言う「囚われの女」とは誰のことか、は、ネタバレになるので敢えて書きません。
そして第11巻のタイトルが「逃げ去る女」であって、「囚われ」ていた女性がその状況から出て行くことがタイトルからも暗示されますね。
そしてそして、ようやく最後の第12,13巻にたどり着き、そのタイトルも「見出された時」となり、総タイトルである「失われた時」が見つかったことが、すなわちすべての伏線が表面に現れ、様々な謎の答が明らかになるのでした。ここでも、プチット・マドレーヌの時と同じような経験を「私」はします。馬車をよけようとして石畳につまずきよろけた時の感覚に始まり、召使いが粗相をして鳴らした食器の音、固いナプキンの糊の感触などから、様々なことが次々によみがえってきます。そして、一時は諦めた文学に対する熱意もよみがえるのでした。
最後に様々な謎の答が明らかになると書きましたが、実はそうでもない点も多々あります。というのは、プルーストの生前に刊行されたのは「ソドムとゴモラ」までであり、その後は、プルーストが残したノートなどに基づいて死後出版されたからです。プルーストは完成した原稿に何度も手を入れるタイプだったようで、残されたノートにも一応「完」と書かれてはいるのですが、その内容には矛盾した点も多々ありますし、解かれていない謎もいくつも残されたままであり、もしプルーストが生きていたなら、絶対に手を入れたであろうと思われる部分が多数あるのです。
ですから、その意味では未完の超大作なのかもしれませんね。
とにかく超大な作品ですので、気軽にお勧めするというわけにもいきませんが、20世紀の文学はこの作品無しには語れないということにもなっていますので、トライしてみる価値は十分すぎるほどにあると思います。
056 「アレクサンドリア四重奏」/ロレンス・ダレル
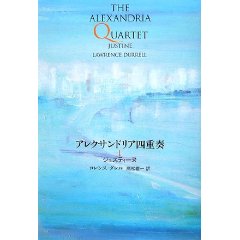

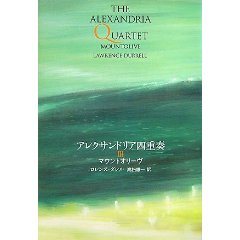
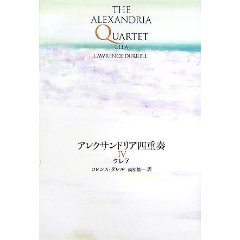
もし、誰かが、ある人たちの間の人間関係を観察し、あるいは、ある出来事を見分してその意味をとらえようとしたなら、それは、その人の視点でしかないのであって、そのことは、自分とある人との関係を考えるときにおいても、また、そのとおりなのでしょうね。
ですから、その同じ人間関係、同じ出来事、同じ、「ぼく」と誰かの関係を、別の人が見れば、それはまた違った様相、意味を持つのでしょう。
「アレクサンドリア四重奏(カルテット)」とは、まさにそのような作品です。
全4巻の作品ですが、普通の4巻本のように、次々と物語が進み、時制が進んでいくという作品ではありません。
時に、行きつ戻りつはしますが、基本的に(特に3巻目までは)同じ場所、同じ時、同じ人たちの事柄を重ねて辿ります。
それぞれの巻には、「ジュスティーヌ」、「バルタザール」、「マウントオリーブ」、「クレア」と、登場人物の名前がつけられています。
そして、これらの人たちが交わる場所が、エーゲ海に面したエジプトの都市であるアレクサンドリアなのでした。
作者ロレンス・ダレルの筆はとても華麗で繊細です。
アレクサンドリアという、この作品においては、ある意味閉鎖された都市(いえ、それは濃密な人間関係においてというだけの意味ですが)を、都市のその美しさと醜悪さとを、たとえようもなく美しい比喩で綴っていきます。
第1巻目の「ジュスティーヌ」(マルキ・ド・サドの、あの名前ですね)では、イギリス人である小説家志望の学校教師である「ぼく」(ダーリー)が、アレクサンドリアで過ごした日々を、踊り子である可憐なメリッサがいながらユダヤの魅力的な女性ジュスティーヌと恋に墜ちたことを、そしてそれを取り巻く愛すべき人たちを、回顧しながら描いた一つの作品となっています。
誰もが繊細で、誰もが傷ついていくようです。
ダーリーは、その時間、その場所を、一つの作品として書き残したかったのでしょう。
ところが、第2巻の「バルタザール」になると様相は一変します。
「ぼく」の友人であったバルタザールが、第1巻目の原稿を見て、それに「行間注釈」をつけたことから始まります。
そう、バルタザールの目から見れば、ダーリーの書いている甘っちょろい感傷など、皮相に過ぎないと。
お前は知っているのか? お前があれほど愛した、メリッサを不幸にさせてすらいることを自覚してまでものめりこんでいたジュスティーヌとの愛なんて、ジュスティーヌからすればめくらましに過ぎなかったのだぞと、ダーリーにしてみればとんでもなく辛いことまで書かれてしまいます。
そして、ダーリーの目から見て何でもなかった出来事には、これほどの意味と謎があったのだということが徐々に描かれて行きます。
しかし、バルタザールの「解釈」も、それは一人のひとの眼を超えることはできないわけです。
何もバルタザールが、すべてを知っているわけではありません。彼は、彼の視点でしか、やはり見ることはできないのです。
そこで、語られた多くの謎や驚くべき出来事だって、その意味を知る者にとっては……
第3巻の「マウントオリーブ」では、若干時が戻ります。
ここまでは、実はマウントオリーブは、ほとんど出る幕が無かった位。
僕も、読み始めた時は、マウントオリーブって誰だっけ?っていう感じで始まりました。
いえ、ですが、これがまた……
マウントオリーブは、有能で魅力ある外交官です。若くしてアレクサンドリアで言語を学び、熱烈に彼の地への赴任を望むのですが(あぁ、そのほんとうの理由もあるのですけれど)果たされず。
しかし、後に、大使となって赴任することになるのでした。
さて、彼の目から見るとこの物語はどう見えるのか。
ネッシムと、実は彼と結婚したジュスティーヌのことが語られます(もちろん、それだけじゃないですけれどね)。
そういう……ことだったの。 と、読者は思うことでしょう。
熱病のように恋い焦がれる者、死んでゆく者、決して会おうとしないこいびとたち、陰謀と謎。
第4巻は、再び「ぼく」(ダーリー)が戻ってきます。
そして、あの頃の、みんながいたころのアレクサンドリアがどういう場所で、あれがどういう時間であったのかが、描かれます。
この巻だけは、時間が、先へ過ぎています。
そして、最後の最後、ダーリーのとある決断について。
「全宇宙が親しげに僕を小突いたような気がした。」と終わります。
ええ、これは、僕は、ダーリーの決断に対して、「よくやったな。」っていう感じで、全宇宙が小突いたようにとらえました。
あぁ、何て余韻の深い作品でしょう。
全4巻という、大変長い作品なのですが、読了した後、もう一度はじめから読みたいと思ってしまうような作品でした。
そうですね。
もし、今、どなたかに、何かの本をプレゼントするとしたなら、今の気持ちでは是非この「アレクサンドリア・カルテット」を、と思ってしまいます。
ところで、この本の表紙はとてもきれいです。良い表紙ですね。
この本が最初に書かれたのは、ちょうど僕たちが生まれた頃だったそうです。
ずっと絶版の時期があったらしいのですが、訳者再訳により復活しました。
たいへん、おすすめできる本なので、興味をもたれたら是非どうぞ。
「アレクサンドリア四重奏」/ロレンス・ダレル
高松雄一 訳 河出書房新社
ISBN978-4-309-62301-6
ISBN978-4-309-62302-3
ISBN978-4-309-62303-0
ISBN978-4-309-62304-7
055 「水源」/アイン・ランド
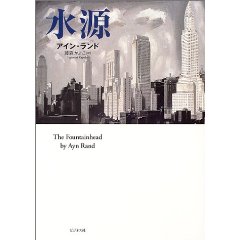 作家は、女性です。
作家は、女性です。
……以前に、女性を強く感じる作品は苦手だってどこかに書いたことがあったかもしれません。
そういう作品も、あっただけ、なのだと思います。
ちょっと、書きすぎたかもしれません。
この作品の作家さんも、いえ、最初は女性だとは、作家さんが、そうだとは何も感じなくて、名前だけからもそうは感じなくて、別に何も気にせず読み始め、そして、読了しました。
「あとがき」を読んで、あ、女性の作家さんだったんだって初めて知りました。
本書は、超大作です。上下2段組で1000ページを超します。
でも、全米のなんたらアワードで2位とかに入ったとかいう作品だそうです。
物語は、ハワード・ロークという天才肌の建築家志望の若者の学生時代から始まります。
建築家には名門のスタントン工科大学で光る才能を示してはいたのですが、教授達が求める課題にことごとく反抗し、退学を選びます。
彼は貧しく、同級生のピーター・キーティングの家に下宿していました。
ええ、ピーターもこの時代は別に裕福でもありませんでした。彼も、抜群に…ある意味で…優秀でした。
そして、教授達の課題にも如才なく答え、主席でスタントン工科大学を卒業します。
彼の前途は洋々です。N.Y.最高の建築事務所に迎え入れられ、そして……彼の上昇志向、どんな手をつかっても成功をつかみ取るという強い意志が、数々の世間に評価される建築物を造る地位に上り詰めます。
一方のハワード・ロークは、過去には評価されたこともあったけれど、今となっては誰にも見向きもされない、アル中になったとある建築家のもとを訪ねます。
そこで、彼は、彼自身を理解してもらうことができ、落ちぶれた建築事務所に入ります。
ですが、仕事など何もなく、金もない生活です。
その後、ピーターはますますこの業界で頭角を現し、知識人として名望高いエルスワース・トゥーイーに高く評価されます。
どういうわけか知らないのですが、世間ではリベラルで市民の味方として高い名望を得ているエルスワース・トゥーイーは、まるで安売りのゴシップやろくでもない記事ばかり追っているような、でも、全米でもっとも読まれている「ワイナンド」系列の新聞に「小さな声」という、世間で非常に良心的と評価されているコラムを書き続けているのでした。
何故、エルスワース・トゥーイーが、あんな「ワイナンド系」の新聞なんかに書くのだろうかという声はあるにはありますが、トゥーイーはそれ以外でも言論活動はしていて、もうちょっと高級な雑誌などにも寄稿していました。
今や時代の寵児となったピーターは、以前からとある冴えない女性と、理由も分からず、何となく会っていました。
それはまったく身勝手なもので、ピーターが思い出したときだけ会っているようなもの。
でも、彼女は、何も苦言めいたことは言いません。すべて受け入れていたのですね。
それは、熾烈な業界で生きていくエリートのピーターにとっては、やすらぎだったのでしょう。それは本当に。
彼女は、ある時、「私たち、婚約してるよね」って言います。
ええ、その時の、その時のピーターはそれを受け入れます。
しかし、ピーターの母親は、表面的には受け入れますが、息子に言います。
お前は中央に出て行く人なのだと。その時、あの田舎娘が妻ではいけないと、暗に言います。
ピーターが就職した超一流の建築事務所の経営者の娘は超美貌の娘でした。しかし、その素行は訳が分からず、父親も手を焼いているほど。しかも、あの下劣な「ワイナンド系」新聞でコラムを書くなどという仕事をしている。
しかし、その美貌と気品と、地位と才能こそ、ピーターにこそふさわしいのではないのか?
一方のハワード・ロークはまるでうだつが上がらない。
でも、滅多にない仕事で、彼は彼なりに仕事をした。
それを目にした、とある有名な作家が、彼に自分の家を建てて欲しいとの依頼が!
彼は、いつものように全力でその仕事をしました。
そして、それは、その依頼主をいたく感動させたのでした。
これは、ここまでのお話はほんの序盤。
だって、これはとても長いお話だから。
最初、とても良い人かもしれないって思っても、それはそうなんだろうか?
どうして、こんなことをするのだろうか、と思うことも沢山ありました。
ええ、最初に女性作家さんのことを書きました。
え、女性の目から見た女性って、こんな描き方をするのですかって、ちょっと、残酷すぎませんかって感じたところもありました。
そんなにまで、あなたの作った登場人物に、辛い思いをさせなくてもいいじゃないですか、って。
最初に、あんなことを書いたのは、ここなんです。
何で?
と、しか、私には思えませんでした。
その「女性」に対応して描かれている男性についてもそうです。
私にとっては、そこまで、他の人を傷つけるようなことが……って、それは最後まで残りました。
そもそもの始まりから嫌いですし、その後だって、勝手だという非難は、それは、私は持ち続けて読んだと思います。
この書き方は残酷ですよね。それを純粋と呼ぶのは自由ですが、私だったら、そういうことは、できない…
思想小説というくくり方もされるそうです。
ええ、確かに、くどいほど、作者の「考え方」を書き連ねている部分も多いです。
それに共感できるか、できないかは、多分「下の次元」 のことなのだと思います。
まずは、物語を、作品を読んで、その時に、既に読者は考えているのですから。
それを、その後、作者が作者の言葉で敷衍しますけれど、それは、余録。
だって、もう、みんな、その前に感じているでしょう? って思いました。
でも、長かったけれど、面白く読みました。
力強い作品ですね。
それに、どこまで同調できるかは、色々ありそうですけれど、でも良い作品じゃないでしょうか。
何だかシニカルなご紹介になってしまったらごめんなさい。
そういう色抜きにして、面白い作品ですよ。
「水源」/アイン・ランド
藤森 かよこ訳 ビジネス社
ISBN978-4-8284-1132-3
054 「フェッセンデンの宇宙」/エドモンド・ハミルトン
 古いSF作家さんだそうですが、私は知りませんでした。
古いSF作家さんだそうですが、私は知りませんでした。
「キャプテン・フューチャー」という、スペース・オペラというかSF冒険活劇が有名な作家さんだそうですが、そのジャンル、ほとんど読んでいなかったこともあって。
でも、巻末の解説を読むと、多彩な顔を持つ作家さんだそうで、短編の名手でもあるそうです。高く評価されてきた割にはこのところあまり紹介されていなかったとか。
本書も短編集ですが、とても面白く読ませていただきました。
本書のタイトルにもなっている「フェッセンデンの宇宙」は、奇矯な教授であるフェッセンデンが生み出してしまったとある画期的な発明(?)にまつわるお話です。
ちょっと(スケールは真逆かもしれませんが)オラフ・ステープルドンを思い出したりしてしまいました。
箱庭宇宙?
「風の子供」は、何ともロマンチックな作品に仕上がっています。
とある探検家が行き着いた場所はとても風が強い場所でした。
しかも、その風は、生きているのでした。
入ってくるなとばかりに風にたたきつけられる探検家。そこを救ったのは、というお話。
「向こうはどんなところだい?」は切なくなるお話です。
宇宙探検隊の一員であった主人公は、大事故を経験したにもかかわらず無事に生還した1人でした。
映画やニュースであるとおり、国民は英雄の帰還を大歓迎します。
でも、亡くなってしまった同僚もおり、その遺族から是非話を聞かせて欲しいとの頼みを受けます。
断り切れない主人公は、遺族達を訪ね、「その時」のことを話すのですが……
「翼を持つ男」という作品も切なさを感じます。
とある原因から翼を持って生まれてしまった男性を描きます。
その悲哀と、彼の選択した途。
「夢見る者の世界」は、現実と夢のどちらが本物なのだろうかという問いかけの作品。
現代に生きる主人公は冴えない保険会社の社員ですが、子供の頃からいつも同じ世界の夢を見続けています。
その世界での彼は、砂漠の国の勇敢な王子でした。
いつも眠りにつくと、王子が目覚めるところから始まり、連続した夢なのでした。王子も眠りにつくと現代世界の冴えない保険会社員が目覚めるところから連続した夢を見ます。
王子は剛胆な性格からか、それは夢だと割り切りますが、現代の会社員はどちらが夢でどちらが現実なのか悩み続けます。それはそれはリアルな夢?なので判断がつかないのです。
王子の世界でも人生を生き、現代社会でも人生を生きている感覚を捨てきれないのです。
とあるとき、王子が絶体絶命のピンチを迎えます。
何とか助けてあげたいのだけれど、夢に持っていける物などなし。
かろうじて、現代社会に生きている冴えない会社員の記憶や経験を、王子の夢として見てもらえるのが精一杯。
さて、結末は?
ハミルトンは、まだ10代だったレイ・ブラッドベリ(私の大好きな作家さんです。037を参照してください。)とも親交があって、多大な影響を与えたそうです。
そういわれれば、ブラッドベリ的テイストがありますよね(逆ですね。ブラッドベリにハミルトン的なテイストがあったということ。)。
河出書房新社の「奇想コレクション」シリーズの一冊です。
同シリーズからは、これまでにも「願い星、叶い星」/アルフレッド・ベスター(012参照)をご紹介していますし、これまた私の大好きなスタージョンの「不思議のひとふれ」という本も出ています。良いシリーズではないでしょうか。
「フェッセンデンの宇宙」/エドモンド・ハミルトン
中村 融 編・訳 河出書房新社
ISBN4-309-62184-8
053 「レ・ミゼラブル」/ヴィクトル・ユーゴー
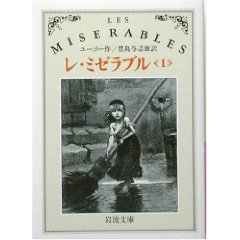
夏休みの課題図書……じゃないけれど、「レ・ミゼラブル」の完訳本を読んでみました。
ええ、子供の頃、読んだことはありますが、あれはジュヴィナイル(子供用に脚色したもの)。
ちゃんとしたものは読んでいなかったので、今回挑戦してみました(「カラ兄」も長いけれど、こちらはもっと長いですぅ)。
しっかし、悲惨な話ですね。
どうしてこうまで不幸がつきまとうのだろう。
最初は御存じですよね。ジャン・バルジャンという主人公が貧しさの余りパンを盗んで徒刑囚となってしまうことから始まります。
これは、社会が悪いのですけれどね(今の日本だったら、こんなことだったら間違いなく起訴猶予だと思います。……昔は、刑罰が厳しかったのですね)。
よせば良いのに脱走を性懲りもなく試みたために刑期はどんどん長くなってしまいます。
ようやく刑期を終えて出所したは良いけれど、どの村に入るにしても自分は徒刑囚であるという証明書を見せなければならず、そうすると誰も相手にしてくれない。
一夜の宿も食事も提供してもらえないわけです(お金はちゃんと持っているのに)。
困り果てた時に助けてくれたのは人徳の司祭さん。
食事も一夜の宿も提供してくれます。
そこで見ちゃったんですよね、銀の食器を。
これを盗んでしまうわけですが、すぐにばれます。
お巡りさんに見つかって司祭さんの所へ突き出されるわけですが、司祭さんは「それは差し上げた物です」と言って罪を救ってくれます。
加えて、「これもお持ちなさいと言ったじゃないですか」と言いながら、銀の燭台も持たせてくれました。
ここでジャン・バルジャンの人生観が大転換するのですね。
司祭様が言った、「正直に生きなさい」という言葉のまま、愚直に残りの人生を歩み始めます。
ええ、それは、まさに愚直です。
最初は、何処へ行っても迫害されるのですが、モントルイュ・スュール・メールという町にうまく潜り込むことができました。
小さな町だったのですが、そこで工夫を重ねてとある事業に成功します。
そのため、町は潤い、発展することになります。
そこで、彼はマドレーヌ氏という名前で過ごし、貧しい人たちを助けようとします。
自分がそうでしたからね。
そこで、大きな富を得て、市長にまで推挙され、安定した生活を手に入れることができました。
ところが、官憲は未だにジャン・バルジャンを追っていたのでした。
それは、彼が刑期を終えて出所した後、司祭様のところでやはり盗みをはたらいたのだということが分かってしまったから(司祭様は最後までジャン・バルジャンのことをかばって亡くなったのですけれどね)。
加えて、ジャン・バルジャンが司祭様の気持ちに打たれて呆然としていたときに、偶然そばにいた男の子が落としたお金を踏みつけてしまい、「返してよ〜」という訴えも耳に入らずじっとしていたためにお金を取ったとされた罪まで加わってしまいました(強盗とされています)。
再犯ですから、とても重く処罰しなければならないということで、ジャベルという法律の権化のような警察官につけねらわれることになります。
ジャベルは、モントルイュ・スュール・メールに赴任しており、マドレーヌ市長(つまりはジャン・バルジャン)を良く知っていましたが、これが指名手配の男だとは確信をもてずにいました。でも、すっごく疑っていたのね。
とある時、ジャン・バルジャンが捨て身で市民を助けに入った事があって、その様から、マドレーヌ市長はジャン・バルジャンであると確信するに至ります。
そして、中央にその報告を上げてしまったのでした。
その回答は……「ジャン・バルジャンは既に逮捕されている」とのことでした。
ええ、全くの別人がジャン・バルジャンと間違われて逮捕され、極刑に処されようとしていたのでした。
そのことは、ジャン・バルジャン本人にも知ることとなりました。
間違われた男は、それなりの罪を犯しており、それだけでも処罰されることは十分にあり得ることでした。
ジャン・バルジャンは、市長として良政をしき、市民からも大変慕われ、町もとても発展していました。
このまま黙っていたとしても、それが何の罪でしょう?
むしろ、市長として善政をしき、貧しい人を救い続ける方がどれだけ良いことか。
しかし、ジャン・バルジャンは、「正直に生きなさい」という司教様の言葉に従い、名乗り出てしまうのでした。
さらにこのエピソードと前後して、コゼットという、非常に不幸な生い立ちを持った女の子を庇護する話があります。
コゼットは、ジャン・バルジャンの死に物狂いの保護のもとで素晴らしく美しい女性へと育っていきます。
それが、最後の最後まで続くエピソードとなるのですけれどね。
この先にもエピソードが山盛りですが、ご紹介はここまで。
「レ・ミゼラブル」は舞台でも上演されていますので、ご覧になった方もあるかもしれませんね。
原作を読むと、本題とは全く関係のない、歴史的、政治的な叙述も多々あり、それが結構な量になってもいます。
ですが、それは、フランス革命の時代に生き、亡命までした、ユーゴーが書きたかった事なのかもしれませんね。
本当に長大な作品です。
都合良すぎる展開と言えばそういうところは多々あります。
饒舌すぎると思われる叙述も多すぎる感あり。
納得できない登場人物の行動もいくらもあります。
ですが、ですが、これはこれなのだろうと思います。
ええ、涙腺弱いですから、ほろっときたところもいくつかありました。
よろしかったら、読んでみますか?
「レ・ミゼラブル」/ヴィクトル・ユゴー
豊島与志雄訳 岩波文庫
:1: ISBN4-00-325311-6
2: ISBN4-00-325312-4
3: ISBN4-00-325313-2
4: ISBN4-00-325314-0
052 「カラマーゾフの兄弟」/ドストエフスキー

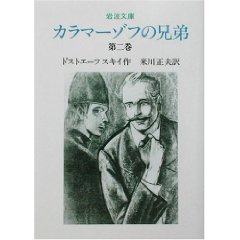
「罪と罰」は読んだ。「貧しき人々」も読んだ。あぁ、「地下室の手記」も読んだ。「白痴」……も読んだと思うけれど記憶に残っていない。
どれも中学生から高校生にかけての頃のこと。
でも、今の今に至るまで「カラマーゾフの兄弟」は読まなかった。
ドストエフスキーの遺作でもあり(何と!死の80日前にようやく第1部のみが完成した未完の作品)、最高傑作と言われているのに。
何しろ長いのにおじけづいたのかもしれない。
あるいは、タイトルが何故か気に入らなかったのかもしれない。
気に入らないと言えば、今出ている岩波文庫の表紙絵もあまり気に入らない。
だけど、いつかは読まなければいけないのだろうなと、思っていた作品。
ようやく読みました。
確かに長い。文庫本で1440ページ余り。1ページ1.5分で読むとぶっつづけで36時間かかるというシロモノ(誰でしょうねこんなヒマな計算をしたのは)。
それでも、確かに読んでおいた方が良い。
昔に比べたら、長い作品は苦にならなくなってきているのも幸いしたのかもしれない。
物語は、極めて利己的であり、物欲の固まりであり、放蕩の限りを尽くし、未だに欲望にぎらぎらしている、カラマーゾフ家の家長であるフョードル・カラマーゾフの元に、幼い頃にはまったく顧みられず、父親からの愛情も受けず、他者の情けにより成長した3人の兄弟が帰って来るところから始まる(2人の母親つまりフョードルの2人の妻は既に他界している)。
父のフョードルは、うらぶれた食客であったが、小金を貯め、債権を買い集め、高利貸しをし、その他もろもろのあくどい商売に手を出し、今は相当な財産をため込み、貴族の地位まで手にした男。
長兄のドミートリー(ミーチャ)は屈強な休職軍人。やはり放蕩家であり、暴れ者ではあるが、プライドを重んじ、一途なところもある、ある意味純粋な極めてロシア的人物。
次男のイヴァン(ヴァンカ)は、優れた頭脳を持ち高い教養を身につけた合理的かつ理論的な男性。この世界にはびこる不合理を受け入れることができず、神は不在であると主張する(そして作中で自作の「大審問官」という戯曲を披瀝する)。長兄が極めてロシア的人物であるのに対しヨーロッパ的なもの(西欧近代的、合理主義的なもの)を代表する。
末弟のアリョーシャ(アレクセイ)は、誰からも愛される純粋無垢な男性。慈愛に満ち、博愛の気持ちから人々を癒す優しさに満ちた男性。物語の初めのころは見習い僧として僧院で生活し、師と仰ぐゾシマ長老を心から尊敬する。もちろん深く神を信仰している。
こんなキャラクターが一堂に会するのだが、まぁ、平穏な物語にはなりそうもない。
最初は強欲な父フョードルが、子供達に分配すべき遺産すら独り占めにし、放蕩の限りに蕩尽してしまおうとすることと特に長兄ドミートリーとの対立が起きる。父の家には父の私生児だと言われているてんかん持ちのスメルジャコフ(料理人として雇われている)とグリゴーリィという頑固な老僕およびその妻であるマルファが同居している。
スメルジャコフは無口ではあるが、時折イヴァンのシニカルな無神論に意見を述べることもある。
何故、ドミートリーが強く遺産に執着するかと言えば、彼の性格および今は零落し、まとまった金も持たないことによるものでもあるが、2人の女性との関係が大問題なのである。
一人は許嫁のカチェリーナ(カーチャ)。そしてもう一人は初恋のポーランド人に捨てられ、生活のため商家の囲い物となっている情熱的な女性グルーシェンカ。彼女はうまく立ち回り今では小金を貯め込んでいる。
ドミートリーは、カチェリーナとの関係もありながら、妖艶なグルーシェンカに惹かれ、許嫁を捨てて彼女を我が物にしようとする。
ところが、父フョードルもグルーシェンカに惚れ込み、金の力を持って彼女を自分の物にしようとする。一人の女性を巡って父子が争うことになる(でもそれを手玉に取るグルーシェンカ)。
そのような2人を冷徹に見つめつつ、カチェリーナに惹かれていくイヴァン。これら登場人物中で翻弄されながらも各人の心の支えとなるアリョーシャ(ゾシマ長老の遺言により、僧院を出て俗社会で生きることになる)。
このようなテーマを主軸としながらも、いくつかのエピソードが絡まるという入り組んだ展開。
その後、物語は急展開を遂げる(ネタバレ注意)。
遂に強欲な父フョードルが自宅で殺されてしまうのである。そして、グルーシェンカに与えようと用意していた3000ルーブリの大金が消えていた。
確かに、ドミートリーはその夜父の家に忍び込み、見とがめたグリゴーリィーを殴打して瀕死の重傷を与えたのであった。
ドミートリーは、カチェリーナに対する名誉を全うするため、そしてグルーシェンカを我が物にするために父から当然分配されるであろう遺産を当てにしていたことも事実である。そして数日前になかなか遺産分けをしようとしない父をこっぴどく殴りつけて怪我を負わせたことも事実。
そして事件後、グルーシェンカを探しに行ったドミートリーは、一度は彼女を捨てたポーランド人の男が帰ってきて彼女を連れ去ったことを知る。
後を追うドミートリー。
当然、彼に父親殺しの嫌疑がかかり、官憲はドミートリーを追跡する。
モスクワに出奔したイヴァンも父の死と兄が犯人であることを知り、急遽舞い戻るが、そこで恐ろしい真実に気づき、正気を失ってしまう。
イヴァンと彼の幻想である悪魔との対話も(一般には「大審問官」が有名すぎて余り取り上げられないようだが)読み応えがある。
この後の展開は、ある意味推理小説や法廷物の小説のようにだって楽しめる。
もちろん、長編大河人間ドラマであることは言うまでもない。
はたまた、エピソード中で出てくる、イヴァンがアリョーシャに語り聞かせる「大審問官」という自作の戯曲のくだりは、神はいるのかという哲学論争でもある。
さらには、粗暴なドミートリーが酒場でののしり乱暴を加えたスネギリョフ退役大尉とその一家のエピソードも感動的である(そう「糸瓜」の話)。
純粋で優しいアリョーシャを愛し、アリョーシャからも結婚の誓いを得ているのに……となってしまうリーザ。
様々な要素が詰め込まれた、重厚長大な作品である。
評論も数多く出ているので、興味を持たれたらそちらも是非参照して欲しい。
とにかく、いつかは、読んでおいて損はない(というよりは、読むべき)作品としか言いようがない。
「カラマーゾフの兄弟」/ドストエフスキー
米川正夫訳 岩波文庫(全4冊)
ISBN-4-00-326150-X
ISBN4-00-326151-8
ISBN4-00-326149-6
ISBN4-00-326152-6
051 「バルトルシャイティス著作集」/バルトルシャイティス
ユルギス・バルトルシャイティスの著作集です。
19世紀末にリトアニアに生まれた……何て言えばいいのだろう、美術評論家?
幻影を、見た人だと思うのです。
あんまり、知られていないのかもしれないけれど、とある領域に興味がある人にとってはとても有名人。
著作集は4巻からなっています。
第1巻は「アベラシオン」。
形態の変容について論じた本です。
左の表紙絵の一番上に、きれいな女性が描かれていますよね。
彼女を動物にたとえたら何に見えますか?
答はひつじ。
意識するとしないとに関わらず、自然や人間の筆致は、ダブルイメージをもたらすことがあります。
自然で言えば、とある鉱石を切った時に、思わぬ絵画が秘められていたりして。
第2巻は「アナモルフォース」。
変容を論じています。
角度を変えて見たら、思わぬ物が見えてしまう、まるでだまし絵のような作品が、とある時期作られたことがありました。
ホルバインの「大使達」という有名な絵画には、どくろが隠されていたりするんですね。
どうやって、そういう作品を残したかという技術的なことにも触れています。
第3巻は「イシス探求」。
宗教に見られるイマージュを追います。
様々な土地で繰り返し語られるイシスたる母のイメージ。
それが色々な物に仮託して残されているのですね。
とっても違うのですけれど、違うのですけれど、あのフレイザーの「金枝編」を彷彿とさせるような感覚がありました。
第4巻は「鏡」。
人類は、古代から、ある種の鏡を持っていたのです。
金属を得る前からね。
金属を得たあとは、有名なのはシュラクサ(シラクサ)でアルキメデスが起こした「奇跡」でしょうか?
鏡で集めた光で、敵艦隊を焼き滅ぼしたというあれ。
その真偽についても語られ、いや、というか、その逸話を巡り、過去様々な人々がなした技を描いたりもします。
博物誌で有名なビュフォンにも、その鏡の図版が残されていたりします(この本の中でも紹介されているのですが、私は酔狂なことに、「ビュフォンの博物誌」も買い込んでいたりして、そっちでもしっかり見させて頂きました)。
と、まぁね。すっごくマニアックな世界かもしれないけれど、不思議を不思議と素直に受け止めて読んで頂けたらこれほど不思議なこともないかもしれない。
遠近法の秘術や、鏡でゆがめられた真実とか。
そんな、秘法を語り尽くしている、ほんと、マニアックな著作集なのです。
ですが、そこで、初めて知る、絵画の見方とか、建造物の由来など、知的好奇心をとっても満足させてくれる本です。
図版も豊富でとても興味深いですよ。
「バルトルシャイティス著作集 アベラシオン」 ISBN4-336-03137-1
「アナモルフォース」 ISBN4-336-03138-X
[「イシス探求」 ISBN4-336-03139-8
「鏡」 ISBN4-336-03140-1
国書刊行会
050 「ウォッチャーズ」/ディーン・R・クーンツ
わんこ(U^ェ^U)大好きな方、良い本ですよ〜。泣けるしね。
もう疲れ切っちゃった、36歳のトラヴィスという男性が、何か暴力的なことをせずにはいられなくなって、銃を持ってサンディアゴ・キャニオンに単身訪れるところから物語は始まります。
そこで、蛇を撃ち殺そうかとか、そんな殺伐とした気持ちになっているトラヴィスなのでした。
そこに来たのは一匹のレトリバー。
トラヴィスの悪い行いをたしなめ、気持ちの良い方へと導くように接します。
その後、色々あるのだけれど、トラヴィスは、彼(わんこね)と一緒に生活するようになります。
このわんこには、どうにも「知性」があるとしか思えないのです。
ええ、とても賢い。いや、犬としての賢さのレベルを超えているのです。
言葉だって、あやつれるのですよ。
かくして、彼は、「アインシュタイン」と名付けられました(愛称はアインね)。
そしてまた、アインを連れて公園を散歩していたら、突然アインに引っ張られていきます。
そこには、訳の分からないような男女が(トラブってる?)。
アインはいきなりそのいやらしい男性に吠えかかります。
そして、そして、その女性ノーラと、トラヴィスは結ばれていくのですけれど。
この辺までは平和なお話なのかもしれませんが、何でアインはこんなに賢いのでしょう?
悲しいことがあったのです。
あぁ、人間って言う奴は……(もちろん、今現在でも生息している、一部の心を持っていない人たちのことを言います)。
アインは犠牲者なのですよ。
そして、アインと共に生まれた、もう一つの存在。
それは、もはや犬ではないです。
巨大な体躯、残忍で、凶暴で。
まるで、アインと正反対な、のろわしい存在。
共鳴……するのでしょうか。
迫り来る闇の生物。
トラヴィスもノーラも必死になってアインを守ります。守り抜こうとします。
ですが、相手は強大です。
アインは最後までけなげです。
あぁ、何ていう……
ネタばれにならないように書くのはいつも難しいなぁって思います。
だまされたと思って読んでみてくださいな。
わんこ大好きな方なら泣けると思うよ。
上下2巻本です。
「ウォッチャーズ」/D・R・クーンツ
松本 剛史 訳 文春文庫
ISDN4-16-713614-7
ISDN4-16-713613-9
049 「エルフランドの王女」/ロード・ダンセイニ
ようやくご紹介の運びとなりましたダンセイニです。
う〜ん、もうちょっと早くご紹介しても良かったですね。
ロード・ダンセイニ。ファンタジーの領域においては外すことのできない作家。
都市に蝕まれていない、ケルトの夢を紡ぐ作家。
1878年に生まれ、12歳で男爵の称号を継承したダンセイニ城の第18代当主。
「指環物語」の作者J.R.R.トルーキン、「クトゥルフ神話体系」を生み出したH.P.ラヴクラフト、そしてSFの大家アーサー・C・クラークその他多くの作家に強い影響を与えたのでした(日本の博覧強記、荒俣宏さんのペンネーム、「団精二」は、もちろんダンセイニのもじり)。
日本でも早い時代から紹介されており、大正から昭和初期にかけて、松村みね子、西條八十、稲垣足穂らが翻訳しています。
ところが、どうしたことか、ある時からぱったりと取り上げられなくなり、しばらく前まではほとんど絶版という哀しい状況にありました。
今回、ご紹介する「エルフランドの王女」も、私が興味を持った時は絶版でした(仕方なく結構高いお金出して古書で入手しましたよ)。
ところが、今回、書き起こすために色々調べたら、今は復刊しているようですね(ぱちぱち)。
ええ、そうなんです。少し前から、ダンセイニ、復刊ラッシュです。
以下、ここ数年の間に、実際に新刊で買えた本だけを挙げますが、それだけでもかなりのものです。
まとまったところでは、河出文庫から、「世界の涯の物語」、「夢見る人の物語」、「時と神々の物語」、「最後の夢の物語」の4冊(ダンセイニの短編をテーマ別に再編集したものでしょうか)が出ています(何とありがたい!)。
そのほか、ハヤカワ文庫も、あの名作、「ペガーナの神々」を復刊してくれましたし(へへ。私も「復刊ドットコム」で投票しちゃいました)、ちくま文庫からは「魔法使いの弟子」が出ています。はたまた、国書刊行会からは「ヤン川の舟歌」も出ていたり。
今は、ダンセイニを読むにはとても良い環境と思われます。
願わくば、再び忘れ去られることなく、出版され続けて欲しいものです。
さて、作品をご紹介しましょう。
「エルフランドの王女」の舞台は、ケルトのおだやかな村、アールです。
この土地を統べる王がいますが、重要な事項は、民人の評定衆が決めることになっていました。
ある日、評定衆は、「魔」を使う者に王になって欲しいという決定を下します。
それは、とてもおだやかで平和な村アールなのですが、よその土地では全く知られていない村でもありました。
そこで、「魔」を使える王が統べれば、アールの名は遠く響き渡るであろうと考えたのでした。
アールの王は、評定衆達のこの決定を受け入れます。
内心、なんと愚かなことよと分かりつつ、しきたりに従います。
王は、息子のアルヴェリックに剣を授け、エルフランドへ行き、王女を妻に娶るように命じます。
ええ、そのころはまだ、人間界とエルフランドは境界を接していたのですね。
その境界は、永遠の黄昏のような、淡く、美しいものでした。
王から授けられた剣ををはいたアルヴェリックは、遠い、遠いエルフランドを目指して旅に出ます。
旅の途中で、ジルーンデレルという魔女に出会い、彼女の力添えを受けて、稲妻から生み出された魔法の剣を得ます。
この魔法の剣が物語の終盤ではたたるのですけれどねぇ……。
苦難の旅の果て、ようやくエルフランドの境界に達したアルヴェリック。
エルフランドの在所を示す青い山々が目に染みます。
暗い、魔の森を抜けて王宮に向かおうとしますが、それを阻止する魔法がかけられた森の木々達。
アルヴェリックの行く手を阻止せんと襲いかかってきます。
父王から授けられた剣で応戦しますが、魔の者達にはかないません。
そこで、魔女ジルーンデレルが鍛えてくれた魔法の剣を構えると、みるみるうちに道が開けていきました。
この剣は、ほとんどすべての魔法を跳ね返すことができました。エルフランドの王が持つ、最大の3つの魔法以外は。
さて、こんな感じで展開する物語なのですが、ここまでの印象では、まるでアニメか何かのように受け止められてしまうかもしれません。
ええ、もちろん、ファンタジックな要素は盛りだくさんですが、もちろん、それだけじゃありません。
この後、アルヴェリックは、首尾良くエルフランドの王女であるリラベルと恋に落ち、リラベルをを妻に娶り、人間界に連れてくることができました。そして、リラベルとの間に男の子をもうけることになります。
ですが、エルフランドで育ったリラベルには、人間界のことがどうしても理解できません。
人間側にも問題があります。旧弊を重んじるあまり、リラベルが美しい星を愛でることさえ禁じたりもします。
あぁ、でも、リラベルは星を愛し、その名前の一つであるオリオンを息子の名前に選びます。
アールの村は農耕、狩猟の村でしたから、王子の名が狩人の星であるオリオンにちなんだものであることについては大歓迎しました。
さてさて。こちらはエルフランド。
娘が駆け落ちしてしまったエルフランドの王はひどく悲しみます。
何よりも決定的なことは、「時」のことでもありました。
エルフランドでは、時は流れません。いつまでも平和で幸せなままでいられるのでした。
しかし、人間界では時が流れます。
それは、エルフランドの者達にとっては恐ろしい事でもありました。
まるで刃のように、時が生を切り取っていくのが人間界なのでした。
ええ、リラベルも時に蝕まれ、年老いていきます。
そんなことは、エルフランドの者としては耐えられないことだったのかもしれません(いや、でもね、物語の後半では、その「恐れ」を押してでも人間界にやってくる者もいるのですけれどね)。
遂に、エルフランドの王は、大魔法のひとつを発動させるのでした。
さあ、これからお話はどんどん深くなっていきます。
ただのゲームRPGなどとは違う所以です。
ストーリーもさることながら、私が、ダンセイニ好きだなって思う大きな所は、その描写なんです。
ケルティックな世界を描くその筆は、私にはとても心地よいものに感じられます。
草を撫でて吹き渡る風、季節になると咲くさまざまな花、遠くかすむ山々。
そういった描写が大好きなのでした。
ダンセイニ、やさしいと思います。
先ほど、書いたとおり、今はとても出版物が充実していますので、よろしかったら、是非、この機会にページをめくってくだされば。
「エルフランドの王女」/ロード・ダンセイニ
原 葵 訳 沖積社
ISBN−10 4806030260
(私の持っている本とは違う番号ですが、先ほど調べて入手可能と思われる番号を書きました)。
048 「特別料理」/スタンリィ・エリン
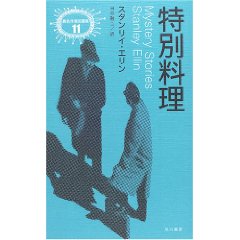 ハヤカワの「異色作家短編集」シリーズの第11巻です(041「一角獣・多角獣」,046「壁抜け男」に続いて3作目のご紹介になります)。
ハヤカワの「異色作家短編集」シリーズの第11巻です(041「一角獣・多角獣」,046「壁抜け男」に続いて3作目のご紹介になります)。
このシリーズは全20巻だそうで、絶版の復刻も含まれているのでかなり期待大です。
私もこれまでに5冊買っていますが、どれも面白いですよ。
軽く読めますし、なかなかお勧めです。
さて、今回のご紹介は「特別料理」です。
ほらほら、何とな〜く結末を予想してませんか?
いえ、その通り。
スタンリィ・エリンのデビュー作が「特別料理」なんですが、ストーリーはと言えば……
「そのレストランで供される料理は、何物もおよばない美味だった。だがその美味の秘密とは……。」ということです(これはwebなどで公表されている限りのご紹介文です)。
でもね、もう、オチって、大体想像ついちゃうでしょ。その特別料理が何で作られているかっていうこと。
そりゃ、スタンリィ・エリンだって分かった上で、敢えてこのタイトルをつけたんだと思うんです。
だって、タイトルからもう想像できちゃうじゃないですか。
そんなオチが分かっている小説なんてつまらないって、思いますか?
いや、そうじゃないんだなぁ、これが。
ええ、オチはご想像通りなんです。その通り。
でも、それが分かっていながら読ませるんですね〜。
この本の巻末解説は山本一力さんが書いているのですが、非常に上手いことを書いています。
先輩との会話という体裁をとっていますが、この「特別料理」は、刑事コロンボみたいに最初から見ている人には犯人(ネタ)が分かっている倒叙物だと読み解いています。
まさに言い得て妙です。
コロンボなどの倒叙物は、最初から犯人は分かっています。だからと言ってつまらないですか?
そんなこと全然ないですよね。
エリンは、それをオチでやったんですね。
オチはみんな分かって読んでいる。だけど、そのオチまでもっていく筆力で読ませてしまうんですね。
実際、とても良い味を出していたと思います。
その他の短編も粒ぞろいでした。
私の感覚では、皮肉なオチというのがエリンのスタイルかなと感じました。
ええ、それはいろいろな場面で。
「お先棒かつぎ」では、何とも不思議な仕事を依頼される主人公のお話です。
ほとんど無駄じゃないかという仕事にそれなりの給料を払ってくれる雇い主。
この辺は、シャーロック・ホームズにもあったね。ただ百科事典を書き写すだけの仕事に雇われた男の話(……なんだっけなぁ、この作品。ごめん、今タイトルを思い出せない)。
それともちょっと違うのだけれど、まぁ、結果的には抜き差しならない状態に陥ってしまうのです。
どうしよう……と思っているところに、警官が踏み込んで来ます。万事休す!……かな?
「アブルビー氏の乱れ無き世界」も不思議な、いや皮肉な味わいのある作品です。
骨董屋を営むアブルビー氏は、とにかく店を維持したい一心で財産持ちの妻を殺害します。
事故に見せかけたわけですが、これがうまく行っちゃうんですね。遺産がっぽりです。
当座の金を手に入れるわけですが商才のないアブルビー氏はたちまち店の経営を危うくします。
じゃあ、また同じ手をということで、財産のある女生と結婚し、また同じ手口で殺害してしまいます。
こんなことを繰り返していたわけですが、そりゃいつか気づかれますって。
同じようにして結婚した女性に見抜かれてしまいます(金目当てに結婚しているので、「女性」としてみたら、彼にとってはもう我慢ならないような女性なんですけれどね)。
しかも、その女性は自分に何か危害が加えられた時のために弁護士を雇っていて、防御をしていたのでした。
もう、手を下せなくなったアブルビー氏なのですが……あぁ、何という結末。
「パーティーの夜」は不思議な味わいの作品。
とある舞台で大当たりを取った俳優が主人公です。
自宅でパーティーを開いていたのですが、ひょんなことから倒れてしまい意識を失います。
部屋に運び込まれたところから話が始まります。
意識を回復した主人公は、もう、こんな舞台を続けるのは嫌だ、妻を捨てて愛人と共に逃げていきたいと願います。
パーティー会場でマネージャーを見つけ、別室に呼び込み、この舞台から降りると宣言します。
そんなことは契約上許されないと食い下がるマネージャー。
そこに登場する愛人。船のチケットを取ってあるので、私を選ぶのならすぐに車に乗ってと迫ります。
それに気づく妻。
ピストルを構えて、「行かないで」と迫ります。
まるで愁嘆場。
ついに火を噴く妻のピストル。
で、この後は?
「決断の時」は、何ともやりきれなくなる最後の決断を迫ります。
詳細ははしょりますが、自分が仕掛けた賭け、それも地所を失うか、自分が最も願っていた地所を得るかという、まぁ一か八かの賭けに出た主人公と、その賭けを受けざるを得なくなった脱出ネタを得意とするマジシャンのお話。
マジシャンは、パーティーの余興で主人公を心理トリックにかけてぎゃふんと言わせたばかり。
その敗北を認めない主人公が、この無謀な賭けに出たのですね。
でも、それは下手をするとマジシャンの命を失いかねないような設定です。マジシャンはそんな無謀な挑戦は断りますが、それを断れない状況に持っていく主人公。
とうとう引き受けざるを得なくなったマジシャンは、危険な状態に身を置きます。
脱出制限時間残り5分というところで、マジシャンからギブアップの宣言が出されます。
このまま放置したらマジシャンの命が危ない状況です。
立会人達はもちろん、すぐに賭けを中止してマジシャンを救出しろと迫ります。
ですが、人生を賭けてしまった主人公は、これもマジシャンの心理トリックではないかという疑いをぬぐいきれず、「賭けは賭けだ!」と救助を拒みます。ええ、確かに、主人公が設定した条件から言えば、このマジシャンのSOSを真に受けて脱出を可能にしてしまい、その結果マジシャンが脱出できたならマジシャンの勝ちになる状況ではありました。
これはまたあいつの心理トリックだって、主人公は思います。
「そんな状況じゃないだろう!」とみんなが助けに入ろうとしますが……
さて、主人公は、どちらの道を選ぶのでしょうか?
どの作品も非常にアイロニカルな色合いが出ていますし、うまくお話を運ぶなぁという印象でした。
たとえば、ちょっと電車に長く乗るけれど、何か面白い読み物がないかな……なんていうときだったら、絶対の自信を込めてお勧めできるような作品かもしれません。
「特別料理」/スタンリィ・エリン
田中 融二 訳 早川書房
ISBN4-15-208741-2
047 「虚無への供物」/中井英夫
本書は、日本推理小説の「三大奇書」の一つに数えられている作品です。
他の二つは何かというと、「黒死館殺人事件」/小栗虫太郎と「ドグラ・マグラ」/夢野久作です。
「黒死館……」は青空文庫で、「ドグラ・マグラ」は高校生の頃文庫で読みましたが、「黒死館……」は、かなりゴシック調の、絢爛豪華とも言うべき荘重な推理小説でした。あんまり奇書という感じはしませんでしたね。
「ドグラ・マグラ」の方は間違いなく奇書でしょう。
推理小説というよりは、怪奇小説とでも言うべきでしょうか。とある精神病院に隔離されている主人公の物語で、現実と妄想が入り交じり、また、その精神病院の院長の学術論文なども入り交じった無茶苦茶に混沌とした世界を描いた作品でした。
それと並び称されるのが本書なのですが、特段、奇書という感じは受けませんでした。
物語は、代々呪いを受けていると言われている氷沼家の子孫達にまつわる密室殺人事件を扱っています。
次々と起きる密室殺人事件を、素人探偵達があれこれ推理するという展開なのですが、それはそれとして別段奇書でも無いと感じました。
ただ、作者の意図の一つに、理不尽な、人災のために死んでいった人たちの無念を思えば、それは人災などで片づけられるよりも、意図を持った殺人者に殺されたと思う方が余程納得できるのではないかというテーマがあり、そこを敷衍していけば、こんな道楽のように人の死を題材に推理を楽しんでいる素人探偵達も同罪であるし、ましてやその成り行きを読んで楽しんでいる読者だって同罪であると断じているのかもしれません。
その意味で、「読者が犯人」というパターンだと主張されるところの作品ではあるのかもしれません(個人的にはこのこの論理展開には無理があってちょっと、と感じましたが)。
これじゃわかりにくいですね。
もうちょっと書くと、「殺人事件」なのか「事故死」なのかは、実は、よく分からない事なのじゃないかって言うことかもしれません。
作中でも、事故死として扱われている件がありますが、件の「素人探偵」達は、それは殺人事件だと見立ててあれこれ議論します。
最後には、まだ起きてもいない事件を仮想して、しかもそのお膳立てまでしてしまうという……(最後までその事件は起きないのですが)。
その辺を指して、あんたら同罪だろ!って言いたいのかもしれませんね(読者も含めて)。
つまりは、事件なのかどうか分からないことを事件だとして読んだとしたらという、そこが奇書なのかもしれません。
洞爺丸(青函連絡船)の沈没事故(これは刑法の教科書には必ず載っている有名な事故です。「期待可能性」という責任論に関する学説で必ず引かれる事故なんですよね。その意味でもよく知っている話ではありました)をきっかけにして構想された作品だそうで、作中でも氷沼家の悲劇の一つとして、この洞爺丸の事故で氷沼家の数人が犠牲になったと設定されています。
物語の設定は、昭和30年の辺りです。
ですから、あの時代特有のレトロな雰囲気が一杯ですし、それは以前書いた江戸川乱歩とも通ずるところがあります(乱歩ワールドよりはもうちょっと新しくて、まさに僕たちが生まれたちょっと前ころの雰囲気だと思います)。
しかも、非常にペダンティックで、この時代にこれだけの情報をちりばめた作品というのは、相当に「おしゃれ」だったのではないかとも感じます(今読むと、ちょっとそこが鼻につくところもありますが)。
さて、どうしてこの作品を取り上げたかというと、三大奇書の一つをご紹介しようという意図もあるにはあったのですが、何よりも「偶然の巡り合わせ」を感じたからなのでした。
この作品は、三宿、太子堂、三軒茶屋なんていう地名が出てくるし、昭和女子大の火災事件(実際に昭和30年にあったようです)にも触れられています。
とある「しもた屋」が出てくるのですが、作中の描写から言うと(現在の町並みは全然変わっていますが)あの交差点の先辺りだろうかとか推測できてしまったりもして。
しかも、この作品を読んで初めて知ったのですが、目白、目黒のほかに、目赤、目青、目黄があったそうなのですね(それぞれにお不動様をまつっていたのだそうです)。
この太子堂の近くにも目青不動があったとか……
何でこの時期にこの作品を読んだかなぁと、ちょっと因縁めいたものも感じました。
本書は、マニアックな興味があれば楽しめるかもしれませんが、純粋に一つの作品としてどうかと言えば、さほどお勧めするものではありません。しかも、長いです(文庫で約720ページ)。
ですから、気軽にちょっと読むというわけにもいきません。
ただ、そのような因縁めいた感じもありましたので、そんな気持ちからここに記させていただいた次第です。
「虚無への供物」/中井英夫
創元ライブラリ ISBN4-488-07011-6
046 「壁抜け男」/マルセル・エイメ
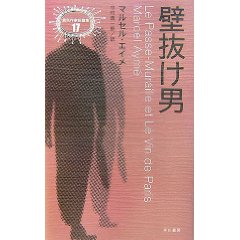 041で、スタージョンをご紹介しましたが、あれと同じ、早川の「異色作家短編集」シリーズからです。
041で、スタージョンをご紹介しましたが、あれと同じ、早川の「異色作家短編集」シリーズからです。
読後感は、やさしかったって思いました。
以下、ねたばれにならないようにご紹介です。
表題作の「壁抜け男」は、とある、冴えない男性が、とある時、壁を抜けてしまったのですね。
ええ、文字通り、固い壁をするっと抜けてしまったのです。
それは、意表を突く体験で、しかも、そんな能力なんてあんまり欲しいとも思わなかったわけです(その気持ちも分かります)。
で、病院に行ったら、とある薬を処方してくれたりしました。
で、そんな能力、犯罪をするならともかく、普通に暮らしている分にはあんまり使い道もなくて、自分の家に入るときも普通に鍵を開けて入っていたりしたわけです。
ところが、とんでもな上司が着任しちゃったのですね。
ここでちょっとキレた!
で、隣にある上司の部屋の壁から顔だけ出して悪口雑言ばりばりです。
最初は上司は怒って彼の部屋に行きますけれど、もちろん、彼は普通の姿で仕事をしてるわけね。
とうとう上司は気がふれてしまって……
ここから火がついたのかしらん。彼は色んな事をし始めます。
最後は、とある幽閉の女性と恋に落ち、壁を抜けて忍んで行くわけですね。
ところが!
というオチです。
舞台になっているモンマルトルの石壁には、エイメのこの作品を記念した物があるそうですよ(どんな物かを書いてしまうとネタばれになるのでご勘弁を)。
「カード」という次の短編も不思議な味わい。
年寄りや、社会に貢献できていない人は、生きている日数を制限すべきだと、議会で決まっちゃうのね。
で、そういう人だって決められた人たちはチケットを支給されるのでした。
たとえば、ある人は15日分のチケットしかもらえなかったとすると、その人は1ヶ月は15日しか生きていられないのでした。
もちろん、次の月になれば復活するのですけれどね。
生活が厳しい貧しい人たちは、人生を制限しようとしたりもします。
だって、1/3だけしか生きなくて良いのなら、それだけお金はかからないから。
病人も、苦しい病から逃げたいから、人生を削ろうとします。
一方で、お金持ちで、この人生が楽しいと感じる人たちは、そういう人生を売りたい人たちからチケットを買うようになります。
そうすると、ある人の3月は35日あったり、50日あったりしてきたりします。
これってどうなるのかな?
「よい絵」
これも良い作品でした。
とある売れない画家が描いた絵がありました。
描いている画家は、ほとんど食事を忘れて一生懸命描いているのですが、痩せるどころか太ってきてるんですねぇ。
何で?
彼の絵を買いたたいている悪い画商がいるのですが、彼も、その画家の絵を見た後では、せっかくのディナーも食べたくなくなっちゃったりします。
とある時、何日も食べられずにいて、死にそうになっているホームレスが、悪い画商のウィンドウ越しにその画家の絵を見ます。
そうしたところ……しばらく見ている間に、何とも幸福でお腹が一杯になったじゃないですか!
彼の描く絵は、「栄養絵画」だったんですね。
さて、この後どうなってしまうのでしょうか、というとても面白い作品でした。
「サビーヌ達」
サビーヌという女性がいました。
彼女は、生まれながらに特殊な能力を身につけていたのでした。
それは、自分を沢山の数に分けることができて、それぞれが自由に振る舞えるという能力でした。
分身の術だね。
彼女は、最初はその能力を嫌っていて、結婚した後もその能力はご主人がいない時だけに使っていました。
たとえば、家事をするときに沢山に分裂して一気に終わらせてしまうとか、長い雨の日、外にも行けず話し相手もない時に、沢山に分かれてお話しするとか。
ある時、貧しい画家と知り合いになります。それで恋に落ちてしまうのですね。
サビーヌは、自分の分身を一人作って、その画家と愛し合うようになりました。
だけど、こいつ、とんでもない奴で、彼女を食い物にして堕落していたわけですね。
彼女は傷ついて病んでしまいます。そうなると、本体の方だって憂えてしまうわけですね。
それを心配したご主人は、社交界で気晴らしをするように勧めます。
そこで、またまたサビーヌは恋に落ちてしまうのですね。
で、もう一人作って大富豪と結婚して。
以下繰り返し。
世界中にとんでもない数のサビーヌが存在してしまうのです。
神様は、そんなことはお許しになりません!
それでどうなるか、というと、おっと、これはネタばれになるのでここまでです。
そのほか、「パリ横断」(映画化もされましたね。肉を持ってパリの町中を歩く2人組。)、「パリのぶどう酒」、「七里の靴」が収められていますが、 特に「七里の靴」のラストなんてやさしくて涙でちゃいました。
皮肉な結果をも、なんとなくやさしくしてしまう作家さんのような感じがしました。
よろしかったら、どぞ。
「壁抜け男」/マルセル・エイメ
中村真一 訳 早川書房
ISBN978-4-15-208786-7
045 「晩夏」/アーダベルト・シュティフター
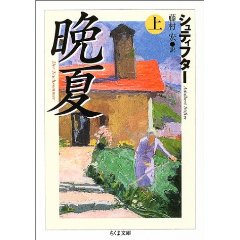

「この小説を最後まで読み通した人には、ポーランドの王冠を進呈しよう」。
それほど退屈で読み通すに値しない作品であると痛烈に批判したのはシュティフターと同時代の劇作家のフリードリヒ・ヘッベルだそうです。
他方、ニーチェは、この作品を、繰り返して読むに値する僅かな作品の一つとして、「ドイツ文学の宝」と推奨したそうです。
このように評価が激しく分かれているのが、011でご紹介した「水晶」の作者でもあるアーダベルト・シュティフターの「晩夏」という作品なのでした。
「あとがき」によれば、どうも一般的には“ヘッベル派”の方が多数を占めているらしく、有名な割には「読まれない」作品であるようです。
本書は、上巻508ページ、下巻456ページという大変長い作品なのですが、その長い物語の中で語られているストーリーはと言えば、「ただ1つの文」で要約できると言われるほど、ストーリー的には何にも起こらない作品なのでした。“ヘッベル派”から「退屈で面白くない」と酷評される所以でしょう。
また、「晩夏」に登場する人物はみな、経済的に豊かで、社会的には成功した人生を歩み、また、自己の願うところの人生を、外形的には大した苦労をすることもなく続けていける恵まれた環境にあり、それが読む人によっては「結構なご身分で」ということになるのかもしれないとも指摘されています(確かに、それはありますけれど)。
でも、私は“ニーチェ派”だったようで、大変感動して読みましたので、ここにご紹介させていただくことにしました。
都会(ウィーンです)の裕福な商家の長男として成長した主人公は、学業を修めた後、自己の進むべき道を決めるため地方に旅に出ます。その過程で地学、鉱物学、気象学等の自然科学に興味を抱き、毎年、研究のために様々な地方を旅するようになります。
ある時、アスペルホーフという地方を旅している際に雲行きが急に怪しくなり、雷雨に見舞われそうになります。
主人公は、近くにあった家を訪ね、ひとときの雨宿りを請います。しかし、その家の初老の主人は「雷雨は来ませんよ。」と静かに言います。「しかし、あなたがそうお考えになるのであればどうかこの家でお休みになりながらお確かめ下さい。」と言い、主人公を家に招き入れてくれます。
果たして雷雨は来ませんでした。雲行きは確かに怪しく、どう見ても雷雨になるのは間違いないと考えていた主人公は驚いてしまい、何故分かったのですかとその家の主人に問いかけます。
このことがきっかけとなり、主人公はこの家に毎年赴き、何泊かしながら、家の主人の人柄や知識に触れ、人間的に成長していきます。
この家には大変見事な薔薇が育てられていたことから、主人公はこの家を「薔薇の家」と呼ぶようになります。
「薔薇の家」の主人は、そんな主人公を好ましく思い、毎年家族のように歓迎してくれていました。しかし、「薔薇の家」の主人は自分の名を名乗ることをしませんでした。主人公も、それを尋ねることはなく、ただ、尊敬する人物として慕っていました。
主人公は、「薔薇の家」の主人の感化により、自然科学だけではなく、文学、美術、建築学、音楽等の芸術分野にも開眼していき、そのすばらしさに驚嘆します。
「薔薇の家」では、グスタフという少年が主人の庇護のもとに養育されていました(主人の子供ではありません。養子に出されているのです。)。
主人公は、グスタフとも親しくなり、グスタフも大変主人公になつきます。
さて、「薔薇の家」には、毎年薔薇が盛りになる頃、近隣のシュテルネンホーフという地所からマティルデという、やはり初老の域に近づいた女性が、その娘のナターリエを連れて訪ねて来るのでした。ええ、マティルデは「薔薇の家」で養育されているグスタフの実母なのでした。
マティルデの家庭も大変裕福であり、経済的な理由からグスタフを「薔薇の家」の主人の養子にしているわけではありません。
それでは何故マティルデは、まだ少年のグスタフを手元から放し、「薔薇の家」の主人にゆだねているのでしょうか?
「薔薇の家」を去るマティルデに対し、主人が、「ここにいたとき思うにまかせぬことがあったとしても、それを私たちの負い目のせいにしないように」と語りかけ、それに対してマティルデが、「これが私の一番大きな負い目です。どうしても償えない負い目なのですわ。」と答える場面があります。
「薔薇の家」の主人とマティルデとの間に何らかの関係があったことが示唆されますが、それ以上のことはしばらくは語られません。
「薔薇の家」の主人も、年に1度程度、マティルデの地所であるシュテルネンホーフを訪ねており、二人は互いに穏やかな行き来を重ねていることのみが示されるだけでした。
「薔薇の家」の主人とマティルデの関係は、物語の最後の方でようやく語られるのですが、それが本作のタイトルである「晩夏」の一つの意味になっているのでした。
「晩夏」というのは、日本語としては「夏の終わり」という意味になりますが、原語のドイツ語では、「夏の終わり」という意味の他に「遅れてきた夏」という意味もあるそうです。つまり、既に夏は終わってしまったけれど、その後の秋に、あの夏のような天気がわずかな日々訪れるときという意味を持っているのだそうです(訳者によれば、日本語で近い意味を探せば「小春日和」ということにでもなるのだろうし、あるいはシュティフターがタイトルに込めたかった意味もこちらの意味なのであろうけれど……と書いています)。
本作の最後には、とあるエピソードが語られます。今の感覚からすれば、大変大仰な、何とも時代がかったやり方にも見えますが、その誠実さにも感じ入るものがありました。
大きなストーリー展開のためとか、感動的なエピソードのためということではまったくないのですけれど、終章のページをめくるたびに静かな涙が次々と流れてきてしまいました。
人と人との関係というのは、終生不変ということは決してないのだと思います。
そのことは、本作でも、「薔薇の家」の主人の過去に関して、とある人物の口から語られています。
人と人との関係は、それぞれの人が置かれた環境、過ごしてきた年月、それぞれの年齢によって、変わってくるのでしょう。
本書は、大変長い作品です。
しかも、多くの人は「退屈」と考えるような作品です。
しかし、今の年齢を迎えている私たちには、これまで生きてきたことを振り返る意味でも、これから先のことを考える意味でも、とても素晴らしい作品なのではないかと思っています。
是非、お読み頂けることを願っています。
最後に、作者シュティフターが、本作品を伯爵夫人に献呈した際に添えられていた言葉をご紹介して終えることにします。
この本は、アーダベルト・シュティフターの詳細な小説「晩夏」です。世界でもっとも急ぐことがなく、もっとも均斉がとれた、もっとも平静な書物の一つです。そして、まさに、それ故に、非常に多くの人生の純粋と穏和が働きかける書物です。あなたがまだ“時間をお持ち”にならなければならない間は、幾時間か、この小説に耳をお傾けになるのがよろしいと思います。と申しますのは、この書物も時間を持っており、あたかもこの世には急き立てたり、慌ただしい思いをさせたり、脅かしたりするものがないかのように、言わば、永遠の生の節度を持っているからなのです……(この小説は、物静かな穏やかな人によって、ゆっくりと朗読されなければなりません)。
「晩夏」/アーダベルト・シュティフター
藤村宏 訳 ちくま文庫
ISBN4-480-03944-9(上)
ISBN4-480-03945-7(下)
044 「百億の昼と千億の夜」/光瀬龍
いつかは書こうと思っていた作品なのですが、どうにも書けずにいました。
この気が遠くなるほどのスケールをどう書けばいいか……
序章では、打ち寄せる波の音から始まります。そして、この世界が生み出されるまでの描写です。
星が生まれ、そこで生命が発生し、生命は海から陸へ上がり……
そして、一人の、何というか、人間の原型のような者が海中に生まれ、彼は長い眠りにつきます。
場面は変わって、古代アトランティスが描かれます。
プラトンが登場し、そして彼は物語の進行と共にオリオナエという司政官へと変容していきます。
そして、アトランティスの最期。火山が噴火し、アトランティスは海底に没します。
次の場面はインドです。漆達太太子(釈迦ですね)が登場します。
漆達太は、世の乱れ、人民の不幸を嘆きます。そして、兜率天(とそつてん)へと上っていきます。
兜率天の首都はTOVATSUE(トバツ)市という未来的な都市でした。
漆達太は、そこで世界の「熱的死」を目の当たりにし、梵天王と出会います。
梵天王が語るところによれば、兜率天は摩仁(まに)宝殿に位置し、この摩仁宝殿こそ天上界全体のあげて守らなければならない最後の砦であり、破局を回避するためには失うことができないところであるのに、阿修羅王の軍勢が侵攻してきており、それが世界の「熱的死」の元凶であるとのことでした。
漆達太は、阿修羅王に会い、何故世界を破滅へと向かわせようとするのかを問いただします。
阿修羅王は言います。「私とて、この世界の従属物だ。この世界の荒廃はこの世界の内部自体に起因するものではない。破滅や発展は単なる変化の部分的性質だ。梵天王は、この世界の荒廃は私が原因だなどと言うのだろうが、梵天王は今こそ転輪王の企図をこそ知るべきである。」と。
転輪王とは、王の中の王であり、この世界の外にある者。転輪王の姿を見た者はいないが、いつか偉大なる絶対神として、そして造物主としてこの世界に現れると信じられているのでした。
漆達太は、阿修羅王に問います。「そのとき現れ出でて人間を救うのが弥勒ではないのでしょうか。弥勒は56億7000万年後にこの世界に現れて救済すると説かれています。」と。
阿修羅王は、何故それが信じられるというのかと逆に問いかけます。何故この世界の救済のために56億7000万年もの絶望的な月日を待たねばならないというのかと……
さらに場面は変わり、エルサレム。
ナザレのイエスが登場しますが、そこで描かれるイエスは、品が無く、田舎言葉でまくしたてる狂人のようなイエスでした。
ナザレのイエスは、はりつけにかけられることになりますが、そこにイスカリオテのユダが現れます。イエスの信徒としてではなく。
このユダこそ、冒頭の序章で永い眠りについた彼だったのです。
イエスはゴルゴダの丘で十字架にかけられ、槍で突かれますが、死ぬことはなく昇天していきます。
そして、交わる世界。
アトランティスのオリオナエが、TOVATSUEの漆達太と阿修羅王が、そしてユダが…。
漆達太は、未来都市の中を疾駆します。そこは「シ」が統べる都市でした。
「シ」とは?
漆達太を消滅させるために追ってくるナザレのイエス。
救いに入るあしゅらおう。そしておりおなえ(ここでは二人は平仮名表記になっています。いや、漆達太もシッタータと表記されているのですけれど)。そして、彼らはそこで目にするのです。「市民」達の姿を……
うわー。やっぱり書けません。
とにかく壮大過ぎて、何ともまとめようがありません。
ざっとした粗筋を書きましたが、さっぱり分からないかもしれませんね。
そして非常に難解なイメージをもたれたかもしれません。
確かに、難解は難解ですが、でも面白いのも間違いありません。
本当に、気が遠くなるような感覚を何度も味わうことができます。
漫画家の萩尾望都さんが、原作に非常に忠実に同名で漫画化してくれています。
こちらも難解と言えば難解ですが、イメージはつかみやすいのでそちらから入ってみるのも良いかもしれません。
個人的には非常に評価の高い、傑作だと思っている作品でした。
「百億の昼と千億の夜」/光瀬龍
ハヤカワ文庫 ISBN4-15-030006-2
043 「万物の尺度を求めて−メートル法を定めた子午線大計測−」/ケン・オールダー
 1メートルってどういう基準で決められているかご存じですか?
1メートルってどういう基準で決められているかご存じですか?
そう、北極から赤道までの距離の1000分の1が1メートルです(今は別のもっと厳格な基準とされていますが)。
メートル法が定められる以前の世界では、地域によって長さの単位がまちまちでした。
とある村で使われている布を測る単位と、隣村での単位は違っていたのです。
また、測る対象によっても単位が違っていました。
こんな状態では広域の取引に支障を来しますし、何事にも不便で仕方がありませんでした。
そこで、恣意的ではない、誰から見ても公平な基準を作ろうということになり、地球の大きさを元にした単位としてメートルが考えられたのでした。
そのためには、地球の大きさを正確に測量しなければなりません。
というわけで、1792年、フランスでドゥランブルとメシェンという2人の優れた学者が、北のダンケルクから南のバルセロナまでの距離を三角測量することになり、ドゥランブルは北から、メシェンは南から測量を開始したのでした。
しかし、時代が悪いです。ちょうどフランス革命が勃発した時期に当たります。当初は王の命を帯びて始まったこの一大プロジェクトですが、フランス革命の結果、その王自身が廃されてしまいました。世情も不安定です。
一般市民には馴染みのない測量機器を携えてなにやら怪しげなことをしているとすぐに逮捕されてしまったりしました。
また、三角測量の測量地点として考えていた教会の塔なども革命のあおりをくって取り壊されてしまったりもします。
加えて、フランスでの革命勃発は周辺国家の危機感をあおります(自国でも革命が起きるのではないかという恐怖です)。
そのため、革命後のフランスと周辺国家との仲は険悪な状態になり、メシェンが赴いたスペインとは戦争状態になったりもします。
こんな過酷な状況の中で、当時としては最新の測量機器を携え、極めて精度の高い測量を進めていく2人の学者。
様々な困難や苦悩があります。
特にメシェンはとある出来事から深く思い悩み、与えられたミッションの遂行も覚束なくなります。
それは、当時の学問として「誤差」についての考え方が確立されていなかったという事情もあります。
どんなに精度の高い測量をしたところで、どこまでいっても誤差はつきまとうのです。
しかし、ついには測量を成し遂げる2人の学者。
ですが、メシェンはいつまでたっても自分の測量データを公表しようとはしません。それは一体何故?
最終的にはそのデータはドゥランブルの手に渡り、ドゥランブルによって検証され、「メートル法の起源」という大著にまとめ上げられます。
しかしながら、メシェンの生データは封印されました。それは何故?
本書は、メートル法が定められ、世界に普及していくまでの課程を膨大な資料に基づいて辿った一大科学史です。
読み物としても面白くできており、まるで小説を読んでいるかのようです。
しっかし、よくもまぁこんなとんでもない情勢下で測量が完遂されたものです。
革命気運はこのミッションの妨げになったこともありましたが、一面では、力強い後押しになった面もあるようです。
それは、王侯貴族を廃し、市民達が平等に権利を享受するという思想が、それまでの恣意的な単位を廃し、地球という普遍的なものを基準とした絶対的な単位であるメートルを採用するという考え方に適合したとも言えるのでしょう。
そのような考え方はメートルだけにとどまらず、暦も改変されましたし、なんと、時間も10進法が採用されていた時期がフランスではあったそうです。つまり、1日は20時間で、1時間は100分とされた時期が実際にあったのだとか。
このような苦労の末にできあがったメートル法ですが、その普及の段階にはまた様々な障害がありました。現に、アメリカでは今でもヤード、ポンド法が使われていてメートル法の完全普及には至っていないくらいですから。
それだけ単位を変えるというのは大変なことなのでしょう(我が国でも、尺貫法からよく切り替わってくれたものだと思います)。
身近なメートルについて、その苦難の歴史を辿ってみませんか?
「万物の尺度を求めて−メートル法を定めた子午線大計測−」/ケン・オールダー
吉田三知世 訳 早川書房
ISBN4-15-208664-5
042 「シャルビューク夫人の肖像」/ジェフリー・フォード
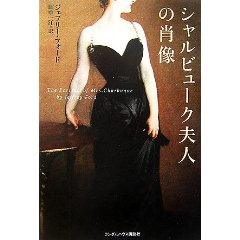 主人公は才能のある画家です。彼は金のために上流階級の人たちの肖像画を描いています。自分の描きたい絵では必ずしもないのですが、良いお金になります。
主人公は才能のある画家です。彼は金のために上流階級の人たちの肖像画を描いています。自分の描きたい絵では必ずしもないのですが、良いお金になります。
今夜もとある上流階級の夫人の肖像画のお披露目パーティーに作者として招待されました。
その夫は浮気をしていたのですが、それが妻にばれたために、ご機嫌取りのために妻の肖像画を注文したのでした。
モデルになった奥様は、決して美しい女性ではなかったのですが、その欠点を隠し、それなりに美しく描いた肖像画……
そのパーティーの帰り道、一人の盲目の男から声をかけられます。
是非、自分の主人であるシャルビューク夫人の肖像画を描いて欲しいとの依頼です。しかも報酬は法外な金額です。
ただし、一つだけ条件がありました。決してシャルビューク夫人を見てはならず、毎日1時間だけ会話をする中から夫人の姿を感じ取って描いて欲しいとの依頼でした。
姿も見ずに肖像画を描けだと! 主人公は最初はとんでもないと思い断ろうと考えます。しかし巨額の報酬は魅力です。それだけの報酬があれば、つまらない肖像画を描いて生活を維持しなくても、自分の描きたい絵が描けるのではないか……
そう考えた主人公は、すでに受けている肖像画の依頼をキャンセルしてシャルビューク夫人の肖像画を描くことに決めました。
シャルビューク夫人の家を訪れてみると、夫人はついたて越に自分についての話をするだけでした。
しかも、その話がどうにも不思議な話であり、にわかに信じられないような内容でもあります。
自分はからかわれているのだろうか……
困惑しながらも、友人の画家のシェンツに相談をもちかけました。シェンツは、「お前ならきっとやりとげられるさ。それだけの金があればお前の好きな絵を描けるじゃないか。」と言って励まします。
そして、裏街道に通じていたシェンツは、「ずるをすればいいのさ。」と言い出します。
つまり、それだけの金がある夫人ならどんな人かを調べるのはたやすいはずであり、夫人を知っている人を見つけて話を聞けば、夫人の容貌も分かろうというものだと言うのです。
シャルビューク夫人からは、そのようなことは一切禁じられていたので気乗りはしなかったのですが、かと言ってついたて越に話をしているだけで夫人の肖像画など描けそうにもなく、また、唯一の手がかりである夫人の話だって荒唐無稽であり、本気なのかどうかすら疑わしいと感じられたので、シェンツの勢いに負けるようにして調査することに同意してしまいました。
その後、シェンツの調査が進むにつれて、どうやら夫人の荒唐無稽な話も嘘ではないという裏付けが取れるようになってきました。
そして、海難事故で亡くなったと聞いていた夫人の夫、つまりシャルビューク氏を名乗る男が現れ、主人公を脅迫し始めます。「お前は俺の妻に何をするつもりだ。」と……
そして、もう一つの謎。街の女性が目から血を流して死んでいくという事件が起こります。
そもそもシャルビューク夫人は、なぜ姿を見せずに肖像画を描けなどと依頼するのでしょうか。しかも莫大な報酬まで約束して。
そして死んだはずのシャルビューク氏は何をたくらんでいるのでしょうか。
はたまた、目から血を流して死んでいく女性達は一体……
と言った、とても不思議な設定の作品です。
ラストのオチは、……かなぁと思いましたが、読みやすく面白い作品だったことは間違いありません(2夜で読み終えてしまった位ですから)。
ラストの方でシャルビューク夫人の家に踏み込んだ主人公が見た物にはちょっとびっくりさせられましたし。
そうですね……014でご紹介した「香水」に近いテイストを持った作品かもしれません。
興味をお持ちでしたら是非ご一読を。
「シャルビューク夫人の肖像」/ジェフリー・フォード
田中一江 訳 ランダムハウス講談社
ISBN4-270-00134-8
041 「一角獣・多角獣」/シオドア・スタージョン
 またまた、スタージョンです。
またまた、スタージョンです。
本書は、長らく絶版だった本なのですが、遂に早川書房の「異色作家短編集」で復刊しました(ぱちぱちぱち)。
大体、末尾の解説のタイトルが、「コレクター垂涎の書、ここに復活!」ですものね。
復刊以前は、相当に入手が困難な本だったようですが、こうして目出度く復活したわけですね。
そして、読んでみて納得。復活を待ち望む声がそれほど高かっただけあって、非常に面白い作品でした。
本作は、10編からなる短編集です。どれも良い味わいの作品ばかり。
いくつかご紹介しましょう。
本のタイトルの由来にもなっている「一角獣の泉」という冒頭の作品は、何ともほんのりしてしまう作品です。
一角獣はご存じですよね。ユニコーン。一本の角が頭に生えた白馬です。一角獣を捕獲できるのは処女だけであるという古来からの言い伝えがありますが、それをモチーフにした作品です。ちょっと寓話というか童話みたいなテイストもある作品。ネタバレになりますので詳しくは書けませんが。
「孤独の円盤」は、なんとも切なくなるお話です。ある日、とある女性の頭上に、突然まるで天使の輪のような光臨が現れます。周囲の人は大騒ぎ。拝み出す人もいる始末。もちろんその女性だって困惑してしまいます。そして騒ぎの中で倒れてしまいます。その光臨から言葉を受け取ってはいたのですけれどね。どうやらその光臨は空飛ぶ円盤ではないかということになり、その女性は国家機関に身柄を拘束され、一体どのような言葉を受け取ったのか尋問されますが、最後までそれを告げることを拒否します。
しかし、彼女はその言葉の重みに耐えかねて海で入水自殺を図ります。そこへ間一髪で助けに入った男性。その男性は彼女のことを探しに来たのです。それは…… あぁ、なんて切ないんでしょう。
「めぐりあい」は、ある時偶然に自分の理想にぴったりの女性を見かけてしまった男性のお話。彼はためらうことなく彼女に声をかけ、自分の電話番号を渡します。毎日電話を待っていたのですがなかなかかかってきません。しばらくして、ようやく彼女から電話があり、会うことになります。会ってゆっくり時を過ごしてみると、二人はお互いがまさに理想の異性であったことが分かり、愛し合うようになります。ところが……ちょっと不思議な現象がいくつか現れるようになり、そして、最後には彼女から別れを告げられます。どうして?お互いが理想の相手ではなかったの?いえ、理想なのです。ただ、「あなたは私から奪わなかったから」と彼女は言います。この作品は、スタージョンが他の作品でも使っている「シジジイ」ということをモチーフにした作品です。え?「シジジイ」って何かですか?それは読んでのお楽しみ。本作の最後にはちょっとした仕掛けもあります。
「死ね、名演奏家、死ね」は、ちょっと不思議な味わいの作品です。主人公はとあるジャズバンド専属のステージ司会者です。そのバンドのリーダーであるラッチはとても良い男で、成功が後を追ってくるようなタイプ。バンドも売れて何も言うことなしの状態なのですが、とある感情から主人公はラッチを殺害しなければならないという思いにとりつかれます。そして……というお話。ちょっと倒叙物(刑事コロンボのように読者には最初から犯人が分かっているタイプの作品)の推理小説みたいな味わいもありますが、オチはスタージョンらしいです。
以前、035で「人間以上」、「夢見る宝石」をご紹介したスタージョンですが、やっぱり好きですね。
本作は短編集ということもあり、「人間以上」や「夢見る宝石」ほど読みでがあるというわけではありませんが、きらきらと輝くセンスはまさしくスタージョンのものです。
全編に漂うやさしさというかやわらかさ切なさのような感覚が大好きなのでした。
「一角獣・多角獣」/シオドア・スタージョン
小笠原豊樹 訳 早川書房
ISBN4-15-208681-5
040 「千夜千冊 松岡正剛」/松岡正剛
遂に買ってしまった「千夜千冊」です。
もともとは、松岡正剛さんの同名のブログでです。
一回に一冊の本を取り上げて語るというスタイルで、延々と続き遂にタイトル通り千冊を超えてしまったのでした。
それをまとめたのがこの全集です。
このブログはまだ継続中で、今は、第二期「遊蕩編」となっています。この全集にまとめられたのは第一期分なのです。
私は、本が大好きで沢山読んでいたいと思うのですが、どんな本が面白いだろうって悩むことがあります。
だって、この世の中には膨大な本があるけれど、一生かかってもそれを全て読むことは決して叶わないのですから。
だから、かぎられた、私に許された、与えられた有限の時間の中でどの本を読むかって悩むことがあります。
「名作」と言われている本を読んでみる。
自分が読んで面白かった作者さんの本を続けて読んでみる、。その本の「あとがき」や「解説」で触れられている関連した作品を読んでみる。本屋さんに行ってそこで惹かれた本を読んでみる。
色々な書評を読んでみる。
そうやって、「次」の本を選んでいるのではないでしょうか?
私もそうです。
その中のweb書評の一つが「千夜千冊」だったわけです。
松岡さんは、非常に幅広いジャンルの本を取り上げています。
知らなければ、決して読まなかったであろう本も。
私も、随分刺激されて。それまでの読書傾向とはかなり違った本も読むようになり、また、それを楽しんでもいます。
そういう意味で、とても感謝しているのですね、千夜千冊には。
ブログは一通り読んでいたつもりですが、書籍化に当たって大幅に加筆修正したということでもありますし、手元に置いておきたいとも思ったので今回購入した次第です。
章立ては以下のような感じです(以下、本書の紹介文からの引用です)。
第一巻『遠くから届く声』は少年少女を追った巻。どんな大人も少年性・少女性を抱えている。この巻にはマーク・トウェイン『ハックルベリイ・フィンの冒険』のような少年の負のヒーローへのあこがれや、樋口一葉『たけくらべ』などに綴られた少女の一途さ、ノスタルジアの町に住む詩人や歌人、作家の幻想的な世界がつまっている。
第二巻『猫と量子が見ている』は自然・科学・宇宙・数学・物理の巻。科学は見ている目によって大きくも小さくもなり、そこに自分というものが組み込まれる。マイケル・ファラデー『ロウソクの科学』のような黒板に描かれた科学から、ロジェ・カイヨワ『斜線』のようなオブリック(ななめ)な複雑系まで、古今東西森羅万象の数式からミームの謎までを網羅した。
第三巻『脳と心の編集学校』は方法と編集の巻。ここでは方法=メソッドと編集=エディティングとそれにかかわった人や本や技術を紹介。M・マクルーハン『グーテンベルグの銀河系』からジョゼフ・キャンベル『千の顔をもつ英雄』まで、編集技法の醍醐味や物語構造の秘密を集約している。
第四巻『神の戦争・仏法の鬼』は古代から現代までの思想・文学・哲学をひもといた、千夜千冊全集の柱ともいえる巻。旧約聖書『ヨブ記』からモーセに潜む西洋の宗教や神話の母系から父系への入れ替わりと、立川武蔵『空の思想史』から空海を含む東洋の空と無の思想を並べ、ダンテ、ドストエフスキー、実存主義、ポストモダンとつづく。近代国家の矛盾とともに、想像力の未来と存在を問う視点が浮上した巻になっている。
第五巻『日本イデオロギーの森』は「日本」をとりあげた巻。一途で多様な国である日本。その日本がアジアの中からどのように出てきたのか。古代大和朝廷の成り立ちから紀貫之『土佐日記』の日本語革命、小林秀雄『本居宣長』や山本健吉『いのちとかたち』の「やまとごころ」、そして島崎藤村『夜明け前』が焙り出した明治日本の問題、さらに現代日本の「アンビヴァレント・モダーンズ」たちまでをパッサージュしている。
第六巻『茶碗とピアノと山水屏風』はアートの巻。古代中国からはじまって、日本・東洋・西洋のアートのながれを読み解く。芸術と趣向と芸能の動向、道具とアートの関係を追ってみた。世阿弥『風姿花伝』からフランク・ロイド・ライト『自伝』まで、古今東西のアーティストが登場する巻である。
第七巻『男と女の資本主義』は現代の男と女、資本主義とエロスとメディア社会の巻。この3つの領域を、フローベール『ボヴァリー夫人』からカール・ポランニー『経済の分明史』まで、縦横無尽にまたぎながら意識の変遷とその奥にある「聖と俗」を一挙に並べている。そして最後に柳田國男『海上の道』で日本の行方を問うている。
手元に置いて、今後も末長く、私の読書ガイドとなってくれる事を願っています。
ところで、私は、千冊の本を読むことができるのだろうか。
これまでに読んだ本は千冊には達していそうだけれど、これから先、次の千冊に手が届くのかな?
039 「大聖堂」/ケン・フォレット
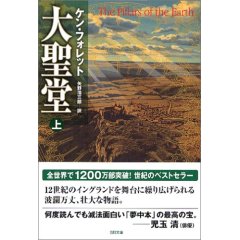
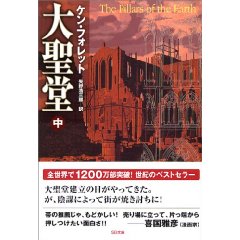
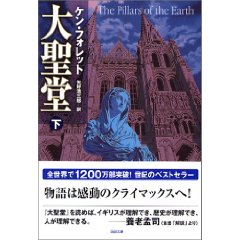
これは面白い! 絶対の自信を持ってお薦めできる作品です。
面白い本に巡り会うと、知らぬ間にどんどんページをめくっているじゃないですか。
まさにあの感じです。
本作は、分厚い文庫で上中下3冊という、相当なヴォリュームの作品なのですが、読み出すとあっという間に読破できてしまいます。
いや、むしろ途中で止めるのが困難なほど。
物語は、1123年から1174年までの出来事を描いています。全6部構成。
舞台はイングランドです。
1123年のプロローグは死刑執行の場面から始まります。
絞首刑を見物しようと、村の人々が集まってきます。
死刑に処せられようとしているのは、赤毛の若い男性。執行に立ち会う3人の男は、州長官、騎士、司祭でした。
執行の間際、赤毛の男性は美しく澄んだテノールでフランス語の歌を歌います。
何でもこの赤毛の男性は、修道院から宝石を散りばめた聖杯を盗んだ罪で死刑に処せられるのだとか。
そこに15才位の美しいのだけれど襤褸をまとった、そして不思議な金色の光を放つ目をした少女が現れます。
少女は呪いの言葉を叫びながら、にわとりの首を切り落とし、それを立ち会っている3人の男めがけて投げつけて逃げていきました。
それで死刑が取りやめになるわけもなく、赤毛の男性は死刑に処せられてしまいました。
さて、ここからが本編です。
最初は、トム・ビルダーという腕の良い石工の家族が主人公です。
トムは、自分の手で大聖堂を建築することが夢でした。
それにこだわらなければ、良い仕事に就ける機会もあり、その仕事をしていればちゃんとした家に定住し、家族みんなと安楽に暮らせたはずなのですが、トムは自分の夢のためにその仕事を断り、妻と、幼い息子と娘と共に町から町を渡り歩き、何某かの仕事にありつければその仕事をして金を稼ぎ、どこか大聖堂を建築している町は無いものかと探し歩きます。
生活は安定せず、思うように仕事にありつけないこともあります。
妻のアグネスは、あの仕事を受けてさえいればこんなにひどい思いをしなくても良かったのに、と内心思いながらも、トムと共に旅を続けています。
旅の途中で無法者(アウト・ロー)に襲われ、貴重な財産を奪われ、娘もひどく殴られて倒れてしまいます。
そんな時、プロローグで呪いをかけた女性と出会うのでした。
その女性はエリンという名で、まだ幼い男の子と森で暮らしていたのでした。
エリンの助けを得て、娘も回復し、また、食うや食わずの状態だったトム達家族に食事も与えてもらえました。
ところが、トム達には更なる不幸が待っていたのでした。
妻のアグネスが3人目の子供を身ごもっていることが分かります。
トムは大変嬉しいのですが、仕事にありつけず、冬を迎えようとしている状態では手放しでは喜べません。
どうやって家族を養っていけば良いのだろうか……
今だってろくにみんなに食べさせてやれない状態だというのに。
そして、アグネスは……
この後、物語は長い期間にわたって続きます。
ネタばれにならないように書くのは大変難しいのですが、やがてトムは自分の夢の大聖堂建築に着手することになります。
しかし、それはそんなに簡単に進むわけもなく、様々な事故や妨害、陰謀などが立ちふさがります。
トム一代で話は終わらず、次の世代にまで引き継がれていく物語です。
他方、フィリップという修道僧も重要な人物として登場します。彼は潔癖な修道僧で、堕落しきった修道院に嫌気が差しており、何とか自分の手で改善したいと願っています。
そんなフィリップに手を貸し、フィリップをキングズブリッジという大聖堂の院長にしてやろうと画策する司祭のウォールラン・バイゴッド。
その見返りは?
はたまた、地方豪族の粗暴な息子のウィリアム・ハムレイは、シャーリング伯爵の一人娘である美しいアリエナに求婚しますが、きっぱりと断られ、その執念深く体面ばかりを気にする性格から、深い恨みを抱き続けます。そして、そんな息子に悪知恵を授ける恐ろしい容姿の母親。
こんなところが主要な登場人物でしょうか。
それぞれの登場人物は、それぞれの思惑から色々な行動に出ます。
それが時として利害の一致を生み、ある時には深い反目の原因となったりもします。
次から次へと巻き起こる事件。息もつかせぬ展開。徐々に解き明かされる謎の数々。
知らず知らずのうちにページをめくってしまうのも無理はありません。
大変長いお話しですが、本当に面白いので、是非読んでみて下さい。
「大聖堂」/ケン・フォレット
矢野 浩三郎 訳 ソフト・バンク・クリエイティブ文庫
ISBN4-7973-3256-5(上)
ISBN4-7973-3257-3(中)
ISBN4-7973-3258-1(下)
038 「イラクサ」/アリス・マンロー
 著者は「短編小説の女王」と呼ばれる、カナダの70才になる女性です。
著者は「短編小説の女王」と呼ばれる、カナダの70才になる女性です。
アリス・マンローを読むのは初めてでしたが、「100年後にも読み継がれているであろう作家」との評価にもあるとおり、大変上手な方でした。
本作は、表題作を含め9編の短編集です。どれもしっかりとした作品で読み応え十分です。
しかも、ヴァンクーヴァーなどのカナダの風景も描かれていて、一時期住んでいた私としてはスタンレーパークやライオン・ゲート・ブリッッジ、ヴァンクーヴァー港などの描写がとても懐かしく思え、それだけでも「読んで良かった」って思ってしまいました。
……ただし、非常に「女性」を感じさせる作品ばかりです。
物語の視点が、多くは女性側から語られます。
ここでいう「女性」というのは、成熟した大人の女性という意味です。「女の子」ではありませんし、男性が時として極めて身勝手に想い抱いているステロタイプ的な女性でもありません。
生身の「女性」です。ティーンエイジャーも登場しますが、それだって、生身の「女性」として描かれています。
きれいごとなんかじゃなくてね。
実は、「イラクサ」も、ちょっとそういう感じを強烈に感じつつ読んでいたのですが、大変上手い作家さんなので、時に「辛いなぁ」と感じつつも無事に読了できました。
そして、読後数日した頃から、何とも言えない「発酵」が始まったのでした。
ワインやチーズが熟成していくかのように、自分の中で物語が豊かに甦り始めるのですね。
そこには、苦手な部分はあんまりなくて、作品の良かった部分が香り高く甦ってくるような感じがしています。
あぁ、これが「100年先でも……」と言われる所以かもしれないなぁと感じました。
作品をいくつかご紹介しましょう。
最初に収録されているのは「恋占い」という作品です。
ちっぽけな街に住むぱっとしない中年の女性の物語。
男性運もなく、年老いた一人暮らしの男性の家で家政婦をしているのですが、とある転機を迎えます。
もしかしたら、「彼」は私と結婚してくれる?
「彼」の手紙には、はっきりとそうは書いてはいないけれど、もしかしたら?
彼女は、彼の元に飛び込む決心をします。
普段なら行きもしないであろう街一番のおしゃれな洋品店に行き、ショーウィンドウで見た素敵な服を買おうとします。
準備万端整えて、雇い主のおじいさんには置き手紙をして(あと、数日分のシチューを作って)、「彼」の住む町に向かいます。
手紙によると「彼」はホテル経営を始めたとのことでしたが、着いた駅はさびれた砂埃が舞っている田舎町の駅。
彼女がこれまで住んでいた街の方がどれだけ大きいことか。
しかもどこにホテルがあるのよ!
重いスーツケースを引きずりながら、わずかに並ぶ商店街(というほどのものですらありません)に行き、店先で仕事をしていた自動車修理工の若い男に尋ねます。「ホテルはどこ?」
ホテルは、駅のそばにあった、倉庫のようなほとんど潰れかけているようなモーテルでした。
中に入ってみると不潔な食堂には食べ散らかしたような汚れた食器と食べ物の残骸が。
2階に上がってみると、しょぼい部屋に気管支炎を患った「彼」が汗をかいて横たわっていました。
なんじゃこりゃ!
読んでいて、「これ、映画みたいだなぁ」って感じていたのですが、同じように感じる方もいらっしゃったのですね。映画化決定ですって!
表題作の「イラクサ」は、幼なじみと再会するお話。
彼女が子供の頃、家で井戸を掘る事になり、井戸掘り職人が子供だった頃の彼女と同じ年頃の男の子を連れてやってきます。
井戸が堀上がるまでの期間、毎日のように仲間達と一緒に、その男の子とも遊びました。
戦争ごっこをしたり、川で遊んだり。
でも、井戸が堀上がると、彼は井戸掘り職人のお父さんに連れられて、また次の次の街へと行ってしまいました。
その後、時は流れて、彼女も結婚し、子供も生まれました。
そして、友人達の集まりに出かけたところ、彼も来ていたのですね。
再開したときの感情を細やかに描いた一作です。
年老いた夫婦を描いた作品、「なぐさめ」。
いえ、夫婦といっても、夫が自殺してしまったところから始まるのです。
きっと、遺書を残したはずだと信じ部屋中探し回る妻。
無神経な葬儀屋。
若かった頃の夫との回想……。
「クマが山を越えて来た」はとても切なかったです。
とても仲の良い夫婦がいたのですが、ある頃から妻の物忘れが極度にひどくなります。認知症?
日常生活自体に支障を来すようになり、妻は自ら施設に入れてくれと言います。
しばらくして、良くなったらすぐに帰ってくるからという約束の下で。
夫は献身的で、時間があれば必ず妻に会いに行くようにします。
ところが……妻はだんだん症状が悪化しているようで、夫のことすら分かっているのだか分からないのだか。
しかも、施設に収容されている他の男性と親しくなり……いや、親しいどころじゃなくて恋人のように仲むつまじく一緒に生活しているのでした。
頻繁に面会に来る夫はそんな二人にとってまるで邪魔者の様に扱われます。
その男性からはあからさまな敵意さえむき出しにされます。
その男性も同じ症状なのですが、介護していた妻が久しぶりに旅行に出かけると言うことで、一時預かりのような形で施設に来ていたのでした。
夫は、「あいつさえいなくなれば」と考えます。早く家族が迎えに来ればいいのにと願います。
そして、ようやく家族が彼を引き取りに来て、これで元通りになると思ったのですが……
妻は、その男性がいなくなってしまったことでうちひしがれてしまいます。
見た目にも分かるほどに衰弱し、病状も悪化してしまいます。
もちろん、夫を夫とも認識できないまま……(ただの知っている男性程度です)。
このままでは、重度病棟に移されかねない…
「あの男がいた方が妻のためには良いのだろうか……」
何とも切ないお話しでした。
というわけで、かなーりずしっと来たし、「女性」を強く読まされたという感じの作品でしたが、極めて上質であることは間違いありません。
「共感できる」という女性の読後感も多いようです。
素晴らしい作品であることは保障できますので、よろしかったらどぞ。
「イラクサ」/アリス・マンロー
小竹 由美子 訳 新潮社クレスト・ブック
ISBN4-10-590053-6
037 「10月はたそがれの国」ほか/レイ・ブラッドベリ
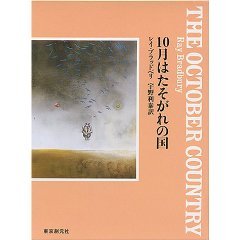 「SFの抒情詩人」と呼ばれることもあるブラッドベリです。
「SFの抒情詩人」と呼ばれることもあるブラッドベリです。
まずは「10月はたそがれの国」という短編集の中からご紹介しましょう。
「大鎌」
主人公の農夫は、実りの時期を迎えた麦畑に出て大鎌を振るい麦の刈り取りをしていました。毎日、毎日。しかし、不思議なことに刈り取った麦はしばらくするとみんな枯れてしまうのでした。いくら刈ったところで枯れてしまうのでは何にもならないのですが、彼にとっては何故か非常に重要な仕事に思えてならないのでした。無駄と承知で今日も麦の刈り取りに出かける主人公。その日の作業を終えた時、……分かったのです。「人を殺してしまった。しかも大勢。」そうなんです。彼が刈り取る麦1本1本が一人の人間だったのです。彼は麦を刈り取る度に刈り取った分だけの人の命を奪っていたのです。「もう、麦刈りには行きたくない。」彼は翌日から畑に出るのをやめました。しかし、どうしても麦を刈らなければならないという強迫観念に駆られて遂には畑に出てしまうのでした。そうやって憑かれる様に麦を刈っていた時、分かったのです。次に刈られるべき麦が自分の妻子の麦なのだと。彼は大鎌を止め、その日の麦刈りもよしてしまいました。翌日も麦を刈らなければならないという強い気持ちに駆られましたが、必死の思いで畑に出ずにいる主人公。
さて、その結末は……
「刺青の男」
次は、短編集「黒いカーニバル」から、「刺青の男」を。
とあるカーニバルの見せ物小屋の一つに「刺青の男」というのがありました。
全身くまなく刺青が入った男を見せ物にしている小屋でした。
ところが、この刺青男の背中に一か所だけ刺青が入っていない部分がありました。
何でも、その部分を覗くと覗いた者の未来が映し出されるのだとか。
その見せ物小屋にやってきた男が刺青男の背中を見てみました。
すると、そこに映ったものは、自分の首を絞めている刺青男の姿だったのです。
「こいつに殺される!」
「長雨」
最後は短編集「ウは宇宙船のウ」から「長雨」を。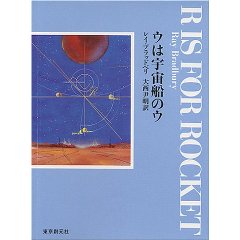
ここは金星。数名の宇宙飛行士が降り続く激しい雨の中を何日間も歩き続けている。
乗ってきた宇宙船にトラブルが発生し、二人の死亡した隊員を残したまま、生き延びた隊員達は徒歩で脱出したのであった。
目指すは太陽ドーム。
決して止むことのない激しい雨の中、冷え切った身体を引きずり何日間も行軍を続けているのであった。
ほとんど気も狂いそうになる日々を重ねてようやくたどり着いた太陽ドームは……何者かによって破壊されていた。しかもその残骸ですらこの雨を防ぐ物ではなかった。
失望し、落胆しつつも、生き延びるために次の太陽ドームを目指して歩き始める……。
ご紹介した作品からもお分かりの通り、SFと言っても非常に広い意味でのもので、むしろファンタジーに近いように思います。
ばりばりのSFを期待して読むとあるいは失望するかもしれません(ご紹介した「長雨」に出てくる金星なんておとぎ話のような話になっていますからね)。
今回ご紹介した作品には現れませんでしたが(カーニバルが近いですけれど)、ブラッドベリが多用するイメージに、ハロウィンがあります。
最新作も(未だご健在です)、ハロウィンを舞台にした「塵よりよみがえり」ですし。
それからもう一つはやはり少年の目、心を持った作家です。スタージョンもそうだって書きましたが、ブラッドベリの方がもっと柔らかくてやさしい感じです。
また、今回ご紹介したのは短編ばかりでしたが、長編にも有名な作品があります。
もっとも有名なのは「華氏451度」でしょうか。これは、本の存在が禁止された未来社会が舞台です。未来の焚書坑儒ですね。本という本は全て廃棄されてしまいます。それでも本を愛する人々がいて、彼らはどうしたかと言えば、一人が一冊の本を暗記することにしたのです。自分が一冊の本として生きていくことにしたのですね。タイトルの「華氏451度」というのは、本が自然発火する温度なのだそうです。
その他、「火星年代記」という長編も有名です。
スタージョンと並んで私の好きなSF系の作家でした。
036 「アルゴールの城にて」/ジュリアン・グラック
本書は極めて読みにくい作品です。台詞は一切無く、幾重にも重ねられた形容詞の茂みに分け入って読まなければならないような、しかも、その描写は非常に観念的なのです。
ただ、そこに描かれている情景をイメージすると、それは何とも壮麗で、素晴らしく美しいものなのでした。
主人公はアルベールという若い貴族の末裔です。頭脳明晰、眉目秀麗ではあるのですが、人をそばに寄せ付けないような冷たさがあります(「氷」となぞらえられる訳ですね)。彼は、ひょっとしたことからアルゴールという城を買い受けることになり、ある夏、その城で過ごすために彼が尊敬して止まないヘーゲル(!)の著作集を携えてアルゴールの城に赴きました。
アルゴールの城は深い森に囲まれた台地にひっそりと建つ古城なのですが、その描写が圧巻です。その全てをここに書くことはとてもできないのですが、テラスになった屋根とその左側に見える高い尖塔。右手にはそれよりも低い方形の塔。城の壁面にはいくつかの窓が穿たれているのだけれど、それが何とも不規則に並んでおり、城内の部屋の配置がいかに凝った物であるかを物語るようです。
城内の部屋々々の描写も圧巻です。家具らしい家具と言えば壁面や柱に沿って無造作に並べられた上質のクッションやソファーだけのだだっ広いホール、銅板とその上の鏡で壁を覆われた天井の低い食堂、もはや天井さえ見えないような(おそらく城の頂上まで吹き抜けになっているのでしょう)大広間には床のすぐ上から垂直に立ち上がっているアーチ型の窓から陽が差し込み、その光線の具合によってまるで海の中にいるかのように感じられることすらあります。
それぞれの部屋が意匠を凝らした作りになっている一つの理由は、「音」にありました。つまり、同じように話していても、部屋によっては明晰で快活な声に聞こえたり、囁くような声に聞こえたりするのでした。
そして、この城を巡る風景描写も素晴らしい。遠くまで連なる手つかずの森、その向こうに見える山々、目を転ずれば白い砂浜と入り江、そしてその上に広がる青緑の空。そのような情景の中を様々な天候が通り過ぎていきます。
さて、物語は、この城にアルベールの親友であるエルミニアンが訪ねてくることから始まります。エルミニアンもアルベールに負けず劣らずの頭脳を持っており、二人は極めて難解かつデリケートな議論を楽しみ合う仲でした。ただ、エルミニアンは、引きこもりがちなアルベールとは違い、極めて活発であり、幾枚かの絵画を見たくなれば精力的にヨーロッパ中の美術館を駆け巡るような青年でした(アルベールの「氷」に対して「火」と例えられる由縁です)。
アルベールは、城に着いた初日に、大広間の中央の銀の盆に置かれていた、ハイデと共に訪ねる旨のエルミニアンのメッセージを見て、その来訪を知るのでした。
しかし、アルベールはハイデなる人物を知りませんでした。それが男性なのか女性なのかすら。
エルミニアンに伴われて城にやってきたハイデとは、非常に美しい女性でした。しかも教養も深く、アルベールらの難解な会話を苦にもしませんでした。アルベールは、エルミニアンとハイデがどのような関係なのかを尋ねたかったのですが、どうにも切り出せずにいました。
その後、3人による城での生活が始まるのですが、エルミニオンは、とある意図を持ってハイデを城に伴ったのでした。ところが……
以上が本作の粗筋です。時としてストーリーを追うのがやや混乱する位読みにくい部分もありますし、そもそもこれといった大きなストーリー展開があるというわけでもありません(あると言えばありますが)。
私は、この城自体が一つの大きな「ストーリー」の様に感じました。非常に絵画的な、ところによっては音楽的なイメージを楽しむのが、今回の私の「アルゴールの城にて」だったように思います。
読書の楽しみは人それぞれです。どうか、みなさんも自分だけの「アルゴールの城にて」を楽しんでみて下さい。
「アルゴールの城にて」/ジュリアン・グラック
安藤 元雄 訳 白水Uブックス
ISBN4-560-07079-2
035 「人間以上」、「夢見る宝石」/シオドア・スタージョン
「シオドア・スタージョンは相当に難解な作家である。解説担当者がのっけから難解さを売り物にしては怠慢の謗りを受けるかも知れないが、熟考の末、ありきたりの解説者的視点では歯が立ちそうにない」……と、これは「夢見る宝石」巻末の解説のくだりです。
そうなんですよ。非常に書くのが難しい……
実際、「人間以上」に関しては、書いておかなければ絶対に後悔するという気持ちもあって、自分への覚え書きというつもりもあって、挑戦してみることにしました。
「人間以上」
「白痴は、黒と灰色の世界に住んでいた。飢えの白い電光と、恐怖のきらめきの中に。」……これが「人間以上」の書き出しです。当初は名前すら持たず、人々から「白痴」と見られていた少年が主人公の作品です。
彼は、何らの欲望すら持たず、何も期待せずに、ただ生きていました。飢えれば飢えたままにし、ただつっ立っていて、もし一片のパンでも与えられればそれを喰らい、あるいは、動物のように森に潜み、口にできる物ならば何でも喰らってただ生きていました。
一方、ひどく歪んでしまった気のふれた父親のもとに2人の娘が暮らしていました。父親は「女性」性を醜悪な罪業と信じ、娘達のいずれかにわずかでもそのような気配を認めると、激しく鞭打つのでした。
ある日、女性に目覚めた娘の一人エヴェリンは、泉に身体を浸し、身体の奥底から湧き上がる節の無い歌を歌い始めるのでした。
「呼ばれた?」…… それまで誰からも声をかけられたこともなく、人として扱われたこともなく、何の感情も持たなかった「白痴」は、吸い寄せられるように泉に近づいていき、二人はプールへと移動し、そこで寄り添い、喜びにふるえたのでした。
エヴァリンの姿を認めた姉のアリシアは、父親に助けを求めます。鞭を持って駆けつけた父親は、「白痴」を激しく鞭打ちます。逃げ出す「白痴」の身体に鞭が巻き付き、父親の手から鞭が滑り出ました。父親の顔に爪を立てるエヴァリンにより、父親は片目を失います。
逆上した父親は家に戻り銃を持ち出そうとしますが、アリシアは初めて父に逆らいそれを止めます。父親の目にはもうそれまでの虐待の対象であった娘達とは見えず、得体の知れない「恐怖」でしかありませんでした。父親は、銃口を自らの口に入れ、引き金を引きました。
……
その後、「白痴」は人の良い(息子を失った)農場の老夫婦に拾われ、そこで初めて人間として扱われ、少しずつ、概念を、言葉を、感情を得ていきます。名前を問われるうちに、彼の頭に”All alone”という言葉がよぎりますが、うまく発音できません。「ウル……ウル……ロ…ン」。
「え? 何だ? そうか、ローンか」。こうして「白痴」は「ローン」という名を得たのでした。
……
数年を経て、農場を出ることになったローンは、森の中の洞窟で暮らし始めますが、そこに吸い寄せられるように集まったテレポーテーション能力を持った黒人の双子の女の子とその庇護者であるジャニイという娘。みんな世の中から遺棄された者達でした。
共に暮らし始める彼らは、人類の新たな進化(?)形だったのです。それは、「集団有機体(ゲシュタルト・オーガニック)という形を取ったのでした。
彼らは、彼らとして進化していっただけであり、人類に仇なす意図があったわけではありませんが、再び人類と関わりを持たざるを得なくなります。そして…
というお話しです。何ともまとまりの悪いご紹介なのですが、そこで語られるSF的なストーリーもさることながら、随所に散りばめられた切なくなるような感情が得も言われぬ感動を導くように感じました。
結局ね、「弱いもの」を描きたかったんじゃないかな、とも思うのでした。だからスタージョンは優しい。
「夢見る宝石」
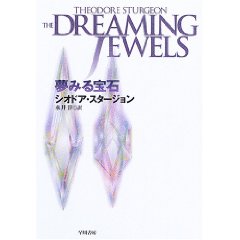 主人公のホーティーは捨て子の男の子でした。判事に立候補していたアーマンドとその妻は、身寄りのない孤児を引き取ることにより地域での名望が上がり、判事選が有利になるというただそれだけの理由でホーティーを引き取りました。しかしそこには愛情はなく、ホーティは虐げられて育てられたのでした。彼の唯一の友達は、孤児院を出る時にもらったジャンキーという小さな木の人形でした。その人形には不思議な光を放つ鉛ガラスのような目が埋め込まれていました。
主人公のホーティーは捨て子の男の子でした。判事に立候補していたアーマンドとその妻は、身寄りのない孤児を引き取ることにより地域での名望が上がり、判事選が有利になるというただそれだけの理由でホーティーを引き取りました。しかしそこには愛情はなく、ホーティは虐げられて育てられたのでした。彼の唯一の友達は、孤児院を出る時にもらったジャンキーという小さな木の人形でした。その人形には不思議な光を放つ鉛ガラスのような目が埋め込まれていました。
ホーティーが8才のとき、ちょっとした気持ちから蟻を口にしたことがありました。彼としてはどうという理由もなく、同級生らの目が無いところで何となくしてみたことでした。しかし、それを同級生に見とがめられてしまい、先生に告げ口され、こっぴどく叱られたばかりか、「蟻喰い」とからかわれ、「蛆虫も食うか?」などと虫を投げつけられ、いじめられます。ホーティーのこの一件は小さな町中の噂になり、それを知った養親のアーマンド夫妻は激怒します(体面が全てといういやらしい奴)。
一人で二階の部屋に閉じこもり、ジャンキーに話しかけているところをアーマンドに見つかり、激しく打擲されます。アーマンドはジャンキーを踏みつぶそうとしたため、ホーティーは必死になって止めに入ります。その拍子によろけたアーマンドは壁にしたたか身体を打ち付けたのでした。「お前はもう面倒見切れん!警察を呼んでやる!」と逆上したアーマンドは、ホーティーをつかみ上げると洋服ダンスに押し込み無理矢理扉を閉めました。そのため、ホーティーの3本の指が扉の蝶番に挟まれ、ぐちゃぐちゃに潰されてしまったのでした。
「これじゃあ、医者まで呼ばなければならんじゃないか!」アーマンドは階下に駆け下り「警察を呼べ」とわめき散らします。
ホーティーは家出を決意し、ぐちゃぐちゃに潰された三本の指をハンカチで縛り付け、ジャンキーだけを持って逃げ出します。
激痛をこらえつつも、唯一優しくしてくれた同級生の女の子のケイだけに別れを告げると道端に停まっていたトラックの荷台に潜り込みました。
そのトラックは、カーニバルを回る一座のトラックでした。彼らの出し物は「奇形」。いわゆる「フリーク・ショー」でした。
小人や皮膚異常を持った人などがその身体を見せ物にする一座。
そのトラックにも四人の「芸人」が乗っていましたが、彼らは咎めることもなく、ごく自然にホーティーを受け入れ、仲間に加えてくれました。
問題は、彼らの興業主。元は優秀な医師だったのですが、世間の誤解から職を失い人生を駄目にし、人間そのものを呪うようになった「人喰い」と呼ばれていた男です。彼が認めなければホーティーは一座から叩き出されてしまうのですが、そこは4人が機転を効かし、ホーティーを女装させ、4人の中の一人の小人ジーナの親類というふれ込みで一座に残ることが認められ、潰された3本の指の切除手術もしてもらえました。
その後、女装したまま一座の中で育てられていくホーティー。
ところが、その幸せはいつまでも続くものではありませんでした。
実は、「人喰い」はとあるきっかけから不思議な宝石にのめり込んでいたのです。その宝石とは夢を見る宝石でした。
スタージョンには、「切なさ」があります。
そして、少年だった頃のやわらかい気持ちが、あるように感じます。
冒頭で「難解だ」という解説をご紹介しましたが、別に文章が読みにくいとか、意味が難しいという意味の難解さは全くありません。普通の小説と何ら変わりはないのです。
その難解さというのは、テーマに関することではないかと思います。いえ、テーマだって分かり易いですよ。ただ、それだけじゃなくて、もっと奥深いものがあって、それを考えると……確かに「難解」かもしれません。
でも、普通に楽しめる良い作品ですので、是非ご一読を。
私の大好きな作家の一人です。
「人間以上」 ISBN4-15-010317-8
「夢みる宝石」 ISBN4-15-011548-6
いずれもハヤカワ文庫
034 「審判」/フランツ・カフカ
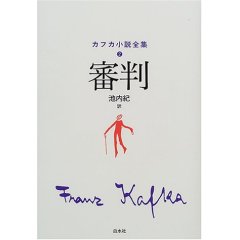 銀行員のヨーゼフ・Kは、ある朝突然逮捕される。
銀行員のヨーゼフ・Kは、ある朝突然逮捕される。
一人暮らしのアパートに黒服の男達が突然やってきて起き掛けのヨーゼフの身柄を監視下においたのであった。
何故逮捕されたのかその理由も告げられず、どのような手続きが行われているのかも説明されない。
その後しばらくして、「監督」なる上司らしき者がいるアパートの隣部屋に連行される。
さして意味のないやりとりがあり、ヨーゼフは銀行に行くことを許されるが、それは無罪放免になったわけではなく、どうやら刑事訴追されているらしく今後裁判が行われることになるようである。
なんと、その場には勤務先の銀行の部下が3人ほど待機していて、ヨーゼフが出勤するのに付き添うのであった。
しばらくしてヨーゼフに裁判所への出頭命令が出される。
これもひどく曖昧なもので、裁判所の所番地と出頭すべき日が告げられるだけで、時間などは何も指定されない。
ヨーゼフは、おそらく役所仕事のことだろうからと推察して役所が開く時間に合わせて出頭する。
しかし、指定された番地にあるのは古ぼけたアパルトマンであり、およそ裁判所とは見えない。
ヨーゼフはその建物の中に入り、狭い階段を上り、何だか訳の分からない場所をうろうろしながらどうやら裁判所らしき所にたどりつく。
何だか、建物の外見よりもその内部の方が広大な感じすら受ける。
そこで目にしたものは、数多くの人がひしめいているホールのような場所。
判事と思われる人が前に座っている。
手続きが始まったのか始まらないのかさえ分からない。
ここに集まっている多くの人達が何者で、そもそも何をやっているのかすら分からない。
そこでヨーゼフは(自分が何故訴追されているのかすら全く分からないけれど)この馬鹿げた状況について一席ぶってしまう。
ヨーゼフの演説に反応する群衆。それが何の意味があるのか全く分からないのだが、ヨーゼフはそれなりにしてやったりと考える。
が、しかし、それによって、ヨーゼフの裁判がどうなったのか、あるいは、それはそもそもヨーゼフの裁判だったのかさえ全く分からない。
その後、ヨーゼフは、気難しい叔父の手配により弁護士を雇うことになる。何故叔父がヨーゼフの訴訟沙汰を知っていたのかもよく分からない。
その弁護士は年老いていて病の床に伏せっていた。まるであてになりそうもないし何の説明もしてもらえない。
それどころか、その老弁護士の世話をしていた娘に誘惑される始末。
ヨーゼフは、あんな弁護士には任せておけない、自分で何とかしなければと考え、例の裁判所に行ってみたりする。
またもや迷宮のような裁判所。
そこで下働きをしている職員の妻と知り合いになる。助力を申し出る妻。
その妻を口説き落とそうとしている裁判官の見習い。
重く澱んだ空気の中に続く素っ気ない廊下のベンチに一日中座って自分の訴訟の行方を気遣う人達。
薄ほこりが充満しているような裁判所。
そして、すでにヨーゼフには出口が分からなくなっている。
吐き気をもよおし、「お願いです、出口まで連れて行って下さい」と懇願するヨーゼフ。
裁判は一向に進展しない。
一体何がどうなっているのやらさっぱり分からない。
取りあえず、裁判のことを考えなければ、身柄を拘束されているわけでもなく、これまで通り仕事にも行っている。
聞きかじった情報によると、裁判というものはおそろしく複雑な手続きが必要らしい。
今、自分の裁判はどのステージにあるのか?
少なくとも入り口にも入れずとどまっていることだけは確からしい……。
とある夜。
突然アパートに2人の吏員が現れる。
2人は両脇からヨーゼフを抱え外に連れ出す。
ヨーゼフも抵抗しない。むしろ、自ら進んで歩いていく。
そうして人気のない広場に着き……
と、まあこれが「審判」の粗筋です。
「不条理の作家」と言われるカフカらしい作品です。
何がどうなっているのか、全く合理的な説明はありません。
ただただ、その訳の分からない悪夢のような状態が続いていくだけ。
「変身」(朝眼が覚めると、自分が一匹の毒虫になっていたという、あれ。グレゴリー・ザムザの物語)を読んだ時にも感じたのですが、登場人物は冷静すぎる……というか、みんなピントがずれている。
本質的なことはお構いなしで、周辺の些細なことばかりが執拗に取り上げられている。
で、結局一番大切な問題については全くの無抵抗だったり。
この不思議な感覚がカフカの魅力なのかもしれませんねぇ。
実は、カフカは生前はほとんど評価されなかった作家でした。
死後、友人の作家だったブロートがカフカの生原稿を独占管理し、ブロートなりに編集・整理したものがカフカの作品として発表され評価されるに至ったのでした。
ところが、公にされたのはブロートが手を加えた作品だけであり、生原稿についてはブロートはその公表を頑なに拒んだのでした。
ですから、「これは本当にカフカが書いたそのままのものなのか」という疑念が渦巻いていたのでした。
その後、ブロートも世を去り、ようやくブロートが独占していたカフカの生原稿が世に出たのでした。
国元のドイツでは名だたる文学者、カフカの研究者がチームを組み、カフカが書いたままの作品の復活作業に当たりました。
そしてその大作業がようやく完結し、日本でもその新しい作品が翻訳されたのでした。
はい、そうなんです。
私たちが、中高生の頃、岩波文庫や新潮文庫などで読んだカフカは「ブロート版」のカフカです。
今回ご紹介したのは、生原稿から起こしたカフカの翻訳本です。
従来の版との違いは巻末に示されています(章立てなどが変わっています)。
で、読んでみてどこか違ったか?と聞かれるとかなり辛い。
「審判」は、高校生の頃読んだのですが、細かい記憶は残っていませんでした。
ですから、それとどう違ったかと聞かれるととても辛いです。
ただ、新版は読みやすかったと感じました。
この機会に、新しいカフカを読んでみませんか?
「審判」/フランツ・カフカ
カフカ小説全集2 池内紀 訳
白水社 ISBN4-560-04702-2
033 「おわりの雪」/ユベール・マンガレリ
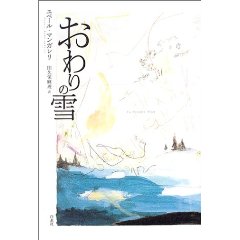 「トビを買いたいと思ったのは、雪がたくさんふった年のことだ。」
「トビを買いたいと思ったのは、雪がたくさんふった年のことだ。」
「ぼく」は、養老院に通い、一人では散歩ができなくなったお年寄り達から声をかけられると手を貸してあげて、一緒に散歩をすることで、お年寄り達からいくらかのお金をもらっていた。
そのお金は半分に分け、半分を家に入れていた。
父さんは病気で伏せっていて、「ぼく」の家は、父さんの年金と「ぼく」が養老院からもらってくるお金の半分とでやりくりしていた。
もしも、父さんが死んでしまっても年金というのはもらえるものなのだろうかと考えたこともあった。
ブレシア通りの道端に古道具屋のディ・ガッソが、ナイトテーブルやらラジオやらと並べてトビを置いた時から、「ぼく」はその鳥が欲しくてしかたなかったのだけれど、ディ・ガッソはとんでもなく高い値段をつけてしまった。
養老院でもらうお金の半分を貯めても到底届く値段じゃなかった。
それでも「ぼく」は、いつかお金を貯めてそのトビを買いたいと思い、養老院の仕事を終えると、いつもディ・ガッソの店に、トビに会いに行った。
ある夕方、ブレシア通りに行くと、ディ・ガッソの店の前に男の人が一人立っていた。
「ぼく」は直感した。この男の人がトビ捕りに違いないって。
緊張しながら、その男の人のあとをつけた。「どうやってトビを捕ったんですか」って聞きたかったから。
男の人は、アジアゴ通りの噴水の所で水を飲むと、また歩き出していった。
「ぼく」は、一言も話せないまま家に帰った。
家に帰って、父さんに「トビ捕りの人に会ったよ。」って話したら、その人と話したかと聞くので、「もちろんだよ。アジアゴ通りの噴水で一緒に水を飲んで、どうやってトビを捕まえたのかすっかり話してもらったからね。」って言ってしまった。
父さんは、「その話、父さんにも聞かせてくれ。」っていうので、トビ捕りの話をその場ででっち上げなければならなくなった。
「それ、ほんとうに聞いたまんまなのか?」
「ぼく」は言った。「うん、聞いたまんまだよ。」
「ぼく」は先を続けた。 途中で父さんがぽつりと言った。「その話、気に入ったよ。」
「トビ捕りの話、しようか。」、「うん、聞かせてくれ。」とベッドの中の父に請われるまま、何度も、何度も「トビ捕り」の話をした。
そうやって、「ぼく」が夜、父さんの相手をしていると、ばたんと戸が閉まる音が聞こえたことがあった。
父さんは「ぼく」が点けたランプの明かりがまぶしかったのだろうか、ぎゅうっと目を閉じた。
ぼくたちが住んでいる屋根裏の部屋から出た廊下の階段の自働消灯ランプがかちりとつく音がして、母さんが外出したのが分かった。
「ぼく」は父さんの顔を見なかった。
父さんが眠ったので、「ぼく」も固い木の長いすで眠ろうとしていたところに、母さんが帰ってきたことがあった。
「ぼく」は黙って眠ったふりをしていた。
「お前、起きているんだろう。」と母さんが言った。……泣いているのが分かった。
「ぼく」は声を出さずに泣いた。そうすることは、ずっと前に覚えていた。
とても静かな作品です。
ご紹介した部分は、要約したこともあって、かなり「強い」印象だったかも知れませんが、実際にはそんなことはありません。
少ない言葉数で、おだやかに流れていきます。
養老院の管理人さんのボルグマンさんという登場人物も出てきます(というか、登場人物はこれで終わりかな)。
とても良い人で、「ぼく」がお年寄り達から散歩の声がかかるまでの間、家に招いてくれて、コーヒーをごちそうしてくれたりします。
「ぼく」もお年寄り達から頂いたお金を貯めて、時々コーヒーを買ってボルグマンさんに持っていっていました。
「お金は、もっと大切につかわなければ。」、「いつまでもごちそうになってばかりはいられませんから。」
ボルグマンさんの妹が、生まれたばかりの数匹の仔猫を押しつけてきたこともあります。
「始末してくれ」って。
ボルグマンさんには、それはできなかったのですね。それで……そんな話も伏線になっています。
作者は、児童文学者として知られていたようです。
でも、この作品はそういうジャンルにこだわらない方がよいでしょう。むしろ、子供には読めないと思います(作者も子供向けには書いていないのです)。
短い作品です。
いつものように、寝床で眠れるようにと思って読み始めたのですが、眠くなる前のしばらくの時間で読了してしまいました。
切なくなりました。
「ぼく」の様な感情、気持ちは、幼い頃の私にも確かにあったのです。
…… 寝床で、声を出さずに泣いてしまいました。
「おわりの雪」/ユベール・マンガレリ
白水社 ISBN4-560-04798-7
032 「指環物語」/J.J.トルーキン
ここは、「中つ国」。ホビット庄なのだ。
ふとしたことから、「指環」を手にしてしまったホビットのフロド。
でも、それは恐ろしい魔力を秘めた指環なのでした。
サウロンっていう悪いマジシャンが呪いを込めて作った悪の指環。
死霊が馬に乗って指環を奪い返しにホビット庄にやってきます。
フロド、ぴーんち!
思わず指環をはめてしまいそうになるけれど、駄目だよ!
そんな悪の力を使ったらいけない!
こんな指環は壊してしまわなければいけません。
というわけで、火山に捨てて壊してしまおう(それしか指環を滅ぼす方法は無いのです)という長い旅が始まります。
もう、今更ご紹介するまでもない超有名な作品ですね。
私が、初めて読んだのは高校生の頃でした。
今回ご紹介している本のブックカバーとは全然違った文庫でしたけれど。
ファンタジーの世界では、「まずは読め!」というほどの基本中の基本。
ゲームやアニメなどに描かれるファンタジーの要素はここから始まったのでした。
ええ、もちろん伝承などでそれは語り継がれていたのですよ。
陽気で、人の良い、子人のホビット達。
鉱山で働く(いや、地面に埋まっているものを掘り出すのが得意なのです)頑強なドワーフ。
森に住む、おだやかなエルフ(素晴らしい弓の使い手なのです)。
人間は、業を背負った存在として描かれます。
そんな種族達がみんな集まって力を結集します。
何で?
それは、邪悪な指環を滅ぼすためにです。
これだけはいけないのです。
だって、私たちみんなが悪い世界に染まってしまう力を秘めた指環なのですから。
色々な読み方ができる作品だと思うのですけれど、私的には「みんなの力」」っていう風にずっと読んできたように感じます。ええ、もう何回も読んだと思います。
ホビットの(確か、従者という位置づけだった記憶です)ピピンやメアリー。業を背負った人間のアルゴラン。
そもそものサウロンに破れたマジシャンの「灰色のガンダルフ」。
そして、業の固まりのような「ゴクリ」。
これが、ファンタジーなのでした。
私が、今になっても大好きな世界です。
031 「文体練習」、「地下鉄のザジ」/レイモン・クノー
 はじめは、「文体練習」から。
はじめは、「文体練習」から。
まずは、「メモ」。
シチュエーションが提示されます。
「S系統のバスの中、26才位の男性の乗客。首がやけに長くて、変わった帽子をかぶってる。リボンの代わりに紐を巻き付けてあるような帽子。混んでいるバスの中、その若い男は隣の乗客に腹を立てている。誰かが横を通り過ぎるたびに乱暴に押してくる。と言って咎める。席が空いたのでその若い男は慌ててその席に座る。…その2時間後、ローマ広場でその男をまた見かける。連れの男がいて、若い男のコートのボタンを、もう一つつけた方が良いというような話をしていた。」
はい。これで終わりです。
ええ。この本の中で語られる「ストーリー」(そこには余り意味はないのですけれど)はこれだけです。
じゃあ、残りのページでは一体何を書いているのか…と言えば、このシチュエーションを99通りの(いや、別刷のも収録してくれていますので、あといくつか多くの)別の「書き方」で書いているという本なのです。
同じシチュエーションでも、書き方によってはいかようにでも書けるのですよということを示した訳ですね。
美文調あり、客観的な書き方あり、時制をひっくりかえしてみたり、あるいは「方言」で書いてみたり。
はたまた「人称」を操ってみたり、言葉遊びをしてみたり、古文を使ってみたり…。
いや、それこそ縦横無尽に書いています。
こんなの読んで面白い?って思いますよね?
「それなりに」面白かったです。つい、にやにやしちゃうところもありました。
最初のメモが本当にテーマの提示なのです。
そこから、段々変形されていくわけですね。だから、いきなり途中から読んでしまったりすると、言葉にすらなっていないモノにぶち当たってしまうことだってあるかもしれません。
だけど、冒頭のメモから読んでいれば、それが言葉になっていなくても、何を書こうとしているのかが伝わるのですね〜。
とても不思議な感覚でした。
そもそも、こんな本を良くも訳してくださいましたと思います。
いえ、これは、「翻訳」を越えているのですよね。だって、どうやったって訳せないような言葉遊びのようなことがいくらでもあって、でも、それを日本人の感覚として理解できる形にしたというこの翻訳はすごいなぁと思いました。
で、そもそもこんな作品を作る、レイモン・クノーってどんな人?
って、思ってしまうわけですけれど、その辺はネットでいくらでも出ている情報を見た方が早いです。
分類によっては、シュール・レアリスムに入っているかも。
ええ、023で書いたマックス・エルンストなんかと同じ感じ…
 で、このレイモン・クノーの超有名な作品が、「地下鉄のザジ」だったりするわけだ。
で、このレイモン・クノーの超有名な作品が、「地下鉄のザジ」だったりするわけだ。
舞台でも何度も演じられているし、(知らないのだけれど)もしかしたら映画にもなってる?
いや、こまっしゃくれた女の子、ザジがパリにやってくるわけです。
で、数日の子守を仰せつかった主人公の冴えない中年男性、ガブリエル伯父さん。
ザジは地下鉄に乗りたくて仕方ないのだけれど、パリはゼネスト中で、地下鉄は運休!
はなはだ面白くないザジなのでした。
そして、このザジが一筋縄ではいかないんだなぁ。
好意的に解釈すれば、反抗期の、思春期でもあるのかしら? 女の子。
あー、可愛くない!……というのは、大人の一方的な都合。
でも、これは難物。
だって、口癖は
「けつ喰らえ!」
もう、これが山盛り沢山出てきます。
お嬢さん、そんな言葉を言ってはいけま……(+_+)\バキッ!
もう、勝手にどこかに行っちゃうは、大人をたぶらかすは、しょーもない女の子。
ジーンズをはいてみたくてうずうずしちゃって、それをゲットするために怪しいおじさんについていったりもしちゃったりして。
それが、段々周りの大人達を巻き込んじゃう。
まるで、周りの大人達の方が子供じみて見えてきたりもして。
保護者のガブリエル伯父さんは、良く言えばアーティスト。
まぁ、言ってみれば、(無責任な……そうじゃないかも……)危ないコメディアン。
悪く言えば、オカマバーの(もしかしたら本人もそっちの気がある? いや無い!と本人は主張しておりますが)変人。
で、しつこく聞くんですよ、ザジが。
「ね、おじさんって、オカマ?」
もう、TPOも何もあったもんじゃない。
ガブリエルがどんなにシリアスな状況にあっても、「ね、オカマなの?」って聞いてきたりするわけ。
「はたいたろか!」とか読んじゃいけませんよ〜。
そんなのは大人の都合。
いや、一瞬でも「はたいたろか!」っていうキモチにさせれば作者は微笑むだろうかしらん?
その後の展開は……ストーリーらしいストーリーもなく、まるでドリフの舞台みたいな展開で……。
最後は、もうドタバタコメディーみたいにもなっちゃうし(でもほんのりシアワセ)。
登場人物は、どんなに怪しい奴でも、本質的に善人なのかもしれない。
最後の最後で、眠ってしまっているザジは、かわいいしね。
うん、楽しいよ〜。
結構、軽く読める「面白い」っていう作品というまとめ方が、「ザジ」の感想かな。
……さて、ここからが問題なのだね。
両作品、ご紹介しちゃったでしょ。
これは、どう、「折り合い」をつけなければならないのだろう…と、自分の中で収支決算しなきゃならなくなるのでした。
えっとね、自由さなのかもしれない。
どちらの作品の面白さも、その「感性」にあることは確かなのだけれど、それは束縛されていないものとしてのこと……じゃないだろうかって。
堅苦しいことや、作法なんて抜き!
柔軟な思考と、因習にとらわれないやり方。
「えー、文学的に言えば、はなはだ……」 …… そんなの「けつ喰らえ!」なのです。
だって、読んでいて楽しかったでしょ?って聞かれたら、「うん!」って答えちゃいます。
そんな自由さが、クノーにはあるのかもね。
文体練習/朝日出版社 ISBN4-255-96029-1
地下鉄のザジ/中公文庫 ISBN4-12-200136-6
030 「稲垣足穂全集」/稲垣足穂
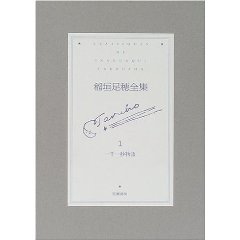 「タルホ」です。
「タルホ」です。
「イナガキ タルホ」と読みます。
前に、「月派」のことを書いた事があったと思います。
タルホは月派です。
いえ、別に、文壇上、そんなくくりがあるわけでもなくて、私がそう思っているだけのこと。
月の青さ……や、冷酷さと薄さ、でもやっぱりやさしかった事などが、見えたのでしょう、ね。
萩原朔太郎なんかも、見えたのでしょうね。
世間一般には、「児童文学者」みたいな紹介をされることもよくあるのですね。
全然当たってないけれど。
ええ、ファンタジックな物語も書いています。
「一千一秒物語」が、一番有名なのかしらん?
それでそういう紹介なんだと思いますけれど、子供の読み物では全くないです。
感性を読まないと、全く面白くないと思います。
ボール紙で作られた煙突、銀紙細工の三日月、坂道の「トア・ロード」(神戸のとある街なのでしょう)。
ときには、ブレリオ式飛行機(初期の飛行機です。プロペラの、木とゴムの枠体だったような)に憧れる少年。
ケンブリッジ式の白い学生帽、ガス灯に浮かび出された色とりどりのキャンディーが並ぶ店先。
横文字の煙草の箱、三日月印の鉛筆、A感覚(これは苦手なのですが、タルホは好きだったみたいですね)。
そんなもろもろの事が綴られている物語なのでした。
誰にでもお勧めできるという本ではないと思いますけれど、心の中のやわらかい部分を、ちょっと覗いてみたくなった時、まだ幼かった、でも、その分だけ純粋だった時間に帰りたくなった時。
少しだけ、そんな気持ちを助けてくれるように思っています。
今夜の月はどんな大きさなんでしょうね。
029 「冬の夜ひとりの旅人が」/イタロ・カルヴィーノ
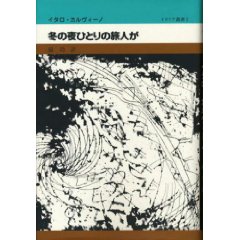 あなたは、今、新しい本を読もうとしている。イタロ・カルヴィーノの新作、「冬の夜ひとりの旅人が」という本である。
あなたは、今、新しい本を読もうとしている。イタロ・カルヴィーノの新作、「冬の夜ひとりの旅人が」という本である。
あなたは、期待に胸をふくらませ本のページをめくりはじめる。
どうやら、この物語はとある鉄道の駅から始まるようだ…
あなたは、徐々にこの物語に引き込まれてゆき、次々とページをめくっていく。
すると、どうだろう、この本には乱丁があるではないか。
とあるページの次にあるのは、あなたが今読もうとしていた「冬の夜ひとりの旅人が」とは全く違う物語のどこかのページである。
興がのってきたあなたとしてはがっくりモノである。せっかく面白くなってきて続きが読みたくなったのに、これだ!
明日、購入した書店に行って、本を変えてもらおう……
というわけで、あなたはその書店に行き、書店の主人に交換を申し込む。
「またですか。どうも今回は出版社がミスをやらかしたようで。ほら、こんな手紙が来ているんですよ。」
どうやら、出版社は、一部製本ミスをしたようで、「冬の夜ひとりの旅人が」という作品と、タツィオ・バザクバルというポーランドの作家による「「マルボルクの住居の外で」という本がごちゃごちゃに製本されてしまったものがあるらしい。
その書店には、ちゃんとしたカルヴィーノの「旅人」もあることは本屋の主人が確認しているそうで、それと取り替えましょうと言ってくれたのである。
そこで、あなたはふと考える。
まてよ、僕が読んで面白い、続きが読みたいと思った本は、「旅人」の方なのか?
違うだろ、そのバザクバルという作家の「住居の外で」の続きを読みたかったということになるじゃないか!
というわけで、あなたは、書店の主人に「バサクバルの方と交換してくれ」と申し入れます。
「お好きなように」とは主人の言。
あなたは、この書店で、あなたと全く同じ体験をした女性のお客さんと知り合いになる。
お互い、交換した本がまたおかしくなっていることも有り得そうなので、後で検証しましょうということで、お互いの連絡先を交わし合う。
あなたは、家に戻り、交換した本を読み始める。
すると、それは、これまでの本とはまた違った別の本が始まるのであった。
そして、あなたはその新しい本にも夢中になるのだが、何故だかこの本も途中で別の本と混じり込んでしまうのだった。
このパターンの繰り返し。
都合10冊の本の冒頭だけが綴られ、その先は決して読むことができません。
それぞれの本を読む間に、あなたと、書店で知り合った同じ目に遭った女性とのエピソードが挟まれます。いや、それは本を読んでいる「あなた」の時間軸、世界軸で描かれている世界なので、その世界はもっと沢山広がっていきます。
「あなた」はその都度現れる魅力的な作品の「次」を読みたくて仕方がありません。
でも、いつも、あなたの前に現れるのは、別の作品の冒頭ばかり。
何とも不思議な作品です。
カルヴィーノらしいって言えばらしいかもしれません。
イタロ・カルヴィーノは、1923-1985の間に活躍したイタリアの小説家です。
評論は色々あるので、検索していただければ沢山読めると思います。
私も何点か読みましたが、「木登り男爵」のような寓話的なお話しもあり(有る意味、この作品なんかは「童話」として読んだってとても面白いかも)。
ええ、とあるいきさつから、一生、木の上で生活した少年(後にバロン=男爵になるわけですが)のお話なんですよ。
あるいは! 「柔らかい月」(短編集です)なんかだと、ある意味SFですね。
作品集のタイトルになった、「柔らかい月」というのは、月と地球との間のカタストロフでありますし、あるいは、「時間」概念を取り扱った不思議な作品も多数書かれていました。
イタロ・カルヴィーノの作品は、どこか、不思議なテイストがあるように思います。
時として、やや難解な面もあるけれど、でも、紡ぎ出される不思議なイメージがそれを補ってくれます。
あんまり、小難しく考えずに、感じたままに楽しむ方が良いように感じています。
何よりも、ちょっと不思議なお話を読んでみませんか?
「冬の夜ひとりの旅人が」 脇功訳 松籟社 ISBN4-87984-022-x
「木のぼり男爵」 米川良夫訳 白水Uブックス ISBN4-560-07111-x
「柔らかい月」 脇功訳 河出文庫 ISBN4-309-46232-4
028 「マルドロールの歌」/ロートレアモン
「神よ、願わくば読者がはげまされ、しばしこの読みものとおなじように勇猛果敢になって、毒に満ちた陰惨な頁の荒涼たる沼地をのっきり、路に迷わず、険しい未開の路を見いださんことを。読むにさいして、厳密な理論と、少なくとも疑心に応じる精神の緊張とを持たなければ、水が砂糖を浸すように、この書物の致命的放射能が魂に滲みこんでしまうからだ。中毒せずにこの毒ある果実を味わうことができるのは特別な者にかぎる。
だからひ弱な魂よ。この前人未踏の荒地にこれいじょう奥深く踏み込まぬうちに踵をかえせ。先へ進むな。いいか言うことを聴くのだ。踵をかえせ、先へ進むな。…」
これが、「マルドロールの歌」の冒頭の「第一の歌」の始まりの部分です(【引用】)。
これから読もうとしている読者に対して、何と毒のあるプロローグなのでしょう。
ロートレアモン(伯爵)というのはペンネームです。本名はイジドール・リュシアン・デュカス。フランスの詩人です。
1868年、自費出版で、「マルドロールの歌」の「第一の歌」だけが世に出されました。
翌年、第六の歌まで書き上げて完成し、「ロートレアモン伯爵」名義で出版しようとしていたのですが、これが頓挫し、本人は、24歳の若さで居住先のホテルで謎の死を遂げてしまいます。
ですから、生前は全く無名のままだったのです。
その後、彼の遺稿が発見され、「第六の歌」まで全てが世に出ました。
19世紀のシュルレアリスムの旗手達に熱烈な歓迎を受け、一時期バイブルとまで言われた作品だそうです。
読んでみると、極めて毒が強いです。
醜悪な描写も続きます。
蛆や鱶、内蔵を引きずり出すような描写や何故にここまでいやらしい描写をするのかという残酷な場面も多々あります。
それは、全て、主人公である「マルドロール」が行う非道の数々だったり、彼が関わる場面で繰り広げられる愁嘆場だったりします。
…それは、何故かと言えば、色々な理由がありそうですし、様々な論評がなされています。
私が、ここまで読んだ範囲で感じた事を書けば、マルドロールは、恐ろしいほどにナイーブだったのだと感じました。
そんな彼の目からすれば、人間はなんて嫌らしく、みにくい存在なのだろうと、そう感じてしまったのでしょうね。
ええ、彼も、そんな人間の一人なのです。
だから、彼は、呪ったのではないでしょうか。人間というものを。
こんなとんでもない存在など肉の一片まで切り刻み唾棄すべきだと、そう呪ったのではないのでしょうか。
もちろん、そこには救いなど何もなく、彼自身を責め苛む結果にしかならないのでしょう。
数々と形を変え、彼が本来の気持ちから微妙な愛情を見せる場面もあるのですよ。
しかしそれは、やはり、すぐに「取り消されて」しまうしかなかったのかもしれません。
詩は、短いフレーズが並ぶようなのが普通ですよね。
でも、ロートレアモンは、それをフレーズで切ることをせず、あたかも小説のように、詩の断片を連ねていきます。
そして、一つの情景を歌い終わると、☆印をつけ、また全く別の情景を歌い始めるのでした。
それらには、何の脈絡もなく、様々な場面が現れるのですが、そこにはいつも、人間に対する呪詛と哀れみと慈しみがあるように感じています。
「そしてなによりも、ミシンと蝙蝠傘との、手術台の上での偶然の出会いのように、彼は美しい!」
これは、バイブル視されていたころに絶賛されたフレーズだそうです(第六の歌に出てきます)。
おかしいですよね、ミシンと蝙蝠傘が手術台で出会うなんて。
それをヴィジュアルに思い浮かべることに意味があるわけではないと思うのです。
これは、「表現」の一つの方法と理解しています。
つまり、そこで描こうとした偶然の出会い(それを形容するものがミシンとこうもり傘であり、そんなものが出会うわけはあり得ないのに出会ってしまったその偶然ということではないでしょうか?)、そのありえないほどの衝撃や重みがそこにあって、そんなことがあったとしたら受けるであろう心の印象ほどの美しさなのだ……、と。
という、形容の「仕方」なのではないだろうか、と、今夜は推測していたりします。
「マルドロールの歌」/ロートレアモン
栗田 勇訳 現代思潮社
ISBN4-329-00152-7
027 「火星の人類学者 脳神経科医と7人の奇妙な患者」/オリヴァー・サックス
 タイトルだけ読むと、「これはSF?」とか思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。むしろ、サブタイトルの方が内容を良く表しています。
タイトルだけ読むと、「これはSF?」とか思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。むしろ、サブタイトルの方が内容を良く表しています。
著者のオリヴァー・サックスは脳神経科医であり、これまでに、「レナードの朝」(映画化もされましたね)や、「妻を帽子と間違えた男」などの著作があります。
雰囲気としては、001でご紹介した「アルジャーノンに花束を」や、013でご紹介した「くらやみの速さはどれくらい」に近い作品です。ただし、ノンフィクションですが。
著者は言います。「とある障害を持った者は、その障害をカヴァーするような発達をするのかも知れない」と。
この作品には、著者が関わりを持った7人の人達が登場します。みんなそれぞれに過酷な障害を持ってしまった人達なのですが、それが可哀想だとか悲惨だとかそんなことを書いているのではありません。または、そういう過酷な障害を乗り越えていて素晴らしいなどということを書いているのでもありません。
その障害に苦しみながらも、適応し、あるいはその障害が持つ「力」とともに生きていく様を描いているように思いました。
いくつかご紹介しましょう。
「色覚異常の画家」: とある画家が事故の後遺症のため全く色を覚知することができなくなりました。全てがモノトーンにしか見えなくなってしまったのです。黒から灰色を経て白に至るだけの世界です。画家にとっては致命的です。そもそも、私たちがどうやって色を覚知しているのかというメカニズムは解明されていません。どうやら、脳のある部分が色の覚知に関係しているのではないかということまでは分かっているのですが、治療方法などは確立されていません。画家は、当初は、それはショックを受けるのですが、次第にそのモノトーンの世界で生きていくすべを身につけ、モノトーンの素晴らしい作品を制作していくようになります。そして、それまでは色に惑わされて見ることができなかった、物の質感や形を認識できるようになったと言っていることです(彼が言うものは、私たちには絶対に知ることができない物なのでしょうね)。
彼は言います。「事故の数ヶ月後だったら治療して欲しいと思っただろうし、治療のためなら何でもすると考えただろうけれど、今では治りたいとは思わない」と。
「トゥレット症候群の外科医」: トゥレット症候群という障害があり、その障害を持った者は、わめいたり、身体をよじったり、奇妙な動作をしたり、無意識のうちに口汚い言葉を吐いたり、暴力的になったりするそうです。これだけ聞くと、とてもまともな社会生活はおくれそうもないし、ましてやデリケートな仕事など到底務まらないと思いますよね。ところが、この障害を持った外科医がいるのです。チックの症状が出るので強迫観念にかられてどうしてもある物を触らずにはいられなくなったり、家の冷蔵庫は色んな物を投げつけられてベコベコにへこんだりしています。そのような症状を抱えながら、見事に外科手術をこなしてしまうのです。それは一体? というお話。
「見えていても見えない」: 「目が見える」ということはどういうことでしょう? 「そりゃあ、周りの物の形や色がそのまま映像として認識されることじゃない」的に思いますよね。 でも、そうなのでしょうか?それだけのことなのでしょうか?
ほぼ先天的に盲目だった人が、40歳を過ぎて手術を受け、生まれて初めて目が見えるようになったらどう感じるのでしょうか? この物語の主人公は、そういう感じでした。全盲ではありましたが努力によりマッサージ師としての仕事も成功し、その仕事ができるおかげで家も手に入れ、彼なりにおだやかな生活を送っていました。そして、とある時、健常者と恋に落ち、目出度く結婚することになりました。彼女は、彼のハンディキャップを何とか取り除いてあげたいと思い、色々な医者に診せたところ治るかもしれないということで手術を勧められました。手術に失敗したところで今が全盲なのですから、失う物は何もないと考え、強く手術を勧めました。本人は決心が付かなかったのですが、婚約者の言うことですからその言葉に従って手術を受けたのです。 手術は成功しました。視力が、完全ではないにしても相当程度回復したのです。
ところが、彼の目に見えた物は何だったのでしょうか? 医師が彼の目の前で「どうですか?見えますか?」と聞きます。
ええ、見えているはずなのですよ、医師の顔も周りの風景も。
でも、彼には分かりません。かろうじて、聞き覚えのある医師の声だとわかったので、目の前に写るものが医師の顔なのだと理解できたのです。
それはそうかもしれません。初めて人間の顔という物を見たのですから。
私たちは、赤ちゃんの頃から、目に見えている物とそれが何なのかという関連づけを長い時間かけて学んでいるわけです。そしてやっと、現在の認識を得ているわけですね。ところが、いきなり目が見えるようになったとしたら…
それだけのことではありません。遠近感や空間の概念が非常に難しいのだそうです。盲人は空間の中で生きているのではなく、時間の中で生きているのだという言葉も紹介されています。
このエピソードの結末は、とても悲しいものに終わっています。
その他、自閉症の人の話や、サヴァン症候群の人の話なども紹介されています。
タイトルになっている「火星の人類学者」というのは、自閉症の女性が、「自分はまるで火星の人類学者のようだ」と言った言葉から取られています。
「正常」とか「異常」っていう見方は、とても偏った、貧しい物の認識なのだろうと感じました。
結局、「健常者」というのは、「数が多い方」という意味でしかないのではないでしょうか?
何を基準として「ノーマル」と言っているかと言えば、それは、「数が多い方」としか言えないように思われました。
きれいごとで、「障害がある人達の保護を」とかなんとか言っているレベルは貧しいのだと感じました。
「火星の人類学者 脳神経外科と7人の奇妙な患者」/オリヴァー・サックス
吉田 利子訳 早川書房
ISBN4-15-208071-X
026 「紙葉の家」/マーク・Z・ダニエレブスキー
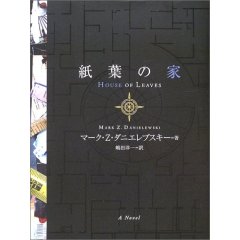 体力が必要な本です。読み終えるためには。
体力が必要な本です。読み終えるためには。
うん、それは、メンタルな面の力もとっても必要だし、物理的にも体力が必要なのですよ。
本書は、ハードカバーで、約800ページという大著です。
でも、まともじゃないんですよ。
活字がね、横になったり、渦巻いていたり、ちぎれていたり……
ページをめくるたびに、本自体を逆さまにしたり傾けたり、いやいや、ページの裏から読まないと分からなかったりと。
そういう、凝りに凝った本なのですが、一体何を書いているかというと……
とある家族がおだやかな土地に家を買います。
そこに住むわけですが、旦那は報道写真家で、高く評価されていたりもします。
旦那は、家族のことを記録したいと思ったのでしょうか、「ハイ8」っていう(日本製ですね)動画も撮れるデバイスを家の色んな所に設置したりもしました。
……で、気がついてしまったのです。
この家、変じゃないか!って。
直接的には、誰も気付くでしょうね。だって、それまで壁で閉ざされていた先に、ある日突然、新しい廊下ができているのですもの。
廊下ができていること自体変なのですが、その廊下はどこにつながっているの?
主人公のネイヴィッドソンは、家の外周の大きさを測り、家の中に新しくできた廊下の長さまで入れた家の中の寸法も測ります。
家の中の距離の方が、外よりも長い!
あり得ないのだけれど、家の中の方が大きいのです。
ネイヴィッドソンは、家の中を探り始めます。
その過程の記録が「ネイヴィッドソン記録」という形で残されます。
それがどうして世に出たかと言えば、ザンパという盲目の黒人老人が亡くなった部屋に残されていた膨大な「紙くず」が、それだったんですね。
それを見つけたジョニーが、狂気に陥っていきます。
ところどころ、スティーヴン・キングっぽいかもしれません。
恐いのですよ。
家の「中」は、どんどん大きくなっていきます。ネヴィッドソンや、彼の友達、弟(あぁ……)、専門家達もこの家の恐ろしく深くなってしまった中に入り込みます。
通路が曲がりくねる様子を、ページの中の文字配列で表したかったのだろうか……。
天井が低くて、這いながらでしか進めない情景は、1ページに、天井が低くなっているような活字配列の数文字だけだったりして……。
何ていう作品でしょうね。
ぞっと、したい夜には、オススメかも知れません。
「紙葉の家」/マーク・Z・ダニエレブスキー
嶋田 洋一訳 ソニー・マガジンズ
ISBN4-7897-1968-5
025 アガサ・クリスティ色々
乱歩が出たからというわけでもないのですが、今夜は、「アガサ」を。
今更言うまでもない、「ミステリーの女王」アガサ・クリスティあれこれです。
それじゃ、いくつかご紹介しますね。
【オリエント急行殺人事件】

うわぁー、懐かしい!
何て言っても、私が初めて自分のお小遣いで「文庫本」というものを買った最初の一冊がこれでした。
(もちろん、左の表紙絵のような本ではなかったですけれど)。
小学校5年生の時。忘れもしません。隣町の本屋さんまで行って買ってきたの。
創元推理文庫で、当時の値段で(今もはっきり覚えています)160円也。
子供向けの推理小説ご紹介みたいな本で「オリエント急行」のことを知ってどうしても読みたくなって、隣町の本屋さんまで探しに行ったのでした。いや、多分、自分が住んでいた町の本屋さんにもあったのかもしれないけれど、そこはいっつも覗きに行っていた本屋さんで、当時は子供向けのコーナーばかり見ていたので、そこに無かったから「このお店には無いんだなぁ」と思っちゃったのだと思います。それで隣町まで行って、よく分からない本屋さんの中をぐるぐる探していたら「文庫本」という棚にぶつかって、そこで見つけたのでしょうね。
レジに持っていったら、本屋のおじさんから、「これ、君には難しいと思うけれど良いの?」って聞かれて、何だかちょっと恐かったけれど、「大丈夫です」って答えて売ってもらったことを今でも鮮明に覚えています。
うん、大丈夫でしたよ。十分読めました。
しっかし、このプロットは秀逸ですよね〜。「やられた!」と思いましたよ。
その後、何度か読み返していますが、「犯人」が分かって読んでいても、なるほどね〜という筋の運びの巧さを堪能できます。
粗筋はこんな感じ。例によって事件にでくわしてしまうエルキュール・ポワロなのですが、今回はオリエント急行の車内の殺人事件です。運悪く雪で閉じこめられてしまったオリエント急行なのですが、そこで殺人事件が起こります。
完全な密室状態ですね、ある意味で。外部からの侵入も、車内からの逃走も不可能という状態です。
そんな状況の車内のとあるコンパートメントで、男性が刺殺されます。
結構むごい殺され方で、めった刺し状態。多数の刃物の痕が死体には残されています。
そこで、ポワロ登場なのですが……困ったことに列車に乗っていた人を尋問しても、みんなどこかしらにアリバイがあるのですよ。犯行推定時刻には、例えばAさんはBさんと一緒にいた(と両者の供述が一致します)、Cさんは車掌と一緒にいた(もちろん両者の供述は一致します)、というような具合で、全員にアリバイが成立しちゃうのです。
じゃあ誰が犯人なのよ〜!
という、密室+不可能犯罪みたいなのが「オリエント急行殺人事件」のコアな部分なのでした。
当時、小学校5年生だった私は、「絶対犯人を見つけてやる」と(名探偵コナンばりに)頑張って、真剣になって読んで、考えたのですが……どうしても分からなかった。
最後まで読み進んで…!!! なんと!
いや〜、やられた!と思いましたね。 なるほどね〜。と素直に脱帽した一冊でした。
【ABC殺人事件】
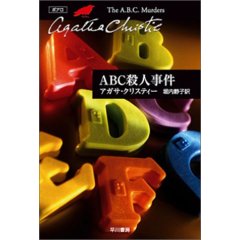 これも、「やられた〜」の一冊でした。いや、クリスティにはやられっぱなしなんですけれど。
これも、「やられた〜」の一冊でした。いや、クリスティにはやられっぱなしなんですけれど。
無差別殺人事件?と思われるような連続殺人事件が起きます。
最初は、そんな状況も分からないのですが、何人か被害者が出ると……何だか相関性のようなものが浮かび上がってきます。
つまり、Aという名前の町でAという名前の人が殺され、次はBという町でBという人が……と続いてきます。
動機なんてありそうもなく、ただ殺人を楽しんでいる奴が徘徊しているかのように思えます。
何とか早く犯人を捕まえて、次のアルファベット殺人をくい止めなきゃ!
この作品の秀逸なところは、本筋の間に間に「挿話」という短い部分が挟まれていることでしょう。
「挿話」では、とある男のことが短く描かれます。
素直〜に読んでいくと、どう考えてもこの「挿話」に出てくる男が犯人としか思えないのです。
子供だった……そう、「名探偵コナン」ぶっていた子供の私としては、「そんなのトリックだ!」って思ったのでした。
この「挿話」に出てくる男は、絶対犯人じゃない!って思って読み進んでいたのですが……やっぱり、どう考えてもその男しか犯人ではあり得ないと思ってしまって……
最後まで読むと……ありゃー!! ですた。
またもや心地よく騙されてしまった一冊でした。
【エルキュール・ポワロのこと】
ここで、クリスティが生み出した何人かの探偵の内、おそらくナンバー・ワンであろう(いやいや、クリスティ原作に限らず、世界の名探偵の5指には絶対入る名探偵の)エルキュール・ポワロに対する私の思い入れなどを書いてみようと思います。
「灰色の脳細胞」、「アームチェア・デティクティブ」(安楽椅子探偵)の代表選手、「ハゲ」(卵形の頭)、「チビ」、「小太り」、「ワックスで固めた髭」、「ベルギーの美食家」、「相棒(ワトスン役)はヘイスティング大佐」、口癖は「モナミ(我が友よ)」……思い浮かぶままにキー・ワードを書けばこんな感じ。
愛すべき名探偵です。
ビジュアルなイメージとしては、TVシリーズで好演した、デビッド・スーシェがイメージにものすごく近いです。
「アームチェア・デティクティブ」とは、犯罪現場に行って、地べたを這い回り、微物を収拾して手がかりにするタイプの探偵(ある意味では、ホームズはそういうところもあったと思う)と対極をなす探偵像なのでした。
そういう「現場主義」を唾棄し、要は理論なのだよと、安楽椅子に座ったまま、卵形の禿頭に詰まった「灰色の脳細胞」をフル回転させて見事に犯人を推理してしまうというタイプの探偵なのでした。
かっこいい〜!
素直に惚れましたね。
こんなポワロを生み出してくれたクリスティに乾杯!
【アクロイド殺人事件】
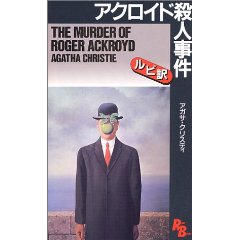 「くっそ〜! やられた〜!」というのは、犯人を当てようと思って推理小説を読んでいる読者の断末魔なのですが、この作品こそそう叫びたい! 思いっきり、完膚無きまでにやられますた。
「くっそ〜! やられた〜!」というのは、犯人を当てようと思って推理小説を読んでいる読者の断末魔なのですが、この作品こそそう叫びたい! 思いっきり、完膚無きまでにやられますた。
え゛〜! そんなのアリ?
みたいな、驚愕の結末があなたを襲っちゃったりするわけですよ、これが。イヤ、ほんと。
もう、何が驚いたかと言えば……おっと、危ない、危ない。これから先は言えないですよ。
ストーリー的には、典型的な推理小説です。
殺人事件が起きて、さて犯人は?といういつもの展開。
だけど……あぁ……(ため息)。やられちゃったなぁ。
こういう「犯人」を作り上げたことだけでも、クリスティは「ミステリーの女王」たる資格十分ですね(これは反則という論評もあまたありますが、私は小気味よく「騙された!」と思えるので支持します)。
【その他もろもろのこと】
クリスティは、戯曲でも素晴らしい作品を沢山残しています。「ねずみ捕り」なんてブロード・ウェイでも好演されていた記憶です。はたまた、「夜鶯荘」というサスペンス風味たっぷりの作品もあったりして大好きです。これは、昔の電話を上手く使ったサスペンスなんですよね。殺人犯が迫ってくる状況で電話で助けを求めるヒロイン。でも、助けを求めているというのを気取られないように、電話を操作するのです。当時の電話は、こちらが話したことを相手に伝えるためにはフックを押さなければ相手には聞こえなかったのね。逆に言えば、フックを外している間に話していることは相手には聞こえないのでした。
そこで、ヒロインは相手に伝えたいこと(救助を求める言葉)を何でもない会話に織り込んで、殺人鬼の見ている前で密かにフックの上げ下げをしながら救助を求めるというシーンが何とも迫真的で大好きだったなぁ。
今回、ご紹介した作品は、割と初期の、しかも名作中の名作でした。
後期は、また、ちょっとクリスティ本人の事情も絡んで、やや哀切を感じてしまう作品もあるようです。
私的には、「騙された〜!」と心地よく思える初期の作品が好きなのでした。
024 「江戸川乱歩全集」/江戸川乱歩
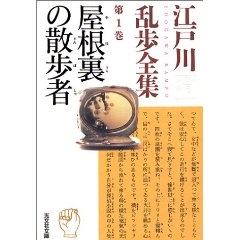 ♪「ぼ! ぼ! 僕等は少年探偵団 勇気凛々瑠璃の色」です〜。
♪「ぼ! ぼ! 僕等は少年探偵団 勇気凛々瑠璃の色」です〜。
あ。いや、これは乱歩が子供向けに書いた「少年探偵団シリーズ」のTV主題歌ですが。
「ふっふっふ…明智君、また会おう!」な〜んて言って消えてしまう怪人20面相、「待て〜!」とか追いかけてしまう小林少年。何だか、結構懐かしかったりします。
私たちが、乱歩に初めて出会ったのは、おそらく昭和40年代だったのではないでしょうか?
それは、何だかとても不思議な経験で。「怪しい」っていう感じがぴったりだったかも。
最初は、怪人20面相と名探偵明智小五郎のサスペンスとして出会ったように思いますが、「乱歩ワールド」を読み進むに連れて、もっと、「怪しい」世界に足を踏み入れてしまうのでした。
江戸川乱歩は、日本に推理小説を広く教えた先人でもありました。
よく知られている話ですが、アメリカの推理小説の創始者と言われているエドガー・アラン・ポーに傾倒し、そこから「江戸川乱歩」というペンネームを採ったごとく、英米のその頃の作品を精力的に読みふけっていた乱歩なのでした。
いや、その他の方も、色々いたのですよ。 例えば、「文豪」谷崎潤一郎だってそういう作品を書いていた時期もあったのです。
でもね、途中で、違う方向に行ってしまったのですね。
最後まで、そこにとどまったのが、乱歩だったのかも知れませんね。
読み直してみたところ、決して文章は上手くない……というか、下手です。
プロットだって、決して誉められた物じゃない。
何も知らずに、ただ、一つの作品として、「乱歩」を読まされたら、きっと、いくつかの作品を除いて「なんですか、これは?」と思ってしまうかも知れません。
語り口の多くは、「講談調」だったりもします。
乱歩の名作は、初期にあります。そう、感じました。
例えば、「心理試験」とか、「D坂の殺人」、「二銭銅貨」などは、今でも秀逸でしょう。
そういう、「切れ味」の良い推理小説は、「乱歩」としては、そこまでだったのかもしれませんね。
じゃあ、その後、何を書いたかというと、それはそれは、不思議で、耽美的で、幻想的な作品群だったのですね。
「乱歩」が、犯罪を多く題材にしたのは、その謎解きを示したかったからではなくて、そもそも、「犯罪」という非日常的な、極めて人間精神にとって異常な事態を取り扱ってみたかったからじゃないのかな。と感じます。
ですから、乱歩の作品には、当時の繁華街であった浅草辺りの情景が沢山書き込まれています。
それは、毒々しい色のクレヨンなどで彩色された、安っぽくて、薄っぺらな街が、何とも良く描かれています。
そこに、曲馬団や見せ物小屋、不虞者やアドバルーン、広告塔などの、その時代の「怪しい」ものがちりばめられていたりします。
そういう街の暗がりに、一寸法師が、人間の切り取られた片腕を持った一寸法師が彷徨っていたりするのが「乱歩ワールド」なのかもしれませんね。
そういう「世界」ですから。エロティックな場面も(当時の基準でね)ふんだんにあるのが「大人の乱歩」なのです。
「屋根裏の散歩者」とか、「人間椅子」なんて、まさにそういう「危ない」感覚の作品ですものね。
そういうのは、子供の頃は、読まなかったなぁ……と感じたりもして(いや、作品としては読んでいたのですけれど、それは子供向けに「水で薄められた」ヴァージョンだったわけです)。
私は、結構、そういう「危ない」感覚は好きだったりもしますので、「乱歩ワールド」も堪能できたりもしちゃいます。
この全集は「コンプリート」だそうです。
ですから、「大人の乱歩」も「少年探偵団」の「乱歩」も、全部入っているそうです。
まだ、前半4巻位しか目を通していませんが、この後の、小林少年の活躍も楽しみです!
023 「百頭女」/マックス・エルンスト
 またしてもおかしな本を選んでしまいました。
またしてもおかしな本を選んでしまいました。
マックス・エルンストというシュルレアリスムの画家さんのコラージュ(切り張りですな)だけで綴られた作品です。
表紙の絵のような不思議な銅版画のような作品がずっと続きます。
絵には短いキャプションが添えられているだけ。
ストーリーはあるようで、無いようで。
全9章立てなのですが、そのような何とも不思議な絵とキャプションだけが延々と続き、そして、最後の絵は最初の絵に戻ってしまうのです。
そう、円還してるのですよ。
この奇妙な世界に入ってしまったら出口はないのです。
そもそも、このタイトルは何と読めば良いのでしょう?
「ひゃくあたまおんな」? 「ひゃくとうめ」? 「ひゃくずめ」?
原題は、「Femme 100 t^etes」(最初のeの上には^がつきます)なのだけれど。
そんな「正解」などないのでしょうけれど、「ひゃくとうおんな」と読んでみたい気がします。
非常に非常に幻想的で、非現実的で、恐ろしくて、謎だらけで、まるで覗き見をしているような怪しい作品です。
う〜ん、もうちょっと普通に分かり易くて良い作品を紹介しなさいよ>自分。
と、突っ込みを入れてしまいそうなご紹介です。
ロプロプと呼ばれている大きな鳥が何度か表れるのですが(いや、不思議な鳥で、夜の街灯に餌をやりに飛んでくるのです)。
このロプロプが、マックス・エルンスト自体の象徴だという「絵解き」もされていますね。
あるいは、キリスト教に関する作品もあったりします。
キャプションで分かるのですけれど、「無原罪の宿りの失敗」とか、その「つづき」などが何枚も出てきます。
うん、「無原罪の宿り」っていうのは、聖母マリアの処女懐胎のことを言うわけですが、それを「罪」と書いてしまうことは、ずっと違和感を持っていたのでした(いや、そこで言う「罪」の意味があるのでしょうけれど……)。
「本棚」を読んで下さっている皆さんは、大体気付いてきていると思うのですが、私が好んで読む本ってかなり「変」です。
人気の高いベスト・セラー小説なんかはあんまり読まないし、むしろ、「何? この本?」みたいなのが圧倒的に多いのでした。 そうですね、傾向的に言うと、何某かの幻想的なテイストがある作品を好む様ですが……
ですから、あんまり参考に何てならないと思うのですけれど、世の中にはこんな本もあるんだよ〜っていう興味本位で読んでくれたらいいかなぁと思ったりしています。
ところで、この本は文庫なんですよ〜。
いや、良く出版してくださいました、河出書房、偉い!
何でも、1974年に河出書房が出版したのが始めてで、それまでは大判の豪華本だったそうです。
う〜ん、そういう大判の本が是非欲しい感じなのですが、当然の様に絶版。
どこかの古本屋さんで見つけたら買っちゃいそうでコワイかも。
PS: すごく時が経った後の追記 ……上に書いた、絶版の大判の本、見つけて買ってしまいました(結構高かったぁ)。あぁ……
「百頭女」/マックス・エルンスト
河出書房 ISBN4-309-46147-6
022 「ドリアン・グレイの肖像」/オスカー・ワイルド
オスカー・ワイルドの長編小説です。
オスカー・ワイルドと言えば……「幸福な王子」ですよね。
町に建っていた、銅像になった立派な王子が、貧しい人達のために自分を飾っている金箔や宝石をツバメの力を借りて届けるというお話。
ツバメは越冬のために南に飛んでいきたいのだけれど、王子の懇請を容れて、自分の命を犠牲にして、貧しい人達の所へ王子の体を飾る財宝をむしっては届けるというお話。
最後は、王子はぼろぼろになり、南に飛べなかったツバメは死んでしまうというお話。
有名なお話ですが、実は、私はちょっと嫌いなお話でした。
子供の頃から何度も読んでもらったり、自分でも読んだ本でした。
その度に、泣いてしまったのだけれど、それは、王子が可哀想とか。崇高な自己犠牲に対する感動とかじゃ全くなかったのでした。
私が流した涙は、全て冷たくなってしまったツバメのために、でした。
この王子は立派かも知れない。
この冬を越せない貧しい家族のために自分の体を犠牲にしたのでしょう。
だけど、そのためにツバメを見殺しにするのはどうしても許せなかった。
この冬を越せずに亡くなってしまう人達もいるでしょうけれど、でも、それは、社会が変わらない限り、来年も、その次の年もまた繰り返されること。
そうであれば、何故、ツバメは、この冬に死ななければならなかったのでしょう?
次の年にだって、また、この町に来て、王子のために働けたのでしょうに。
ツバメに死を要求した王子は……子供心に、嫌いでした。
冷たくなってしまったツバメが可哀想で、可哀想で……。
だから、子供の頃からずっと。 流した涙は、ツバメのため。
さて、「ドリアン・グレイ」をご紹介しなければ(以下、ご紹介文中で書く作中の言葉などは、私の感覚で書いていますので、原文とは全く違います。それがたとえ「 」でくくられていても、その中身は私の感覚の言葉だけです。それだけ、お断りしておきます。)
絶世の美青年がいました。それが、ドリアン・グレイでした。
画家のバジル・ホールウォードは、ドリアンを得て「天啓」を受けたのでしょうね。
それまでの彼の技量をはるかに超える作品を生み出す力を得たのでした。
その傑作が、「ドリアン・グレイの肖像」だったわけです。
その作品には、若く、美しいドリアンの全てがあらわされていました。
その美しさは、何にも比類なきもので、決して色褪せないような美しさをたたえた作品でした。
当のドリアンと言えば、純真無垢で、自分の美しさにすら気付かない様子でした。
その時、出逢ったのが、ヘンリー・ウォットン卿。逆説家で皮肉癖のある貴族。でも審美眼は超一流という人物でした。
ヘンリー卿は、ドリアンに対して、己の美しさを教え、それがなんとも儚い物であるかも教え解きます。
そして、バジルが描いた、傑作である「ドリアン・グレイの肖像」を高く賛美します。
ヘンリー卿との交流により、ドリアンは「世辞」を知ってしまうのですね。
それまでは、本当に純粋無垢で、みずみずしかったドリアンだったのですが、世の中のことを、そして、自分が絶世の美青年であるということを強く意識するようになってしまったのでした。
バジルが描いてくれた「ドリアン・グレイの肖像」はモデルであるドリアンの物になりました。
ドリアンは、その肖像画を見るたびに、その中に封じ込められている己の美しさに驚嘆しました。
そして、ヘンリー卿の言葉を思い出すのでした。
「ドリアン、君は素晴らしく美しい。でもそれは、君の今の若さがあるからこそ。残念なことに、人は年老いてしまうのだ。叶うのならば、この肖像画のままに美しさを保っていられればどれほどよいものか。」
そこで、ドリアンは「願い」を口にしてしまうのでした。
「年を取るのは僕ではなくて、この肖像画であったらよいのに」って。
若々しい、純粋なドリアンは、恋をしました。
ドリアンは貴族なので、お金なんて何も困らないのですが、ヘンリー卿の感化もあり、たまさか、場末の劇場に入ってみました。
安っぽく、暑苦しく、オケの音だってとんでもない劇場だったのですが、そこに登場した17歳の女の子に心を奪われてしまいました。
「ロメオとジュリエット」が演じられていたのですが、ビール腹にふくらんだとんでもない場末のロメオと、安っぽい書き割り背景の中で演じているジュリエット。
そのジュリエットのすばらしさに感動し(ドリアンの審美眼も確かなことと描かれているのでそれはそうだったのかもしれません)恋をしてしまいます。
確かに身分は大違い。でも、ドリアンは、彼女の芸術的なすばらしさそして、彼女自身の可憐さに心を奪われました。
彼女は、こんな場末の劇場で一生を終わる人じゃない。ピカデリーに僕が出してあげたい。
その素晴らしい才能を讃え、育んでいきたいと思った訳です。
二人は愛し合い、身分の差を超えて結婚する誓いを立てました。
ドリアンは、自分の無二の親友であるバジルとヘンリー卿を場末の劇場に案内します。
「さあ、僕の花嫁の演技をみて下さい」ということでしょう。
……ところが、それはひどいものでした。
いつもなら、いつもの様に演じていたのならそれは素晴らしかったのでしょうけれど、その時の彼女の演技は、しらじらししく情もこもってなく、三文芝居以外の何でもありませんでした。
場末の客さえ、怒って足を踏みならし、出て行ってしまうほどのていたらく。
バジルもヘンリー卿も、これはひどい……って思いつつ、口には出さず早々と引き上げます。
楽屋に飛び込むドリアン。「一体どうしたんだ?」
「私、初めて分かったの。プリンス・チャーミング!(彼女、シビルはドリアンのことをそう呼んでいました)。わたし、今まで色んな役をやって、その役で恋をしてきたわ。でも、そんなの嘘っぱち。私、本当に本当に愛している人を知ったの。だから、あんなお芝居なんてできないわ。お客さんがブーイングしてるのだってわかってたわ。でも、そんなの関係ないの。あなたが見ていてくれただけで良かったの!」
それが、シビルがとんでもない舞台を踏んだ理由でした。
ドリアンは、シビルのこの気持ちを許容できませんでした。
そもそも、ドリアンがシビルを愛した大きな理由の一つには、彼女の舞台での素晴らしい表現力があったのですから。
その素晴らしい力を、自分が持っている地位やお金で中央に上り詰めさせて上げたいと言う気持ちが強かったのかなぁ。
短慮だとは思いますが、ドリアンは言ってしまいました。
「もう、二度と、君に会うことは無い」って。
その後、色々あるのですが、ドリアンは。自分はあまりにもひどすぎたって後悔します。
そして、最初の自分の純粋な気持ちのままに、シビルと結婚しようと思います。
でも……シビルは、ドリアンに捨てられた苦しさに耐えかねず自殺してしまっていたのでした。
それから先、ドリアンの苦悩が続きます。
「願い」を口にしただろう?
お前の罪は、この肖像画に表れるのだよ。
ほら、お前の純粋無垢な美しい唇の端に、嫌らしい線が見えないか?
ドリアン、お前は年を取らず、いつまでも美しいかも知れない。
でも、お前の代わりに全てを請け負ってしまったこの肖像画を見るのだ。
その、醜さ、醜悪さを見るのだ。
そうして、その後……というお話でした。
「ドリアン・グレイの肖像」/オスカー・ワイルド
福田○(すみません、字が分かりません)存 訳 新潮文庫
ISBN-10-208101-1
021 「銀河ヒッチハイクガイド」 /ダグラス・アダムス
 楽しい〜! もう、こういうジョーク大好き!
楽しい〜! もう、こういうジョーク大好き!
とっても面白くて、はちゃめちゃなお茶目さんな作品です。
主人公はアーサー・デントという冴えない男性。
自分の家がバイパス道建設のルート上にあって、立ち退きを迫られている……というか、市役所の公示を見ていなかったばかりに異議申し立ても手遅れで、家は取り壊し寸前。
業者のブルドーザーがやってきて、すぐにも家を取り壊しにかかろうとしています。
もう、こうなったら実力阻止しかありません。
ブルドーザーと家の間のぬかるんだ泥道に寝ころんで抗議行動に出ます。
……そうしているところへ、変わり者の友人フォード・プリーフェクトがやってきます。
泥道に寝転んでいるアーサーに、「ものすごく重要な話があるんだ。飲まなきゃやってられない。」などと言って強引にパブに誘います。
「いや、だからさ、俺は今家を取り壊される寸前でさ、こうやって体を張って抗議しているわけ!」
そんなアーサーの言葉には全く耳を貸さないフォードなのでした。
取り壊し現場に来ていた市役所の職員を捕まえて、「アーサーはずっとあそこで寝転んでるつもりだけど、だったら別に彼がいてもいなくても同じ事じゃない?僕たちはちょっとパブに行って来たいだけなので、アーサーの変わりにあそこで寝転んでいてくれない?君たちがパブに行きたくなった時には代わるからさ。」とかなんとか言って役人をアーサーの代わりに泥道に寝かせて、アーサーを連れてパブに行くフォードなのでした。
で、パブでフォードが言うことには、「もう数分で地球は消滅するよ」ってな話。
実は、フォードは「銀河ヒッチハイクガイド」という全宇宙的に出版されている本の取材記者だったのでした。
もちろん地球人ではなく、ペテルギウスの近くの小さな星の出身で、地球人に化けて新版の「銀河ヒッチハイクガイド」(宇宙版「地球の歩き方」みたいな本と思って下さい)の記事を書く取材のために地球に立ち寄ったところ、何の手違いか15年も地球を離脱できずにいた男でした。
フォードは、早いとこ、このちんけな地球から出て行きたいと思いいつもヒッチハイカーを拾ってくれる宇宙船が地球のそばを通らないかと空を見つめていたのですね。
で、そこで分かったわけです。
おいおい、地球は宇宙航路のルート上にあって、立ち退きを迫られているぞって。
立ち退かない場合は取り壊す(破壊する)だって!
「そんなことはアルファ・ケンタウリの出張所に地球年にして50年も前から張り出されていたことで、アルファ・ケンタウリなんて地球からたった4光年しか離れていないのに見ていないとは言わせない。今更抗議は遅すぎる。」
というわけで、地球は「取り壊されて」しまいましたとさ。
だけど、間一髪のところでフォードは、アーサーと共に脱出し、近傍を通行していた船にハイカーとして拾われます。
どうですか、とんでもない話でしょ。
もう、まいっちゃいます。
沢山の皮肉とジョーク満載です。
この後、アーサーとフォードは絶体絶命のピンチに陥るのですが、奇跡的とも言える確率で生き残ります(それ自体がジョーク!)
その後の展開も「にやにや」ものです。
人間そっくりに作り上げたために重度の鬱病にかかっているロボットとか、とりあえずいい加減にやっていることが命脈を保つ大統領とか(いや、彼にはまた……なんだこりゃ!的なヒミツもあるのよん)。
もう、読みながら「にやにや」しっぱなしでした。
おおよそ、3時間くらいで読了できた軽い、でも面白い作品でした。
何でも、映画化もされたとか?
映画の大好きな方なんかにもオススメの作品かもしれませんよ〜
「銀河ヒッチハイクガイド」/ダグラス・アダムス
安原 和見訳 河出文庫
ISBN4-309-46255-3
020 「さかしま」 /J.K.ユイスマンス
 「さかしま」って使わない言葉ですよね。
「さかしま」って使わない言葉ですよね。
どういう意味に感じますか?
広辞苑をひいてみましょうか。
「さかしま: サカサマの転」(第二版補訂版)。
これだけ? ちょっと、もうちょっと、という感じ。
じゃあ、もうちょっと古い言葉を扱っている辞書で調べてみましょう。
「言海」という旧仮名使いで書かれた辞書があります(復刻版を買いました。本当は「大言海」というのが本家なんだけど、そんなのの復刻版は出ていないと思うし、古書で買うには高過ぎます)。それによると……
「さかしま:逆転(サカサマ)の転」(「言海」の表記は旧字ですが出ないのでご勘弁を)。
う〜ん同じですね。
だけど、このユイスマンスの「さかしま」というタイトルには(このタイトルを選んだのは訳者の渋澤龍彦さんなのですが、タイトルの和訳は名訳だと思っているのです)もっと、それ以上の意味が込められているように読めるのです。
単なる、逆さま、リバース、upside down じゃなくて……
じゃあ……「大辞林」でいくと。
「さかしま: 道理にそむくこと。また、そのさま。よこしま。」
うんうん、この雰囲気!
ユイスマンスについては、「本棚」では既にご紹介していました。
はい、010で「ルルドの群衆」をご紹介しました。そのリードで「さかしま」のことも触れていましたし、いつかはこの作品はマストでご紹介したいと思っていました。
この夜、ようやく書けそうな気がしてきたので取りかかってみました(とは言え、難物ですのでどこまでご紹介できることか……)。
「デカダンス」という言葉……というか、「概念」はご存知ですか?
一言で言えば「退廃的」ということになるのでしょうか?
ただ……その言葉だけでは済まないかなぁという感覚を、感じていたりもします。
えっと、じゃあ、「耽美的」とはどう違うのかなぁとか(いえ、確かに違うのですけれど、デカダンの中にある耽美主義と、耽美主義の中にある廃退性の関係って……)。
いや、小難しい事を書くつもりはないのですけれど、私自身は、おそらく一面において自分自身はデカダンだと思うところがあるのでした。
傍論はさておき、「さかしま」をご紹介します。
主人公は、デ・ゼッサントという病弱な貴族です。
で、主要な登場人物は……彼一人だけです。
これだけでも何とも異様な作品かもしれません。
デ・ゼッサントは、有り余る金にものを言わせ、放蕩の限りを尽くします。
「エピキュリアン」という概念もありますよね。日本語では「快楽主義者」と訳されます。
でも、哲学的には、日本語の語感というのははなはだ間違っているのですけれど。
だって、「快楽主義者」なんていうと、本当に放蕩主義みたいに感じますものね。哲学概念における「エピキュリアン」は決してそうではないのですけれど、このデ・ゼッサントが過去において過ごした時間は、その誤った「エピキュリアン」で良いのかも知れません。
でも、その刺激にも飽いてしまうのでした。
そして、彼が何をしたかというと、フォントネエという地所に居所を設け、そこに自分の美意識の結晶とも言える世界を作り出します。
昼夜を逆転し、鋭敏な色彩感覚と美的意識を満足させる意匠を凝らした部屋を作り上げ、耽美的な、極めて耽美的な自分だけの「城」を築き上げていくのでした。
ね、ほら、これを退廃的、デカダンスと、一般には評論されるわけですけれど、そこにある耽美主義はデカダンスとどう関わるのだろうか……というのが、私の(ちょっとだけ哲学的な)思索なのでした。
デ・ゼッサントの美意識からすれば、ひとつひとつの物に大変なこだわりを示します。
敷物の色、材質、質感、その部屋の本棚に並べられる本の装丁、いや、本自体のこと。
光にも敏感です。香りにももちろんのこと。
きわめてデリケートな感性によって、彼の「居所」が整えられていきます。
病的なほどの繊細さ、鋭敏でデリケートな感覚が描かれます。
美術に関しても、彼なりの審美眼が発揮されます。
まがいものはもちろんのこと、彼の感性が選ぶものしか許されない世界なのです。
そうそう、ギュスターブ・モロウの「サロメ」が取り上げられているのですが、確かにこの絵画は、私も大好きだったりして。
そういう、デ・ゼッサントの過程を読む物語なのかもしれません、「さかしま」という作品は。
そのこだわり、審美眼(耽美性?)、退廃主義、ダダイズム、だからあるいは無政府主義?いやもしかしたらシュール・レアリスト達が考えていたことだって、そう遠くは無いのかも知れないね……。
やっぱり難しいです。この作品のご紹介は。
とにかく、よろしかったら読んでみるのが一番の近道。
でも、決して双手をあげてお勧めできる作品ではありません。
小難しいこと抜きにして読んでみて、「変なお話、病的だよね」って感じるのがふつーかも。
そういう部分に魅力を感じる方であれば、それだけでも大変に興味深く面白い作品であることだけは請け負います。
でも、何故、そこまでに「病的」なのか(いや、そもそも何をもって「病」的というのか、どちらが病んでいるの?)。
その「病的」の病とは何に基づき、何を求めていることなのか。
それはもしかしたらとても純粋なことなのではないだろうか?
僕たちと、デ・ゼッサントのどちらが「病的」なのだろうか?
軽く読めば(読めれば)、波長が合えば、「奇譚」文学として楽しめると思います。
でも、ハマってしまったら、そこには、もしかしたら永遠の深みがあるのかもしれませんよ。
だから、「さかしま」なのですよ。
「道理」にそむいた、よこしまな世界……なのかもしれません。
でも、それは、誰の心の中にもあることなのですけれどね。
「さかしま」 /J.K.ユイスマンス
渋澤 龍彦訳 河出文庫
ISBN4-309-46221-9
019 「ファーブル昆虫記」 /ジャン=アンリ・ファーブル
 かなりの人が、子供の頃一度は読んだことがある本ではないかと思います。
かなりの人が、子供の頃一度は読んだことがある本ではないかと思います。
もっとも、それは子供用に脚色されたものだったでしょうけれど。
この度、集英社の創業80周年記念出版ということで、ファーブル昆虫記の完訳版全10巻(いずれも上下ですから全部で20冊ですね)が刊行されることになりました。
で、いち早くその第1巻上下を購入してきました。
これは、完訳版ですから、「大人のためのファーブル昆虫記」です。
でも、表紙が良いですよね。何だか子供の頃に読んだ本の表紙を彷彿とさせるような色遣いとデザインです。
内容はというと、第1巻はスカラベ(ふんころがし)と蜂たちの事が書かれています。
う〜ん、懐かしい。
いや、懐かしいだけじゃなくて、子供の頃にはここまで細かい話は読んでいなかったなぁと思い、それもまた楽しい感覚でした。
特に、蜂の部分はあまり記憶に残っていなかったこともあり、ほほう……と思ってしまったこともありました。
そして何よりも、ファーブル先生、虫が大好きなのですねぇ。
今から見ればそれほど正確ではない部分もあるようですし、特に虫の同定に関してはやや曖昧な点もあるそうなのです。
ファーブル先生は、虫の分類学に対して結構批判的な目を持っていたようで、そんなことよりも虫たちの生態を観察し、実験することが重要だと力説されていますから、そういうスタンスのある意味弱点もあったのかもしれませんね。
そして、ダーウィンの進化論にも否定的な立場だったことも分かります(ファーブル先生の時代は、例のチャールズ・ダーウィンではなく、そのお父さんのダーウィンの時代のお話になりますが。ダーウィンお父さんも進化論の基礎的な考え方を発表していたそうです)。
それにしても、懐かしさだけではなく、まるで少年のようなキラキラした感情が読みとれるように思います。
今の子供達は、ファーブル昆虫記とかシートン動物記とか読むのでしょうか?
いや、そもそも「昆虫採集」なんてしないのでしょうね。
私が子供の頃は、東京育ちでしたけれどそれでもまだまだあの時代は、チョウチョだけじゃなくて、カミキリ虫やクワガタ、玉虫なんかも頑張れば採れたのですよ。カナブン、セミ、カマキリ、バッタなんかはもっと容易に採れました。
で、昆虫採集キットなんていうのも売っていて、それを使って標本造りのまねごともしましたっけ(上手にできなくてただ虫をダメにしていただけだったのですけれどね)。
今の子供達だって(ムシキングじゃないけれど)虫は大好きなはず。
何だか、そんな自分の子供時代のことすら思い出されてしまうような本でした。
この「昆虫記」では、新たに用意された豊富な図版も添えられています。
また、これも子供の頃読んだ「昆虫記」を思い出させてしまったのですが、活字が大きいのですよね。
だから、厚さの割りにはどんどん読み進めてしまいます。
私は、眠る前に本を読む習慣があるのですが、その時間だけを使って2晩で読み切ってしまいました。
あの頃を思い出しながら軽く読むには良い本かもしれませんよ。
さて、問題は、全10巻(20冊)をどうしようかなぁということです。
マニアック及びコレクター的な観点からは全冊揃えたいとも思いますが、一冊2千数百円ですから、20冊揃えると約5万円かぁ……(まぁ、これは仕方ないかなぁ。)一番の問題は本棚からあふれちゃうことですね。これは悩ましい……。
現時点では第1巻上下までしか刊行されていませんが、さて今後どうするかなぁ……。
「ファーブル昆虫記第1巻上」 /ジャン=アンリ・ファーブル
奥本 大三郎訳 集英社
ISBN4-08-131001-7
018 「驚異の発明家の形見函」
「形見函と王妃の時計」 /アレン・カーズワイル
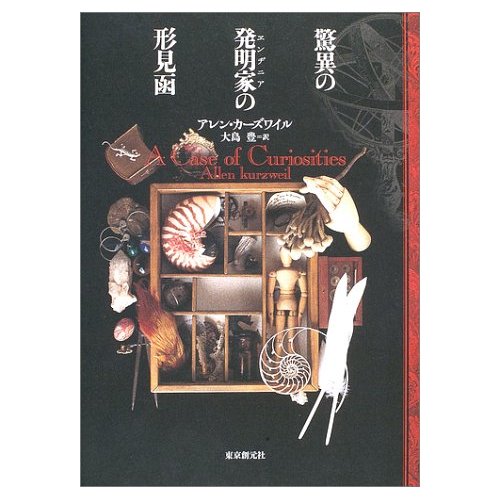

「形見函」(かたみばこ)というものがあったそうです。
イメージとしては本の表紙にあるように、小さな仕切で区切られた函なのだそうです。
それぞれの仕切には、色んな雑多な物が入れられています。
例えば、広口瓶、木偶人形、渦巻貝……
事情を知らない人が見たら、何だかがらくたが詰め込まれた箱の様に見えます。
でも、これは、ある人の人生を綴った函なのでした。
その人の人生にとって、転機となったような出来事、あるいは非常に重大な出来事を象徴するような物を集めて詰め込んだ、まるでその人の人生の縮図のような函が「形見函」というものなのだそうです。
今ではそんな習慣も忘れ去られていますが、実際に、一時期、ある地方ではこういう物が作られたのだそうです。
この2冊の物語は、とある一つの「形見函」を巡った別々のお話です。
どちらがどちらの続編というわけではなく、ただ、同じ「形見函」を巡っての、時代も、登場人物も違う、2つのお話です。
ですから、どちらから読んでも良いのだろうと思います。
私は、発表された順番に、「発明家」→「王妃」の順番で読みました。
読み終わった感想としては、逆に読んでも面白いかもしれないと思いました。
「発明家」の物語は、そもそも、この形見函が作られていく過程を描いた作品です。
始まりは、とあるオークションです。
巡り合わせでどういう物かも知らずにこの形見函を手に入れた人がいました。
その人が、一体これはどういう物なのだろうかと調べ始める内に、その頃の時代に話は移ろい、この形見函が作られた経緯が語られます。
時代的にはマリー・アントワネットの時代です。
そして、背景に描かれるのは様々な物に対する「知」です。
この形見函の主は……書かない方が良いのかなぁ……
でも、タイトルにもなっていますので、この位は良いかな。
ええ、「驚異の発明家(エンジニア)」なのですよ。
彼が、ある意味不遇の人生前半を乗り越え、様々な友を得て、遂には彼の才能を活かして成功する……でも……
というような、波瀾万丈、幻想的な物語が綴られます。
その、人生の節目節目を象徴する様々な物が収められたのがこの「形見函」だったというわけです。
これが「発明家」の方のほんのあらすじです。
そして、「王妃」の方と言えば、時代は現代。
この形見函を巡り巡って入手した人物がいます。
彼は、この作品の主人公となる図書館の司書に目をつけます。
彼が入手した形見函には10個の区切りがあったのですが、その内の一つの区切りだけは空だったのです。
一体、ここには何が収められていたのだろう……
どうしてもそこに収められていた物を知りたい、できるのなら手に入れたいということから「王妃」の物語は始まります。
そして、主人公である司書は、その空の一区切りの中身を探索するために、形見函を入手した人に雇われるということになります。
雇われると言っても、司書自身その秘密を知らされた後は、「知」に対する欲求が高まり、自分の関心事として、奥さんもかえりみずのめり込んでいくのですけれど。
さあ、それからは、空っぽだった区切りに収められていた物が何だったのか、そしてそれはどこにあるのかの探索劇が始まります。
あ! 勘の良いあなた! 気がついちゃいましたか?
「発明家」の時代はマリー・アントワネットの時代。で、「王妃」ですから……
そう、「王妃」はマリー・アントワネットなのです。
じゃあ、「王妃の時計」なのだから、空の区画には時計が入っていたの?
うん、そうなんです。「王妃」の時計が入っていたように思われるのです(そこまでも謎解きなのですよ)。
こちらの作品は、謎解きの要素が強いように思います。それに比べると「発明家」の方は伝奇ものという感じが強いかなぁ。
さらに両者を比べてみると、「王妃」で主人公に接触する形見函の持ち主のイメージと、「発明家」に出てきた発明家を育てる領主のイメージが妙にだぶったんですよね〜(そして、人間関係としての両方の結末も……)。
そういう効果も狙っている作品なのかもしれません。
どちらも、知的興奮があり、スリリングな面もあり、権謀術数的な駆け引きもありでとても面白く読みました。
結構厚い本なのですが、「発明家」の方など、正月休みの一日で読み切ってしまえるほど面白かった(つまり飽きさせず、次はどうなるのと読み進んでしまう面白さがあったということ)です。
ペダンティックと言えばそうなのですが、私はそういうの大好きなのでむしろ魅力的でした。
ちょっとだけ好きじゃなかった部分を書くと、そんなに露骨ではないのですが、セクシャルな場面が時々出てくるのですが、この部分は必要なのかなぁという気がしたことが一つ。
もう一つは、登場人物(特に主人公)の性格描写の掘り下げがやや甘いというか、薄っぺらいのかなぁ。でもエンタテイメントとすればこれで十分なのかもね。
実際、面白く読ませて頂けました。
こういう傾向の作品に興味がおありならオススメできますよ。
さて、どちらから先に読みますか?
「驚異の発明家の形見函」/アレン・カーズワイル 大島豊訳 ISBN4-488-01635-9
「形見函と王妃の時計」/同上 ISBN4-488-01640-5
017 「ムーン・パレス」/ポール・オースター
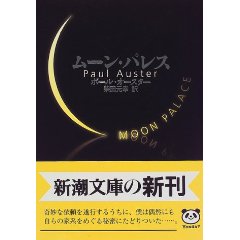 なんて奇矯な小説なのでしょう。
なんて奇矯な小説なのでしょう。
数年前、東京新宿紀伊国屋の文庫本コーナーを何気に通り過ぎようとした時に、目に飛び込んできたのがこの本でした。
「ムーン・パレス」……「月の宮殿」……何て素敵なタイトルでしょう!
「月派」の私としては、一も二もなくまいってしまいました。
あ、「月派」のことは、また、今度書きますね。
で、ポール・オースターという人がどういう人かとか、この作品がどいういうものかとか、そんなことは一切知らずに、この文庫本を持ってレジに並んでいたのでした。
で、読んでみたら……何なのよ〜!
と思ったわけです、正直言って。
ニューヨークで暮らす「僕」なる大学生。
何をしたいんだか、どうしたいんだかさっぱり伝わってこないの。
いや、色々本を読んだり、仲間と語り合ったりするシーンもあったのだけれど……
「思索」らしいことも色々していて、精神を肉体から分離させるためにはむにゃむにゃ
一向に現実と向き合うことを拒否しつづけているような。
そういうことを、「ムーン・パレス」という名前の安っぽい店で語り続けたり。
で? 君はどうするの?
いや、どうなったかというと、持っていたいくばくかの金を使うがままに任せ、読書家だったのでしょうけれど沢山の本も放り出し、食うや食わずの状態になり、やったことと言えばセントラル・パークでただ死ぬまで寝ていること。
何なんだ、これは?
あまりにも虚無、あまりにも不感性、そうやって死ぬまで地べたに寝そべっているのかい?
死ぬにしても、もっとマシな死に方だってあろうものなのに。
結局、仲間に助け出されて死にきれなかった「僕」。
本気で死ぬ気があったのかよ!と思った。
本気で死にたいなら、そんなぬるいこたぁしないよ!
何だ、こいつ、結局人に迷惑をかけて甘えているだけの大馬鹿野郎だ!と、当時、思ったわけです。
未だに、どう解釈すればいいのか、分からないのですが、「死にたい」(全然死にたくない!)よりも「逃げたい」なのかなぁ……と思ったり。
で、その後、「僕」はどうしたかと言えば、 何とも奇妙なバイトを見つけ、それにはげみます。
どんなバイトかと言えば、車椅子に乗った盲目の「くそ」頑固老人のために本を朗読するというバイト。
何なのよ〜このストーリー展開は!
しかも、「僕」はまんざらでも無さそうで、この老人との生活が結構書き込まれます。
さらにその後……(段々記憶が怪しくなってくるのですが)、その頑固老人と冒険の旅に出てしまうのですよ。
これで数回目ですが、何なのよこれ〜!
本当にワケわからんでした。
それだけの作品なら、忘れ去るし、少なくともここで取り上げようなんていう気には絶対ならないのだけれど、本棚を始めた頃から、「ムーン・パレス」のことはいつか書かなければと思い続けていたのも確か。
あの、まるで訳が分からなかったことが、ずっと記憶に残り続けているのです。
その正体が一体何なのかは未だに分かりません。
ですけれど、全然分からないのですけれど、意識の中に刻み込まれたような作品でした。
この本は、いつかまた、必ず読み直さなければ自分が納得しないと思っている本でした。
* その後、再読しました。自分の記憶の何といい加減なことか。上記では「頑固老人と冒険の旅に出る」などと書いてありますが大変な記憶違いでした。
これは、その頑固老人が、「遺書」として主人公に口述した老人が若かりし頃の物語のことでした。
ええ、その老人は、まさに冒険と言っても良い旅に出たのです。そして、そこで瀕死の目に遭い、世間的にはもう死んだものとされてしまいました。
そこから、別の人生を歩み始め、今に至ったというわけでした。
そこには、実は沢山の伏線があるのです。その老人は、一度結婚していたのですが、その生死不明になる旅に出た後、妻は精神を病んでしまい、廃人となり死んでしまうのでした。
彼の妻は、(その老人の言葉を借りれば)ほとんど病的に潔癖症なのか、夫との交わりを拒否し続けていたような女性だったそうですが、一度だけそういう夜があったそうです。
老人は、別人として生還した後、妻が病死したことを知り、その後別の人生を、別の人間として歩き始めるわけですが、ひょんなことから、自分に息子がいることを知ります。
そう、あの夜の子供がいたのでした。
老人が、老人となるほど年を重ねたのと同じように、その子供も今では年を重ねています。
老人は、主人公に口述筆記させた自分の一代記を、自分が死んだ後にその子供に送るように言い残します。
それは、それで残酷なことですよね。だって、その子供だって自分の父親である老人のことなどなにも知らないのに、でも知らないなりに「思い」を持って育ってきたわけでしょ。それにそぐうのかどうか分からないけれど、でも老人の意思として、一方的に突きつけられるわけですから。
主人公は、そのようにして、頑固老人と暮らしている傍ら、とても美しく魅力的な中国籍の女性と恋に落ち、いつかは結婚しようと(言葉には出さないけれど)二人とも思うようになります。
彼女は才能も豊かで、ジュリアード音大にも通い、また、ダンスにも精を出しています。
時間があれば逢瀬を重ね、精神的にも肉体的にも交わりを深めていきます。
で、この後、その頑固老人が自分の死期を宣告するに至ります。その時主人公は……
物語はまだまだ続きます。「御都合主義」と言ったらそれまでのような、そういう巡り合わせも描かれます。
そんな偶然なんてありゃしない、というのが普通。作者にもそれはよくわかっているのです。ある人の著作の粗筋が作中で紹介されますが、それに対して主人公の口を借りて「偶然に過ぎる」と批評を加えていたりもします(それを言うのなら、この作品自体そうなのにね)。
でも、そういう「あざとい」人間関係を設定しつつも、しれっと書いてしまうわけですね。
何にしても、僕の初読とその記憶というのは何とも貧しい、しかも混乱したものでしかなかったということを、ここに自白します。
確かに、最初の感想に書いたことは、記憶に誤りが無かった部分に関しては再読しても事実その通りでした。
ですが、特に後半部分は全く読めていなかったのか、完全に記憶がぶっとんでいたとしか思えないていたらくでした。大変恥じ入っています。
以前、書いた部分を消して、最初からもう一度書き直そうと何度思ったことか。
でも、そういうことも、本を読んでいる内には、何度かあることでもあります。
そういう、苦い悔悟もこめて、このままにすることにしました。
本作を総体的に再度見直せば、良い作品だと思います。好みはあると思いますが、私が最初に読んだ時ほどには「嫌な」感じはありませんでした。
あぁ、読書って、その時の、自分の気持ち、状態、体調、あるいは、置かれていた立場、そんな、まるで自分の全部が投影されて、その上で「読後感」というのが生まれてくるものなのかなって、また、感じました。
特に、この作品に関しては、初読では、何も読んでいなかったということがよーく分かった再読でした。
こんなにいい加減なことを、最初に書いておきながら、唯一救いだったのは、やっぱり、どこかにひっかかっていたことでしょうか。
「この本は、いつかまた、必ず読み直さなければ自分が納得しないと思っている本でした。」
と、言うのは本当のことでした。
そして、そもそも、こんなことしか当初は書けなかったのに、でも、何か残しておかなければと感じたことは、正しかったのだなと、再読して確認しました。
すみません。本当を言えば、もっときれいにして、最初から書き直した方がどれほど、ある意味で書きやすかったことか。
でも、そのままの形を残すことにしました。
はい、とても、良い作品でした。
「ムーン・パレス」/ポール・オースター
柴田元幸 訳 新潮文庫
ISBN-10-245104-8
016 「素数の音楽」/マーカス・デュ・ソートイ
 またまた数学関係の本です(そんなに嫌な顔をしなさるな)。
またまた数学関係の本です(そんなに嫌な顔をしなさるな)。
「素数」って、ご存知ですよね。
1と、自分自身以外では割り切れない数のこと(1を除く)です。
例えば、2、3、5、7、11、13、17、19、23、29…などの数のことですね。
そして、全ての整数は、素数のかけ算と足し算で表わすことができるということも証明されています。
素数って、まるで、原子のような、整数の基本単位なんですね。
ところが、この素数を順番に並べてみても、どうにもその出現の仕方には法則性が無いように思われるのです。
29の後に続けてもっと沢山書いてみましょうか。
31、37、41、43、47、53、59、61、67、71、73、79、83、89、97…
今、書いたのは、100以下の素数全てです。
ね、素数が出現する法則性って、ちょっと分からないでしょ?
大体、素数って全部でいくつあるのでしょう?
それは証明されています。無限にあるのです。
じゃあ、その無限にある素数は、一体どのようなパターンで現れるのでしょうか?
それは非常にランダムに現れるように見えるのです。
例えば、999万9,900から〜1000万の間にある100の数の中の素数の数は9個あります。
でも、次の100の数、つまり、1000万から1000万100の間にある素数の数はたった2つだけです。
「いったいどうなってるんだ〜?」と、大昔から数学者達は頭を悩ませてきました。
ここで登場するのがガウスという最高級の大数学者です。
ガウスは考えに考え抜いて、とある整数以下にある素数の数を見つける公式を編み出しました。
しかし、それはかなり良い線を行っていたのですが、完璧ではありませんでした。
誤差が出るのです。おおよその目安にはなるにしても、完全ではなかったのです。
その後も、名だたる大数学者達がこの素数の謎に挑戦し続けました。しかし、非常に難しい……
ですが、とうとう、登場した人物がいました。
1859年、ベルンハルト・リーマンは、ゼータ関数を駆使して一つの予想を打ち立てたのです。
え? ゼータ関数って何かですか? えっと…
ζ(x)=1/1^x+1/2^x+1/3^x+1/4^x+…というものです(「^」の記号はべき乗ね。つまり2^2は2の2乗という意味)。
で、xに任意の数を入れるとこの計算式の結果導き出せる数が答えになるというのがゼータ関数です。
リーマンは、このxに虚数(「i」で表されますね)をぶち込むことを考えたわけです。
もうちょっと正確に言えば、「i」を使った複素数(つまり、a+ibという形で書き表すことができる数)を入れたのですね。
その結果、xより小さい数の中にある素数の個数は、この複素数の実数部(つまり、aに相当する数)が1/2になる時に現れると思われたのです!
これが、かの有名な「リーマン予想」です。
リーマンは、その証明まではできずに世を去りました。
ですから、「予想」と呼ばれているわけです。
で、その後も大数学者達が、この「リーマン予想」を証明しようと努力し続けてきたのです。
しかし、現在でもまだ、この予想は証明されていません。
リーマンの生前には使うことができなかったコンピュータを使って、ものすごく大きな桁数の素数まで計算し続けていますが、ことごとくリーマン予想は的中し続けています。
でも、先ほども書いたとおり、どんなに計算を続けても、素数が無限にあることは証明されているので、これではリーマン予想の証明にはならないのです。
もう、リーマン予想はほぼ間違いないだろうということを前提にして、その次、さらにまた次の理論まで進展しているのですが、肝心要のリーマン予想が、残念ながらまだ証明されていないのでした。
今回、ご紹介した「素数の音楽」という本は、このような素数の不思議をご紹介し、その上で、ガウス、オイラー、そして極めつけのリーマンらの苦闘を描き、さらには、その後に続いた幾多の数学者達の健闘を描いた作品です。
作品の性質上、数式は出てきますが、これは、「フェルマーの最終定理」と同様、読み飛ばしたって一向に構いません。
人類の英知が未だに届かない分野があって、でも、その解決のために、素晴らしい努力が積み重ねられてきたこと、その知的興奮が描かれている作品です。
何故、「音楽」か?ですか?
作者によれば、リーマン登場以前は、素数というのは、まるで、楽譜に無作為に書き散らされた音符のようにしか見えなかったのに、リーマン予想によって、初めて調和的に、、まるで、それまでばらばらの音だったように思われていた素数が、一つの音楽になったように思えたのだと、そう表現されています。
作中に、リーマン予想を座標軸に落としたグラフなども掲載されていますが、本当に見事に1/2のラインに素数が並ぶのですね。ちょっとした感動物です。
同様の話題を扱った作品をもう一つご紹介します。
こちらの方が古い作品かな?
「リーマン博士の大予想」という作品です。こちらの方がどちらかというと、若干、数学的色彩が濃いかもしれません。
併せて読んでみるのも良いかも知れません。
「素数の音楽」/マーカス・デュ・ソートイ
富永 星 訳 新潮社
ISBN4-10-590049-8
「リーマン博士の大予想」/カール・サバー
黒川 信重・南條 郁子訳 紀伊国屋書店
ISBN4-314-00973-x
015 「アウステルリッツ」/W・G・ゼーバルト
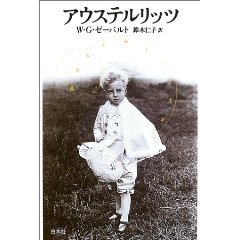 とても、とてもきれいな文章の本です。
とても、とてもきれいな文章の本です。
純粋で、儚くて、誠実です。
この本には、ほとんど途切れがありません。
ただ、ただ、ひたすらに、主人公である「アウステルリッツ」が話す言葉を聴いている(そして書き留めている)「私」が記す言葉が連なっていきます。
章割りのようなことはほとんどありません。
ただ、「私」が(多くは偶然に)、アウステルリッツに出会い、彼の言葉を聴いている、そういう作品です。
とても、おだやかで、静かな、しずかな作品です。
「私」とアウステルリッツが初めて出会ったのは、1967年、ベルギーのアントワープ中央駅。
「私」がそこへ行くと、人気も疎らな構内で、熱心に駅舎の構図を見つめ、何某かを書き込み、時にはカメラを取り出して写真を撮っていたのがアウステルリッツでした。
何気なく声をかけてみたことから、「私」とアウステルリッツの線が交わります。
アウステルリッツは、建築史学者でした。
様々な建築物を研究していたのでした。
「私」は、彼が話すその驚くべき知識に魅せられました。
「私」は、彼が話す言葉を、こう感じました(以下、引用)。
「会った当初から私を驚嘆させたのは、アウステルリッツがこうした思索を話ながら纏め、いわばとりとめのない思いつきからこのうえなく端正な文章をつむぎ出し、さらに彼にとって専門知識を語り伝えることが、一種の歴史の形而上学へのゆるやかなアプローチになっている−−−そしてそこでは想起されたものがいまひとたび命をもって甦る−−−ことであった。」
「私」は、アウステルリッツと伴に様々な建物を巡り、彼の驚くべき知識の披瀝を受ける。
そしてまた、彼から教えられた建造物に赴き、その偉容を目にする。
この作品には、沢山のモノクロ写真が添えられています。
それは、物語に出てくる様々な建築物、風景、アウステルリッツが見たこと。そんな写真です。
それが、端正な、そしてみずみずしい文章と共に、心に浸みてきます。
途中から、アウステルリッツは、これまで全く語ってこなかった自分のことを語るようになります。
自分が、何故、「アウステルリッツ」という名前になったのか、少年時代に見て、感じてきたことがどういうことだったのか、そして、そして、自分は一体どういう者だったのかを。
その後は、ほとんど、アウステルリッツの一人称独白です。
ですが、ここで、文体のマジックがあります。
あくまでも、アウステルリッツの話を聞いているのは「私」なのです。
ですから、アウステルリッツの「… … …」という長いモノローグが続いた後、「、とアウステルリッツは語った。」と書かれ、この後、再び、何の前置きもなく、アウステルリッツの独白が続くという構成になっています。
これがまた、読んでいると独特の感覚を呼ぶのですね。
そして、アウステルリッツの過去が(いや、彼すらちゃんとは知らなかった過去なのですが)、アウステルリッツの口から語られていくに連れて、彼が、ナチス時代のドイツからイギリスへ送られてきた子供だったのだということが明かされます。
彼の、彼を、アウステルリッツと名付けた両親は、今はどこへ?
そう、彼は、イギリスに移送された後、とある聖職者の夫婦に育てられ、15歳まで別の名前を与えられていたのです。
この後も、アウステルリッツのモノローグが続きます。
表紙の写真は、アウステルリッツが、アウステルリッツであったころの写真だそうです。
仮装舞踏会に連れて行かれた時に、「薔薇の女王の小姓」の扮装をした(させられた?)時の写真。
この作品は、建築物への深い造詣を記した作品とも読めます。
または、もちろん、ナチス・ドイツについて書いた作品とも。
でも、私は、私が一番強く感じたのは、その文章の清冽さでした。
淡々としていながら、何ていう言葉を紡ぐのだろうと、そこに一番感動しました。
自然描写も、建築物の描写も、季節の描写も、光や陰の描写も。
私としては、この文章を読んでもらいたいな、という気持ちから、今回、「本棚」でご紹介しました。
その文章は、ここで切り取って書いてみてもなんの意味もありません。
是非、ご自身で、最初から、添えられた写真とともに、味わってみて下さい。
作者のゼーバルトの遺作だそうです。
こんなに素晴らしい文章を残して下さって…… 素晴らしかったです。
「アウステルリッツ」/W.G.ゼーバルト
鈴木仁子 訳 白水社
ISBN4-560-04767-7
014 「香水」/パトリック・ジュースキント
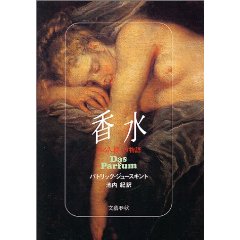 時は18世紀。場所はフランス。
時は18世紀。場所はフランス。
当時の衛生観念なんて今から思えば不潔極まりない状態でした。
かのベルサイユ宮殿だって、ろくにトイレもなく、園遊会などに招かれた貴族達も、庭園の茂みで用を足すというのが当たり前(いや、これ本当)。
ましてや、庶民が住む町などはそれはそれはという状態で、町中悪臭が立ちこめていました。ペストなどの悪疫が流行するのもさもありなんです。
物語は主人公が産み落とされるところから始まります。
主人公の母親は魚屋で生魚を捌いていました。
陣痛が来ましたが、何、いつものこと。
彼女はこれまでも何人もの子供を産み落としてきました。
そう、いつものこと。いつものように、魚を捌いている包丁で産み落とした子供と自分をつなぐへその緒を切ってしまえばよいこと。
その後、産み落とした子供は、地べたに放り出してある魚の臓物と一緒にして捨ててしまえば良いこと。
時には、魚の臓物と一緒にそばを流れるセーヌ川に放り込めば手間もかからない。
もちろん、今度だって同じこと。
いつものように、へその緒を切って地べたに捨てた。
でも、今回はちょっと違った。
どういうわけか出血がひどくて。ついふらふらと倒れてしまった。
それに気付いた周りの人間が「どうしたんだ」と駆け寄るけれども、「どうもしないよ。何でもないさ。」と言うだけ。
でも、その時、産み落とした赤子が泣き出したんだね。
それで全てがばれてしまって、(当時は拷問のようなこともしたのでしょうね)、母親はこれまでに産み落とした何人かの子供のこともしゃべってしまい、死罪になったそうです。
さて、生まれてすぐに身寄りの無くなった主人公は、修道院に預けられます。
修道院とて、慈善事業じゃやってられない。
わずかな金を与えて、乳が出る女にそういう身よりのない子供を預けます。
主人公もそうやって、とある「乳母」(と、いうのだろうか?)のもとに預けられます。
しばらく後、その乳母は、主人公を突っ返しにやってきます。
「子供はさ、子供の匂いがするもんじゃないか。こいつは何の匂いもしやしない。恐いんだよ。」
そう言って、給金を上げてやるという司祭の言葉も聞き入れず、主人公を押し返してしまいます。
時は流れて、主人公は革のなめしやにほとんど売られるようにして連れて行かれます。
それはそれは重労働で。
でも、彼は、自分がどういう人間かということに気付いていたのです。
自分は、毒虫の様な奴なのだと。
だから、何を言われても、どんなにひどい仕打ちを受けても、じっと毒虫のように身を固くして耐えていました。
とある時、あるきっかけで、彼は自分の秘められた才能に気付きます。
その才能とは、匂いに極めて鋭敏だということ。
どんなにかすかな匂いでも、どんなに混じり合った匂いでもたちどころにかぎ分けてしまえたのです。
たとえば、吝嗇家が家のどこかに隠した金貨の匂いだって分かってしまいます。そこに金貨を隠してあるのだって、忽ちお見通しになってしまうのでした。
そして、「毒虫」は蝶(なのだろうか? あるいは毒蛾?)に成長します。
過去の名声だけはかろうじて保っているけれど、もう力も何もなくしてしまった香水の調合士に取り入ることに成功します。
正に天職! 彼は素晴らしい香水を次々と調合していきます。
そして、それを師とした調合士の名前で売り出すことだって許します(というか、それが条件なのでしょうね)。
彼の鋭敏な嗅覚はさらにすごい「香水」を作り出すようになります。
人間の感情さえも左右してしまえるような「香水」です。
さらには、「とある」香りに魅せられてしまうのでした。
その香りを定着させるためにはどうすれば良いのか?
彼は、従順を装い、師からその技術をある程度まで学び取ります。
しかし、それでもまだあの「香り」を残すことはできない。
何という小説でしょう。
ある意味、猟奇的です。
心地よく読める本をお探しでしたらお薦めしません。
ですが、不思議な魅力をもつ作品です。
詳しくはお話しできないのですが、まぁ、なんていうことを……
物語としてのおもしろさは十分にあります。
ここまでのご紹介文を読んでピンと来たら読んでみても損はさせないと思いますよ。
「香水」/パトリック・ジュースキント
文藝春秋社
ISBN-16-310660-x c0097
013 「くらやみの速さはどれくらい」/エリザベス・ムーン
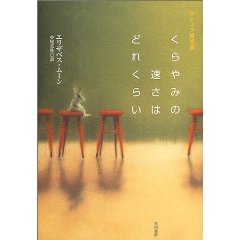 この物語の主人公は、ルウ・アレンデイルという30歳を過ぎた架空の自閉症の男性です。
この物語の主人公は、ルウ・アレンデイルという30歳を過ぎた架空の自閉症の男性です。
そして、この物語の舞台は、現在よりもちょっとだけ先の、明確には書かれていませんが、おそらく僕たちがまだ生きているであろう程度の「未来」と受け止められます。
描かれている社会環境や生活習慣は現在と異なることは全くありません。
ただ、少しだけ、おそらく現在にはないであろう医学的な技術が盛り込まれているだけです。
……私は、これまで、自閉症の方達についてほとんどまったくと言って良いほど知りませんでした。
わずかに知っていたのは、「レイン・マン」のダスティン・ホフマンの様な感じ。
私は、「レイン・、マン」すら見ていないのですけれど(評論で知っているだけです)。
それから、わずかな、本やwebで知った、「障害者」のように見えるのだけれど、ある領域については非常に優れた能力を有している場合があるということ。
そして、それはどうやら「脳」に関係しているらしいこと。
この本の冒頭に書かれている「謝辞」を読むと、作者は実際に多くの自閉症の方達と接してきた経験があるようです。
そして、この本を書くにあたって。それらの方達との接触を断ったとのこと。
それは、この作品はあくまでもフィクションであり、特定の、実在する自閉症の方をモデルにしたわけではない、しないようにするために、自分の中の記憶を不鮮明なものにするためにそうしたのだそうです。
それでも、作者との交流を求めた方達もいたそうで、そこまではさすがに断絶はしていなかったようですが。
さて、物語のあらすじをご紹介しましょう。
主人公のルウは、とある企業の「Aグループ」と呼ばれるセクションで働いている独身男性でした。
「Aグループ」というのは、自閉症の人たちばかりを集めたセクションで、彼らの精神の安定(なのだろうか?)のために、勤務中でも好きな音楽を聴けるシステムや、これも精神の安定に効果があるらしいトランポリンがあるジムや、色彩に関する効果を生み出す(様に思えたのですが)ぐるぐる回る「扇風機」のような物などを、企業の費用で備えたセクションでした。
作中で十分に解説されているわけではないので詳しくは説明できないのですが、ルウなどの自閉症の人たちは、健常人(ノーマルと作中では呼称されていますが、つまりは普通の、私たちみたいな連中です)に比して、「パターン」の認識能力に優れているのだそうです。
そのため、ルウ達は、「ノーマル」が見ただけでは分からないような、パソコンのディスプレイ上に映し出される複雑なデータを見て、そこからある「意味」を見いだす仕事をしていました(つまりは、ある種のプログラミングのような仕事なのでしょうか?)。
事実、その「Aグループ」は非常によい業績を上げていました。
ルウは、大変几帳面で、きれい好きな性格の良い、とても素直な男性でした。
自閉症の人たちは、自分が自閉症であることを(世間がそう「見ている」ことを)知っていました。
そして、実際、自分たちが、「ノーマル」の人たちと同じように振る舞えないことを自覚していて、それを「負」の要素として自覚していました。
社会は、彼らに対して、「自分は自閉症です」というカードを持たせていました。
それは、社会生活の中で、対応ができなくなったときに、そのカードを見せろということです。
そうすれば、「ノーマル」な連中は、「あぁ、自閉症なのか」と分かってくれるということです。
ルウは、「ノーマル」な人たちの言葉を理解することに苦しみます。
嫌だったら、どうして「嫌です」と言わないのだろう? どうして「考えてみましょう」などと言うのだろう(すみません、これはそういう意味ですという創作であって、原作で触れられていた例を思い出せなかったので、そういうシチュエーションのことを書きました)。
ルウは、「考えてみます」と言うのは、考えることじゃないのだろうか……と、本当に素直に悩んだりもしました。
でも、経験を経て、「ノーマル」がそういう言い方をする時は、本当は考える訳じゃないのだということを学びます。でも決して納得はしないのですよ。やっぱり、どうして、そう言うのだろうという疑問は残り続けているのでしょうね。
ルウは「ノーマル」な人たちが運営しているフェンシングのクラブに入ります。
最初はどうにもならないわけですが、徐々に腕を上げていきます。
私は、フェンシングのことは知らないので何とも言えないのですが、例のノーマルには無いルウの「パターン」認識能力が徐々にフェンシングに応用されていきます。
つまり、相手の攻撃、防御のパターンを、まるで音楽を聴いているように見切ってしまえるようになるのです。
ルウのフェンシングの腕は格段に向上し、上級者をもうならせるほどの腕前になります。
ルウはそこで、マージョリという女性と出会います。
ルウは、マージョリとのフェンシングの剣の接触に独特の感覚を覚知し、あるいはそのフェンシングを音楽の様にとらえ、それをとても心地よいものとして認識します。
また、マージョリの髪の色についても大変な魅力を感じます。ノーマルの目には、マージョリの髪は茶色にしか見えないようだけれど、もっと沢山の色がある。それが光の具合によって美しく変わる……などと覚知します。
それは、恋をしているのでしょうね……僕たち「ノーマル」の感覚としては。
ええ、ルウだって「恋」という概念は理解しています。ですが、「ノーマル」が言うところの「恋」と自分が感じている意識とは同じなのか、をはかりかねるわけです。
加えて、恋愛感情やsexのことも知識としては理解しているのですよ(自閉症というのは、この作品を読む限りにおいては、理解には何の障害もなくて、ただ、それを表現し、フィードバックする部分にトラブルがあるため、自分の知覚の検証が妨げられてしまい、その結果認知が阻害されてしまうのではないか……などと勝手なことを感じたりしました)。
だけど、恋愛やsexという意味(文字面の意味じゃなくて)を検証できなくて、ただ事実行為としてそういうことをするという観念におぞましさのような気持ちを感じたりもしていました。
ノーマルな人たちは、あんなことをすることが平気なのだろうか……って。
……あぁ、それって、私たちが初めてそういうことがどういうことかって知ったときの気持ちに近いかもしれないね。
はたまた、自閉症のエミーという女性は(おそらくルウを愛していたのでしょうね)、ルウはノーマルとつきあっている、マージョリと恋人関係にあると声高に、執拗に非難し続けます。
その感情の奥に潜む「キモチ」の切なさも……賛同はできないけれど、私なりに理解できるようにも思えました。
……あぁ、どこまで書いても良いのでしょうね。
私は、書評を書くのはあんまり向いていないような感じがします。
「良い本だったよ」っていう気持ちをお伝えしたいというのは、それはそれは沢山あって、だからここも、今までやってきているのですが、書評自体はうまくない様な気が、いつもいつもしています。
だって、この調子で書いていたら、どんどんストーリーを追ってばかりいてしまいそうですもの。
それで、ぐっとはしょることにします(下手をするとストーリー全部を書いてしまいかねないですものね)。
この後に起きること。
ルウの命が狙われるような事件が起きます。
その理由は?
ルウには全く落ち度はありません。
あぁ、人間って……て奴かも。
ルウの勤めている企業に、トンデモな上司が赴任します。
彼は、ルウ達自閉症の「Aグループ」に無駄な金が費やされていると主張し(全く外れているのですが)、「おまえらクビになるか、自閉症を治す手術のモルモットになるかどっちか選べ!」とまぁ、極端に書くとそういう汚い違法な強制をします。
もちろん、簡単に言えば、モルモットになった研究データを金にしようという魂胆なんですけれどね。
さて、ルウはどういう選択をするか……
というのが、かなーり書き過ぎとも思える下手くそなご紹介でした。
フィクションですし、設定に、今はないことも沢山あります。
自閉症の一端は知ることができるかもしれませんが、それがオーソライズされた見解であるという保障は何もありません。
ですが……、私のように、自閉症ということに対する知識が全くなかった者にとっては、「偏見」(私は、そのような気持ちは持ったことはないし、決して持ちたくはないとは思っていましたが、でも「知らない」ということは「偏見」と大差がないことなのかもしれないと感じました)を持たないように……という意味はあるように思えます。
「くらやみの速さはどれくらい?」
光の速さは分かっている。
くらやみは光が届かないところに、いつも、ある。
だから、くらやみは、光より速いのかもしれない。
光はくらやみに、追いつけない。
難しいことです。
えっと、本棚の001でご紹介した本を覚えていらっしゃいますか?
「アルジャーノンに花束を」という、私の大好きな本でした。
「くらやみの速さはどれくらい」は、アルジャーノンテイストを持った本だなっていうのが、一番短い、ご紹介文かもしれません。
「くらやみの速さはどれくらい」/エリザベス・ムーン
小尾 美佐訳 早川書房
ISBN-4-15-208603-3
012 「願い星、叶い星」/アルフレッド・ベスター
 SF(一応、そうなのだろうね)短編集です。
SF(一応、そうなのだろうね)短編集です。
著者のアルフレッド・ベスターと言えば、SF好きな方なら真っ先に思い浮かぶのが「虎よ、虎よ!」でしょう。
これはかなりヘビーな復習劇を描いた作品です。
大分以前に読んだきりなので、記憶違いもあるかもしれませんが、印象は残っていますね。
ダイナミック、かつスピーディーで、ある意味ハードボイルドな味もあり、しかも、主人公の強烈な個性でぐいぐい読ませてしまう復讐劇なのです(何せ、顔中に入れ墨を入れられてしまったという主人公なのですから)。
今、本棚から取り出して見たところ、末尾につけられた書評には「十年に一度の傑作」というタイトルがつけられていました。
確かに、各種のアワードでも高い評価を得ていたのが、「虎よ、虎よ!」でした。
で、私は、「アルフレッド・ベスター」と言えば「虎よ、虎よ!」のイメージばかりだったので、この「願い星、叶い星」を読んだ時には、「へぇ〜、こんなのも書くんだ」という、「小気味よさ」のようなものも感じました。
いや、「虎よ、虎よ!」とは相当にイメージが違うのです。
良い意味で、もっと軽く、ちょっと切なく、スピード感などは生かしたままの、まるで別の作家さんだと言われても信じてしまう位の印象でした。
そんな意味で、言えば、うまい作家さんなのでしょうね。
短編集なので、いくつかより抜きでご紹介を。
1作目は、「ごきげん目盛り」
巻末の解説を読むと、「自他共に認める短編最高傑作」だそうです。
うん、確かに、「ストーリーテリング」としてはうまいです。
あらすじは、高性能アンドロイドを手に入れた主人公が「ラッキー」と思っていたところ、こいつがとんだ食わせ物で。
億万長者も夢じゃない……はずだったのに、何でこうなるの!
ところどころで繰り返される歌詞のフレーズのような繰り返しの言葉が大変効果的。
ちょっとユーモラスにも感じてしまった作品でした。
本書のタイトルにもなった「願い星、叶い星」
子供たちの話です。
ある時、何かちょっとした違和感に気づいた一人の教師がいます。
そして、とある行動をとっていたところ、それに目をつけた悪者ギャング(みたいな印象なんだなぁ……作中ではそうではないのですけれど)。
絶体絶命のピンチに陥る教師なのですが、自分が何を探していたのかを教え、それがとてつもない富の元になり得ることを説明してギャング達を仲間に引き入れてしまいます(いや、便宜上ギャングと言っていますがそうじゃないのですよ)。
ところが……その謎を追っていたギャングの仲間が消え去ってしまいます。
その訳は?
タイトルの「願い星、叶い星」の意味は最後に分かります。
小気味よい短編SFという印象です。
「地獄は永久に」
アルフレッド・ベスターを読んで良く感じるのは、ユーモアのセンスかもしれません。
実を言うと、その「センス」は、キライじゃないけれど、それほど好きでもない、というのが正直な感想なのですが、でも、どこかに良い意味でユーモアをちらしているように感じます。
この作品は、中編と言っても良いでしょう。
とある状況から、自分が望む世界に転移できることになった数人の男女の行く末を描きます。
はい、アルフレッド・ベスターのことですから、そうそう簡単にはハッピー・エンドには持っていきませんが、バッド・エンドだって、そこにはある種のユーモアがあって、それなりにニヤっとできたりもします(そういう選択をする、自分も含めた弱い人間なのだよね……と思ったりして)。
この作品で特に面白いのは地獄に堕ちるところかもしれませんよ〜。
意表をつく舞台装置をこしらえてあります。
波長が合えば楽しく読めると思います。
「願い星、叶い星」 中村融訳編 河出書房 ISBN4−309−62185−6
「虎よ、虎よ!」 中田耕治訳 ハヤカワ文庫 ISBN4−15−010277−5
011 「水晶」/アーダベルト・シュティフター
うつくしく、やさしく、おだやかで、正直で、健気で……そんな作品です。
短編集で、いずれも鉱物の名前がつけられた「水晶」、「みかげ石」、「石灰石」、「石乳」が収められています。
別に、鉱物のお話ではないのです。
例えば、表題作の「水晶」には、水晶のことは全く出てきません。
あらすじは、隣村のおばあさんの家に遊びに行った幼い兄妹が、その帰り道に雪に降られてしまい、道を見失ってしまいます。
幼い妹を懸命に守って、何とか家への帰り道を見つけようとする兄のコンラート。
妹のザンナは、決してくさったり、弱音を吐いたりせず、兄の言葉に、いつも「そうよ、コンラート」と健気に答えます(ここは、訳の問題があるんですよね〜。原文は「ya コンラート」なのですけれど、おそらく日本人的には「うん、お兄ちゃん」という訳が近いのじゃないのかなって感じます。これが何度も繰り返し出てくるので……気になって)。
兄だって、実際の所かなり参っているのに。
そうこうしている内に、二人は道をどんどん外れてしまい、巨大な氷が立ちふさがる氷原に出てしまいます。
陽も落ちて、もうこれ以上歩けなくなり、氷の間にもぐりこみ一夜をあかす幼い兄妹です。
二人は、おばあさんが持たせてくれたパンや濃いコーヒーなどで何とか眠らずに一夜を過ごそうとします。
二人は互いのことをかばい合い、そして、何とか一夜を過ごしてまた歩き始める……そんなお話です。
他の作品もそうですが、とりたてて変わったことが語られるわけでもなく、おだやかに、静かに物語は進んでいきます。
あるいは、「みかげ石」という作品は、ちょっとしたことで母親にしかられ、しょげかえってしまった子供をなぐさめる優しいおじいさん、というお話。
優しいおじいさんに連れられて、美しい森や山が連なる道を一緒に歩いていく男の子。
おじいさんは、色んな話をしてくれます。
そうやって一日を過ごして、家に帰ってくるという、ただそれだけの話なのですが、じ〜んときてしまいます。
「石灰石」は、とても感動的なお話でした。いえ、と、言っても本当に静かに静かにお話が進んでいくだけで、ドキドキするようなクライマックスも、盛り上げるようなこともしません。
ですが、その静けさと、思いやりと、礼儀正しさと……そんな気持ちで読み進めていって、最後に「あぁ」ってため息をついてしまうような物語です。
人の善意、ひたむきさ、思いやる気持ち、そういうことを、信じられる(信じたいと思う)人でしたら、とても好きになる作品ではないかなと思います。
私が、「すごいなぁ」といつも感心してしまう、編集者の松岡正剛さんは、この本をなるべく早く子供達に読ませてあげることを推奨しています。
その気持ちはとってもよくわかるように思います。
私の大好きな本の一つです。
「水晶」/アーダベルト・シュティフター
手塚富雄 訳 岩波文庫
ISBN4-00-324223-8
010 「ルルドの群衆」/J.K.ユイスマンス
ユイスマンスだったら「さかしま」をご紹介しようかと思ったのですが、本書もなかなか強烈だったので、今回は「ルルドの群衆」を。
さて、これはキリスト教に深く根ざした作品です。
世界の色々な場所に聖母マリアが降臨したという伝説は数多く残っています。
ルルドもそんな場所の一つです。
聖母マリアが貧困で純朴な少女の前に現れたという伝説が残っています。
そこで、マリアは信仰を説き、その言葉に耳を傾けた者の病苦を癒したそうです。
泉がマリアの言葉により発見され、その泉の水が癒しの力を持っていたということです。
この話が各地に伝わって以降、世界各国から巡礼団がルルドを目指すようになりました。
作者ユイスマンスがそのありさまを描いたのが本書です。
それはそれは、重病人が長旅で疲弊しつくしてルルドに到着します。
世界中からそのような人達が集まっているので、ルルドの街はごった返しています。
重病人ばかりではなく、物見遊山の様な者達も押し掛けます。
ルルドの街では、この様な人達を目当てにした、安物の信仰グッズを売る店などがひしめき合います。
さて、問題の重病人ですが、時代が時代ですから、今なら治癒するであろう病気も当時はどうにもならない死に至る病として描かれています。もちろん、ハンセン氏病などのことも描かれますし、何の病気なのか分からないのですが、非常に醜悪に描写する部分も不断に出てきます。
瀕死の状態で、膿を垂れ流しながら、異形とさえ言えるように崩れていく身体を持った病人達。
それが、奇跡の泉と信じられている不潔な水たまりに投げ入れられます。
その水のよどみには、病人達の身体から流れ出た血や膿、あるいは脱脂綿などで汚れきっています。
もちろん、ほとんどの者は治癒するわけもなく、絶望にかられて、滞在期限を過ぎて帰っていくのでした。
ですが、中に、どう考えても奇跡としか思えない回復を示した病人がいたとのことです。
ほとんど瞬間的にとてつもない症状が改善してしまう者。
ルルドには科学的にそのような例を検証するための施設があり、医師がそのような奇跡を体験したと名乗り出た者を診察し、その後の状況についても調査をしているのでした。
もちろん、「嘘」も沢山あり、かかってもいない病にかかったと称してそれが治ったのだと主張する者もいましたが、その辺りは見極めているようです。
しかし、この医師達にもどうしても説明がつけられない奇跡があるのだと書かれています。
では、これはキリスト教を信じる信仰の力によって癒されたのか?
ユイスマンスはそれを否定します。信仰を持ちようもない幼児が癒された例などを引き合いに出しながら。
では、一体この現象は(事実あったとしなのなら)どう理解すれば良いのでしょうか?
ルルドのことを描いた作品は以前から多数ありました。
エミール・ゾラもその様な作品を描いた一人でした。
ゾラはルルドの奇跡については否定的で、メンタルな影響等の理由を提示し、奇跡ではないとの論陣を張ったそうです。
さて、ここからが微妙なところ。
一体、ユイスマンスはどのような立場に立っていたのでしょうか。
表面的には、理性的、冷静な分析を凝らし、その結果、奇跡はあるのだと結論づけているように読めます。
そして、(この辺の読み解きが難しいのですが)非常に敬虔な信仰的態度も見せます。
文字通り受け止めればその通りなのですが、本当に? と思ってしまったり。
解説を読んでも、この作品はユイスマンスの晩年の作品であり、ユイスマンス自身重病に犯されつつ書き上げた作品だということです。
ですから、あの「さかしま」を書いたユイスマンスも神を信じていたのだと解説されていたりもします。
……そうなのだろうか……
まあ、そんなことは放っておいて、語られる、ある意味非常に残酷で辛い描写を経ながら、一体どういうことなのだろうかと思いをめぐらせてみるだけでも価値はあると思いました。
読んでみて、私は結構ずっしり来ました。
こんな本も読んでみてはいかがでしょうか?
「ルルドの群衆」/J.K.ユイスマンス
田辺保 訳 国書刊行会
ISBN4-336-03525-3
009 「エンディミオン」、「エンディミオンの覚醒」/ダン・シモンズ

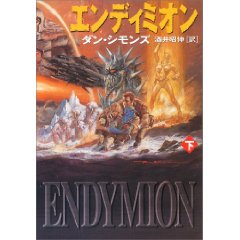
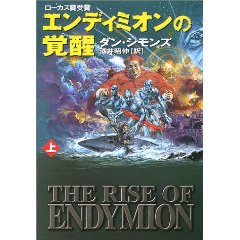
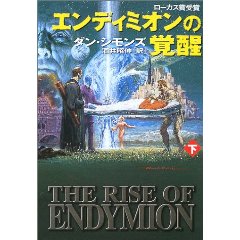
お話は、前にご紹介した「ハイペリオン」の続編です。はい、まだまだ続きます。
あのご紹介はほんのさわりだけ。
何も核心には触れていない(触れないようにして書いた)ご紹介でした。
……どなたか、読んで下さった方はいらっしゃいましたでしょうか?
くどいようですが、とても面白いです。掛け値なしに。
ですから、よろしかったら、是非、ご一読を。
これからご紹介するのはその続編です。
続編……と言っても、どれだけ長い月日が経ってしまったことか。
長大な……気が遠くなるようなスケール
この作品の時空のスケールは「とんでも」です。
もう、気が遠くなり、くらくらしそうな時空を駆け巡ります。
特に、この「エンディミオン」シリーズに入ってからはそうでしょう。
謎は徐々に解き明かされます。
「エンディミオン」シリーズの始まりは、12歳の女の子の救出劇からです。
……前の……「ハイペリオン」を読んで下さった方はお分かりだと思いますが、「ブローン・レイミア」という、とても魅力的な、強い女性「探偵」が出てきましたよね?
ある時、ある時空で、……それは例の時の墓標なのですが、決定的な時間に、その12歳の娘が現れるのです。
「7人の巡礼」の一人、マーティン・サイリナースを覚えていますか?……詩人です。
この世界を詩に託して書き続けた、偉人? いや、むしろ変人。 でも、とある理由で、「世界」の真実をちょっとだけかいま見た人。
いや、それでも言葉が足りないかも……(ハイペリオンを読んだ人はもっと言いたい?)でも、良い……ひとだった……んだろうね。
もう、彼は、超超よぼよぼのおじいさんなのです(パウルセン処理という、人工的な延命治療を受け続けて生きながらえています、それも気が遠くなる程の時間を。その選択自体も考えさせられるものもあったりします)。
彼が見た「ビジョン」がありました。
それは、このすべての世界にかかわること。
そのために……ものすごくはしょりますが、ロール・エンディミオンという若者に全てを託します。
我が儘なこの老人は、不可能としか思えない沢山のミッションをエンディミオンに与えます。
そもそも、エンディミオンは、もう死んで当たり前の状態で救い出されたわけです。
もう、何でもやったろう!的な…… ある意味、自暴自棄だったのかしらん?
この辺の心理の描き方はかなり「雑」ではあるのですけれど、そんなことにはこだわらないのが「吉」です。
彼に与えられたミッションは沢山ですが、とにかく第一に、とある時間に、時の墓標に現れる12歳の「アイネイアー」という女の子を守れ!です。
守れったって、そりゃ無理的状況です。
「パクス」……まぁ、未来のキリスト教が支配している強大な社会……いえ、「ハイペリオン」が崩壊した……あ! 言っちゃった! そう、前にご紹介した「テクノ・コア」の燦然たる世界、ハイペリオンは既に消え去ってしまっているのです。それに代わったのが「パクス」です。
で、アイネイアーのことはパクスも当然察知しています。
パクスにとっては、未来予測としては、アイネイアーは絶対的に排除しなければならない「要素」なのでした。
そのため、アイネイアー……たかだか12歳の女の子ですよ、を死滅させるために大量の精強部隊を幾重にも巡らせます。
見つけ次第……殺すようにと。
それを救い出せ!との盟約をマーティン・サイリナースと交わしてしまったエンディミオン!
これって……ラブ・ストーリー?
読んでいて、最初は、この「小娘」にはあんまり感情移入ができなくて、魅力なんてまるで感じませんでした。
つないだ気持ちは「冒険物語」かも。それ自体とってもエキサイティングで面白かったですよ。
絶体絶命のピンチを乗り切っちゃう爽快さが各所に出てきます。
そう、ロール・エンディミオン、アイネイアー、そしてアンドロイドのA.ベティックの長い旅が始まります(ベティックのAはアンドロイドという呼称なんでしょうね。人間には「M」がつきます。「M.エンディミオン」とかね)。
A.ベティックがまた良いんだぁ。 後々、泣いてしまうようなエピソードも山盛りです。
で、問題の「アイネイアー」です。
彼女は、この世界を変える存在として生まれてきた……のでしょうね(考えてみれば、本当に過酷な宿命を背負って生まれてきたとしか言いようがありません)。
「ウィルス」だって、パクスからは言われます。
殲滅すべき対象だと。
で、すんごい艦隊とかがたかが一人の「小娘」を殺すために出てきちゃったりするわけです。
もう、絶体絶命ですよ。
そのピンチを、その時なりにしのいで、しのいで。
時空のマジックもあります。
エンディミオンも相当にぼろぼろにされてます。
生死の境をさまようことも度々。
「復活漕」という、作品世界の中の最先端医療機器でよみがえることもしばしば(でも時間もかかります)。
そして、時間軸をぐちゃぐちゃにするような超高速移動。
そうなんですよ、光速を越えてしまうと時間軸はずれてしまうのですね。
で、この作品でも、時間軸の呼び方は色々出て来ざるをえないのです(「○○標準時間で言えば……」とかね)。
エンディミオンは、無茶苦茶な時間軸を放浪しなければならなくなって、果てしない時間の果てにアイネイアーと再見できます。
この後がぐっときちゃうんだなぁ。
最初に読んでいて、ほとんど好きじゃなかったアイネイアーなのですが、この後はとても魅力的に感じられました。
いえ、別に素晴らしい美人のように描写されていたわけでもないし、「女性」として、美しいとかその他の「女性的魅力」?が描かれていた訳でもないのです。
ただ、ただ、理由は一つだけ。
アイネイアーは、ただ一人の人としてエンディミオンを愛していたのです。
その気持ちはとても純粋で。
その、気持ちに泣けてしまいました。
エンディミオンだって、もうぼろぼろになりながらアイネイアーを守り続けます。
最初は愛情なんてことじゃなくて、ただただサイリナースと交わした盟約のためだけだったのですが、最後には心からアイネイアーを愛します。
「愛する」っていう気持ちをすごくピュアに書いている作家さんです。
ちょっと照れ恥ずかしくなってしまうような描写だって……素敵じゃないですか!
これは「長大なSF小説」というジャンルに入れられる作品だと思うのですが、でも、読みようによっては「せか中」以上にピュアな恋愛小説でもあるんですよ〜。
それは、それは、本当にピュアで。
「愛している。ずっと。」 という単純な言葉の重さに何度も涙が出てしまいました。
エンディミオンは、決してヒーロー的には描かれていません。
どうにもならなくて、ぎりぎりの所で何とか頑張っちゃうみたいな(あ、でも、活躍する場面もありますよ)。
彼が死闘を続ける中で、ふっと思う感情の一つにこういうのがあります。
これは加速する時間の中で、強大な敵と出会い、まるでコマ落としの様に、一つの動作ごとに想いがめぐるような描写です。
「まるで、チェスのようだ。 僕はアイネイアーを守るためにここにいるのに…… 僕は、ポーン(兵卒、チェスで言えば一番弱い駒。将棋の「歩」のようなものです)だ。だから、僕は死んでも良い。いや、死んでアイネイアーを守らなきゃ!」(これは原文じゃないです。私の中に残った言葉と理解して下さい)。
そう思って、残酷な程に描かれるダメージを受けつつ守りきります。ただ一人の愛する人を。
エンディミオンは、スーパーヒーローでもなんでもないのです。
そして、アイネイアー(彼女の背負ってしまった運命のなんと過酷なことでしょう)も、エンディミオンを深く愛します。
あぁ…… なんという感情なんでしょうね。
「愛してる」、「大好き」っていう気持ちの貴さ、慈しみの気持ち……そんなのになんども涙が出てしまいました。
本筋はとてもよくできたSFです。
それ自体、とっても面白いです。
でも、最後に、心の中に残った気持ちは、「愛してる」って、心から言える「ひとの気持ち」の大切さのように……感じました。
こんな要素も盛りだくさんです。
興味をもっていただけたら、是非ご一読を(と、いってもすっごく長いお話ですけれど)。
「エンディミオン(上)」 ISBN4-15-011389-0
「エンディミオン(下)」 ISBN4-15-011390-4
「エンディミオンの覚醒(上)」 ISBN4-15-011423-4
「エンディミオンの覚醒(下)」 ISBN4-15-011424-2
いずれもダン・シモンズ 酒井 昭伸 訳 ハヤカワ文庫
008 「春と修羅」/宮沢賢治
宮沢賢治です。
結構、好きなんですよ。
その中の詩集ですが、「春と修羅」をe-bookで読みました。
「紙」の本を買っていないので、表紙はなしね。
う〜ん、深いなぁ。
通勤の時間に、Clieを使ってe-bookを読んでいるのですが、「春と修羅」、中盤にさしかかった時に出てきた詩を読んで、泣いてしまいそうになりました。
「永訣の詩(ありゃ?「朝」だっけか?)です。
妹さんがもう、間もなく亡くなってしまいそうな時の詩です。
言葉のひとつ、ひとつが「立って」いて、一行読むたびに涙が出そうになりました。
これ、確か、小学校か中学校の時、教科書ベースで読んだことがあった記憶です。
「あめゆき……」のところ、はっきり記憶していますもの。
やりきれなくなるような想いも感じました。
連作なのでしょうか。その後の賢治の想いも詩に託されて書かれています。
あぁ、なんて純粋なのでしょう。
通勤途中に、心が洗われたような詩でした。
よろしかったら、是非、読んでみてね。
007 「薔薇の名前」/ウンベルト・エーコ
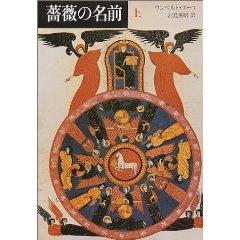
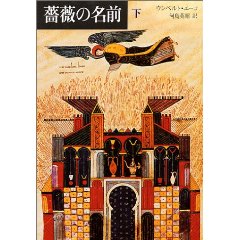
今回ご紹介するのは「薔薇の名前」です。傑作の呼び声高い作品だし、ショーン・コネリー主演で映画化もされていますので、ご存じの方も多いと思います。
物語は中世イタリアの僧院を舞台にします。
この当時、キリスト教は様々な宗派に分派しており、皇帝と教皇も対立していました。それぞれの思惑から教義が違う宗派が協力し合ったり、あるいはほとんど同じような教義なのに相手を異端呼ばわりしたり。
そんな状況下でアヴィニョンにいる教皇側は、皇帝側についているフランチェスコ会の宗主をアヴィニョンに召喚しようとします。
そんなところへのこのこ出かけて行こうものなら「異端」と糾弾されて殺されかねません。かといって教皇の命に背くわけにもいかず、フランチェスコ会は、教皇派と事前会談を行い、宗主の命の保障を取り付けることにします。
この密使を帯びて事前会談の場所となるこの作品の舞台となる僧院に派遣されたのが頭脳明晰と誉れの高いフランチェスコ会修道士のウィリアムでした(ショーン・コネリーが演じた役ですね)。
ウィリアム修道士は、弟子でありベネディクト派の見習修道士であるアドソを連れて僧院を訪れました。
この僧院にはキリスト教世界随一とも言える文書館があり、当時の知識の集大成とも言える膨大な写本が保管されていました。文書館には「写字室」があり、そこでは沢山の写字生が世界各地から集めてきた貴重な本の写本を作り、美麗な細密画を書き加える作業をしていました。修道僧達は写字室に入ることはできますが、その上階にある書庫に無断で立ち入ることは禁じられており、書庫に出入りできるのは文書官長とその補佐のみでした。この辺の設定だけでも本が好きな人だったらわくわくです。
ところが、ウィリアム修道士達が到着して間もなく、文書館そばの崖下に転落して死亡している修道僧が発見されました。
文書館の窓は閉ざされており、またかなり高い位置についている窓でしたので、その窓から崖下に大の男を放り投げるのはかなり困難なことの様に思われました。
教皇派との会談を目前に控えた僧院長は、会談の前に事件を解決する必要に迫られます(そうでもしないことには、殺人者が徘徊している僧院は安全を確保できない等の理由で、教皇派に僧院の管理権の一部を剥奪されかねません)。
とは言え、僧院の中に殺人者がいるなどという不名誉な事態は公にすることもできないため、白羽の矢を立てたのがウィリアム修道士だったというわけです。僧院長から事件の調査を命じられたウィリアム修道士はアドソと共に調査に乗り出すのですが、またまた死体が発見されます。今度の被害者は厨房の近くに置いてあった豚の血をためた(後にソーセージを作るのです)桶の中に真っ逆さまに突き立てられ絶命している修道僧です。しかも、文書館から死体が発見された場所までは雪の上に重く沈んだ足跡と何かを引きずったような後が見つかります。またまた文書館……
というわけで、ウィリアム修道士とアドソの調査が続くのですが、迷宮の様な文書館の内部や、様々な仕掛け。また、そもそもそこに納められている本自体の魅力。そして夜の僧院で起こる様々な事件。
中世イタリアの僧院というちょっと陰鬱で暗い場所を舞台にしていることもあり、一種独特の雰囲気がある作品です。
そしてまた、さまざまに語られる蘊蓄の数々。
う〜ん、それだけでも十分に面白いのですが。
作者のウンベルト・エーコは世界的な記号論理学の教授でもあり、その膨大な知識と論理的やりとりは大変魅力的です。
推理小説として読んでももちろん面白いですし、中世の僧院を巡るファンタジーというかサスペンス物として読んでも面白いです。
写真でお分かりの通り、上下巻であり、しかも結構細かい字でびっしりと書かれていますのでなかなかボリュームはありますが、傑作ですので、機会があったら是非挑戦してみてください。
「薔薇の名前」/ウンベルト・エーコ
河島 英昭訳 東京創元社
ISBN4-488-01351-1(上巻)、ISBN4-488-01352-X(下巻)
006 「ハイペリオン」「ハイペリオンの没落」/ダン・シモンズ
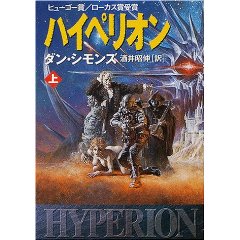
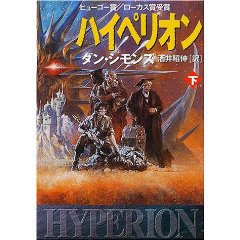
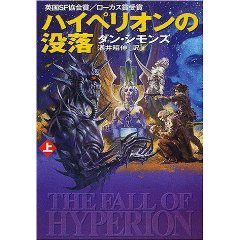

面白い! 相当に力を入れてお勧めできる作品です。
時は28世紀。地球から巣立った人類は広大な宇宙をつなぐ連邦政府を樹立します。
超高速飛行でも何十年もかかるような遠い星さえ連邦傘下に組み入れています。
それを可能にした技術は「転移ゲート」と呼ばれる、要はどこでもドアですな。
これにより、何光年も離れた星でも、ドアを通るだけで瞬間的に移動できてしまうのでした。
そして、これらの超高々度の科学を維持しているのは「テクノコア」と呼ばれるハイパーコンピュータシステムです。
超精度で未来をも予測できるコンピュータシステムなのですが、一つだけ予測不能の星がありました。その予測不可能さ故に連邦への編入がためらわれている星。
それがハイペリオン。
その不確定要素が連邦自体を危機に陥れます。
その星には時間を超越して未来から送り込まれた「時の墓標」が立ち並び、不死身とも思える刃の突き出た4本の手を持ち、体中から鋭い棘を突き出し、真っ赤な切り子の目をした「シュライク」という……なんだろうこれは。殺人のための存在のような物を送り出します。
その恐怖が「シュライク教」という宗教まで確立してしまうほど。
そしてもう一つの勢力アウスター。
連邦に敵対する勢力、と思われるのですが……
物語はこのような背景(いや、実際はもっと複雑)のもと展開されます。
とにかく、連邦の安定のためにはハイペリオンにある不安定要素、「時の墓標」の謎を解明しなければなりません。
はたまた、既に伝説となっているシュライクとの対峙。
各勢力の思惑や、それぞれの個人の抱える「痛み」とが折り重なり、伝説の「巡礼」をハイペリオンに送ることとなりました。
「巡礼」は素数からなる人数で構成されなければならず、険しいハイペリオンの地形を渡り、時の墓標に詣でます。
そこでシュライクに対峙したとき、願いが叶うという伝説です。
しかし、過去何度となく送り出された巡礼達は帰らぬ人となっています。その行方さえどうなっていることか。
連邦はすでにアウスターとの極度の緊張状況にあり、戦争間近です。
「巡礼」もこれが最後のものとなるでしょう。
その最後の巡礼に選ばれた7人の男女。
おのおのがハイペリオンにどうしても行かなければならないと願う過去を引きずりながら……
とにかく「お腹一杯」という感じの作品です。
ざっとあらすじの様なことを書いてみましたが到底書ききれません。
設定に使われているSFの要素だけでも、基本的なSFアイテムは全て盛り込んであるような豪華さ。
普通はこんなことすると陳腐な作品になってしまうのですが、それがそうはなりません。
何という作者の力量でしょう。
筆も冴えます。
前半は、巡礼に参加した7人の男女のエピソードが語られます。
その一つだけでも十分に一冊の本が書けるくらいの密度なんですよ。
どのエピソードも素晴らしい!
しかもヴァリエーションに富んでいて、しっとりと泣けてしまうような穏やかな話もあれば、スピードとサスペンスに満ちた緊張した展開もあり、はたまた非常に良質のSF要素満載のものもありで、それがどれもしっかりと描かれています。
そして絡み合う7本の糸。
はぁ…… どうしてこんな作品が書けたのでしょう!
ハヤカワ書房主催の「1990年SFベスト」ではぶっちぎりの第1位。
「本の雑誌」主催のあらゆる本からベストを選出する「1990年代」でも堂々の第3位。
それだけ熱狂的に支持される理由は読めば分かります(納得!)。
とにかく、この世に生を受けたならこれを読まずして終わるなかれと言いたくなるようなすごい作品です。
長いです。
どちらも上下巻ですし。しかもそれなりに厚いです。
でも、是非ご一読を。
騙されたと思って読んでみてください。決して後悔はさせませんってば!
…… 実はね、このさらなる続編「エンディミオン」シリーズがあるのだよ。
私はこれからチャレンジなんだけど、実はこれが一番面白いという話もあったりして。
お楽しみは続くのだ!
「ハイペリオン上」 ISBN-15-011333-5
「ハイペリオン下」 ISBN-15-011334-3
「ハイペリオンの没落上」 ISBN4-15-011348-3
「ハイペリオンの没落下」 ISBN4-15-011349-1
いずれもダン・シモンズ著 酒井昭伸訳 ハヤカワ文庫
005 「ダ・ヴィンチ・コード」/ダン・ブラウン
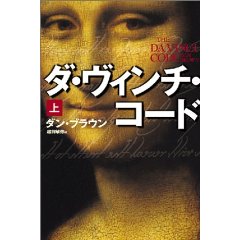
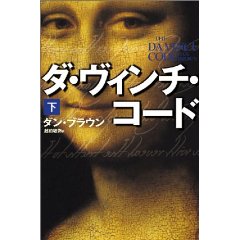
表紙を見てもお分かりのとおり、レオナルド・ダ・ヴィンチにも関係してたりするお話です。
「シオン修道会」という組織があります。
もう歴史上連綿と続いている古い組織で、歴史上の偉人(ダ・ヴィンチもね)が多数関わっていたりする組織です(事実とも言われています)。
「フリー・メイソン」は、それは本当にあるようです。
元々は石工達のギルド組織だったんですけれど、今では社会の上層部の方達が加盟している…なんでしょうねぇ、取りあえず表向きは同好の士の集まりみたいになっていますが…。
さて、その組織は、宗教上の教義から、ひとつの宗教的信念を持っているのですが、それがとあるとんでもない秘密を持っていたのです。
もう、歴史をひっくり返してしまうほどの凄いことです。
一方、やはりキリスト教の一つの派なのですが、「オプス・デイ」という、超強力な組織があります。
ある意味、純粋な考え方なのでしょうが、上級になると肉体的苦痛を修行として与えたりして、私的にはだめ〜な組織なんですけどね。
で、この組織が「シオン修道会」を阻止にかかります。 ことがことだけにもう手段を選びません。
そこには複雑なお話もからむのですが、その犠牲者の一人がソニエールというルーブル美術館の館長でした。
ソニエールの死体は、それはそれは異常な状態でした。
自ら作ったダイイング・メッセージを体で表していたのです(何と、全裸で…それには意味があります)。
そこに巻き込まれてしまうラングドンという図象学の学者先生。
その日、ソニエールから会いたいというメッセージをもらっており(一度も会ったことなかったんですけどね)、しかも、ダイイング・メッセージには「P.S.ラングドンを探せ」とまで書かれているじゃないですか!
そりゃ警察に疑われます。
でも、ラングドンは犯人じゃないんですよ。
絶体絶命のピンチに救いに入った一人の女性。
これがまた、運命の……
彼女は警察組織の職員で、暗号解読を専門にしています。 え〜い! 書いちゃえ、ソニエールの孫娘なんですよぉ!
彼女は、ソニエールによってそこに(結果的に)呼ばれたんですね〜。
そう、これは暗号をめぐるサスペンスなんです。
ソニエールは必死の思いで幾重にも張り巡らされた暗号を残します。
その謎解きをして真実にたどり着かなければ!
暗号の専門家でもあるソニエールの孫娘と、図象学(これも読み解くのは暗号みたいなもんです)の教授。
迫り来る刺客と警察の手。
「シオン修道会」、「オプス・デイ」、英仏警察と入り乱れての探索劇が展開されます。
途中に出てくる暗号用の道具に「クリプテックス」というものがあります。
筒状の道具なのですが、中に大切な知らせるべき事柄が書かれたパピルスが入っています。
その円筒を開けるためには、周囲に作られている文字盤(数字を合わせる鍵みたいなものです)を正しく合わせなければなりません。
これを無視して円筒を引っこ抜くと、中に酸が入っていて、大切な情報が書かれたパピルスは解けて無くなってしまいます。
これが後半の大きな謎解きに使われています。
とにかく、謎の一つ一つが濃いんですよね〜。
宗教史、美術史、世界の歴史そんなことにまで絡むようなとんでもな謎が展開されます。
おっと! その辺の知識がなくても全然大丈夫ですよ。
主人公の女性も、暗号の専門家ではありますが、その辺は素人なので、自然と分かるように解説されていきます。
良質のサスペンスです。
とにかく面白いものを読みた〜いという時にお勧めかな。
「ダ・ヴィンチ・コード」/ダン・ブラウン
越前 敏弥訳 角川文庫
ISBN4-04-791474-6(上)、ISBN4-04-791475-6(下)
004 「あなたの人生の物語」/テッド・チャン
 SFです。短編集なんですけど、すごくお話が面白いです。最初に収録されているのは「バビロンの塔」という作品。
SFです。短編集なんですけど、すごくお話が面白いです。最初に収録されているのは「バビロンの塔」という作品。
石工が大きな都に集められます。その都には天まで届くような大きな大きな塔があって、その最先端でさらに塔を伸ばすための仕事をするために集められたのです。
塔のてっぺんまで上る間の情景も、それはそれは不思議な物です。雲を越え、星を越え…
そうしてたどりついた塔のてっぺんで、天に穴を開けたらどうなるの?
そんなお話しでした。
「七十二文字」
昔、昔、言葉が力を持っていたころのお話です。
言葉って、本来とっても強い力を持っているのですよ。
その、言葉の力を「名辞」という、何だろうね、護符のような、あるいは今風に言うとプログラムを入れたディスクのような…そんなものに託して物を動かしたりすることができる世界を描いています。
たとえば……「大好き」という言葉って、本当にその気持ちがこもっていれば、それはそれは、重い、それこそ世界を動かすかもしれない位重い言葉なんですよね…なんてことを(ストーリーとは全然関係ないけど)思ったりした作品でした。
「地獄とは神の不在なり」
天使が降臨する場面を思い浮かべてください。おそらく、その場面は幸せに満ちた安らぐような場面でしょう?
ところが、そうじゃなかったんです。
実際に、天使は降臨しました。そして、多くの人が救われました。でも、その降臨の際には爆風が起こったり、稲妻が落ちたりもしました。
そして、その爆風などで、理不尽に亡くなってしまう人も出ていたんです。
天使が降臨したために、最愛の妻を亡くしてしまった夫の物語です。
何で?……って思ってしまいます。そりゃ、天使のために救われる人だっているでしょうけれど、どうして私の妻が召されなければならないの?
そんな気持ちを軸にした、ぐっとくる短編です。
テッド・チャンの作品はこれが初めてでしたが、本当にうまい人だなぁって感じました。
本のタイトルになっている短編、「あなたの人生の物語」も秀逸です。
これも、言葉ということを考えさせられるお話です。そして、我が子への溢れるような愛情を抱いた母親の気持ちのお話です。
「あなたの人生の物語」/テッド・チャン
浅倉 久志訳 ハヤカワ文庫
ISBN4-45-011458-7
003 「フェルマーの最終定理」/サイモン・シン
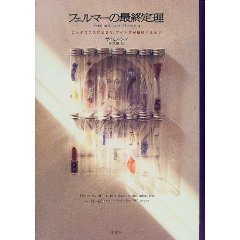 X^2(Xの二乗)+Y^2(Yの二乗) = Z^2(Zの二乗)
X^2(Xの二乗)+Y^2(Yの二乗) = Z^2(Zの二乗)
これは中学生の頃習ったピタゴラスの定理ですよね。
「直角三角形の斜辺(Z)の二乗は、他の2辺(X、Y)の二乗の和に等しい」って奴。
じゃあ、三乗以上にしたら?
これが「フェルマーの最終定理」のとっかかりです。
素人数学者(つまり、数学を生業とはしていなかったという意味でですが)のフェルマーは、沢山の数学の業績を残しています。
彼が著した本の中には素晴らしい定理が山と盛り込まれていました。
しかし、悪いことに、かれはその証明を書いていないことが多かったのだそうです。
「最終定理」もその一つ。
「X^n(Xのn乗) + Y^n(Yのn乗) = Z^n(Zのn乗)
この方程式は、nが2より大きい場合には整数解を持たない。」
極めて単純なこいつが、「フェルマーの最終定理」というものです。
フェルマーは、この定理を証明できた! と書き残したのですが、その証明部分は全く記述されていませんでした。
その後、約300年間にわたって、世界中の名だたる大数学者達がこの最終定理の証明をしようと挑んできましたが、ことごとく失敗!
時は流れて1993年6月23日。 場所はケンブリッジ大学。
アンドリュー・ワイルズという若き数学者が、まさにこの「最終定理」を制覇すべく、聴講に集まった沢山の数学者の前で黒板に数式を書き続けていました。
…… 「これで終わりにしたいと思います。」
解けたのです!
300年間に渡って、きら星のごとき大数学者達が挑んでもことごとく敗れ去ったあの「最終定理」が。
本作は、フェルマーの最終定理が解き明かされるまでの歩みを描いた作品です。
「え゛〜 数学の話なんて難しくって」なんて言いなさるな。
これは、ある種の推理小説でもあり、良質のドキュメンタリーでもあり、はたまたとても分かりやすい数学史の本でもあるのですから。
つい最近、本当につい最近解明された「フェルマーの最終定理」について、非常に分かりやすく、しかも面白く綴っているのが本書です。
作者はBBCのドキュメンタリー番組も手がけたそうで、その手法も見事に生かされています。
ええ、私だって高等数学なんて分かりません。
でも、分からなくても良いんです。少しだけ考えながら、素直に読んでいけば、「知的興奮」を味わえることは間違いないと思っているのですよ〜。
ワイルズの最初の証明は、実は失敗していたことも後に判明します。
その時のワイルズの苦悩の様な人間くさい話も沢山あります。
でも、ワイルズは指摘された問題点をも見事克服して完全な証明を達成するのです。
あぁ、何て素晴らしいんでしょう!
実はさらなる謎もあるのです。
ワイルズが見事に証明した手法は、実はフェルマーの時代には絶対に知られようも無かったテクニックを駆使してのものでした。
そのテクニックが生み出されるまでに、ものすごい数学の発展が必要だったのです。
その発展には日本の数学者も寄与しているのですよ!
ですから、フェルマーが本当に「最終定理」を証明できたとしても、その手法はワイルズとは違った手法であったはずです。
その意味では、ワイルズといえども、フェルマーの証明を再現できているわけではないのです。
ここで謎が登場します。
「フェルマーは本当に証明できていたのか?」
それは、フェルマーの誤解だったという考え方ももちろん強くあります。
結果的に、フェルマーの最終定理は正しいことが証明されましたが、フェルマーが成し遂げたと当時考えていた証明は不完全なものでしかなかったのだという説ですね。
他方、いや、フェルマーは証明できたのだと信じている方も沢山いらっしゃいます。
そういう数学者の中には、フェルマーが生きていた時代に使うことが可能だった数学的テクニックだけを使って最終定理を証明しようと今でも頑張っている方がいらっしゃるそうです。
数学…と聞いて毛嫌いしないでくださいね。
確かに数式は出てきます。でも分からなかったら飛ばしてしまっても良いのです(全然問題ありません)。
私だって分からない数式は沢山ありました。でもこの作品のおもしろさは全く損なわれることはありません。
分からないなりにちょっと考えてみるのもとても楽しいことです。
本書は、とても素晴らしい作品です。
作者のサイモン・シンは、豊富な素養に裏付けられた上で、ふつーの人達にも分かるように楽しく説明してくれています。
彼の著作の「暗号解読」というのも読みましたが、これも良書!
良質の「知的興奮」がそこにはあります。
毛嫌いしないで読んでみても絶対損はないですよ〜というオススメの一冊でした。
「フェルマーの最終定理」/サイモン・シン
青木 薫訳 新潮社
ISBN4-10-539301-4
002 「シーラという子」/トリイ・L・ヘイデン
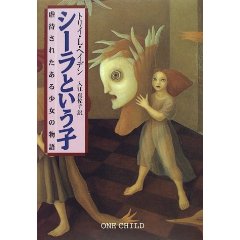 子供に火をつけてしまった6才の女の子……というところから物語は始まります。
子供に火をつけてしまった6才の女の子……というところから物語は始まります。
主人公はシーラという6才の女の子。
アル中の父親と季節労働者のキャンプで生活しています。
ある日、近所に住む子供を連れ出し、火をつけてしまうという事件を犯し、警察に捕まります。
彼女は精神病院に収容されることになるのですが、どこの施設も満杯。それで、作者(ノン・フィクションだそうです。作者は教育心理学者で特殊学級を受け持っていました。)のクラスに取りあえず入れられることになりました。
シーラはとても不潔で反抗的で、そして何かにとてもおびえているようでした。
作者はシーラに色々なことを教えようとしますが、どんなテキストを用意しても破って捨ててしまうような子供でした。
シーラの……おそらく恐怖が、他の子供達にも伝染して、教室はパニックになったりもします。
でも、作者はシーラの心の中にある、とても素晴らしい知性のきらめきに気付きます。
さあ、そこからが忍耐です。
作者は本当に根気強くシーラと接していきます。
シーラも、自分のことを愛してくれる人がいるということに気付いて、徐々に心を開いていきます。
シーラは児童虐待の被害者だったんです。満足な教育を受けられなかったばかりではなく、すさんだ家庭で、ひどい仕打ちを物心ついたころからずっと受け続けていた子供。
作者がシーラに「星の王子様」を読んであげるところが印象的でした。
…… 王子がキツネに「友達になって」って言います。でも、キツネは「「君に飼い慣らされているわけじゃないから、友達にはなれないよ」って答えます。
キツネ:「人間っていうものは、この大切なことを忘れているんだよ。だけど、あんたは、このことを忘れちゃいけない。めんどうみたあいてには、いつまでも責任があるんだ。まもらなきゃいけないんだよ。バラの花との約束をね…」
このお話を聞いていたシーラが言います。
「あたしもトリイを少しは飼い慣らした。そう? トリイはわたしを飼い慣らし、あたしもトリイを飼い慣らした。だから、あたしもトリイにシェキニン(言葉がまだ十分ではなく「責任」と言えません)がある。 そう?」
「飼い慣らした責任」です……
その後、シーラはどんどん素敵な女の子に成長していきます。
シーラが成長するということは、周りの人達も成長するということです。
作者も父親も、シーラと共にいた人達は、みんな成長していきました。
父親も、ちょっとだけお酒を控えて、安っぽいながらもちゃんとしたスーツを着てシーラに会いにいったりもします。
あぁ、でも、人間って奴は……
叔父が幼いシーラを強姦してしまいます。
ひどく傷つき、また元に戻ろうとしてしまうシーラ……
その後、作者が転任するエピソードがあります。
シーラは、「飼い慣らした責任がある」と言って、作者を非難します。
そう、愛情に飢えているのですよね。
ご紹介はここまで。
これも、読みながら何度も泣いてしまった作品でした。
続編も出ています。
興味をお持ちになったら、まず、この1冊から。
「シーラという子」/トリイ・L・ヘイデン
入江 真佐子訳 早川書房
ISBN-15-207999-1
001 「アルジャーノンに花束を」/ダニエル・キイス
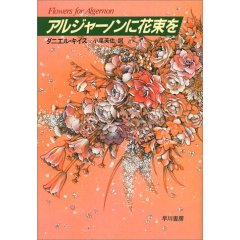 アルジャーノンというのははつかねずみの名前です。 脳にとある特殊な手術を施された実験体なのですが、その手術のために驚異的な知性の発達が起こりました。 この実験をした科学者達は、次に人間にこの手術を試みることにします。
アルジャーノンというのははつかねずみの名前です。 脳にとある特殊な手術を施された実験体なのですが、その手術のために驚異的な知性の発達が起こりました。 この実験をした科学者達は、次に人間にこの手術を試みることにします。
さて、ここはとある町のパン屋さん。主人公のチャーリィは精白の少年です。彼は周囲に満ちている人間のいやらしさや悪意さえも、善意に解釈し、彼なりに懸命に生きていました。
ただ……おそらく自分はみんなのように賢くはないのだということを、彼なりに感じつつ。
ところがある日、科学者達はチャーリィに例の脳の手術を受けてみないかともちかけます。
モルモット……ですね。
チャーリィはみんなのように賢くなれるのだと思い、喜んで手術を受けます。
この物語はチャーリィの一人称独白のスタイルで進みます。
物語の初めの方は、チャーリィの書く文章は拙く、たどたどしく、間違いだらけのとても読みにくい文章です。
しかし、そのうち、チャーリィにも変化が現れます。
手術の結果、チャーリィの頭脳も飛躍的に成長を始めるのです。
チャーリィの書く文章はどんどん上達し、形而上的な思考もじきに身につけていきます。
いえ、それにとどまらず、天才的な頭脳へと発達していくのです。
そのうち、チャーリィは自分と同じ手術を施されたアルジャーノンにある変化のきざしが現れ始めたのに気付きます。
脳の退行……
チャーリィは恐怖します。すでに常人を遙かに超える知性を身につけたチャーリィは、アルジャーノンに現れた変化が、直に自分にも生ずるおそれに気付いてしまうのです。
また、あの精白の自分に戻ってしまう。
これ以上は書きません。
再び自分の知性が退行してしまう恐怖に直面したチャーリィ。
そして、結局、何が幸せということなのかを深く考えさせられた作品でした。
涙が止まらなくなるような切なさにあふれた、私のとても好きな作品です。
TVドラマでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、是非、本で読んでみてください。
チャーリィの書く文章(作品の文体)の変化という、TVでは味わうことのできない深い感慨がそこにあります。
「アルジャーノンに花束を」/ダニエル・キイス
小尾 芙佐訳 早川書房
ISBN:4-15-203393-2
 最初は、「DUNE」シリーズに出てくる、砂虫。もう砂の中からぐわっと出てきちゃう結構危険で巨大な虫です。
最初は、「DUNE」シリーズに出てくる、砂虫。もう砂の中からぐわっと出てきちゃう結構危険で巨大な虫です。

 ヒルからの連想。この作品にも、ある登場人物が体中ヒルに食いつかれて殺されるという場面が出てきます。うわぁもうダメだ。
ヒルからの連想。この作品にも、ある登場人物が体中ヒルに食いつかれて殺されるという場面が出てきます。うわぁもうダメだ。

 最愛の人を失った後、その人と瓜二つな人に出会えたとしたら?
最愛の人を失った後、その人と瓜二つな人に出会えたとしたら?


 夫婦仲は冷え込んで行ったのでした
夫婦仲は冷え込んで行ったのでした
 スタージョンには、切なさと、少年の気持ちがある、って以前書きましたが、この中・短編集も思いっ切りそういう要素満載です。
スタージョンには、切なさと、少年の気持ちがある、って以前書きましたが、この中・短編集も思いっ切りそういう要素満載です。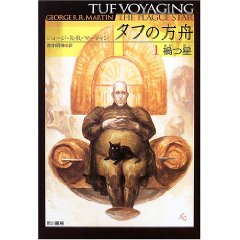
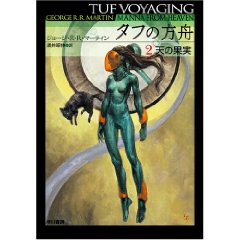
 またまた再読シリーズからのご紹介です(今では絶版のようなのでごめんなさいなのですが、とても面白いので)。
またまた再読シリーズからのご紹介です(今では絶版のようなのでごめんなさいなのですが、とても面白いので)。 飛行船のテロリスト達が頼りにしていたのは、偶然手に入れたとある「爆弾」のようなもの。テロリスト達もその実体はまるで理解できていないのだけれど、それが壊滅的な被害を及ぼすということは仲間の身をもって分かっていました。
飛行船のテロリスト達が頼りにしていたのは、偶然手に入れたとある「爆弾」のようなもの。テロリスト達もその実体はまるで理解できていないのだけれど、それが壊滅的な被害を及ぼすということは仲間の身をもって分かっていました。
 ちはモルモットかい!ですよね〜
ちはモルモットかい!ですよね〜 生き残った10人のうち、9人は、人間とも思えないような異形の物に変化してしまいます(それは見るもおぞましいような)。この騒ぎの後、生き残った彼等は「ジョーカー」と呼ばれ、迫害されてしまいます。こんな身体になって生きていくよりも「黒の女王」を引いて死んでしまった方がどれだけ良かったかと思ったジョーカーも沢山いたことでしょう。
生き残った10人のうち、9人は、人間とも思えないような異形の物に変化してしまいます(それは見るもおぞましいような)。この騒ぎの後、生き残った彼等は「ジョーカー」と呼ばれ、迫害されてしまいます。こんな身体になって生きていくよりも「黒の女王」を引いて死んでしまった方がどれだけ良かったかと思ったジョーカーも沢山いたことでしょう。 最初に人々の前に姿を現したエースは「タートル」でした。
最初に人々の前に姿を現したエースは「タートル」でした。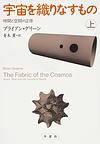 これは難物です。上手くご紹介できる自信などまるで無いのだけれど、是非ともお勧めしたい本なので、無謀にも敢えて挑戦してみることにしました。
これは難物です。上手くご紹介できる自信などまるで無いのだけれど、是非ともお勧めしたい本なので、無謀にも敢えて挑戦してみることにしました。 空間と時間
空間と時間
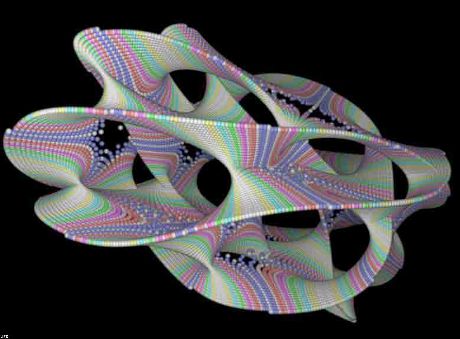 とにかく見て頂きましょう。左図が「カラビ=ヤウ図形」です。
とにかく見て頂きましょう。左図が「カラビ=ヤウ図形」です。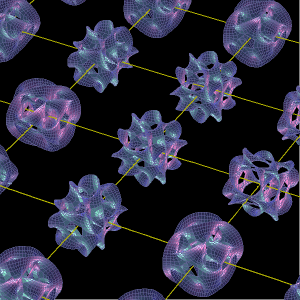
 舞台は中国。年代は、作中でははっきりとは記されていませんが、解説によれば日清戦争(1894〜1895)、義和団の乱(1900)、辛亥革命(1911〜1912)、清朝の滅亡(1912)、中国国民党の成立(1919)、南京事件(1927)等を題材にしているとのことであるので、時代背景としてはその頃と考えても良いのでしょうか。
舞台は中国。年代は、作中でははっきりとは記されていませんが、解説によれば日清戦争(1894〜1895)、義和団の乱(1900)、辛亥革命(1911〜1912)、清朝の滅亡(1912)、中国国民党の成立(1919)、南京事件(1927)等を題材にしているとのことであるので、時代背景としてはその頃と考えても良いのでしょうか。 「老人と海」
「老人と海」


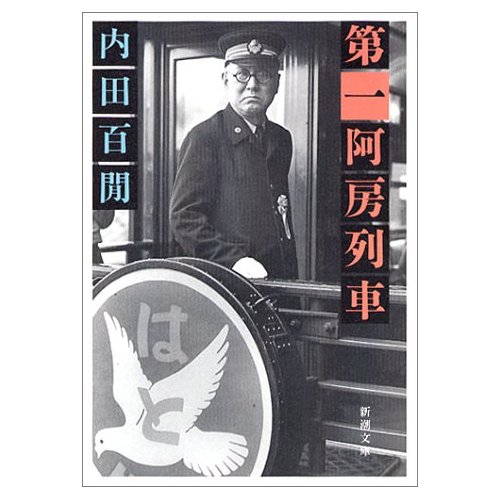
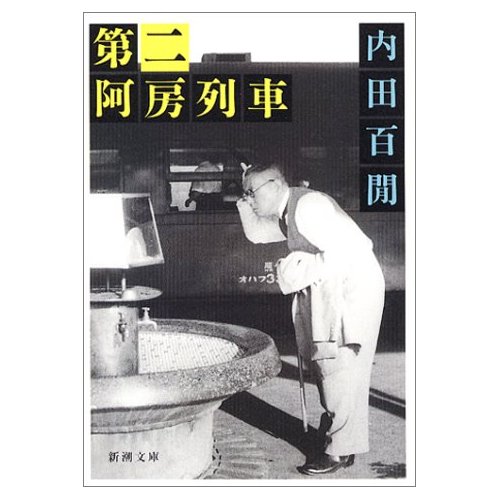
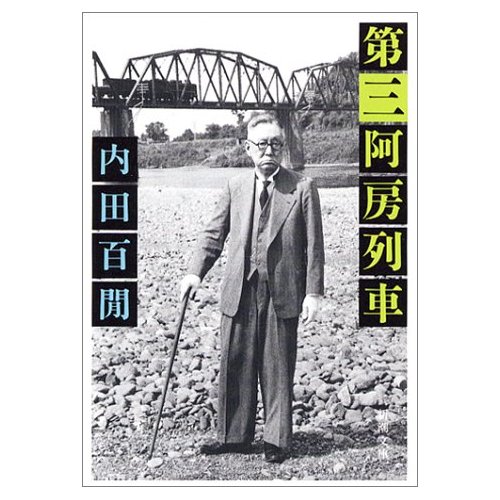
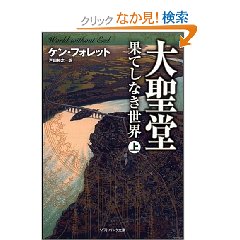
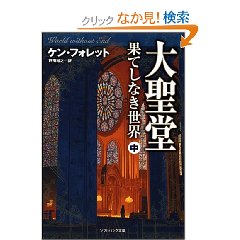
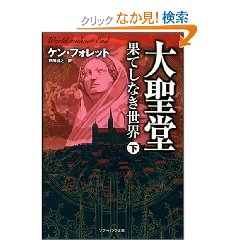

 な〜んで、三島の最初の紹介が「ホモ本」(いやらしい書き方ですみません、敢えてです)の「禁色」(「きんじき」)なの! という声が聞こえてきそうではあります。
な〜んで、三島の最初の紹介が「ホモ本」(いやらしい書き方ですみません、敢えてです)の「禁色」(「きんじき」)なの! という声が聞こえてきそうではあります。 アンドレ・ブルトンは、シュルレアリスムの総帥などと言われています。
アンドレ・ブルトンは、シュルレアリスムの総帥などと言われています。 ブロンテ姉妹の、世に言われる「名作」を二つ取り上げさせていただきます。
ブロンテ姉妹の、世に言われる「名作」を二つ取り上げさせていただきます。
 全22巻、読み終えるまでは書かないことにしようと、思っていました。
全22巻、読み終えるまでは書かないことにしようと、思っていました。
 作者の、アラン=ロブ・グリエは、「去年マリエンバートで」の原作者です。
作者の、アラン=ロブ・グリエは、「去年マリエンバートで」の原作者です。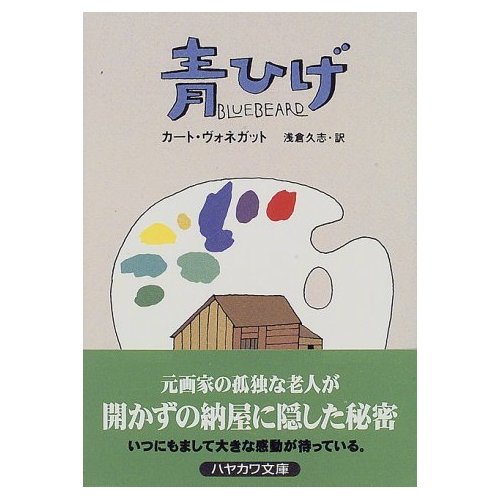 軽妙洒脱というのが、カート・ヴォネガット(・ジュニア)の持ち味でしょうか。
軽妙洒脱というのが、カート・ヴォネガット(・ジュニア)の持ち味でしょうか。

 ポオについて、これまで書かずにいたのにも程がある、と、思っています(すんまそん)。
ポオについて、これまで書かずにいたのにも程がある、と、思っています(すんまそん)。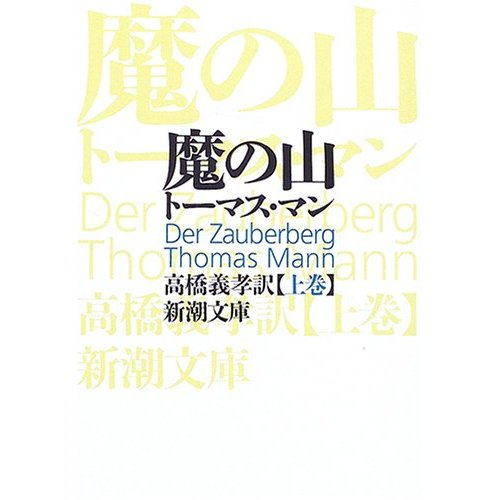
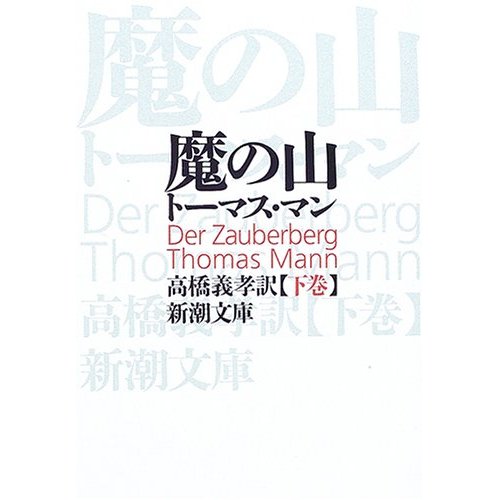

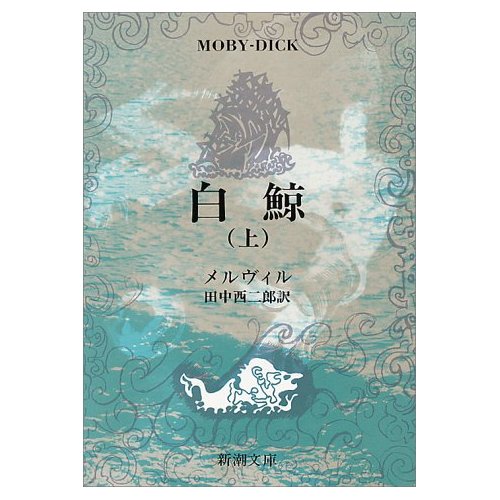
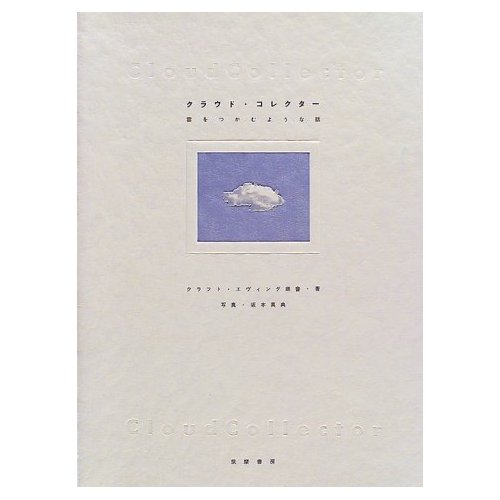 昭和9年、とある科学雑誌のそこだけ紅色が使われた広告頁に「雲、売ります」という広告が出ていたそうです。
昭和9年、とある科学雑誌のそこだけ紅色が使われた広告頁に「雲、売ります」という広告が出ていたそうです。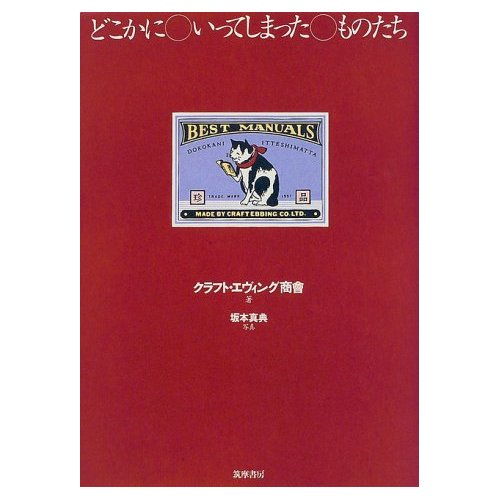 クラフトエヴィング商會にある、古い引き出しには色々な物が入っています。
クラフトエヴィング商會にある、古い引き出しには色々な物が入っています。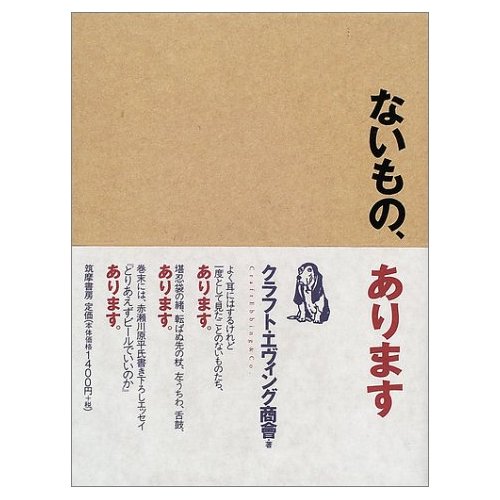

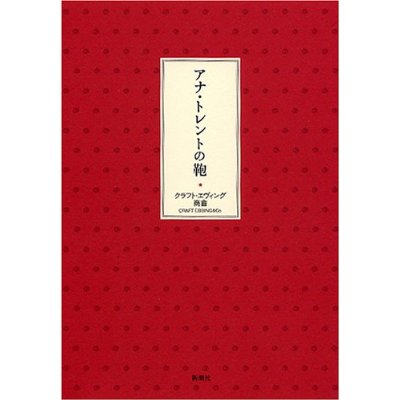
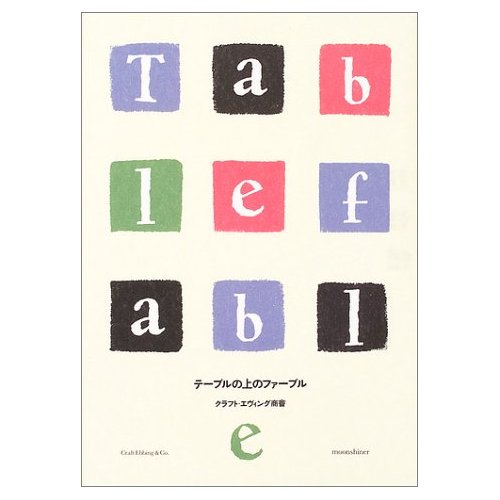

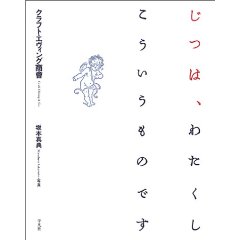
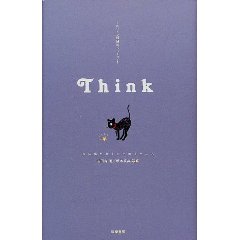
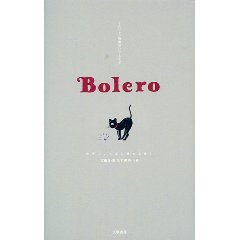


 主人公のルイス・ケインは、かつてカントンという名で闘った、レジスタンスの闘士。戦後の現在は、ビジネスエイジェントを生業としています。
主人公のルイス・ケインは、かつてカントンという名で闘った、レジスタンスの闘士。戦後の現在は、ビジネスエイジェントを生業としています。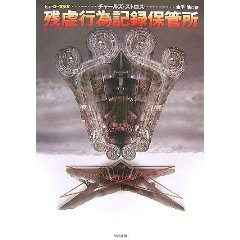 主人公は、イギリスの秘密組織「ランドリー」に所属する冴えないコンピュータおたく。のっけから、ほとんど侵入盗のようなミッションを与えられ、雨でずぶ濡れになりながら、何とか目的を達成してすたこら逃げ帰って来ます。
主人公は、イギリスの秘密組織「ランドリー」に所属する冴えないコンピュータおたく。のっけから、ほとんど侵入盗のようなミッションを与えられ、雨でずぶ濡れになりながら、何とか目的を達成してすたこら逃げ帰って来ます。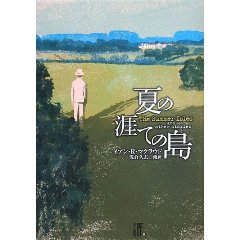 短編集です。一応、ジャンル的にはSFということになるのかもしれませんが(そう分類されています)、非常に叙情的で、中にはSFというジャンルでは語れない作品もあります。
短編集です。一応、ジャンル的にはSFということになるのかもしれませんが(そう分類されています)、非常に叙情的で、中にはSFというジャンルでは語れない作品もあります。 スティーブン・ミルハウザーの短編集です。
スティーブン・ミルハウザーの短編集です。 本作は、とある男性の「四巻からなる伝記」です。とはいっても、本自体はとても分厚いのが一冊ですが。
本作は、とある男性の「四巻からなる伝記」です。とはいっても、本自体はとても分厚いのが一冊ですが。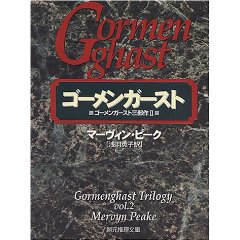


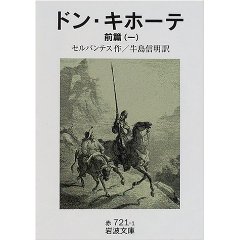
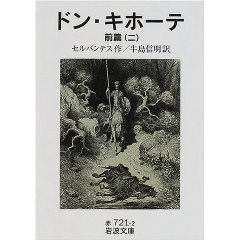
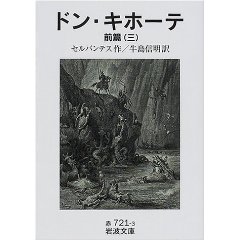
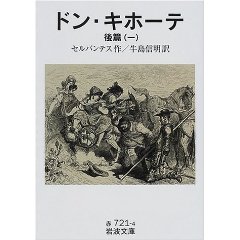
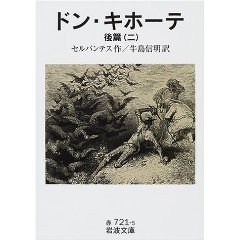
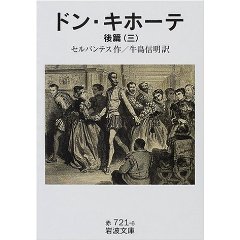















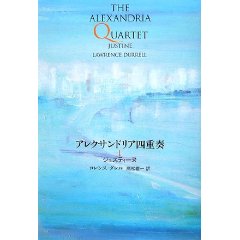

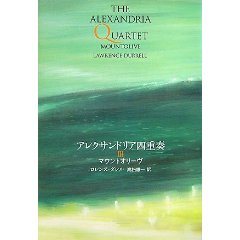
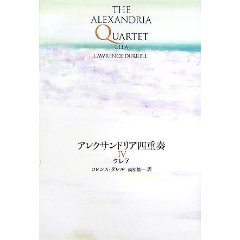
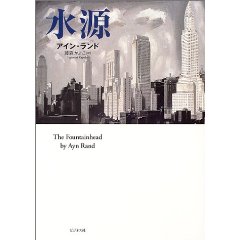 作家は、女性です。
作家は、女性です。 古いSF作家さんだそうですが、私は知りませんでした。
古いSF作家さんだそうですが、私は知りませんでした。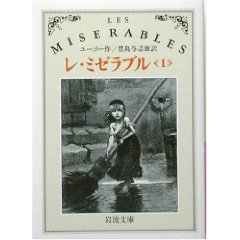

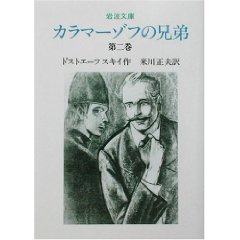
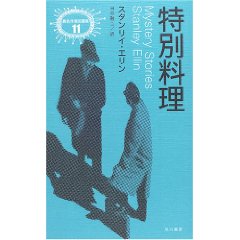 ハヤカワの「異色作家短編集」シリーズの第11巻です(
ハヤカワの「異色作家短編集」シリーズの第11巻です(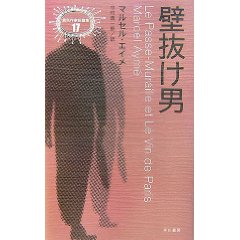
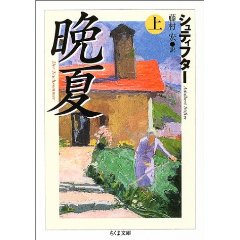

 1メートルってどういう基準で決められているかご存じですか?
1メートルってどういう基準で決められているかご存じですか?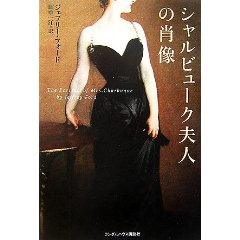 主人公は才能のある画家です。彼は金のために上流階級の人たちの肖像画を描いています。自分の描きたい絵では必ずしもないのですが、良いお金になります。
主人公は才能のある画家です。彼は金のために上流階級の人たちの肖像画を描いています。自分の描きたい絵では必ずしもないのですが、良いお金になります。
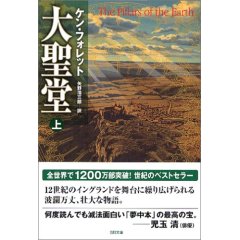
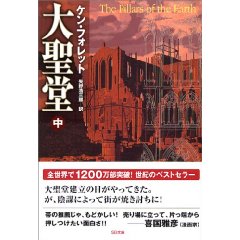
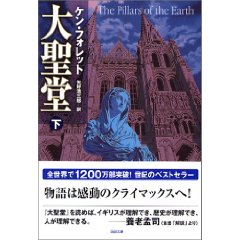
 著者は「短編小説の女王」と呼ばれる、カナダの70才になる女性です。
著者は「短編小説の女王」と呼ばれる、カナダの70才になる女性です。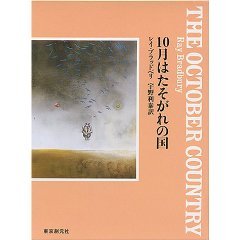 「SFの抒情詩人」と呼ばれることもあるブラッドベリです。
「SFの抒情詩人」と呼ばれることもあるブラッドベリです。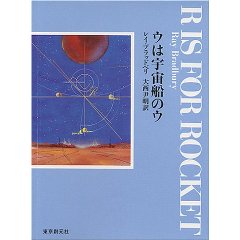
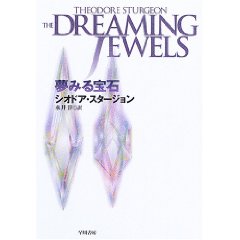 主人公のホーティーは捨て子の男の子でした。判事に立候補していたアーマンドとその妻は、身寄りのない孤児を引き取ることにより地域での名望が上がり、判事選が有利になるというただそれだけの理由でホーティーを引き取りました。しかしそこには愛情はなく、ホーティは虐げられて育てられたのでした。彼の唯一の友達は、孤児院を出る時にもらったジャンキーという小さな木の人形でした。その人形には不思議な光を放つ鉛ガラスのような目が埋め込まれていました。
主人公のホーティーは捨て子の男の子でした。判事に立候補していたアーマンドとその妻は、身寄りのない孤児を引き取ることにより地域での名望が上がり、判事選が有利になるというただそれだけの理由でホーティーを引き取りました。しかしそこには愛情はなく、ホーティは虐げられて育てられたのでした。彼の唯一の友達は、孤児院を出る時にもらったジャンキーという小さな木の人形でした。その人形には不思議な光を放つ鉛ガラスのような目が埋め込まれていました。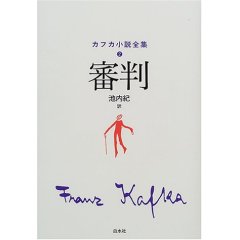 銀行員のヨーゼフ・Kは、ある朝突然逮捕される。
銀行員のヨーゼフ・Kは、ある朝突然逮捕される。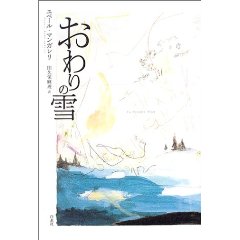 「トビを買いたいと思ったのは、雪がたくさんふった年のことだ。」
「トビを買いたいと思ったのは、雪がたくさんふった年のことだ。」
 で、このレイモン・クノーの超有名な作品が、「地下鉄のザジ」だったりするわけだ。
で、このレイモン・クノーの超有名な作品が、「地下鉄のザジ」だったりするわけだ。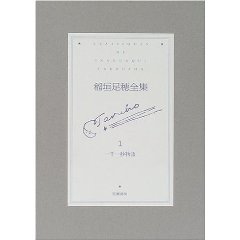 「タルホ」です。
「タルホ」です。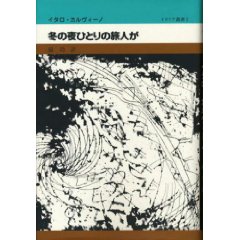 あなたは、今、新しい本を読もうとしている。イタロ・カルヴィーノの新作、「冬の夜ひとりの旅人が」という本である。
あなたは、今、新しい本を読もうとしている。イタロ・カルヴィーノの新作、「冬の夜ひとりの旅人が」という本である。 タイトルだけ読むと、「これはSF?」とか思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。むしろ、サブタイトルの方が内容を良く表しています。
タイトルだけ読むと、「これはSF?」とか思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。むしろ、サブタイトルの方が内容を良く表しています。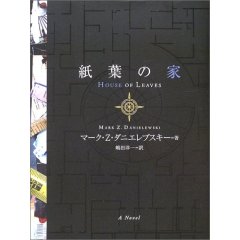 体力が必要な本です。読み終えるためには。
体力が必要な本です。読み終えるためには。
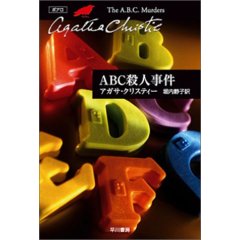 これも、「やられた〜」の一冊でした。いや、クリスティにはやられっぱなしなんですけれど。
これも、「やられた〜」の一冊でした。いや、クリスティにはやられっぱなしなんですけれど。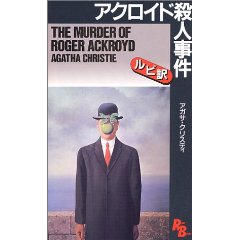 「くっそ〜! やられた〜!」というのは、犯人を当てようと思って推理小説を読んでいる読者の断末魔なのですが、この作品こそそう叫びたい! 思いっきり、完膚無きまでにやられますた。
「くっそ〜! やられた〜!」というのは、犯人を当てようと思って推理小説を読んでいる読者の断末魔なのですが、この作品こそそう叫びたい! 思いっきり、完膚無きまでにやられますた。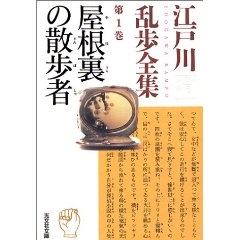 ♪「ぼ! ぼ! 僕等は少年探偵団 勇気凛々瑠璃の色」です〜。
♪「ぼ! ぼ! 僕等は少年探偵団 勇気凛々瑠璃の色」です〜。 またしてもおかしな本を選んでしまいました。
またしてもおかしな本を選んでしまいました。 楽しい〜! もう、こういうジョーク大好き!
楽しい〜! もう、こういうジョーク大好き!
 かなりの人が、子供の頃一度は読んだことがある本ではないかと思います。
かなりの人が、子供の頃一度は読んだことがある本ではないかと思います。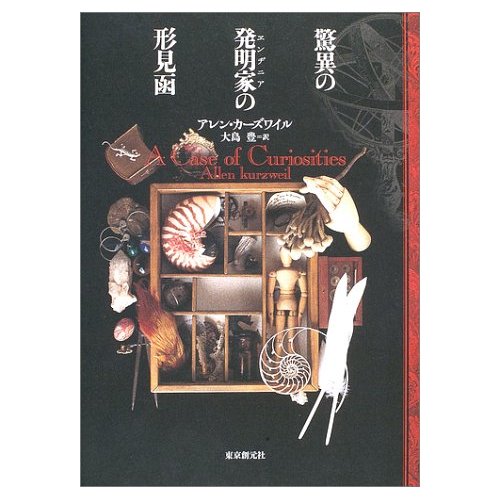

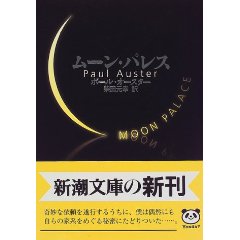 なんて奇矯な小説なのでしょう。
なんて奇矯な小説なのでしょう。 またまた数学関係の本です(そんなに嫌な顔をしなさるな)。
またまた数学関係の本です(そんなに嫌な顔をしなさるな)。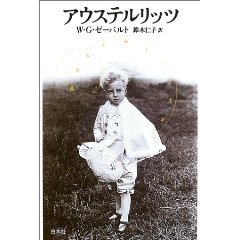 とても、とてもきれいな文章の本です。
とても、とてもきれいな文章の本です。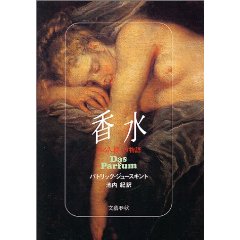 時は18世紀。場所はフランス。
時は18世紀。場所はフランス。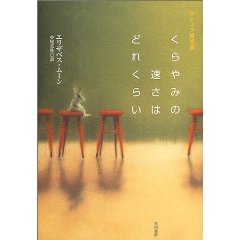 この物語の主人公は、ルウ・アレンデイルという30歳を過ぎた架空の自閉症の男性です。
この物語の主人公は、ルウ・アレンデイルという30歳を過ぎた架空の自閉症の男性です。 SF(一応、そうなのだろうね)短編集です。
SF(一応、そうなのだろうね)短編集です。
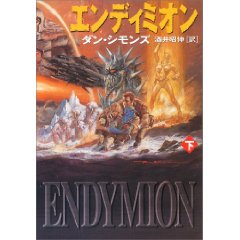
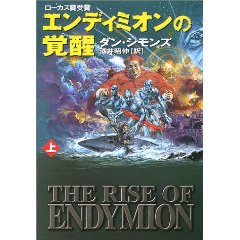
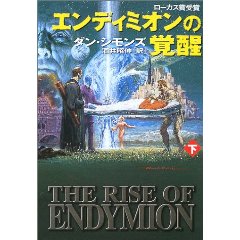
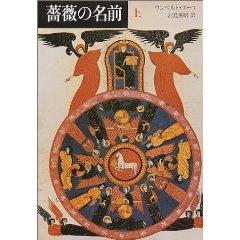
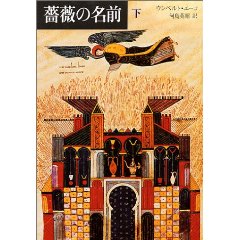
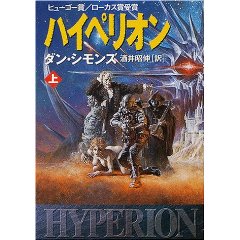
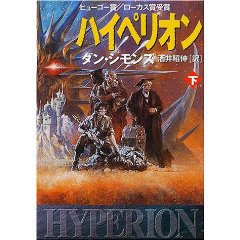
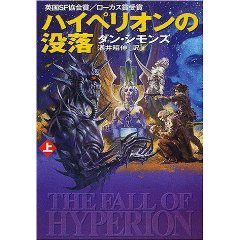

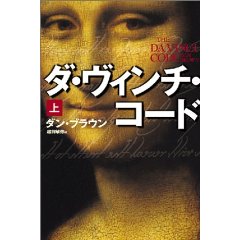
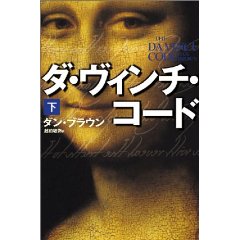
 SFです。短編集なんですけど、すごくお話が面白いです。最初に収録されているのは「バビロンの塔」という作品。
SFです。短編集なんですけど、すごくお話が面白いです。最初に収録されているのは「バビロンの塔」という作品。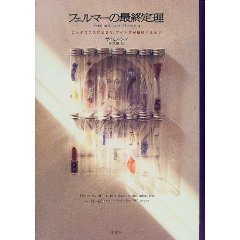 X^2(Xの二乗)+Y^2(Yの二乗) = Z^2(Zの二乗)
X^2(Xの二乗)+Y^2(Yの二乗) = Z^2(Zの二乗)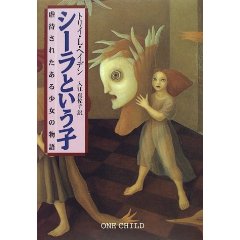 子供に火をつけてしまった6才の女の子……というところから物語は始まります。
子供に火をつけてしまった6才の女の子……というところから物語は始まります。